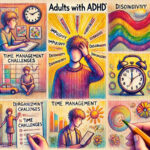この記事が含む Q&A
- ADHDの成人では過去1年間に転倒した人がどの程度いますか?
- 回答: 45名を対象にした調査で12か月の転倒率は37.8%、約8割が転倒を恐れていると報告されています。
- 薬の服用(日となし)で転倒リスクは変わりましたか?
- 回答: 飲んだ日と飲まない日で転倒リスクの有意な差は認められませんでした。
- 転倒予防のためにはどんな支援が有効と示唆されていますか?
- 回答: バランスを鍛える運動と心理的支援を組み合わせる方法が有望だと提案されています。
ADHDというと、集中力や衝動性の問題がよく知られています。
けれども、この研究が注目したのは、少し意外なテーマでした。
「転倒」です。
クウェート大学(クウェート)、アラバマ大学(アメリカ)、ノーザンボーダー大学(サウジアラビア)の研究チームは、ADHDをもつ成人が、どのくらい転びやすいのか、そしてどんな要因が関係しているのかを調べました。
その結果、ADHDをもつ成人の約4割が、過去1年のあいだに転倒していたのです。
これは、高齢者で知られている転倒率(およそ3割)を上回るものでした。
研究に参加したのは、20歳から55歳までの45人の成人。
全員が医師や心理士からADHDと診断され、少なくとも3か月以上、メチルフェニデートやアンフェタミンなどの精神刺激薬を服用していました。
参加者は、薬を飲まない日(オフ)と飲んだ日(オン)の2回にわたり、体のバランスや筋力、歩行動作のテストを受け、過去の転倒経験や不安感などを質問票で答えました。

結果は、驚くほどはっきりしていました。
12か月間の転倒率は37.8%。そのうちの8割近くが「転ぶのが怖い」と感じており、6割以上が「立っているときや歩くときに不安定に感じる」と答えていました。
転倒の方向は、前方への転倒がもっとも多く、次いで後ろ向き、横向きでした。転倒によってケガをした人も4人に1人おり、骨折やねんざを含むものもありました。
転倒は、女性の方が男性より多く見られました(42.9%対20%)。
また、ADHDの「不注意」と「多動衝動」の両方がある混合型(Combined subtype)の人で、転倒がもっとも多くみられました。
BMI(体格指数)や年齢、学歴、薬の種類などとは有意な関連が見られませんでしたが、「ふらつきを感じる」「転ぶのが怖い」といった心理的要素が、実際の転倒と強く結びついていました。
研究チームは、この背景にはADHDの特徴的な脳機能が関係していると考えています。
たとえば、注意の持続や反応速度、運動の計画性の難しさが、バランスの乱れにつながりやすい。
過去の研究でも、ADHDの成人は姿勢のゆらぎが大きく、安定して立つことが難しい傾向が示されています。
これらは、認知症やパーキンソン病など他の神経疾患で見られる転倒とは違い、発達の過程で形成された脳の制御の特徴と関係していると考えられます。
薬の影響についても調べられました。
メチルフェニデートやアンフェタミン系の刺激薬は、注意や実行機能を高めるだけでなく、運動制御にも関係する脳のドーパミン系を活性化させるため、バランス改善に役立つことが先行研究で報告されています。
しかし今回の調査では、薬を飲んだ日と飲まない日で転倒リスクの明確な差はみられませんでした。
統計的には、筋力テストや歩行テスト(Timed Up and Go)などの数値と転倒率のあいだにも有意な関連は見られませんでした。
ただし、「心理的な不安」と「身体的な安定感の自覚」は、確実に転倒と関係していました。
つまり、実際にバランス能力が劣っているかどうかだけでなく、「自分は転ぶかもしれない」と感じていること自体が、転倒のリスクを高めているのです。
これは高齢者の研究でも知られる現象で、「転倒恐怖」が体の動きをぎこちなくし、逆にバランスを崩すことがあります。

研究者たちは、この発見がADHD支援の新しい視点になると述べています。
ADHDの人は、注意や衝動性だけでなく、体のコントロールにも小さな困難を抱えることがある。
そのため、運動療法やヨガ、太極拳などの「バランス感覚を育てる運動」が役立つかもしれないと提案しています。
これらの運動は、ADHDの症状軽減にも効果があるとされており、体と心の両面からのアプローチが期待されます。
さらに、研究チームは、転倒の恐怖を和らげる心理的支援――たとえば認知行動療法(CBT)なども有効だろうと指摘します。
運動と心理支援を組み合わせることで、身体的な安定感と自信の回復を同時に促すことができます。
実際、高齢者の転倒予防では、身体訓練と心理サポートを組み合わせる方法が、もっとも効果的だと報告されています。
今回の研究は小規模で、対象が女性に偏っており、転倒の報告も自己申告によるものでした。
そのため、結果を一般化するには慎重さが必要です。

しかし、これまでほとんど注目されてこなかった「ADHDと転倒」の関係を、初めて体系的に示した点に大きな意義があります。
ADHDの成人が、注意や感情だけでなく、体の安全面でもリスクを抱えている可能性を示したのです。
研究者たちは、今後はより多様で大規模な追跡研究を通して、転倒の原因や予防法を明らかにしていく必要があるとしています。
薬の効果、運動の種類、心理的要因がどのように組み合わさって影響するのか。
それを理解することが、ADHDの人々の生活の安全と質を守るうえで重要になると強調しています。
そして何よりも、この研究が伝えているのは、「転倒」は注意力の問題だけではないということです。
自分の体を感じ取る力、動きを制御する力、そして「怖い」と感じたときにどう向き合うか。
そのすべてが、ADHDの人々の生活の一部として存在しているのです。
その現実を知り、支援や理解の視点を広げることが、これからの社会の課題でもあります。
(出典:Frontiers in Psychiatry DOI: 10.3389/fpsyt.2025.1673400)(画像:たーとるうぃず)
「ADHDの人は、注意や衝動性だけでなく、体のコントロールにも小さな困難を抱えることがある」
ADHDの人は転倒しやすい。
これは初めて知りました。
多くの人に知っていただきたいと思います。
ADHDを持つ子どもたちの心を支える「体を動かす習慣」の効果
(チャーリー)