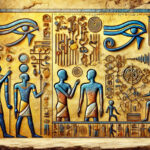この記事が含む Q&A
- ADHDの子どもは時間ベース予期記憶(TBPM)が苦手ですか?
- はい、戦略的な時間モニタリングが低いため、TBPMの成績が低くなる傾向があります。
- 時計を見る合計回数はADHDと定型発達の子どもで違いがありますか?
- いいえ、時計を見る総チェック数には大きな差はありません。
- ADHDの子どもが「時計を見るタイミング」を改善するためにはどうすれば良いですか?
- 訓練やゲームを通じて戦略的な時間モニタリングのスキル向上が期待されます。
時間に合わせて行動することは、私たちの日常生活で欠かせない力です。
朝の支度を終えて決まった時間に学校へ向かったり、習い事の時間に遅れないように準備を始めたりするなど、子どもたちも日々このような行動を求められています。
この「決まった時間に予定された行動を思い出して実行する力」は、「時間ベース予期記憶(Time-Based Prospective Memory, TBPM)」と呼ばれています。
そしてこのTBPMは、ADHD(注意欠如・多動症)のある子どもたちにとって、とくに困難な分野であることがこれまでの研究で示されてきました。

今回の研究は、このTBPMの困難の背景にある行動の特徴を明らかにするために行われたものです。
研究は、ヘルシンキ大学、ジュネーブ大学、オウル大学、アールト大学など、フィンランドとスイスの複数の研究機関が共同で実施しました。
これまでの研究の多くは、単調で現実離れしたタスク(たとえばボタンを一定時間ごとに押すなど)を用いており、実際の生活に近い状況で子どもたちがどのように時間を意識して行動しているかを正確に捉えることは難しいものでした。
研究チームは、この課題を解決するために、まるで本物の家のような仮想空間の中で子どもたちが自由に動き回りながら様々な生活場面を再現できるバーチャルリアリティ(VR)タスク「EPELI(エペリ)」を用いて、ADHDのある子どもたちとそうでない子どもたちのTBPMの違いを調べました。
この研究には9歳から13歳の子どもたち142人(ADHDのある子ども71人、定型発達の子ども71人)が参加しました。
ADHDの子どもたちは、診断は受けているものの、薬は服用していない状態(24時間の休薬)で実験に参加しました。

子どもたちは、VRゴーグルを装着して、自分の家にいるかのような仮想空間の中で、日常的な13のシナリオ(例:朝の支度、学校から帰った後の行動、寝る前の準備など)に取り組みました。
各シナリオでは、いくつかの指示(例:「おかゆを火にかけてね」「お母さんに電話してね」など)を最初に聞き、それを覚えながら自由に部屋の中を移動して、決められた時間にタスクを実行する必要があります。
この研究では、特に「時計をどのように見ていたか(時間モニタリング)」に注目しました。
時間モニタリングには2つの側面があります。
1. 総チェック数(absolute clock-checking):シナリオ中に時計を見た合計回数
2. 戦略的モニタリング(relative clock-checking):設定された時間直前(例えば45秒以内)に時計を見た割合
このように分けることで、「たくさん時計を見ていたけど、タイミングがずれていたのか」「必要な時にうまく見られていたのか」といった、時間を見る行動の質的な違いがわかります。
結果として、ADHDのある子どもたちは、TBPMの成績が明らかに低く、また戦略的モニタリングの度合いも低いことがわかりました。
ところが、時計を見る合計回数(総チェック数)には、ADHDのある子どもと定型発達の子どもとの間に大きな差はありませんでした。
つまり、ADHDの子どもたちは「時計は見ているけれど、タイミングがうまくいっていない」という特徴があるのです。
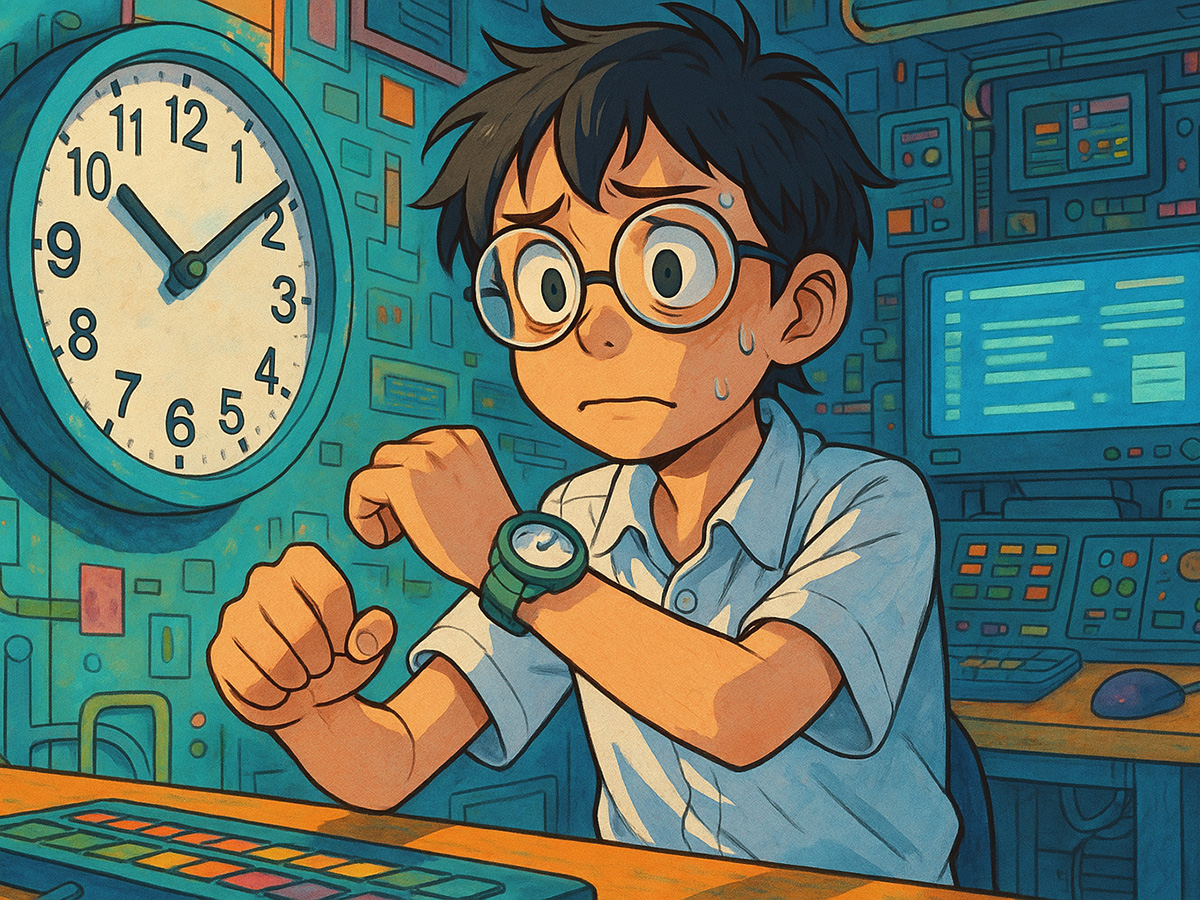
さらに分析を進めると、この「戦略的モニタリングの低さ」が、TBPMの低さをほぼ完全に説明できることがわかりました。
統計モデルによると、戦略的モニタリングだけでTBPM成績の22.1%を説明し、総チェック数と合わせると53.9%を説明できることが明らかになったのです。
これは非常に重要な発見です。
なぜなら、戦略的に時間を見る力は「訓練によって改善が期待できる力」であるためです。
研究チームは、この戦略的モニタリングの低さが、ADHDの子どもたちに特徴的な「注意の持続の難しさ」や「時間感覚のずれ(時間の見積もりが早すぎるなど)」と関係していると考えています。
たとえば、ADHDのある子どもは「そろそろ45秒が経ったかな」と早めに感じてしまい、早い段階で時計を見てしまう。
そして、その後にもう一度見直すことがうまくできないという傾向があるようです。
このような特性は、注意の制御や時間の感覚を司る脳の仕組みと深く関係していると考えられており、VRを使った課題によって、従来の方法では見えにくかったこうした微細な行動の違いが明らかになったのです。
また、VRによって記録される行動は非常に多彩で、たとえば「無関係な物への関心」や「視線の動き」なども分析可能です。
実際にこの研究でも、ADHDの子どもたちは「課題とは関係のないもの」に触れる回数が多い傾向があり、注意の逸れやすさが行動に表れていました。
このように、EPELIという自然な状況を再現したVRタスクは、ADHDの子どもたちの実生活に近い形での困難さを捉える上で有効であることが示されました。
これまでの実験室的なタスクでは気づけなかった「現実の中でのつまずき」を見つけることができるのです。

この研究成果は、診断や評価だけでなく、支援や訓練の場面でも応用が期待されます。
たとえば、VRを活用した訓練プログラムを開発し、「いつ時間を確認するのが効果的か」をゲーム感覚で学べるようにすることで、TBPMの力を高める支援が可能になるかもしれません。
実際に、過去の研究では「メタ記憶(自分の記憶についての意識)」をトレーニングすることで、子どもたちが戦略的な時間モニタリングを身につけ、TBPMの成績が向上したという報告もあります。
こうした支援が、ADHDの子どもたちが日常生活をよりスムーズに送る助けとなる可能性があります。
今回の研究は、課題としては比較的短い時間(15〜45秒の範囲)での記憶実行でしたが、それでも明確な差が表れていたことから、ADHDにおけるTBPMの困難さが、短時間でもすでに目立つほどのものであることを示しています。
今後は、より長い時間を対象にしたTBPMの課題や、実際の生活の中での行動との関係(たとえば保護者や教師による観察との比較)なども検討していく必要があります。
また、子どもたち自身が自分の「時間の感覚」や「記憶の得意・不得意」にどのような意識を持っているのかという「メタ認知」の側面も今後の重要な研究課題です。

ADHDは、単に「集中できない」「じっとしていられない」というだけでなく、時間の感覚や行動の組み立て方にも影響を与える多面的な特徴を持った発達特性です。
今回の研究は、そうした複雑な特徴を丁寧に読み解き、支援につなげるための新たな一歩となりました。
未来の支援では、こうしたVR技術を活用して、単なる行動観察では捉えきれない「内側の思考プロセス」や「時間の使い方のクセ」にまでアプローチできるようになるかもしれません。
そしてそれは、子どもたち一人ひとりの「できる力」を伸ばし、「生活の中で困りにくくなる」ことに結びついていくことでしょう。
(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-08944-w)(画像:たーとるうぃず)
時間にあわせて行動するのが苦手なADHDの子は時計を見る回数は多い。
けれど、「見るタイミング」がうまくいっていないとのこと。
それは練習すればうまくなる可能性があるので、毎日の「忘れちゃった…」を減らせるかもしれません。
(チャーリー)