
この記事が含む Q&A
- 自閉症の人は実行機能に課題を抱えやすいのですか?
- はい、自閉症の方は事前準備や集中に特別な努力が必要とされることがあります。
- BCI技術は自閉症のどのような支援に役立つのでしょうか?
- 脳波を利用して認知トレーニングやエラー認識を促進し、実行機能の向上を目指しています。
- 自閉症の人はミスやエラーに気づきにくいとされていましたが、この研究から何がわかりましたか?
- 高負荷の課題では、彼らもエラーに反応し、脳は適切に対応していることが示されました。
自閉症の人は「実行機能」と呼ばれる能力に苦手さを抱えることが知られています。
実行機能とは、頭の中で考えをまとめたり、状況に応じて行動を切り替えたり、失敗した時にやり直す力などを含む、人間の「脳の司令塔」のような働きです。
しかし、なぜ自閉症の人がこうした力を発揮しにくいのか、その脳の動きについては、まだはっきりと分かっていませんでした。
そんな中、ポルトガルのコインブラ大学の研究チームが、自閉症の人が実行機能を使う時に脳がどのように働くのかを、最新の脳波測定技術を使って詳しく調べました。
この研究では、自閉症の成人14人と、自閉症でない成人10人が参加しました。
課題は少し変わったものです。
「でたらめな言葉」を覚えて、頭の中で逆さまにし、それを脳波だけでコンピュータに入力する、というものです。
まるでSF映画のようですが、これは「ブレイン・コンピュータ・インタフェース(BCI)」と呼ばれる技術で、脳波から人の意図を読み取るシステムを使っています。
この課題は、覚える、考え直す、正しい順番で答える、という複数の実行機能をフルに使わなければできません。
さらに、入力ミスが起きやすい仕掛けになっていて、ミスに気づいて修正する力(エラー監視)も試されます。

測定した脳波の中で、とくに注目されたのが「シータ波」と「アルファ波」という2つのリズムです。
シータ波は脳の前の方(前頭部)で、間違いを察知したり、集中して考えたりする時に強くなります。
一方、アルファ波は後ろの方(後頭部)で、リラックスしている時に強くなり、逆に集中すると弱まる性質があります。
結果はとても興味深いものでした。
まず、課題そのものの成績は、自閉症の人も自閉症でない人も、ほとんど差がありませんでした。
しかし、その裏で脳は違う働きをしていたのです。
自閉症の人は、課題が始まる「準備段階」でシータ波がとくに強くなっていました。
これは、課題に備えて脳がフル稼働し、集中力や認知の制御を一生懸命働かせている証拠です。
いわば、スタートラインでエンジンをふかしているような状態です。
一方で、アルファ波も特徴的でした。
自閉症の人は、リラックス時に強いはずのアルファ波が、課題中も高いままでした。
ただし、実際に文字を逆さにして考える場面では、アルファ波が大きく下がり、自閉症でない人よりも大きな変化を見せました。
これは「普段は注意を向けにくいが、頑張って集中するとしっかりと脳を切り替えている」ことを示しているかもしれません。
また、課題中に起こるミスに対する脳波の反応は、意外にも自閉症の人と自閉症でない人でほとんど差がありませんでした。
どちらのグループも、システム側のミス(脳波を読み取るコンピュータの誤認識)が起こった時には、シータ波とアルファ波がしっかり反応していたのです。
つまり、自分自身の失敗ではなく、機械のエラーに対しても、両者は同じように脳が動いていたわけです。
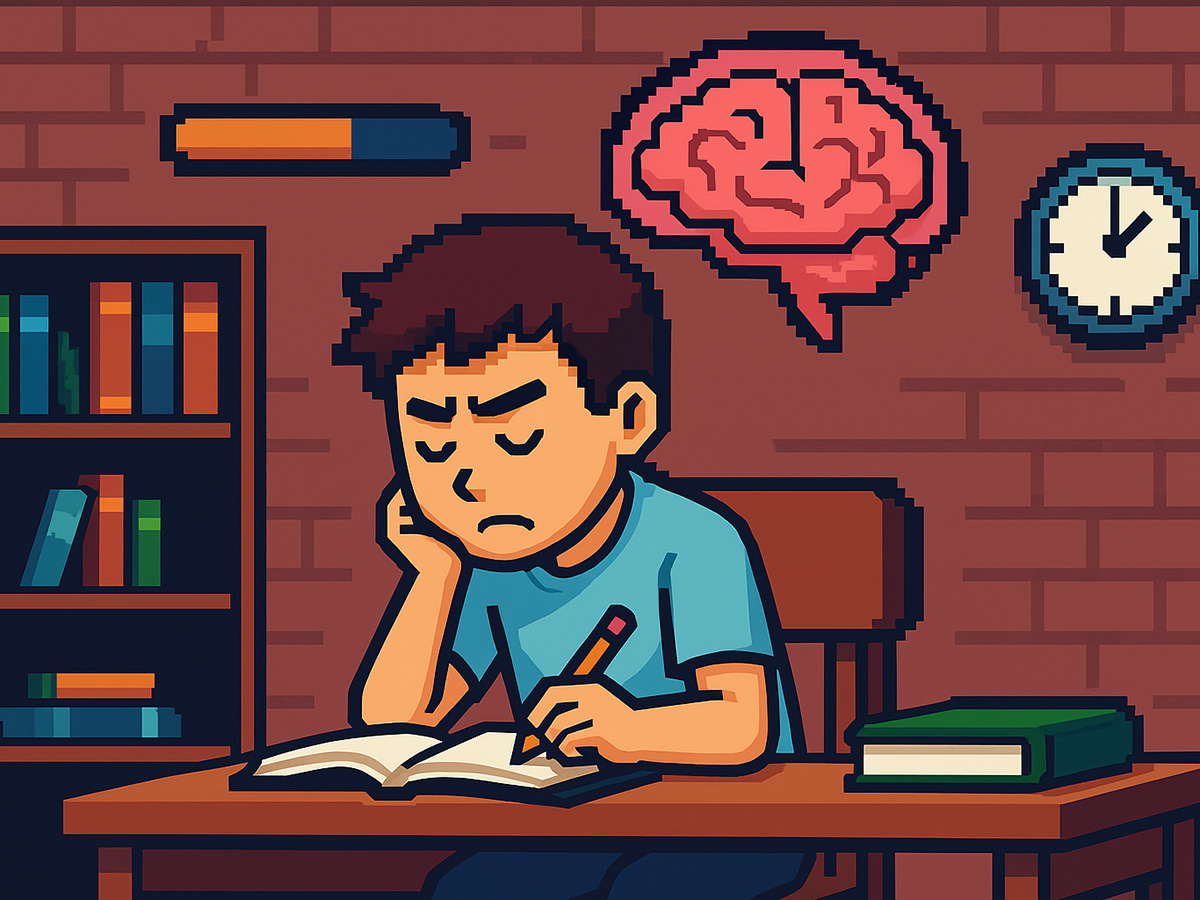
この結果は、自閉症の人が「自分のミスに気づきにくい」という過去の研究結果とは少し違っています。
今回のような高負荷でゲーム感覚の課題では、モチベーションが上がり、ミスへの反応も自然と高まった可能性があります。
今回の研究は、「自閉症の人は、課題をこなすために、事前準備で多くの認知資源を使い、集中するために特別な努力をしている」ことを、脳波の変化として示した貴重な成果です。
そして、BCIを使ったこうしたゲーム的な課題が、自閉症支援の新たな方法として役立つかもしれないことも示唆されています。
実際、BCI技術は、もともと体が不自由な方のために開発されましたが、最近では自閉症の人の認知トレーニングにも応用され始めています。とくに、エラーへの気づきや注意力の向上といった分野で期待されています。
今回の課題に参加した自閉症の人のうち、IQが85未満の方はBCIとの相性が良くないケースがありましたが、それ以上の方では成績に差は出ませんでした。
つまり、ある程度の認知レベルがあれば、BCIを使った支援は有効である可能性が高いのです。

今後、この研究チームは、自閉症の中でもとくに実行機能に課題をかかえる方や、ミスに対して不安やストレスを感じやすい方に向けて、BCIを使ったトレーニングを発展させていく予定です。
さらに、長期的なトレーニングによって、実行機能の改善や脳波パターンの変化が見られるかどうかも検証されるでしょう。
自閉症は、行動や社会性の違いだけでなく、脳の使い方そのものが独自であることが、こうした研究から少しずつ明らかになってきています。そして、その違いを理解し、活かすことで、自閉症の人がより快適に、能力を発揮できる社会が実現していくのです。
「苦手だからできない」ではなく、「違う方法で工夫すればできる」。
この研究は、そんな前向きなメッセージを私たちに伝えてくれているのかもしれません。
(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-00670-7)(画像:たーとるうぃず)
「自閉症の人は、課題をこなすために、事前準備で多くの認知資源を使い、集中するために特別な努力をしている」
知っておいてほしいと思います。
(チャーリー)




























