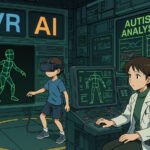この記事が含む Q&A
- ADHDと音楽の関係についてどのような研究結果がありますか?
- ADHDの人はリズムやテンポの把握がやや苦手でも、感情表現や即興演奏が得意な面もあると報告されています。
- 音楽はADHDの人にどのように効果があるのですか?
- 好きな音楽を聴きながら学習することで集中力が高まり、ストレスや衝動行動の緩和にも役立つとされています。
- どのように音楽療法を取り入れると良いですか?
- 個々の好みやニーズに合わせた音楽とグループ活動を組み合わせて、心の安定や社会性の向上を目指すのが効果的です。
音楽とADHDとの関係に注目が集まっています。
イギリスの研究チームが、これまでに行われたADHDと音楽に関する研究を集めて分析した論文を発表しました。
この研究は、ロンドンにある名門のキングス・カレッジ・ロンドンを中心としたチームによって行われたもので、1981年から2023年までに発表された、ADHDと音楽に関する20件の研究(合計1170人が参加、そのうち830人がADHDの診断を受けていた)を取り上げ、さまざまな角度からその関係性を探りました。
ADHD、つまり注意欠如・多動症は、多くの人が知っているようで実はよく知られていない発達特性です。
「落ち着きがない」「じっとしていられない」「集中が続かない」といった特徴がある一方で、「自分の好きなことには夢中になれる」「アイデアが豊富」「エネルギーにあふれている」など、環境や支援のあり方によってその特性が大きく変化することもあります。
そんなADHDの人たちと「音楽」との関わりを探ることで、彼らの理解が進み、新しい支援の可能性が見えてくるかもしれません。
まず研究チームが注目したのは、「ADHDの人たちは、音楽をどう聴き、どう感じ、どう演奏するのか」という点です。
過去の研究によると、ADHDの人たちはリズムやテンポの把握にやや苦手さが見られる傾向があることがわかりました。
たとえば、音楽の中のタイミングのズレや、リズムの変化を感じ取りにくい人がいるということです。
これはADHDの人に見られやすい「時間感覚のずれ」や「動作のタイミングの不一致」と関係している可能性があると考えられています。
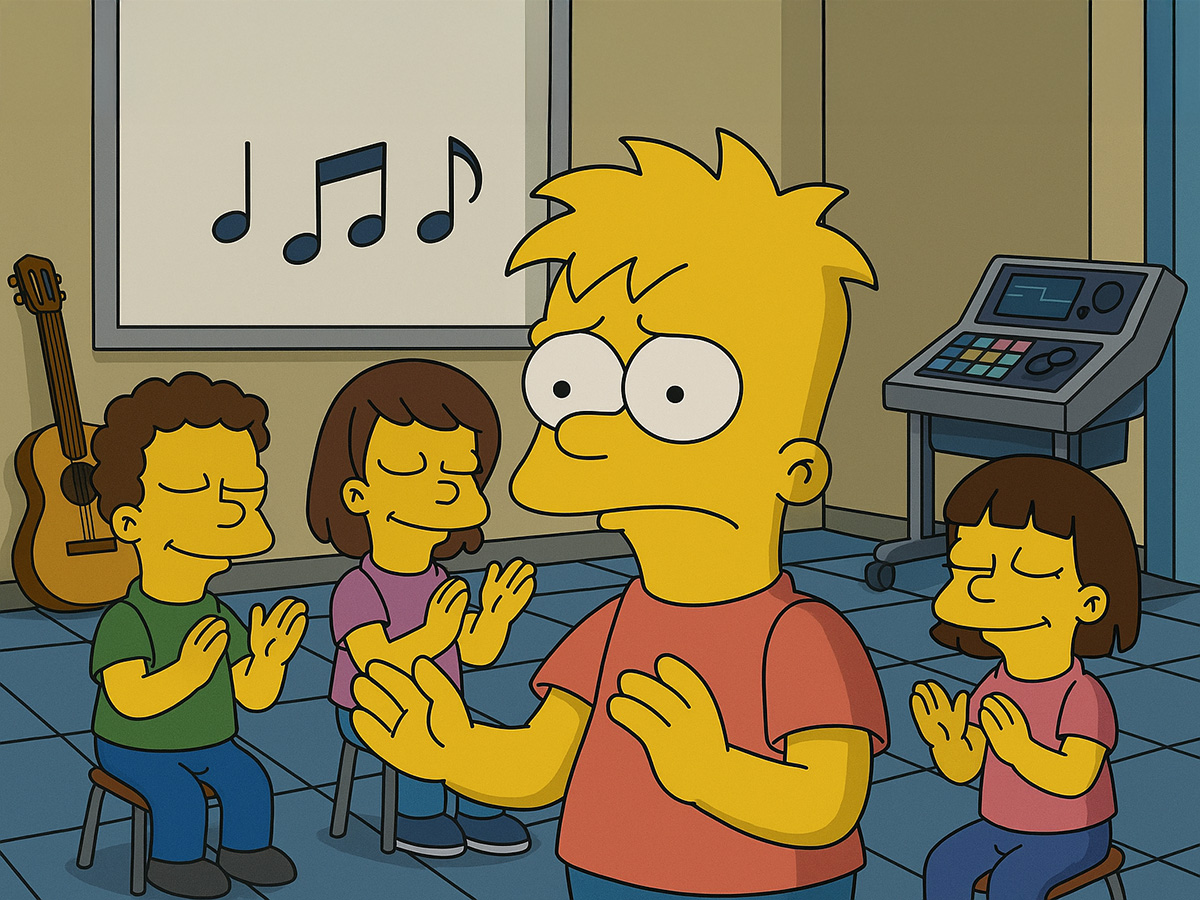
一方で、すべてが「できない」わけではありません。
いくつかの研究では、ADHDの人たちは即興的な演奏や、感情を込めた表現に優れていることが報告されています。
あらかじめ決められた譜面を正確に演奏するのではなく、その場の気持ちや雰囲気に合わせて自由に表現する力は、むしろ定型発達の人以上に豊かな場合もあります。
つまり、「苦手な部分がある一方で、得意な面もある」という、多面的な姿が見えてきたのです。
次に研究者たちが注目したのは、「音楽を聴くことで、ADHDの人たちの気分や行動がどう変わるか」という点です。
ADHDの人たちは、一般的に「脳の覚醒レベル」が低めだと言われています。
つまり、ぼんやりしていたり、集中しづらかったりするのです。
しかし、その状態を適度な刺激で「ちょうどよい状態」に持っていくと、集中力や作業の効率が高まるということが知られています。
ここで登場するのが「音楽」です。
研究によると、ADHDのある子どもたちにとって、自分の好きな音楽(たとえば、ロックやラップ)を聴きながら学習することで、むしろ集中力が高まり、テストの成績が良くなることがあるそうです。

一見、「うるさくて集中できないのでは?」と思われるかもしれませんが、ADHDの人にとっては、音楽がちょうどよい刺激となり、脳を「オン」にするスイッチのような役割を果たしているのです。
このような効果は、「モーツァルト効果」や「ホワイトノイズ」など、一般にも知られる現象とも関係がありますが、ADHDの人にとってはさらに個別性が高いという点も重要です。
ある人にはクラシックが効果的でも、別の人にはEDMの方が集中しやすいということもあるのです。
つまり、「どんな音楽が合うか」は人それぞれであり、そこに配慮することが大切だと研究者たちは述べています。
そして最後に、研究チームが注目したのは「音楽療法」の効果です。
音楽療法とは、音楽を使って心の安定や行動の改善を目指す方法で、最近では病院や学校、福祉施設などでも導入が進んでいます。
ADHDのある子どもたちに音楽療法を行ったいくつかの研究では、落ち着きが増し、衝動的な行動が減ったり、感情のコントロールがしやすくなったりしたという報告がありました。
また、音楽を通じて他者と関わる経験を積むことで、社会性が育まれることもあります。
たとえば、グループでの合奏やリズム遊び、歌のセッションなどでは、「相手の音を聴きながら、自分のタイミングを調整する」といったスキルが求められます。
これは、ADHDの人たちが苦手とする「順番を待つ」「人の話を聞く」「空気を読む」といった力を、楽しく、自然な形で身につける機会になります。

さらに驚くべきことに、音楽療法によって、ストレスホルモンの一つである「コルチゾール」の量が減少したというデータもありました。
つまり、音楽には「体の反応」にまで影響を与える力があるのです。
リラックス効果や幸福感の向上も報告されており、音楽が持つ力の大きさが改めて実感されます。
しかしながら、この分野の研究にはまだ課題もあります。
たとえば、研究の対象となった年齢層や性別、診断の基準、音楽のジャンルや使用方法などが、研究ごとにバラバラで、直接比較が難しいという点です。
また、参加者の数が少なかったり、研究期間が短かったりするものも多く、より大規模で長期的な研究が望まれています。
それでも、今回の系統的レビューは、これまでバラバラに報告されていた知見を一つにまとめることで、ADHDと音楽との関係をより立体的に理解する手がかりを与えてくれました。
そして、音楽という身近な手段が、ADHDの人たちにとっての「力」になり得ることが明らかになったのです。
「苦手を減らす」支援だけでなく、「得意を伸ばす」支援へ。
音楽は、そのための大きなヒントを私たちに与えてくれる存在です。
今後も、ADHDと音楽の関係をめぐる研究が進み、より多くの人に希望と可能性をもたらしてくれることが期待されます。
(出典:behavioral science)(画像:たーとるうぃず)
自閉症に音楽はとても良い。
そんな研究などはこれまでにもお伝えしてきましたが、ADHDにも良いんですね。
(チャーリー)