
この記事が含む Q&A
- 自閉症の成人がフィジカルアクティビティに参加しづらい主な要因は何ですか?
- ニューロノーマティブな前提・信頼の欠如・感覚過敏・過去のトラウマ経験など、個人・対人関係・環境・制度が複雑に絡むことです。
- 効果的な支援には、指導者がどのような点を重視し、どのようなアプローチを採用すべきですか?
- 個人の目的や体調・感覚ニーズを確認し、それに合わせた方法と安全・信頼・選択を重視するトラウマ・インフォームド・アプローチを取り入れることです。
- この研究の結論は、どのような場づくりが必要だと示していますか?
- 自閉症の成人が中年期でも健康で充実した生活を送るには、多様なニーズに対応できるフィジカルアクティビティの場を共同で作る必要がある、ということです。
自閉症のある成人にとって、日常的に体を動かすこと(フィジカルアクティビティ)は、心身の健康を保ち、生活の質を向上させるために重要な役割を果たします。
心臓や筋肉の健康の改善、気分の安定、睡眠の質の向上、ストレスの軽減、日常生活の動作能力の維持など、多くの恩恵が知られています。
しかし、実際には、自閉症の成人は非自閉症の人々と比べてフィジカルアクティビティへの参加率が低く、その背景や理由は十分に解明されていません。
とくに、36〜59歳の「中年期」にあたる人々の視点からこの問題を掘り下げた研究はほとんどありませんでした。
この英ダラム大学による研究では、イギリス在住の17人の自閉症の成人を対象に、2回ずつのオンライン面接を行い、フィジカルアクティビティに関する経験や考え方を直接聞き取りました。
参加者は全員が自閉症の診断(臨床診断または自己診断)を受けており、多くが注意欠如多動症(ADHD)、不安障害、うつ病、関節症、感覚処理の困難などの併存症も抱えていました。
フィジカルアクティビティの内容はウォーキング、ヨガ、ピラティス、サイクリング、ランニングなどさまざまでしたが、多くの人がグループ活動よりも個人で行う活動を好んでいました。
研究の分析には「社会生態学モデル(Socio-Ecological Model:個人、対人関係、環境、政策の4つの要素が行動に影響するという枠組み)」が用いられました。
このモデルを通じて、参加者の経験から、フィジカルアクティビティへの参加に影響を与える要因が複雑に絡み合っていることが明らかになりました。
参加者の語りから浮かび上がった大きなテーマは3つです。
- 「ニューロノーマティブな前提(neuro-normative assumptions:非自閉症的な価値観や考え方を当然とすること)」
- 「信頼(trust)」
- 「感覚過敏(sensory sensitivities:音や光、におい、触感などに敏感であること)」
これらは個別の要因として説明されますが、実際には互いに密接に関わり合いながら影響を及ぼしていました。
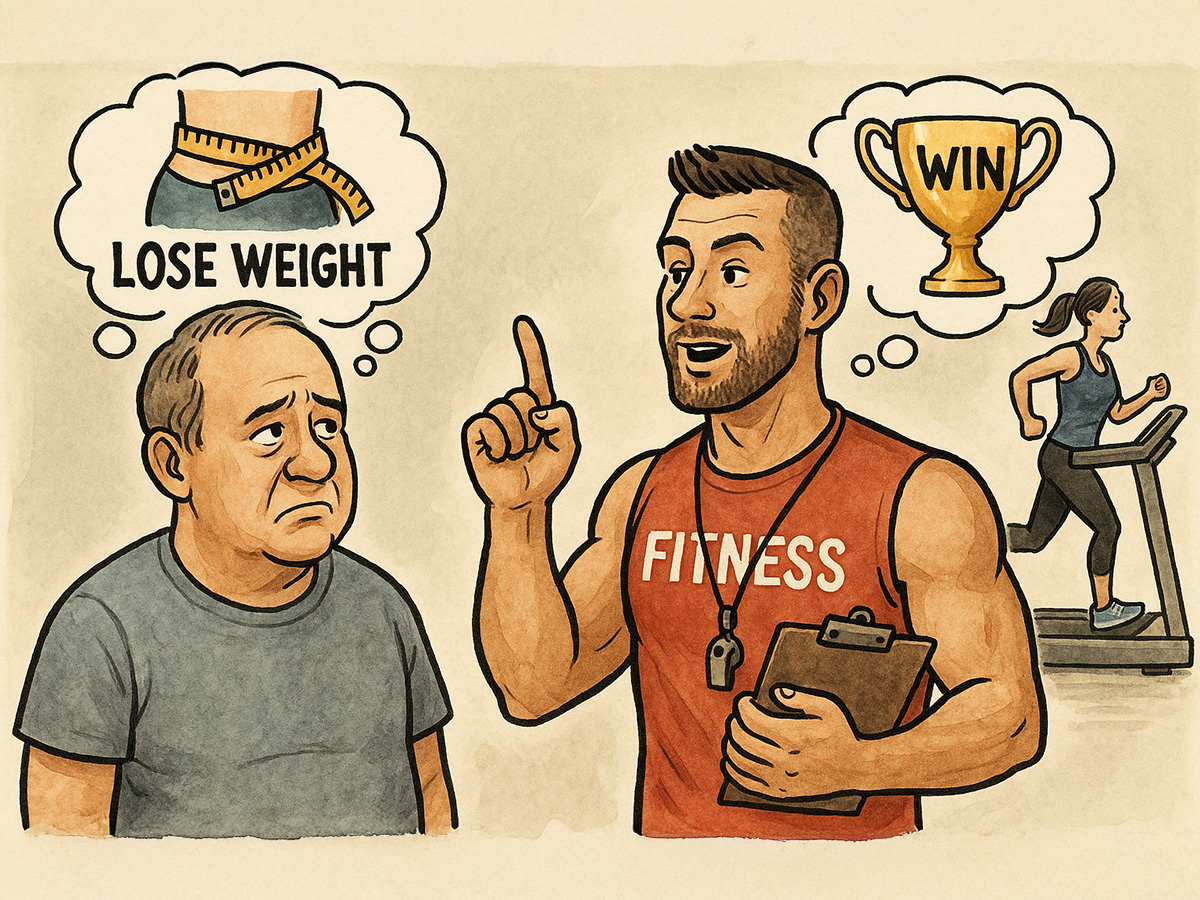
「ニューロノーマティブな前提」とは、フィジカルアクティビティの目的や方法を、非自閉症の社会で一般的とされる価値観だけで決めてしまうことです。
多くのフィットネス指導者やパーソナルトレーナーは、体重を減らす、外見を改善する、競技で勝つといった目標を当然とします。
しかし、参加者の多くは、精神的な健康の維持や体を動かす楽しみ、生活の質の向上を求めており、外見や勝敗へのこだわりはむしろ参加意欲を下げるものでした。
ある参加者は「ジムやクラスは痩せることや理想的な体型づくりばかり。50歳の私には関係ない。健康でいたいだけ」と語り、別の参加者は「勝つことばかり強調されると、負けたときの気持ちを考えていない」と指摘しました。
こうした価値観のずれは、指導者との信頼関係にも影響します。
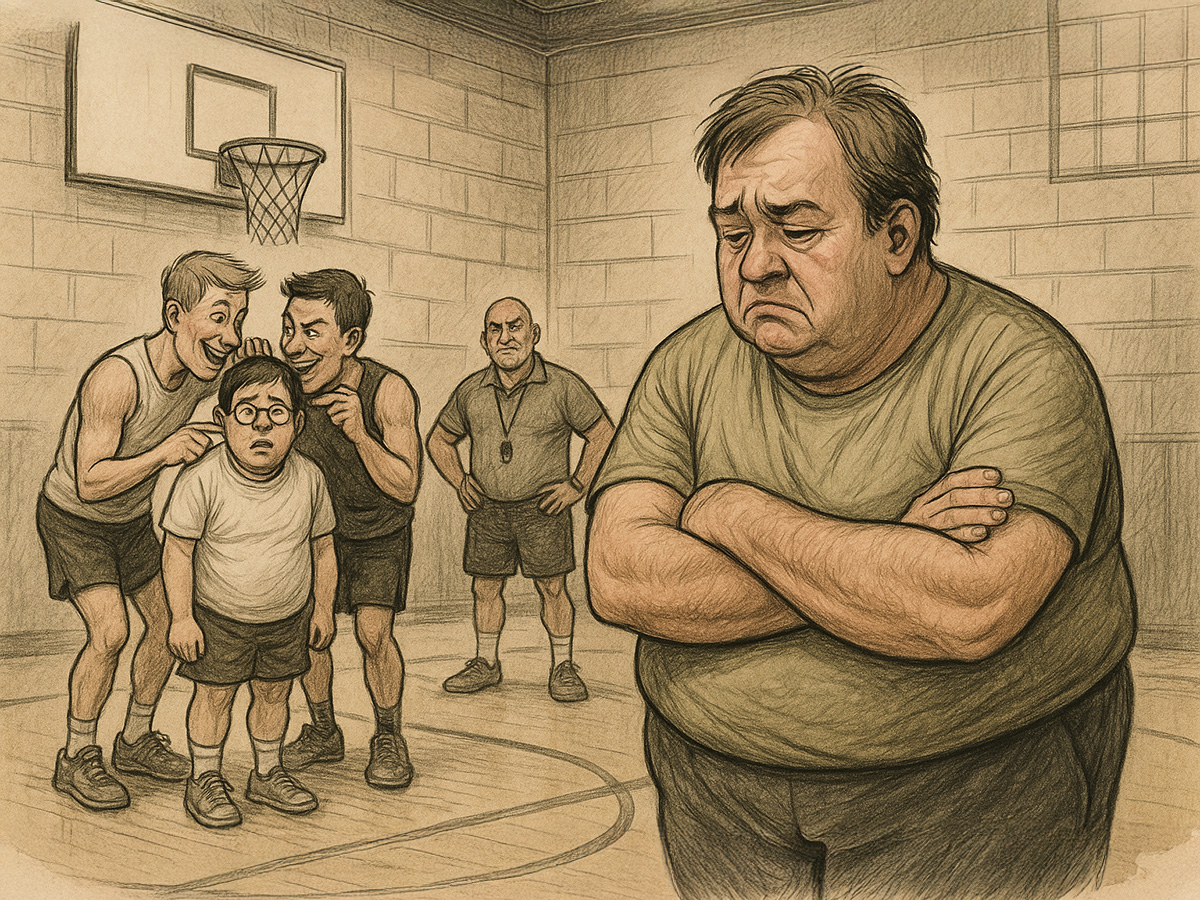
過去に体育の授業や運動の場でいじめや恥をかかされた経験を持つ人が多く、その記憶は成人しても消えず、フィジカルアクティビティの場に不安や不信感を抱かせます。
中には、性的なからかいや暴力を受けた経験もあり、そうした体験は特定の環境や人を避ける理由になっていました。
ある人は「体育の先生に体型をからかわれ、それ以来運動指導者を信頼できなくなった」と話しています。
さらに、感覚過敏も大きな障壁でした。
音への過敏さでは、大音量の音楽や金属音、複数の音源が同時に鳴る環境が耐えられず、ジムやスポーツ施設を避ける人がいました。
光への過敏さでは、蛍光灯や人工照明のまぶしさが集中を妨げ、自然光のある場所を好む人が多くいました。
触覚や嗅覚でも、運動用カーペットの感触や香水、柔軟剤、ゴムのにおいが不快で活動できなくなる人もいました。
これらが複数同時に起こると、脳が常に複雑な計算をしているような疲労感に襲われ、活動どころではなくなります。

参加者は、障壁を減らすためには、指導者がまず本人の目的や体調、その日のエネルギーの状態、感覚のニーズを確認し、それに合わせた方法を取ることが必要だと訴えました。
また、「トラウマ・インフォームド・アプローチ(trauma-informed approach:過去のつらい経験を理解し、それを再び引き起こさないよう配慮する方法)」の導入も有効だとされました。
これは、安全、信頼、選択の尊重、相互尊重を重視し、心理的にも安心できる環境を作る考え方です。
この研究は、フィジカルアクティビティへの参加の低さを「やる気がない」や「知識不足」など単純な理由に求めるのではなく、社会の価値観、個人の感覚特性、過去の経験、環境、制度といった多層的な要因が絡み合っていることを明らかにしました。
そして、自閉症の成人が中年期でも健康で充実した生活を送るためには、こうした多様なニーズに対応できるフィジカルアクティビティの場を共に作り上げる必要があると結論づけています。
(出典:Autism DOI:10.1177/13623613251360)(画像:たーとるうぃず)
自分にあった環境(自宅内とか、一人で外に散歩なども)で、無理せず運動ができたらいいですね。
私は、一人とぼとぼ重い足取りで、よくジョギングをしています。
(チャーリー)





























