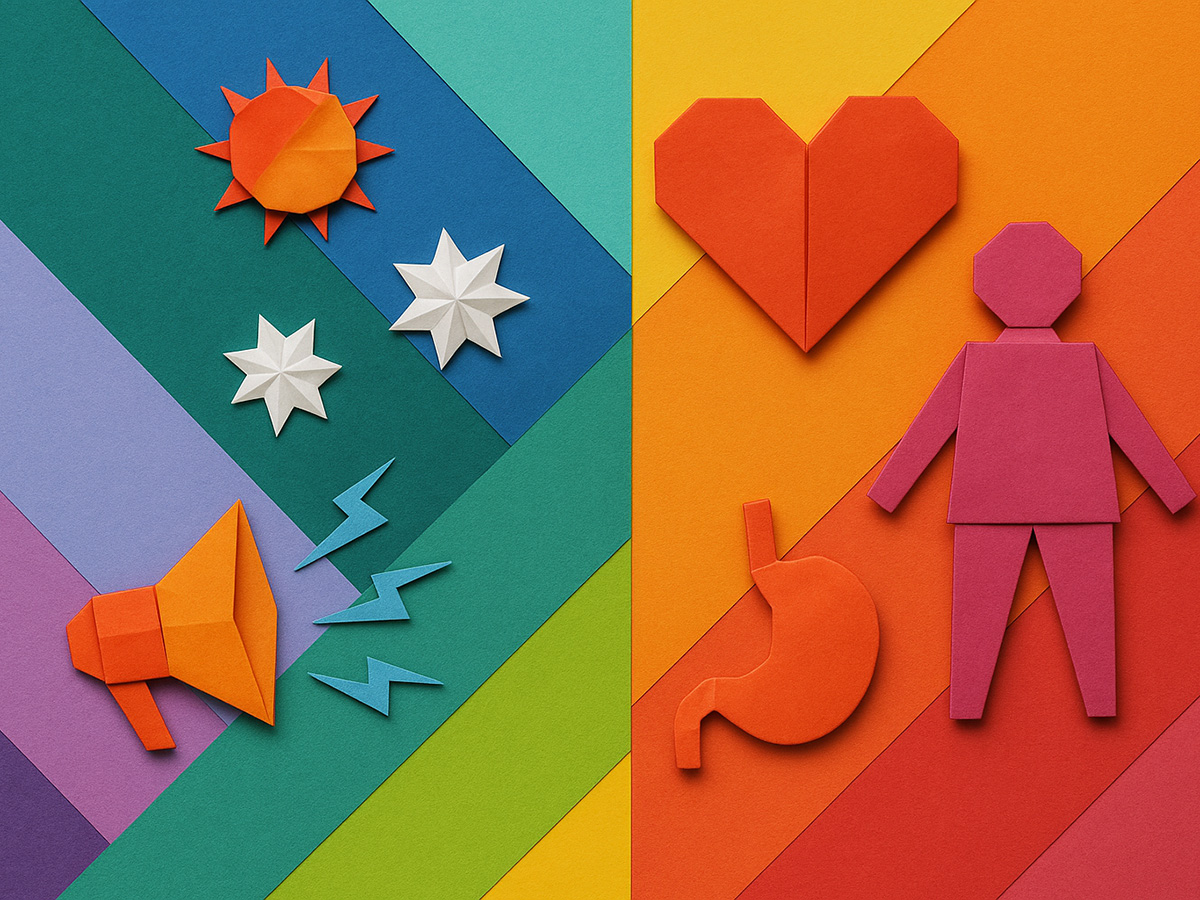
この記事が含む Q&A
- モノトロピズムとは何ですか?
- 注意の向きがひとつのことに深く集中する傾向で、外受容と内受容の視点から感覚の感じ方の違いを説明する考え方です。
- なぜ自閉症の反応は「冷たい」と捉えられがちですが、それはどういう理由からですか?
- 感情の欠如ではなく、注意と感覚の働き方の違いによるものとして説明されています。
- 具体的に日常でどんな支援が有効ですか?
- 予定を見える形で示す、話す情報を一度に一つずつ伝える、音や光が強い場所を避け静かな場所を一緒に探す、などの工夫が有効です。
自閉症のある人が、なぜ周囲と世界の見え方や感じ方がちがうのか——。
それを「心の理論」や「社会性の障害」といった言葉で説明しようとしても、どうしても届かないものがあります。
今回オーストラリアのカーティン大学の研究チームがまとめた論文は、その届かない部分を「内側から見た理解」で照らし出そうとしています。
彼らが注目したのは、「モノトロピズム」という考え方です。
モノトロピズムという言葉は少しかたく聞こえますが、意味はとてもシンプルです。
モノ(ひとつ)+トロピズム(向き)という言葉のとおり、「注意の向きがひとつのことに深く集中する傾向」を指しています。
自閉症の人が見せるさまざまな行動——ひとつのテーマに没頭すること、切り替えが難しいこと、感覚に敏感だったり鈍感だったりすること、人とのやり取りのテンポがずれること。
それらをすべて「問題」ではなく、「注意の向き方の違い」として見直してみようという提案です。
たとえば、まわりの音や光。
ある人にとっては気にもならない空調の音が、ある人には強く響き、頭の中に広がってしまうことがあります。
一方で、夢中になって本を読んでいるときには、同じ音がまったく聞こえなくなることもあります。
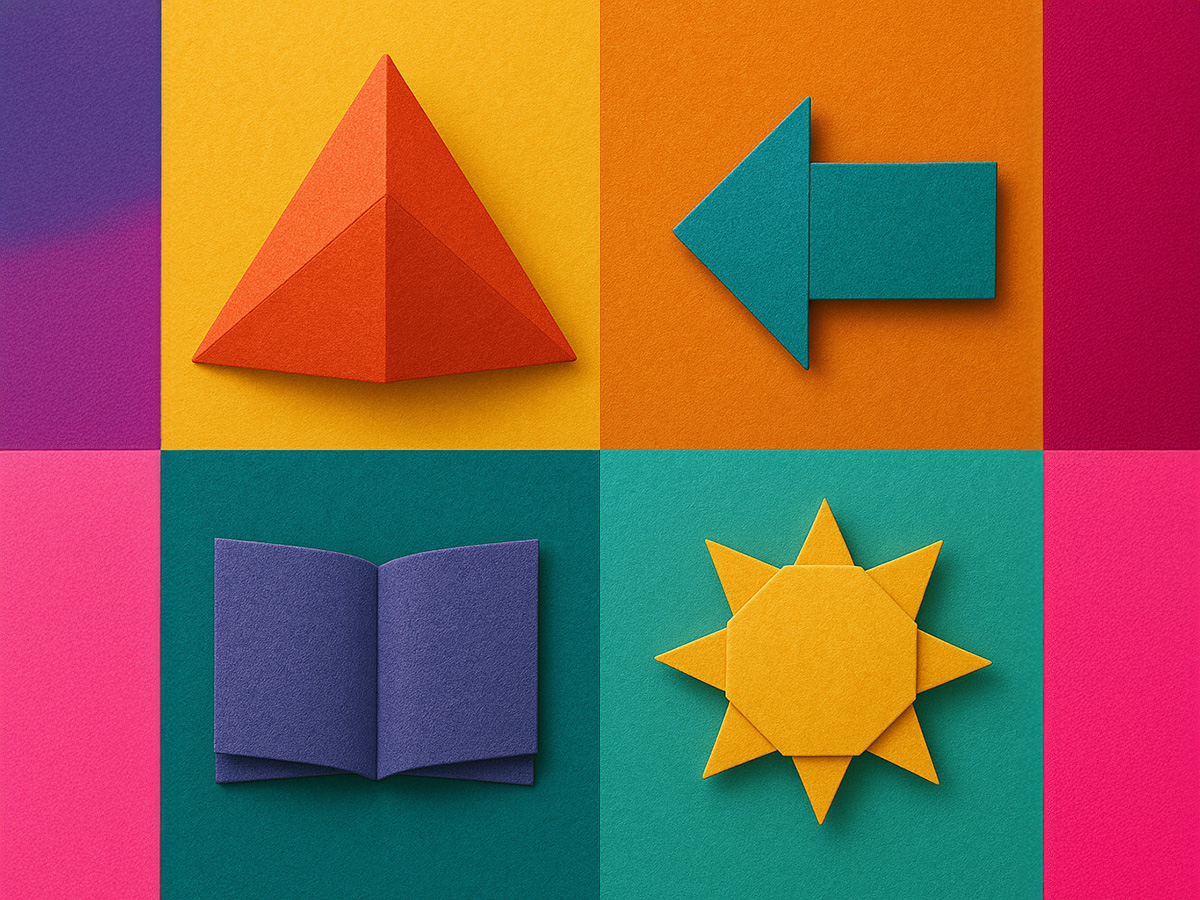
モノトロピズムの視点では、これは「感じ方の異常」ではなく、注意の焦点がどこに向いているかによって、世界の音や光の入り方が変わるという「自然な違い」です。
感覚の世界には「外側」と「内側」があります。
外側の感覚——たとえば音や光、触れる感じ——を「外受容(がいじゅよう)」といい、内側の感覚——お腹の空き、体のだるさ、心臓のドキドキ——を「内受容(ないじゅよう)」といいます。
注意がひとつのことに深く向かっているとき、人は外側の感覚には敏感でも、内側の合図には気づきにくくなります。
たとえば、遊びや作業に集中している間に、お腹がすいているのに気づかない、トイレを我慢してしまう、気持ちの変化を感じ取れずに急に爆発してしまう——そうした経験を説明できるのがこの視点です。
つまり「感情をコントロールできない」のではなく、「体や心の信号を受け取るタイミングがずれている」。
そこに焦点を当てると、支援や理解の仕方も変わってきます。
論文ではもうひとつ、「見えなくなっても、そこにあると感じられる力」についても触れています。
心理学ではこれを「対象の永続性」と呼びます。
たとえば、親が部屋を出ていっても、子どもは「お母さんはまだ存在している」と頭の中で保つことができます。
ところが、自閉症の人の中には、その「存在の手ざわり」が薄れやすい人がいます。
好きな物やいつもの場所が変わると、それが「なくなった」と感じてしまい、強い不安に包まれることがあるのです。
逆に、誰かの死の知らせを聞いても、その人がもういないという実感がなかなか追いつかない。日々のルーティンが変わって初めて、深い悲しみが押し寄せてくる——。
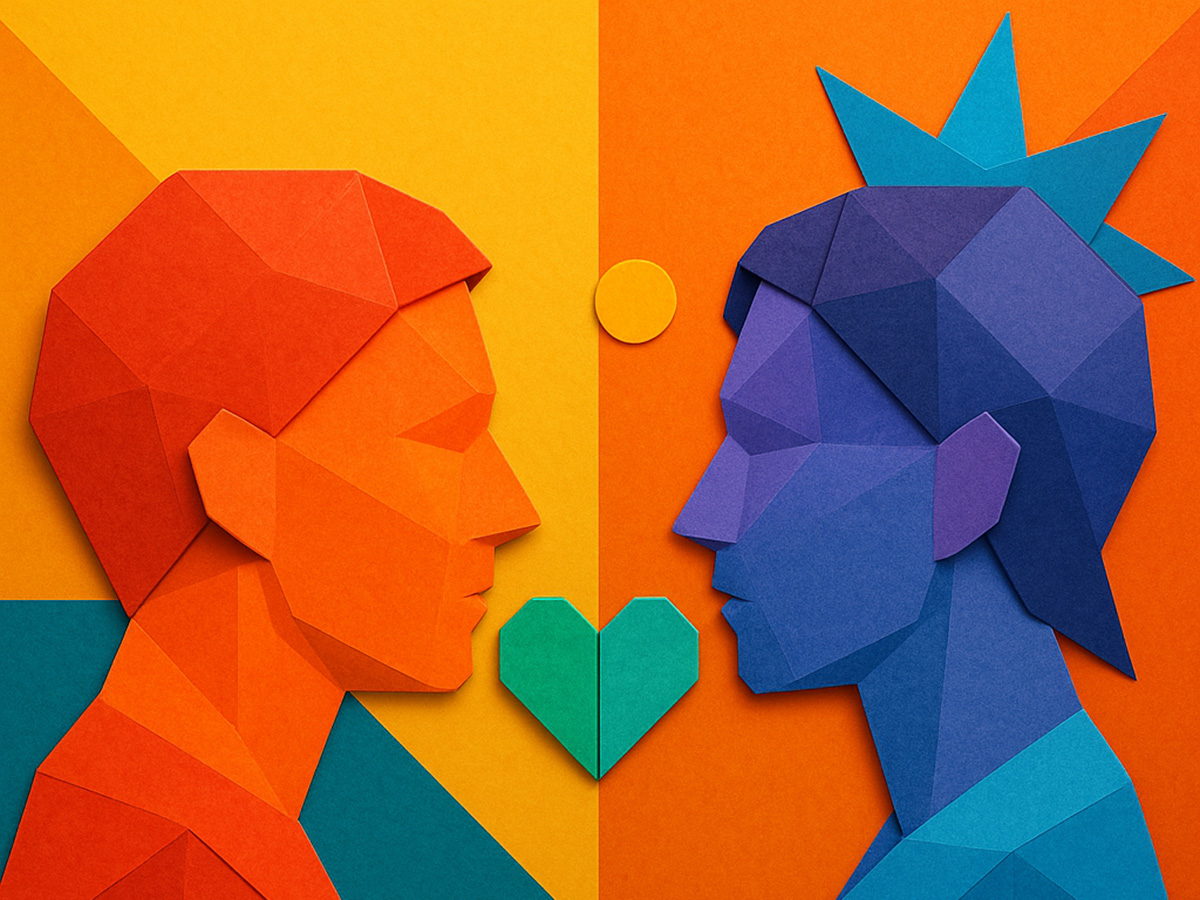
そうした反応を「冷たい」「感情がない」と見なすのは間違いだと、研究者たちは言います。
それは「感じ方の欠如」ではなく、注意と感覚の働き方の違いによるものだからです。
自閉症のある人と、そうでない人のあいだには、「共感のずれ」が生じやすいことが知られています。
でもそのずれは、「心を読めない」からではありません。
同じ場面を見ていても、どの手がかりに注意を向けるかが違うだけなのです。
たとえば、ある人は相手の目の動きや声の調子に注目し、もう一人は言葉の内容や背景の物音に集中する。
同じ空間でも、拾っている世界が違う。
この違いが積み重なると、「分かり合えない」という誤解が生まれます。
研究者たちはこれを「ダブル・エンパシー(ふたつの共感のすれちがい)」と呼び、どちらが悪いのでもなく、「前提としている世界の切り取り方が違う」だけだと説明します。
この考え方が教えてくれるのは、「治す」ではなく「調整する」という視点です。
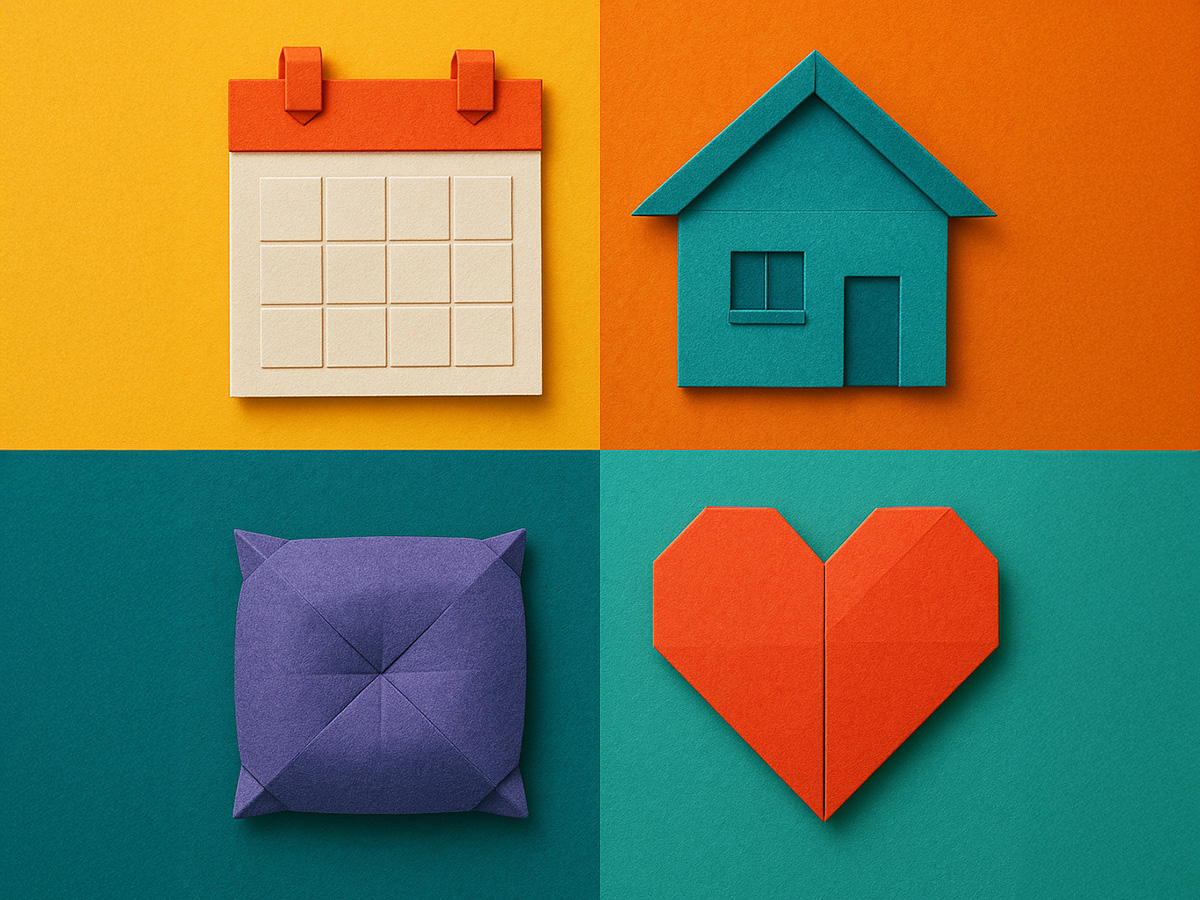
たとえば、予定が変わるときには、いきなり言うのではなく、その変化が見えるように時間をかけて伝える。
話すときは、同時にたくさんの情報を投げず、一つずつ、順番に。
感覚が乱れやすい場所(音が大きい・光が強い)では、少し静かな場所を一緒に探す。
こうした配慮は「特別扱い」ではありません。
相手の集中の流れを壊さず、安心して次の行動に移れるようにするための工夫です。
モノトロピズムという考え方は、日常の小さな困りごとを「性格の問題」ではなく、「注意の向き方の違い」として説明してくれます。
それは、責めるためではなく、理解と工夫の出発点にするための言葉です。
家庭でもできることがあります。予定を見える形で示すカレンダー、好きな物を置く「安心の場所」、疲れを感じる前に休むリズム。
そうした環境の工夫が、「気づける」「切り替えられる」力を支えます。
また、自分自身を責めすぎないことも大切です。
うまくできない日があっても、「集中が深いからこそ、まわりを見落とすこともある」と受けとめる。
それが「自己へのやさしさ(セルフ・コンパッション)」です。

研究チームは、モノトロピズムを「特別な理論」ではなく、「当事者が世界を説明するためのレンズ」として紹介しています。
これまでの研究では、自閉症を「欠けたもの」として語ることが多くありました。
母親の育て方が原因だとされたり、「男性的な脳」といった一面的な説明で括られたり。
しかし近年は、多様な脳のあり方を価値としてとらえる「ニューロダイバーシティ」という考え方が広まり、自閉症の理解は大きく変わり始めています。
モノトロピズムは、そうした流れの中で、当事者の経験と研究をつなぐ「ことば」として注目されています。
この論文のメッセージは明確です。自閉症の理解を「外からの観察」で終わらせず、「内側からの経験」を研究の中心に置くこと。
一人ひとりの集中の流れや、世界の感じ方を尊重すること。
そして、「どうすればもっと生きやすくなるか」を、本人・家族・支援者が一緒に考えていくこと。
そのために私たちができる最初の一歩は、「ちがいをなおす」のではなく、「ちがいを支える」ことです。
モノトロピズムの視点は、そのためのやさしい道しるべになります。
(出典:Frontiers in Psychiatry DOI: 10.3389/fpsyt.2025.1664507)(画像:たーとるうぃず)
>私たちができる最初の一歩は、「ちがいをなおす」のではなく、「ちがいを支える」
大賛成です。
(チャーリー)





























