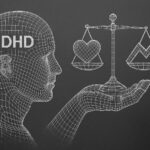この記事が含む Q&A
- ADHDのある人が職場で直面する主な困難は、締切厳守や細部への注意、長時間の会議・デスクワークが求められる点ですか?
- はい、職場の設計がADHDの脳の特性に合わせられていない点が大きな困難の原因です。
- どの職種がADHDの人にとって負担になりやすいですか?
- 具体的にはデータ入力・編集・イベントプランナー・長距離トラック運転手・コールセンター・一般的な事務職など、細部管理や長時間集中を要する仕事が負担になりやすいです。
- ADHDの人が職場で活躍するにはどうすればよいですか?
- 環境・文化・配慮を整え、普遍的デザインのカーブ効果を取り入れることで、ADHDの人も活躍できる職場になります。
ADHDのある人たちは、仕事においてさまざまな困難に直面しやすいことが知られています。
その理由のひとつは、社会の多くの職場環境や仕事の進め方が、ADHDの脳の特性に合わせて設計されていないからです。
統計的にも、ADHDのある人は就業率が低く、フルタイム勤務の割合も少なく、収入も低くなりやすい傾向があります。
これは、締め切り厳守や細部への注意、長時間の会議への集中、長時間のデスクワークなど、ADHDで苦手になりやすい要素が、多くの仕事に必須とされているためです。
ADHD当事者スズ・ベラ・バローズは仕事の中でADHDの人を支援しており、「神経多様性のある人は“ウィジェット化”しない」と表現します。
これは、企業の機械的な歯車の一部としてきっちり収まることが難しいという意味で、「このミスマッチはお互いの歯車をきしませます。
とくに私たちの歯車を!」と語ります。
もちろん、ADHDといっても一人ひとり特性や強み、苦手は異なります。
しかし傾向として、特定の職種はADHDの脳にとってとくに負担になりやすい場合があります。
ここからは、その例をいくつか紹介します。
ただし、ここに挙げる仕事がすべての人に当てはまるわけではなく、逆に得意とする人もいます。
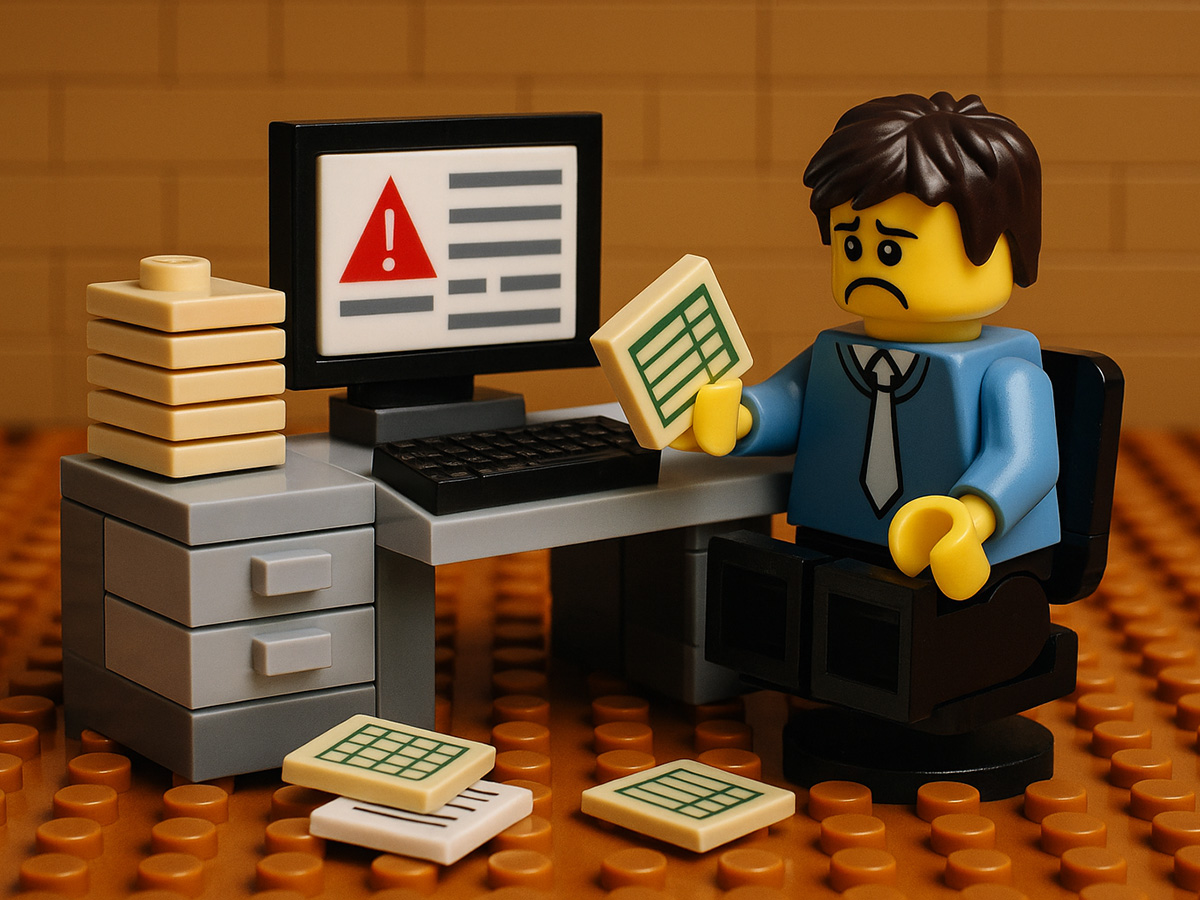
1.データ入力や処理の仕事
まず、データ入力や処理の仕事は細部への注意力や正確さが求められます。
ADHDの診断基準でも最初に挙げられる不注意の症状として、「細部に注意を払えず、不注意な間違いをする」があります。
こうした特性があると、精密さが命の仕事は負担になりやすく、また単調で刺激の少ない作業は集中を保つのが難しい場合があります。
逆に、新しい刺激や変化のある環境では力を発揮しやすい傾向があります。
2.編集や校正の仕事
編集や校正の仕事も似た課題があります。
細かなミスを見つけるために全体ではなく細部を見続ける必要があり、ADHDの人にとっては疲れやすい作業です。
加えて、新しいことに惹かれる傾向から、すでに作られた文章を繰り返し見直す作業はモチベーションを保ちにくくなります。
3.イベントプランナー
イベントプランナーも高い組織力と細部管理が必要です。
多くの期限やタスクを同時に覚えて進める必要があり、意思決定も頻繁に求められます。
会議や予算管理も多く、こうした要素がADHDの苦手と重なることがあります。

4.長距離トラック運転手
長距離トラック運転手は、ADHDの人が交通事故のリスクを高めるという長期研究結果とも関係します。
安全運転には持続的な注意力や衝動抑制が必要であり、単調な道を長時間運転することは集中力の低下や眠気を招きやすくなります。
5.コールセンターやカスタマーサポートの仕事
コールセンターやカスタマーサポートの仕事も繰り返しが多く、厳しい管理体制の中で働く必要があります。
さらに、怒った顧客への対応は感情の自己調整を必要とし、拒絶過敏性(RSD)がある人にとってはとくに消耗しやすい状況です。
6.一般的な事務職
一般的な事務職も、長時間座って作業することや会議での集中、組織立った作業が求められるため、落ち着きのなさや多動傾向のある人には負担になります。
バローズは「ADHDの人は軽い仕事や監督を増やすより、むしろ複雑な課題、明確な期限、そして自律性を必要としている」と述べます。
とはいえ、もし憧れの職業がこのリストにあっても、あきらめる必要はありません。
多くの仕事は環境ややり方を工夫することで続けられます。

米国ではADHDは障害として法的に認められており、職場での合理的配慮を求める権利があります。
また、雇用主が柔軟であれば、従業員自身がスケジュールや作業環境を調整することで働きやすくできます。
バローズは、職場づくりを考えるうえで「カーブ効果」という考え方が重要だと指摘します。
これは、特定の人のために行った改善が、結果としてすべての人にとって使いやすくなる現象のことです。
もともとは歩道の段差をなくす“カーブカット”から生まれた言葉で、車椅子利用者のための設計が、ベビーカーや自転車、荷物を運ぶ人にも役立った事例に由来します。
職場でも、ADHDの人のために用意したノイズキャンセリングヘッドフォンが、集中したい他の社員にも恩恵をもたらすように、全員にメリットが広がります。
こうした普遍的デザインは、特別扱いではなく、職場全体の生産性や士気を高める仕組みとして機能します。
最終的に、ADHDの人がその職場で活躍できるかどうかは、仕事そのものよりも、環境・文化・配慮のしやすさといった条件に大きく左右されます。
適切な理解と柔軟な対応があれば、多様な脳の特性を持つ人が互いの歯車をうまくかみ合わせて働ける職場は十分に可能なのです。
(出典:verywell mind)(画像:たーとるうぃず)
「カーブ効果」
たしかにそのとおりです。ADHDなど発達障害の方に良いと思われることは、そう診断されていない多くの人にとっても良かったりすることは多くあると思います。
企業全体にとってメリットがあるはずです。
(チャーリー)