
この記事が含む Q&A
- IVR訓練とはどのような取り組みですか?
- 自閉症の子どもが日常生活で必要なスキルを、安全な仮想環境で反復的に練習するVR訓練です。
- どの場面を体験したのですか?
- 地下鉄、スーパーマーケット、家庭、遊園地の4場面で指示の理解・判断・行動の順序づけを練習しました。
- 研究の効果はどのように示されましたか?
- 完了率の高さと得点・所要時間の改善、対人関係の困難や実行機能の改善が保護者報告で見られましたが、対照群なしなどの留意点もあります。
中国・上海交通大学医学院と上海市精神衛生センターの研究チームは、自閉症の子どもや青年を対象にした新しい取り組みを行いました。
それは、日常生活で必要なスキルを「イマーシブ・バーチャルリアリティ(IVR)」という技術を使って練習する試みです。
この研究は、親にとっても子どもにとっても関心の高い「生活の中で役立つ力を育てる」ことに焦点を当てていました。
参加したのは、8歳から18歳までの33人の子どもたちです。
いずれも知能指数が80以上で、高機能自閉症と診断されていました。
研究チームは、彼らに週1回、1時間のセッションを6〜10回受けてもらいました。
すべてのセッションで36種類の課題が用意されており、それを2周体験するというプログラムでした。
つまり、同じ課題を繰り返すことで「慣れ」や「学びの定着」を確認できるようにしたのです。
研究方法は「単群前後比較」と呼ばれるもので、子どもたちが訓練を始める前と終えた後を比べて変化を見ました。
対照群は設けられていませんが、その代わりに評価を多面的に行いました。
質問紙によって保護者が子どもの行動を評価し、実行機能を測る質問紙(BRIEF)を用い、さらに注意力や記憶、表情認識を測る認知課題を加えました。
加えて、保護者への半構造化インタビューを行い、数値では表しきれない日常の変化を記録しました。
これらを組み合わせることで、子どもの行動を立体的に捉えようとしたのです。

VRのシステムも特別に設計されていました。
ヘッドセットとコントローラを使うだけでなく、全方向に歩けるトレッドミルを組み合わせることで、実際に歩いたり動いたりしながら体験できるようになっていました。
単に映像を眺めるのではなく、自分の体を使って没入的に参加できる仕組みです。
この点が、従来の「画面を見るだけの練習」と大きく違っていました。
体験する場面は「地下鉄」「スーパーマーケット」「家庭」「遊園地」という4つでした。
地下鉄では改札を通り、切符を扱い、車内アナウンスを聞き取りながら行動します。
スーパーでは商品を選び、量り売りを利用し、レジで会計します。
家庭では持ち物を整理したり、危険なものを見分けたりします。
遊園地では地図を見て目的地を探し、友人との会話を通じて適切な反応を選ぶ場面がありました。
これらの課題にはすべて共通点があります。
それは「指示を覚え、状況に合わせて判断し、順序立てて行動する」ということです。
子どもたちが日常でつまずきやすい部分をそのまま再現し、繰り返し体験できるようにしてありました。

結果を見てみましょう。
全体の課題完了率は87.9%でした。
深刻な副作用はなく、安全性が確認されました。
初めのうちは酔いや疲労、ヘッドセットの違和感を訴える子どももいましたが、回を重ねるごとに慣れて快適さが増していきました。
成績面では、2周目に入ると平均得点が5.5%上昇し、課題の完了時間はおよそ30%も短くなりました。
迷いながら行っていた行動が、次第に素早く正確になっていったのです。
これは「知識が理解され、行動として定着していった」ことを意味します。
保護者が回答した質問紙では、自閉症の症状の中でも「対人関係」の困難が減ったことが示されました。
また、行動の調整や感情の切り替え、計画性や記憶といった実行機能の改善も見られました。
認知課題の結果では、反応速度が速くなり、表情を素早く認識できるようになっていました。
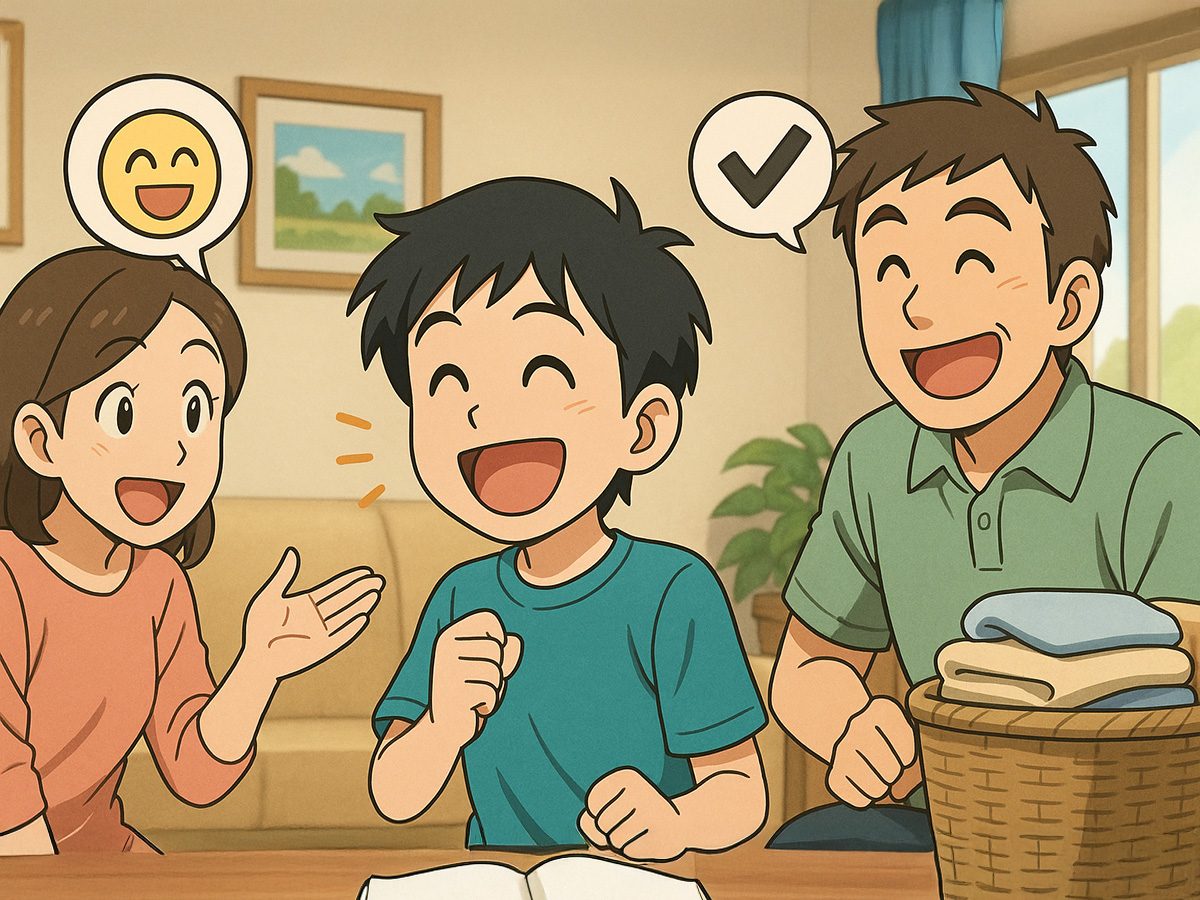
保護者へのインタビューでは「会話ややり取りが増えた」「笑顔や冗談が増えた」「感情のコントロールが良くなった」という声が聞かれました。
さらに「危険に気づくようになった」「家事を思い出して手伝えるようになった」といった日常生活に直結する変化も報告されています。
この研究の大きな特徴は、単なるゲーム感覚ではなく、実際の生活に近い複雑な状況を安全に繰り返し練習できるところにあります。
自閉症の子どもは知識を持っていても、それを現実の場面で柔軟に使うことが難しいことがあります。
静かな環境で学んだことが、人混みや騒がしい場所では崩れてしまう。
そんな場面をVRで再現し、練習できることがこの訓練の強みでした。
一方で、この研究には課題もあります。
まず、対照群が設けられていないため、自然な成長や学校・家庭での経験と切り分けるのが難しい点があります。
また、評価の一部はVR内での得点や時間であり、現実世界のスキル評価と完全に一致しているわけではありません。
さらに、どのくらい効果が持続するのか、長期的な追跡はまだ行われていません。

それでも、この研究が示す意義は大きいものです。
日常の行動を「部分」ではなく「流れ」として練習することで、実生活に変化が現れやすいことが示されました。
買い物や移動といった行動を一連のシーンとして繰り返し練習すること。
課題の中に「予想外の出来事への対応」や「相手の反応を見る会話」を組み込むこと。これらが効果を高める要素だと考えられます。
まとめると、IVR訓練は自閉症の子どもにとって、日常生活のスキルを安全に反復しながら身につけるための新しい方法です。
今回の研究では、課題の効率化、対人関係の改善、実行機能や感情調整の向上といった成果が示されました。
まだ長期的な効果の検証は必要ですが、家庭や学校と連携して活用すれば、大きな可能性を持つ実践的な手法といえるでしょう。
(出典:Frontiers DOI: 10.3389/fpsyt.2025.1570437)(画像:たーとるうぃず)
「全方向に歩けるトレッドミル」
ヘッドセットからの映像だけでなく、体を動かせることでよりリアルに、より深く学べそうです。
危険を知る。
とくにこれは重要です。VRのような安全な環境であれば、それがよく学べます。
(チャーリー)





























