
この記事が含む Q&A
- ADHDの人の強みにはどんな例があり、研究は何を示していますか?
- ハイパーフォーカス、ユーモア、クリエイティビティなどが強みとして高く評価され、強みの認識は幸福感や生活の質と関連することが示されています。
- 強みを理解して活かすことはADHDにどんな影響を与えますか?
- 自分の強みを理解し活かすことは幸福感や生活の質、メンタルヘルスの改善に寄与する普遍的な要素とされています。
- 強みを活かす際の注意点や限界はありますか?
- 研究にはオンライン募集や自己評価の限界があり、知るだけでなく日常で活かすことが大切だと示されています。
ADHDというと、多くの人は「集中できない」「落ち着かない」「忘れっぽい」といった困難の面を思い浮かべるかもしれません。
しかし近年、研究の世界では、ADHDを「欠点の集合」ではなく「特性のあり方」として捉える動きが広がっています。
その中心にあるのが、「ストレングス・ベースド(強み重視)」という考え方です。
つまり、人がもつポジティブな特性や能力に焦点を当てることで、より良い生活の質や幸福感につなげようという視点です。
この考え方はもともと自閉症研究で発展してきました。
自閉症の人が持つ「細部への注意力」「論理的思考」「パターン認識」などを活かすことで、教育や就労での満足度が高まるという研究が次々に報告されています。
しかしADHDに関しては、創造性に関する研究が中心で、強みの全体像はまだよくわかっていませんでした。
そこで、イギリスのバース大学とオランダのラドバウド大学医療センターの共同研究チームは、成人ADHDの「心理的強み」がどのように幸福感や生活の質に関係するのかを大規模に調べました。

研究チームは、イギリス国内でADHDの診断を受けた成人200人と、ADHDのない成人200人をオンラインで募集しました。
どちらのグループも性別、年齢、学歴、社会経済的地位ができるだけ同じになるように調整されています。
ADHD群では、全員が医師または心理士による正式な診断を受けており、ADHD自己評価尺度(ASRS)でも診断基準を満たしていました。
参加者はまず、ADHDに関連すると考えられてきた25項目の「心理的強み」について、自分にどの程度あてはまるかを7段階で答えました。
たとえば「クリエイティブ」「ハイパーフォーカス(特定のことに強く集中できる)」「ユーモア」「柔軟」「直感的」「社交的」「エネルギッシュ」「イメージ思考」などです。
さらに、自分の強みをどの程度理解しているか(ストレングス認識)と、日常でそれをどのくらい活かしているか(ストレングス活用)をそれぞれ測定しました。
そのうえで、幸福感、生活の質(身体・心理・社会・環境の4領域)、うつ・不安・ストレスなどのメンタルヘルス指標も併せて評価しました。
結果は興味深いものでした。
まず、ADHD群は非ADHD群よりも平均してやや多くの「強み」を自覚していましたが、その差は大きくはありませんでした。
個別に見ると、「ハイパーフォーカス」「ユーモア」「クリエイティビティ」「イマジネーション(想像力)」「自発性」「直感」「チャンスを見抜く力」「幅広い興味」「イメージで考える力」「なんでも挑戦してみる姿勢」など10項目では、ADHD群のほうが有意に高く評価していました。

これは、従来の研究で指摘されてきた創造性や発想力の高さを裏づけるものです。
一方で、「粘り強さ」だけは非ADHD群のほうが高く、衝動性の高さが根気の持続を難しくする傾向を示していました。
興味深いのは、「自分の強みをどれだけ理解しているか」「日常でどれくらい使っているか」という点では、ADHD群と非ADHD群にほとんど差がなかったことです。
つまり、ADHDの人たちも自分の強みに気づき、それを使おうとする姿勢は同じくらいあるのです。
ただし、幸福感や生活の質についてはADHD群の方が全体的に低く、メンタルヘルス上の症状(うつ、不安、ストレス)は高い傾向が見られました。
それでも、「強みを知っていること」や「強みを使っていること」は、両グループに共通して幸福感の高さや生活の満足度、メンタルヘルスの良好さと関連していました。
とくに、「自分の強みを意識していること」はほぼすべての指標でプラスの影響を示しました。
たとえば、「自分の強みをよく理解している」と答えた人ほど、人生の満足度が高く、うつやストレスの得点が低かったのです。
一方、「強みを使うこと」は幸福感や心理的・社会的な生活の質を高める効果が見られましたが、すべての領域で同じほど強いわけではありませんでした。
ADHD群の中だけを取り出して分析すると、「強みをよく使っている」と答えた人は、「強みをよく知っている」人よりも、全体的な生活の質が高い傾向を示しました。
つまり、知っているだけでなく、日常の中でそれを積極的に活かすことが大切だといえます。
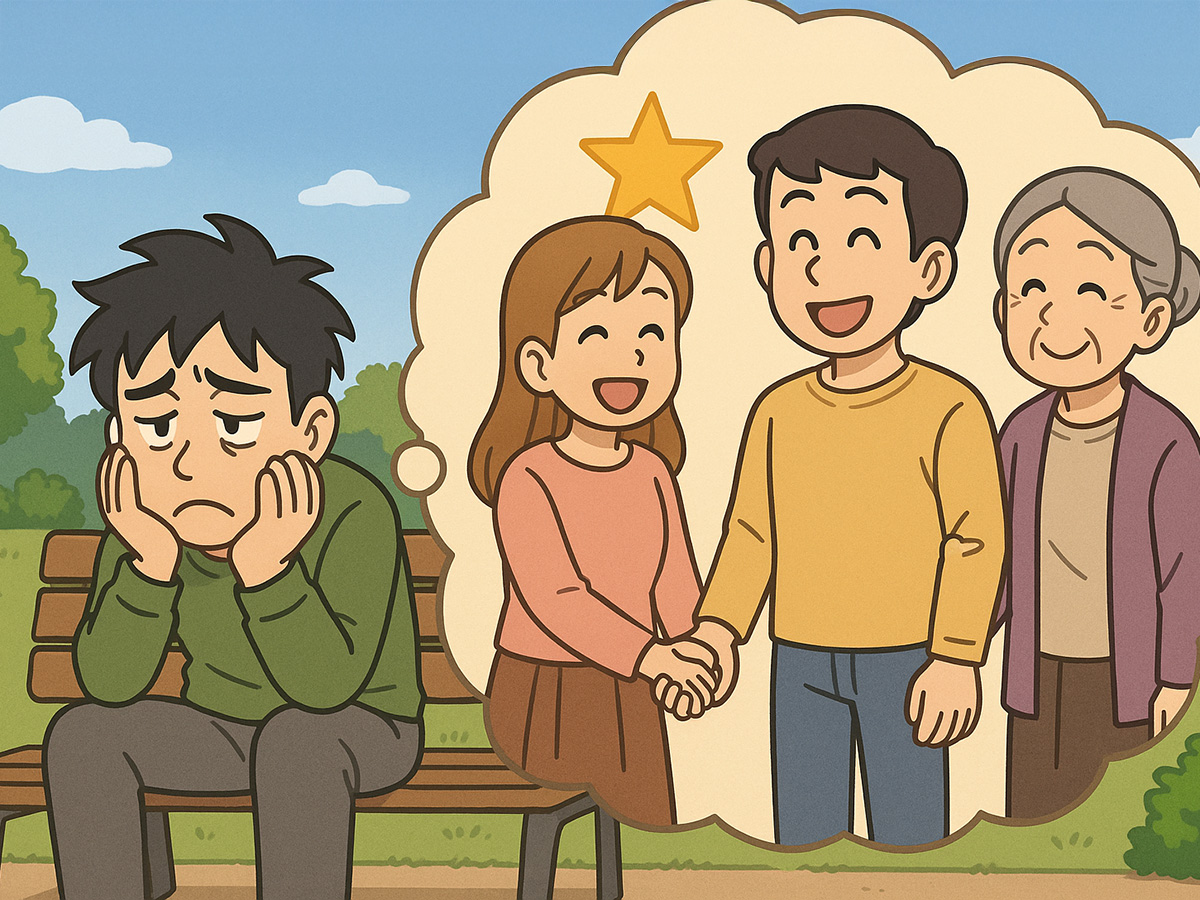
さらに重要なのは、ADHDの症状の重さ(不注意や衝動性の程度)は、この「強みの効果」に影響していなかったという点です。
症状が軽くても重くても、「強みを意識し」「活かす」ことができれば、生活の質が高まる傾向が見られたのです。
研究チームはこの結果を、「自分の強みを認識し、それを活かす力は、ADHDの有無を問わず幸福感を高める普遍的な要素である」とまとめています。
強みを活かす習慣は、うつのリスクを下げ、仕事や人間関係での満足度を高める可能性があります。
実際、一般の人を対象にした心理学研究でも、自分の強みを日常で活用することがポジティブな感情や人生満足度を高めるという結果が報告されています。
この研究は、ADHDを「欠点」からではなく「特性」から理解する新しい方向性を強く示しています。
創造的で、柔軟で、直感的。時に衝動的であっても、そのエネルギーや発想力が他の人にはない強みになる。
こうした特性を自分で理解し、日々の中で活かすことが、幸福や生活の質を支える鍵になるというのです。
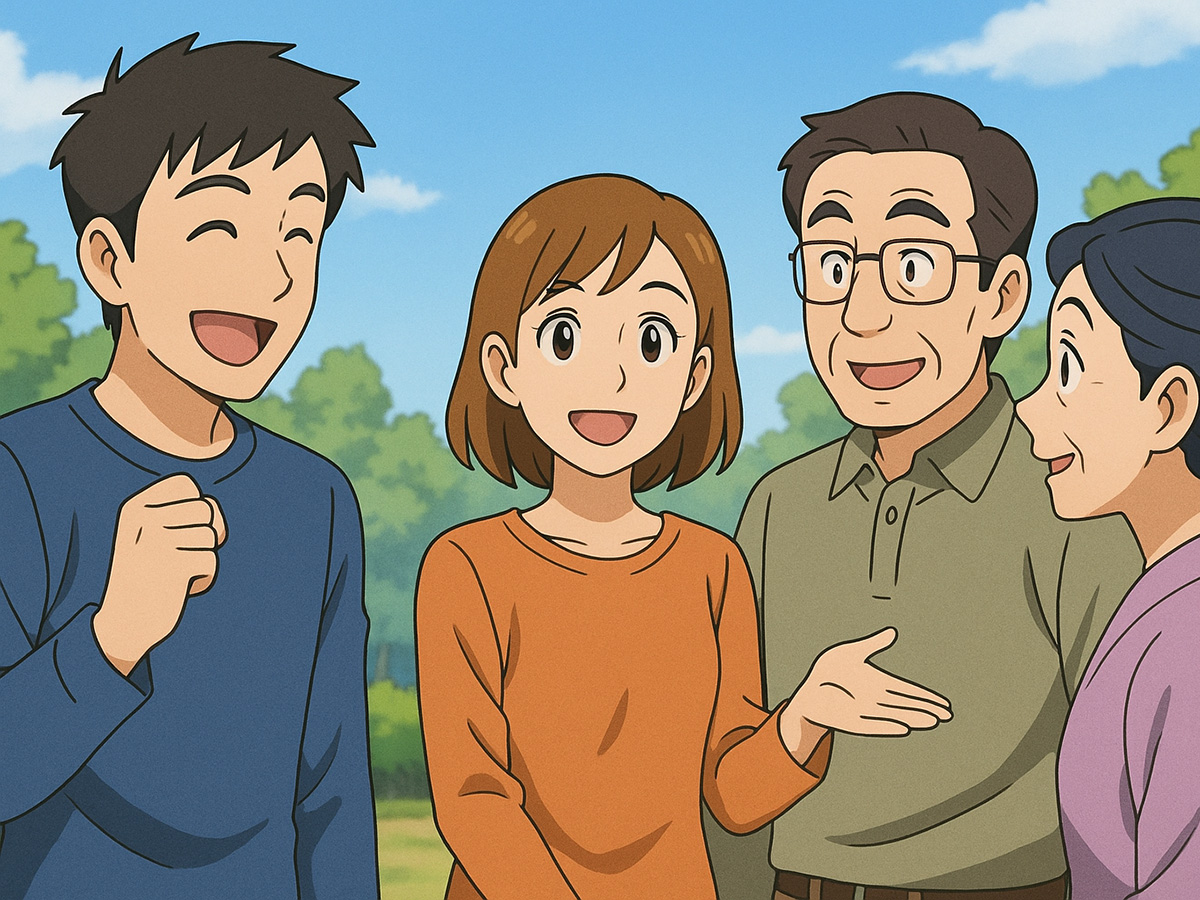
もちろん、この研究には限界もあります。
参加者はオンラインで募集されたため、支援をあまり必要としない比較的安定した人が多かった可能性があります。
また、強みは自己評価に基づいており、実際の行動や能力とどの程度一致するかは検証されていません。
今後は、客観的な課題や実験を通して、ADHDの強みが実際の成果にどう反映されるのかを調べる必要があります。
それでも、この研究はADHDを持つ成人にとって大きな希望を示しています。
自分の特性を「弱点」としてではなく、「自分らしさの一部」として見つめ直すこと。
その中にある強みを意識し、日常の中で使っていくこと。
それが、幸福感や生きがいを育む最初の一歩になるかもしれません。
研究を率いたのは、イギリスのバース大学心理学部と、オランダのラドバウド大学医療センター・ドンダース脳認知行動研究所の共同チームです。
彼らは論文の最後でこう述べています。
「ADHDの成人は、ハイパーフォーカスやユーモア、クリエイティビティなど、いくつかのポジティブな特性をより強く持っている。
けれども、ADHDの有無にかかわらず、自分の強みを知り、活かすことが幸福な人生につながるのだ」
つまり、ADHDを持つ人だけでなく、誰にとっても「自分の強み」を見つけることが大切なのです。
苦手さを補うだけでなく、得意なことを伸ばす。それは、心の健康にも、人生の満足にもつながります。
今回の研究は、ADHDを新しい光で捉え直す試みのひとつです。
私たちは、困難の奥にある強さを見つめることで、人の可能性をより豊かに理解できるようになるのかもしれません。
(出典:Psychological Medicine DOI: 10.1017/S0033291725101232)(画像:たーとるうぃず)
「自分の強みを認識し、それを活かす力は、ADHDの有無を問わず幸福感を高める普遍的な要素である」
行動して、活かしましょう!
(チャーリー)





























