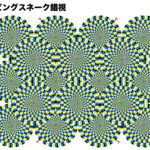この記事が含む Q&A
- 子どもが少しでも体を動かすと、親の生活の質にも影響があるのでしょうか?
- はい、子どもの軽い身体活動が親の気持ちの安定や環境の満足度と関連している傾向が示されました。
- 軽い身体活動(LPA)とはどんな動きですか?
- 激しい運動ではなく、室内の動作や散歩、軽い家事など穏やかな時間を指します。
- 親と子の身体の動きと心の状態には因果関係がありますか?
- いいえ、因果関係ではなく相互に関連し合う循環的な関連性が示されています。
自閉症のある子どもを育てる毎日は、楽しい瞬間がたくさんある一方で、体にも心にも大きなエネルギーを使います。
わが子の小さな変化に気づくために常に気を張り、予定通りにいかない毎日の中で、親自身の時間や余裕を後回しにしてしまうことも少なくありません。
そんな親子にとって、「体を少し動かす時間」が、実はお互いの気持ちや生活そのものを支える力になるかもしれない——。
中国とアメリカの研究チームが行った最新の研究は、そのことを静かに示しています。
研究を行ったのは、中国の集美大学、セントラルチャイナ師範大学、中国地質大学、そしてアメリカのウェイン州立大学の研究者たちです。
彼らは、自閉症のある子どもとその親が、どのくらい体を動かしているか、そしてそれが親子の「生活の質(クオリティ・オブ・ライフ)」にどんな影響を与えているのかを調べました。
この「生活の質(QOL)」という言葉は、少し専門的ですが、簡単に言えば「毎日をどれだけ心地よく生きられているか」ということです。
体の健康だけでなく、気持ちの安定、人とのつながり、環境の心地よさなど、生活全体の満足度を含みます。

研究チームが注目したのは、「親と子の関係の中で、体を動かすことがどんな意味をもっているのか」という点でした。
これまでの研究では、運動や身体活動が健康に良いことはよく知られていましたが、「親と子がともに影響し合う」という視点で調べた研究はあまりありませんでした。
そこで今回の研究では、親子がどのようにお互いの動きや気持ちに関係しているのかを見つめました。
この研究には、中国の自閉症リハビリセンターに通う85組の親子が参加しました。
子どもの平均年齢は5歳。まだ幼く、親の関わりが特に大きい時期です。
参加した親のほとんどは母親で、年齢は30代が中心でした。
子どもたちは、診断の上で自閉症が確認されており、研究ではそれぞれの子どもの特徴や症状の重さも考慮されました。
研究チームは、親子それぞれがどのくらい体を動かしているかを調べるために、1週間の間にどんな動きをしていたかを質問しました。
ここでいう「体を動かす」とは、激しい運動だけではありません。
家の中でのちょっとした動き、散歩や外遊び、軽い家事なども含まれます。
このような強すぎない体の動きを、研究では「軽い身体活動(LPA:Light Physical Activity)」と呼びました。
たとえば、子どもと一緒に公園で歩く、庭で遊ぶ、買い物に行く、風に当たりながらベンチに座る——そうした穏やかな時間です。
また、研究では、子どもの「生活の質」を親が代わりに評価しました。
たとえば「体の調子」「気持ちの安定」「友だちとの関わり」「学びや遊びの様子」など、生活のいろいろな側面について尋ねました。
一方、親自身の生活の質は、世界保健機関(WHO)が作った質問票を使って調べました。
そこでは「体の健康」「気持ちの健康」「人との関係」「暮らしている環境への満足」の4つの面が見られました。

その結果、ひとつのはっきりした傾向が見えてきました。
それは、「子どもが少しでも体を動かしているほど、親もよく体を動かしている」という関係です。
とくに、激しい運動ではなく、軽い動きの方が親子の間でよくつながっていました。
統計的にも有意な関連がありました。
そしてさらに重要だったのは、「子どもの軽い身体活動が、親の気持ちの安定や環境の満足度と関係していた」という点です。
つまり、子どもが少しでも体を動かすような生活をしていると、親の心が少し楽になる傾向があったのです。親が「気持ちが落ち着く」「周りの環境を心地よく感じられる」といった変化が見られました。これらは数字で見ると小さな関係ですが、親子の心のつながりを考えると、とても意味のあることです。
なぜこのような関係が生まれるのでしょうか。
研究チームは、「互いに影響し合う力」を説明する考え方として「相互決定論(リシプロカル・ディターミニズム)」という理論を使いました。
これは、心理学者のバンデューラが提唱したもので、人の行動や気持ちは、まわりの環境とお互いに影響し合いながら形づくられるという考え方です。
たとえば、子どもが外で少し体を動かすようになると、親も一緒に出かける機会が増え、親自身の気持ちも軽くなり、その雰囲気がまた子どもに伝わる——そうした「行動」「心」「環境」がぐるぐるとつながっているという見方です。

この研究ではまさに、そうした「親と子の間の循環」が確認されました。
子どもが動けば親も動き、親が元気を感じれば、その空気が子どもに返っていく。
その小さな循環の中に、生活の質を高める手がかりがあるのです。
興味深いのは、この「軽い身体活動(LPA)」がとくに意味を持っていたことです。
自閉症のある幼児は、運動に挑戦するときにたくさんのサポートが必要になります。
手をつないだり、声をかけたり、一緒に笑ったりしながら行う活動が多くなります。
そのため、親と子が同じ時間を共有しやすく、気持ちを通わせやすいのです。
研究者たちは、「このような活動こそが、親の心理的な安定を支えているのではないか」と考えています。
さらに、親が「環境を心地よく感じる」ようになるという結果も出ました。
これは、おそらく親子で外に出て過ごす時間が増えることで、近所の公園や散歩道、地域の空気に触れる機会が増えるためです。
外の世界を「安心できる場所」として感じられるようになることが、暮らし全体の満足感につながっていくのかもしれません。
一方で、親がどれだけ体を動かしているかと、子どもの生活の質との間には、直接的な関係は見られませんでした。
つまり、親が運動をしても、そのこと自体がすぐに子どもの生活を良くするわけではないということです。
しかし、親が元気でいることが、まわりの雰囲気をやわらかくし、子どもにとっての「安心できる環境」をつくっていくことは確かです。
研究の中で、著者たちは慎重に「これは因果関係ではなく関連です」と述べています。
つまり、子どもが体を動かすから親の気持ちが良くなる、という一方向の話ではありません。
親が少し余裕をもって子どもと関わることができた日、その日が子どもにとっても「楽しい体の動きの時間」になっている——そのような双方向の関係を大切に見ているのです。

また、この研究で見られた「軽い身体活動」は、どんな家庭でも比較的取り入れやすいものです。
特別な施設や器具がなくても、親子でできる活動です。
たとえば、室内で一緒にストレッチをしたり、ゆっくり散歩をしたり、公園でしゃぼん玉を追いかけたり。大きな達成感ではなく、「気持ちよかったね」と笑い合える時間こそが、家族の心の栄養になることを、この研究は示唆しています。
もちろん、この研究にも限界はあります。
参加したのは中国の特定地域の家族であり、文化や社会の違いによって結果が変わる可能性があります。
また、体を動かした量は親の記録によるもので、正確さには限りがあります。
今後は、活動量をセンサーなどで客観的に測る研究が必要とされています。
それでも、この研究は大切な問いを投げかけています。
「親と子が一緒に体を動かす時間」が、家族の生活にどんな意味をもつのか。
その答えは、数字ではなく、親子が交わす目線や笑顔の中にあるのかもしれません。
研究チームは最後にこう述べています。
「親と子の身体の動き、親の心の状態、そして家庭という環境。
この3つはお互いに影響し合いながら成り立っている。
これからは、家族全体をひとつの単位として支えるような活動を考えていく必要がある」と。
つまり、「子どもだけを支援する」「親のストレスを減らす」という別々の視点ではなく、「親と子が一緒に参加する」ことが、両方に良い影響をもたらすという考え方です。
これは、支援や療育の現場だけでなく、家庭でもすぐに生かせる視点です。
たとえば、親子で行う体操やダンス、ボール遊び、短いお散歩など。そうした時間を、治療の延長ではなく「楽しい家族の時間」としてとらえることで、子どもも親も自然とリラックスできます。
それは「がんばること」ではなく、「一緒に感じること」。
この研究が示したのは、そのシンプルで力強い事実でした。
この研究が行われた中国の家庭では、多くの母親が子どものケアに多くの時間を費やしていました。
仕事を離れ、子ども中心の生活を送ることで、自分自身の体や心のケアを後回しにしてしまう親も少なくありません。
そのような現実の中で、子どもと一緒に少し体を動かすことが、親の心を回復させ、家族の空気を少し軽くするきっかけになる。
研究のデータの裏には、そんな人間らしい温かい物語があるのです。

自閉症のある子どもたちにとって、世界はときに予測できず、感覚が強すぎたり、社会のペースが速すぎたりする場所です。
だからこそ、親子が一緒に過ごす穏やかな時間が、子どもの安心の土台になります。
親がリラックスして子どもと関わる時間を持てることは、子どもの発達にとっても大切な環境の一部です。
体を動かすことは、特別なトレーニングでなくてもかまいません。
風を感じる散歩、好きな音楽に合わせた手拍子、ゆっくりした呼吸。そうしたささいな動きが、心と心を近づけていきます。
今回の研究は、そのような「親子で共有する体の時間」が、家族の幸福感につながっていることを示したのです。
親の疲れを「がまん」で乗り切るのではなく、子どもと一緒に「感じる時間」に変えていく。
家の中の小さな運動、外の世界との小さな接点、笑い合える小さな瞬間。
それが、研究者たちが見つけた「親子の幸福のサイクル」です。
——体を動かすことは、親子の心を動かすことでもある。
この研究は、そんなあたりまえのことを、あらためて科学の言葉で証明してくれたように思います。
(出典:Frontiers in Psychology DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1669728)(画像:たーとるうぃず)
私も小さなころからずっと、うちの子といっしょに歩いたり踊ってきたりしてきました。
いつも笑顔が見たくて。
理屈抜きに、一緒に体を動かすことが親子の幸せにつながることは間違いありません。
(チャーリー)