
この記事が含む Q&A
- 迷走神経刺激を用いた訓練がASDの人の音の理解に役立つ可能性はありますか?
- 研究では脳の音処理の改善が示されており、将来的なリハビリに期待されています。
- ASDの人が音の聞き取りや言葉理解に苦労するのはなぜですか?
- 脳の音の処理の仕組みが違うため、音に対する反応や識別が遅れることが関係しています。
- 脳の可塑性はどのようにしてASDの困難を克服する手助けになるのですか?
- 訓練や刺激によって脳のネットワークを変化させ、学習や改善の可能性を引き出せるからです。
あなたの身近な人が「音の聞き取り」や「言葉の理解」に苦労している場面を見たことがあるでしょうか。
自閉症スペクトラム症(ASD)のある人たちの多くは、「音が聞こえるのに、何を言っているのか分かりにくい」「似たような音を聞き分けるのが難しい」など、コミュニケーションに関する特有の悩みを持っています。
なぜこうした困難が生まれるのでしょうか。
その背景には、脳の音の処理の仕組みの違いが深く関わっています。
こうした問題に対して、世界中の研究者がさまざまな方法でアプローチしていますが、アメリカのテキサス大学ダラス校の研究チームが新しい視点からの挑戦を始めました。
今回紹介する研究は、「音」と「迷走神経刺激」を組み合わせることで、ASDのモデル動物であるラットの脳の音処理を改善できるかどうかを調べたものです。
この研究で使われたラットは、胎児期にバルプロ酸(VPA)という薬剤を投与されました。
VPAはてんかん治療薬として使われていますが、胎児期の曝露によってASDに似た特徴が生じることが知られており、世界中でASDモデル動物として利用されています。
VPAを投与されたラット(ASDラット)は、脳が音を処理する際に「反応が遅い」「反応が弱い」「音の違いをうまく見分けられない」といった特徴が現れます。
これは、人間のASD児が「言葉の聞き取りに苦労する」「騒がしい環境が苦手」と感じる現象に似ています。

研究チームはまず、ASDラットに「音」と「迷走神経刺激」を組み合わせる訓練を行いました。
具体的には、ある音(たとえば「ダッド」など)の直前に迷走神経刺激を与えるという操作を、1日あたり300回、20日間続けました。
迷走神経刺激は、首の迷走神経に電極を取り付けて電気刺激を与える方法です。
刺激を与えることで、脳内のノルアドレナリンやアセチルコリン、セロトニンといった神経伝達物質が放出され、脳の可塑性(変化する力)が高まると考えられています。
訓練後、ラットたちの脳の「前聴覚野」から、音への神経反応を詳細に記録しました。
その結果、ASDラットは、ASDでないラット(VPAを投与されていないラット)と比べて、音に対する神経反応が遅く、反応の強さも弱いことが改めて確認されました。
とくに、「ダ」や「バ」など、わずかな違いしかない破裂音の区別が苦手でした。
ところが、迷走神経刺激を音と組み合わせて訓練したグループでは、反応の遅れや弱さが「部分的」あるいは「完全に」回復するという結果が得られました。
音の強さや繰り返しに対する追従性、複数の音を正確に見分ける能力など、脳の神経活動に大きな改善が見られました。
とくに、訓練した音に対する反応が明確に強化された点が特徴的です。
これは、学習したい音や単語をピンポイントで強化できる新しいリハビリ法への応用可能性を感じさせる発見です。
さらに、音に対する神経活動の違いをAIを用いて解析したところ、迷走神経刺激を受けたASDラットでは「音ごとに神経活動パターンが明確に分かれる」ことも確認されました。
これは、脳内の「音の地図」が、訓練によってはっきり描き直されたことを意味します。
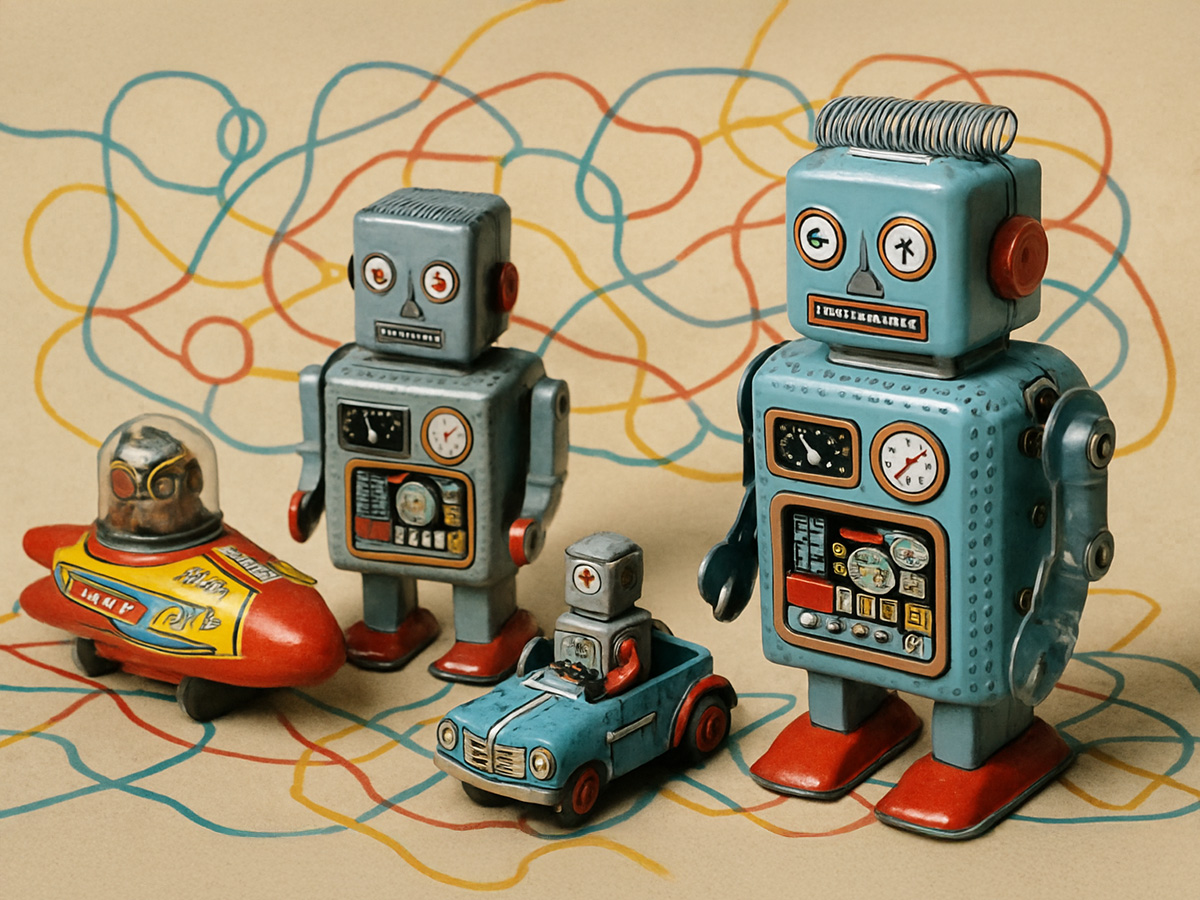
次に、こうした脳の変化が「実際の行動」に現れるかどうかを調べるため、ラットたちに「音を聞き分けて正しく行動する」テストを実施しました。
例えば、「ダッド」という音が鳴ったときだけ鼻先でボタンを押すとエサがもらえる、という課題です。
ここでも迷走神経刺激を用い、正解したときにだけ刺激を与える「ごほうび型」の訓練も行われました。
しかし、意外にも行動レベルでは迷走神経刺激訓練の効果は明確に現れませんでした。
つまり、脳の中では音の処理が改善されているにもかかわらず、「音を聞き分けて行動する」力はASDラットでもASDでないラットでもほとんど変わらなかったのです。
この理由について、研究チームはさまざまな可能性を指摘しています。
ひとつは、今回のテスト方法(鼻先でボタンを押す)が過去の研究で使われていた「レバー押し」と異なるため、感覚運動の違いが影響したのかもしれません。
また、ラットたちが十分に訓練を受けたことで、「音を聞き分ける」力が補われてしまい、脳の変化が行動に現れにくくなった可能性も考えられます。
とはいえ、今回の研究の意義は大きいものです。
ASDによる音の困難さが「絶対に治らない障害」ではなく、「後から回復し得る可塑性」が脳に残っていることが示されたからです。
迷走神経刺激と音の組み合わせによる訓練は、脳のネットワークを実際に変化させることができ、将来的には人のリハビリや療育の新たな選択肢になるかもしれません。
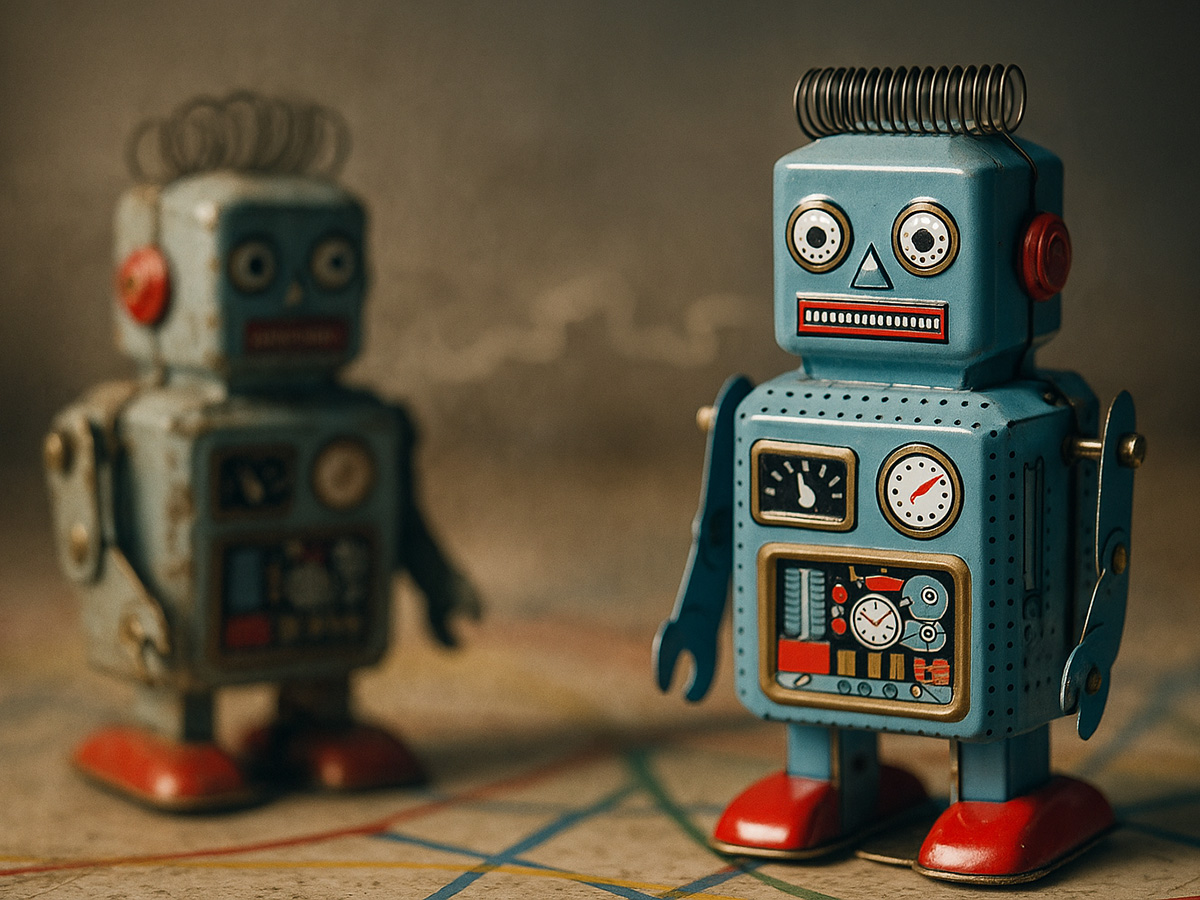
ただし、脳の変化と行動の変化は必ずしも同時に起きるわけではなく、リハビリの現場でも「目に見えない進歩」や「学びの予兆」を大切にする必要があります。
今回の成果は、「脳はいつでも変わる力を持っている」という希望を与えてくれます。苦手な音や言葉も、脳の学び直しによって少しずつ克服できるかもしれません。
この研究はまだラットを使った動物実験の段階ですが、迷走神経刺激と音を組み合わせたアプローチが、ASDのある人たちの音への困難に新しい解決策をもたらす可能性を持っています。
今後は、人への応用を目指して、より精密な刺激のタイミングや方法の工夫、安全性の検証など、多くの課題を乗り越えていく必要があります。
ASDを持つ本人やご家族、支援者にとって、「脳は変わることができる」という科学的な証拠は大きな励みになるはずです。
自分や身近な人の「苦手」にも、あきらめずに可能性を見つける――そのための新しい科学の一歩が、今回の研究から始まろうとしています。
(出典:frontiers DOI: 10.3389/fnins.2025.1600024)(画像:たーとるうぃず)
「脳は変わることができる」という科学的な証拠。
効果的な療育などの支援につながることを期待しています。
(チャーリー)




























