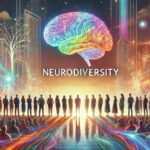この記事が含む Q&A
- 子どもに診断名を伝えることは、本人の自己理解に役立ちますか?
- 診断名は自己理解を深めることもありますが、必ずしも成長や変化の妨げにならないとは限りません。
- 神経発達の違いをラベルで表現することは、子どもたちにとって最善の支援となりますか?
- ラベルが支援の一助となる場合もありますが、過剰なラベリングは自己肯定や成長を阻害する危険性もあります。
- なぜ近年、自閉症やADHDの診断数が急増していると言われていますか?
- 診断技術の向上や社会的要請の増加により、多くの子どもに診断が下されるケースが増えています。
最近の子どもたちを見ていて、気になることがあります。
少し扱いにくい、内気、心の距離がある──昔ならそんなふうに表現されていた子どもたちが、今ではしばしば「神経発達の違い(ニューロダイバージェンス)」とラベルを貼られるようになってきています。
ADHD(注意欠如・多動症)やADD(注意欠如障害)、自閉症など、16歳以下の若者たちが、「非常に深刻で一生続く医療的な問題を抱えている」と告げられるケースが増えているのです。
最近では、自分の無礼なふるまいや衝動的な行動を「スペクトラムにあるから」と説明する子どもまでいます。
いまや、子どもたちが自分の行動を「診断名」で説明する時代になっているのです。

でも、それは本当に誰のためになっているのでしょうか?
子どもたちのためになっているのでしょうか?
私は心理学者として10年以上、子どもたちと関わってきましたが、正直に言って「役に立っているとは限らない」と感じるようになってきました。
「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」という言葉は、1990年代に登場しました。
この言葉は、人がそれぞれ異なる考え方をし、社会に関わり、集団で生きているという「多様な在り方」を肯定するもので、脳の働き方に「正解」がないことを伝えるものでした。
実際、どんな人もまったく同じ脳の働きをしているわけではありません。
この言葉が特に力を発揮するのは、大人になってから診断を受ける人たちの場合です。
たとえば、長年悩み続けてきた人が、「自分はADHDや自閉症だったのか」と気づくことで、心が軽くなったり、生きづらさの理由がはっきりしたりすることがあります。
それはまさに「そうだったのか!」というような、救いにも似た気づきになることもあります。

しかし、ここ数年でこの言葉はあまりにも頻繁に、あまりにも気軽に使われるようになってきました。
自己理解のプロセスを経ることなく、子どもたち──つまり社会のなかでもっとも未熟で弱い立場にある存在──に、次々とラベルが貼られていっているのです。
ここで改めて問うべきなのは、「そのラベルで、誰が得をしているのか?」ということです。
多くの人が思うように、それは子ども自身ではないのかもしれません。
むしろ、得をしているのは大人なのかもしれません。
たとえば教師は、「この子はADHDと診断されている」と知れば、授業中に落ち着きのない行動をしても「なるほど」と納得しやすくなります。
つまり、この診断ラベルは、大人たちが子どもの行動を「理解した気になる」ための手段になっている面があるのです。
けれども、昔からこうしたタイプの子どもたちはずっと存在してきました。
急に神経発達の問題が増えたわけではありません。
ただ、私たち大人が「それを診断する技術」を手に入れ、それを使うようになっただけなのです。
そして今、その技術をやみくもに振りかざしているようにも見えます。
実際、過去20年のあいだに、若者に対する自閉症の診断は800%近く増加しています。
さらに、診断を受けたくても待機している子どもも多く、イギリスではNHS(国民保健サービス)の待機リストがいっぱいになっています。
でも、子どもたち自身が「診断を受けたい」と言っているわけではありません。
親や教師、介護者がそうしているのです。

「診断」という言葉には、もともとネガティブな響きがあります。
たとえば「統合失調症と診断された」「がんと診断された」といったように、病気や恐れと結びついて使われることが多いからです。
誰も「幸せと診断された」とは言いません。
そうした中で、「自閉スペクトラム症(ASD)」「注意欠如・多動症(ADHD)」といった言葉が子どもに与える影響は大きなものです。
そこに共通して含まれているのは、「障害(Disorder)」という言葉です。
発達途中の子どもに「あなたには障害があります」と言ってしまうのです。
これでは混乱するのも当然です。
ある研究では、自閉症と診断された子どもの約70%が、不安やうつの症状を持っていることがわかっています。
こうしたデータからも、「このラベルは本当に役立っているのか?」という疑問がわいてきます。
もちろん、診断によって受けられる専門的な支援があるのは事実です。
行動療法、教育的なサポート、薬物療法などが提供されることもあります。
そしてそれらが役立つ場合もあります。
ただし、それは「いつも」ではありません。
むしろ、「どう対応していいかわからない大人たち」が安心するための「絆創膏」のようなものになっていることもあります。

さらに気になるのは、診断された子ども自身が、それを「自分の個性の一部」として扱うようになってしまうことです。
「私はADHDだから失敗しても仕方ない」「これは自閉症のせいだ」と、自分の振る舞いに言い訳をつける盾にしてしまうのです。
確かに、自己肯定感を守るためにそうするのかもしれません。
でも、多くの大人が知っているように、「言い訳」では本当の成長にはつながりません。
人が成熟していくには、自分自身のなかで向き合うのが難しい部分にも、しっかりと向き合っていく必要があります。
にもかかわらず、子どもに診断を与えることで、「あなたはもう変わらなくていい」「これはあなたのせいじゃない」というメッセージを送り、変化のチャンスを奪ってしまうのです。
大人たちは、子どもを理解しようとしてこのラベルを使っていますが、皮肉なことに、子どもという存在は常に「変化の途中」にあるものです。
もっと言えば、社会でもっとも柔軟で、これから成長していくはずの子どもたちに、わざわざラベルを貼るのは、子どもたちのためではなく、大人が「理解したつもり」になるためです。
「診断」という結論を得ることで、大人たちが安心したいだけなのかもしれません。
そしてその背景には、「私たちには十分な道具がない」という不安があります。
でも、実際には「問題を必要以上に大きく見積もっている」のかもしれません。
子育てはもともと大変なものですが、「発達の違いがある」と診断された子どもとなると、その責任は専門家へと移されがちです。
そしてそのことが、子どもに「自分は正常ではない」という強いメッセージを与えてしまうのです。
今の子どもたちは、技術の進化やコロナによる孤立など、これまでにない時代を生きています。
だからこそ、1990年代に登場した「ニューロダイバーシティ」という考え方とは、前提が変わってきているのです。

これはまるで「パンドラの箱」のような状況です。
一度開けたこの箱は、もう元には戻せません。
そして、診断を待つ子どもたちの列は、今後ますます長くなっていくでしょう。
私たちの「神経多様性」に対する理解は進みました。
しかし、ラベルが子どもたちにもたらす影響は、必ずしも前向きなものばかりではありません。
むしろ、そのラベルによって子どもたちの成長が妨げられることもあるのです。
私たちは、この言葉を子どもたちにどう使うかを、いまこそ見直すべきです。
それは、言い訳であり、子どもを「ラベルの箱」に閉じ込めてしまうものになっていないでしょうか?
子どもが「その診断名」を知る必要があるのかどうか──まずはその問いから、始めてみてもよいのではないでしょうか。
(出典:英THE STANDARD)(画像:たーとるうぃず)
ずっと診てきた心理学者だからこそ言える、なおさら説得力のある鋭い指摘であり、警鐘だと思います。
(チャーリー)