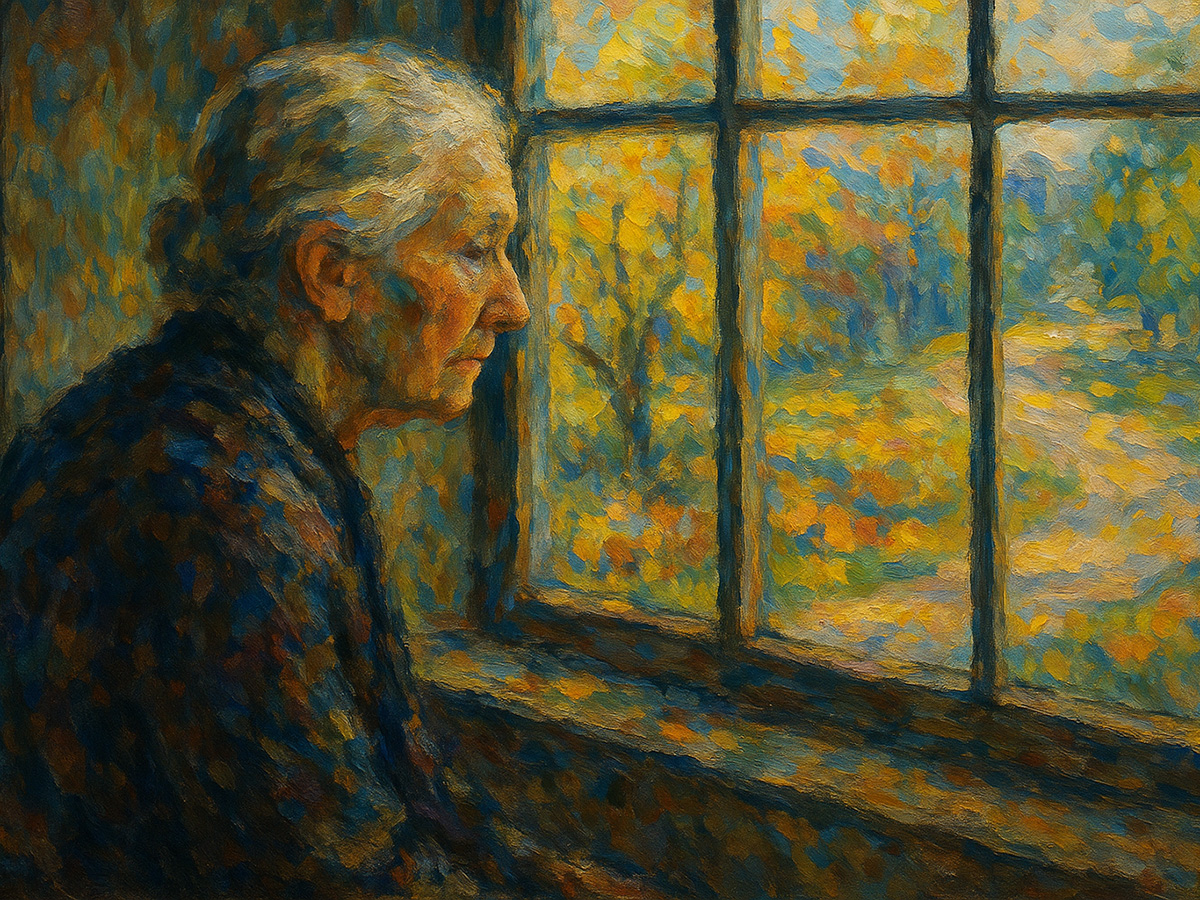
この記事が含む Q&A
- マルチセンサリー研究にはどんな偏りが指摘されているの?
- 年齢は子ども〜若年成人に偏り、高齢者はほとんど含まれず、IQ基準で知的障害を伴う人が排除され、男性中心で併存症を持つ人の対象も少ない点が挙げられています。
- 研究デザインの改善として具体的に何が提案されていますか?
- 言語を使わない応答方法の標準化、アイ・トラッキングやVRの活用、脳計測装置の感覚過敏対応、縦断研究の推進などです。
- なぜ多様な参加者を含めることが重要とされているのですか?
- 現状の偏りでは結果の一般化が難く、併存症や高齢者・女性を含む研究で支援の在り方をより正確に理解できるためです。
自閉症に関する研究は近年ますます増えてきていますが、誰が研究の参加者になっているのかを詳しく見てみると、はっきりとした偏りがあることがわかります。
今回、米ヴァンダービルト大学と米カリフォルニア大学デービス校の研究チームは、とくにマルチセンサリー研究(複数の感覚を統合して処理する研究)を題材に、その偏りを数値で明らかにし、今後の研究に向けた改善策を提案しました。
この総説は単なる批評ではなく、具体的な方法論まで提示している点で注目に値します。
研究チームは、299件のマルチセンサリー研究を精査し、基準を満たす102件を抽出しました。
これらの研究の参加者データを整理してみると、まず平均年齢は17.18歳であり、対象は子どもから若年成人に大きく偏っていました。
年齢層の上限は44.9歳にとどまっており、高齢の当事者はほとんど含まれていませんでした。
自閉症は生涯にわたる状態であるにもかかわらず、年齢を重ねた当事者の感覚や認知がどのように変化していくのかを検討した研究は事実上存在していないことが示されました。

さらに知能指数(IQ)の分析からも深刻な偏りが見つかりました。
参加者の平均IQは104.79であり、研究の約48%がIQの下限を設定していました。
その基準はおおむね65から85で、知的障害を伴う自閉症者は研究から排除されてきました。
実際にIQ85未満の参加者を含む研究はわずか4.35%に過ぎません。
逆に平均以上のIQを持つ人々は多く含まれており、とりわけ成人を対象とする研究では「平均より高いIQ」を条件とするものが多く見られました。
この結果は、支援を多く必要とする人々が研究から除外されてきた実態を示しています。
性別の構成も大きな偏りを示しました。
全体の参加者のうち男性は平均で80.25%を占めており、圧倒的に男性中心です。
しかも年齢が上がるほど男性比率は低下していく傾向が見られましたが、それでも全体的に女性は大幅に少なく、女性特有の自閉症の姿が研究に反映されていない状況が続いています。
女性は診断されにくく、とくに社会的にカモフラージュする傾向があることが知られています。
にもかかわらず研究における女性比率が低いことは、実態の偏った理解を招く要因となります。

もう一つ重要なのは併存症に関する扱いです。
フラジャイルX症候群やレット症候群といった遺伝症候群、あるいはてんかんなど、自閉症と共通する感覚特性を示すことが知られている状態があります。
しかし今回調べられた研究の多くは、こうした人々を対象から外していました。
そのため、研究結果を自閉症の多様な人々に一般化することが難しくなっています。
研究チームは、神経科学的な仮説を検証するためにも、併存症を持つ人々を積極的に研究に含める必要があると主張しています。
このような偏りが生じる理由の一つは、研究課題の設計そのものにあります。
多くの課題は、長い口頭での説明や複雑な手順、細かな手指の操作やボタン押し、言語的な応答を前提としています。
こうした設計は、支援を多く必要とする人々や言語を使うのが難しい人々には大きな負担となり、参加を難しくしています。
研究の仕組み自体が「参加しやすい人」だけを選んでしまう構造になっているのです。
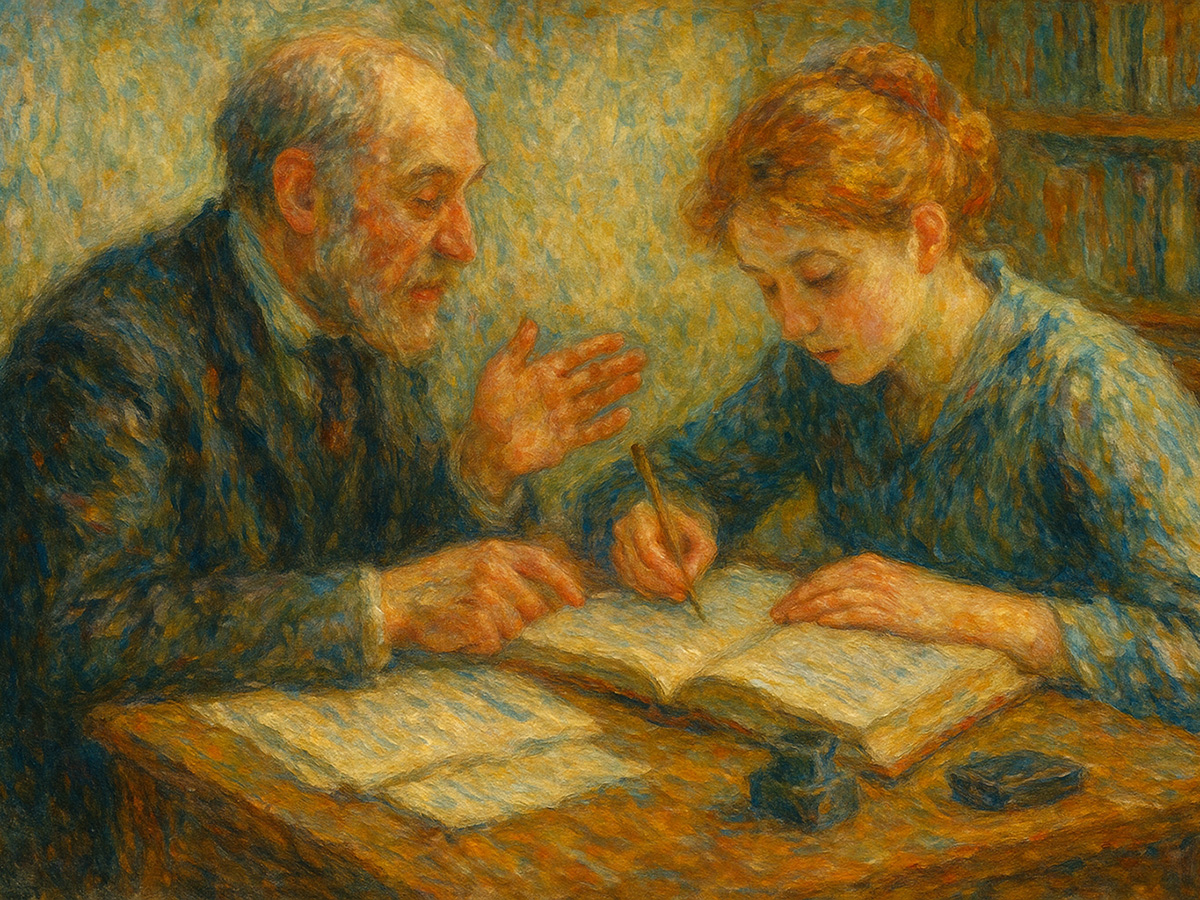
しかし今回の総説の重要な点は、こうした問題に対して具体的な解決策を提示していることです。
まず応答方法を柔軟にすることが強調されています。
言語的な回答やボタン操作に限定せず、指差しや視線、瞳孔の変化など非言語的な反応を活用すれば、言葉を使うのが難しい人々も研究に参加できます。
たとえば視線による好みの選択課題やアイ・トラッキングはその代表です。
また仮想現実や拡張現実の技術を使い、視線や身体の動きを反応として計測する方法も有効です。
脳活動を測定する方法にも改善が求められています。
EEGでは、従来の電極キャップに比べて負担の少ない塩水ネットやドライキャップを利用することで、耐容性が高まります。
fMRIについても、装置音を25デシベル以上抑える静音fMRIが感覚過敏の人々に適しています。
さらに、動きやすい人に対応するためにモバイルEEGを活用したり、fMRIで動き補正技術を導入したりすることが有効です。

また、研究の対象年齢を広げる必要性も強調されています。
現在の研究は若年層に集中しており、時間の経過とともに感覚処理がどのように変化するのか、獲得したスキルが社会的認知や感情理解にどのように影響するのかを追跡する縦断研究が欠けています。
高齢期における感覚や社会的スキルの変化を把握することは、支援の在り方を考える上でも重要です。
サンプルサイズが小さいことも問題です。
平均28名という小規模な研究が多く、とくに介入研究は限られています。
しかし支援を多く必要とする人々こそ、感覚に焦点を当てた介入の恩恵を受けやすい可能性があります。
その意味でも、より大規模で多様な参加者を対象とした介入研究が求められています。

研究チームは結論として、次のような具体的提言を示しています。
- 言語を必要としない応答方法を標準に含めること。課題は短く単純なものにする
- アイ・トラッキングやVRを活用して操作を伴わない反応を測定する
- 脳計測の装置や方法を感覚過敏や動きやすさに配慮したものに最適化する
- IQの足切りを安易に設けない
- 高齢者や女性、併存症を持つ人々を含めた縦断研究を推進する
この総説が強調するのは、「現在のマルチセンサリー研究は支援の少ない若い男性に偏っており、そのままでは一般化が難しい」という現実です。
そして研究デザインを工夫すれば、多様な当事者を含めることができ、研究成果もより広く役立つものになるという展望です。
研究は社会の鏡であり、参加しやすい人だけを反映すれば結果も偏ります。
多様な自閉症の人々を含めてこそ、正確で実践的な理解が得られるのです。
今回の研究は、そのための具体的な方法論を提示しました。
(出典: Journal of Autism and Developmental Disorders DOI: 10.1007/s10803-025-07022-4)(画像:たーとるうぃず)
うちの子について言えば、重度自閉症で知的障害もあり、話すこともできません。意思表示も難しいところがあります。
なので、こうした人を研究参加させることは、それはそれは難しいことだろうと思います。
しかしながら、こうした人だからこそ、たくさんの研究によって、もっと理解できるようになりたいと心から願っています。
「意思決定できない」自閉症や知的障害の人の研究参加(と選挙)
(チャーリー)

























