
この記事が含む Q&A
- 年齢と性別でADHDの困りごとと症状の結びつきは変わるのでしょうか?
- 男性は若いほど衝動性と自己抑制の難しさの関連が強く年齢とともに弱まる傾向があり、女性は年齢を重ねても困りごととADHDの結びつきがほぼ変わらず強いままであると報告されています。
- 支援は性別やライフステージごとにどのように調整すべきですか?
- 男性には衝動のコントロールを学ぶ機会を重視し、女性には不注意や感情の整理を長期的に支える環境整備とスキル積み重ねが有効とされています。
- 研究の特徴と解釈の注意点は何ですか?
- 日常生活の主観的困りごとを中心に横断的調査を行い、因果関係は断定できず、女性が多い点など解釈には慎重さが求められます。
ADHDというと、多くの人は「子どものころに落ち着きがない」「忘れ物が多い」といった姿を思い浮かべるかもしれません。
けれども、ADHDの特徴は子どもの時期に限られるものではありません。
大人になってからも、注意が散りやすい、感情の波が大きい、衝動的に行動してしまうなど、さまざまなかたちで日常生活に影響します。
そしてそのあらわれ方は、年齢を重ねるにつれて少しずつ変わっていくことが知られています。
けれども、「どのように変わるのか」「男女で違いがあるのか」は、まだ十分にはわかっていませんでした。
カナダのユニバーシティ・オブ・カルガリーの心理学部とホッチキス脳研究所、そしてワークランド教育学部の研究チームは、この問いに正面から取り組みました。
研究者たちは、10代後半から70代までの118人の成人を対象に、ADHDの症状が「日常の困りごと」とどのように結びついているのかを、年齢と性別の両面から詳しく調べました。
ここでいう「困りごと」とは、たとえばうっかりミスが多い、物事を順序立てて進めにくい、気持ちが爆発しやすい、後悔しても同じことをくり返してしまう――といった、自分の中で感じる認知面や感情面のむずかしさのことです。
研究参加者のうち、およそ7割がADHDの診断を受けていると自己申告していました。
全体の約8割が女性で、年齢は17歳から70歳まで幅広く含まれていました。
研究では、オンラインの質問紙調査を用い、ADHDの症状(ASRSおよびCAARS)、認知のつまずき(CFQ、BDEFS)、そして感情の調整の難しさ(DERS)という3つの側面を測定しました。
これらの尺度は、日常生活における「自分の感じ方」「実際の困難さ」を数字で捉えるために広く使われているものです。
研究チームはまず、ADHDの症状が強いほど、日常の認知や感情の困りごとが増えるという中程度から強い関連があることを確認しました。
これは、ADHDの診断を受けているかどうかにかかわらず、症状の強さそのものが日々の生活のしづらさにつながるという、これまでの研究とも一致する結果です。

しかし、ここからが本研究の重要な部分でした。
研究者たちは、この関連が「年齢によって変わるかどうか」、そして「男性と女性でその変化が違うかどうか」をさらに詳しく検討したのです。
解析の結果、男性と女性で異なる傾向が見えてきました。
男性では、年齢が若いほど、ADHD症状と「衝動的な行動」や「自己抑制の難しさ」との関連が強くあらわれました。
つまり若い男性ほど、ADHD症状と衝動性が強く結びついており、年齢を重ねるにつれて、その結びつきが少しずつ弱まっていく傾向があったのです。
たとえば、若いころには思いついたらすぐに行動してしまう、怒りを抑えられない、といった行動が目立ちやすい一方で、中年期以降になると、同じADHD症状があっても、行動として表に出にくくなる可能性が示されました。
これは、脳の成熟や社会的経験によって、衝動を抑えるメカニズムが少しずつ働くようになるためではないかと研究者たちは考えています。
一方、女性ではこのような変化の傾向は見られませんでした。
女性の場合、年齢が上がってもADHD症状と日常の困りごとの結びつきはほとんど変わらず、むしろ一貫して強いままでした。
たとえば、不注意やうっかりミスの多さ、感情の波の大きさなどが、若い時期だけでなく、年齢を重ねても続く傾向が見られたのです。
平均値の比較でも、女性は男性より「不注意」や「認知的うっかり」(CFQ)で高いスコアを示していました。
これは、女性ではADHDの特徴が「外に出る衝動性」よりも「内面の混乱」や「集中の持続しにくさ」としてあらわれやすいことを反映しているのかもしれません。
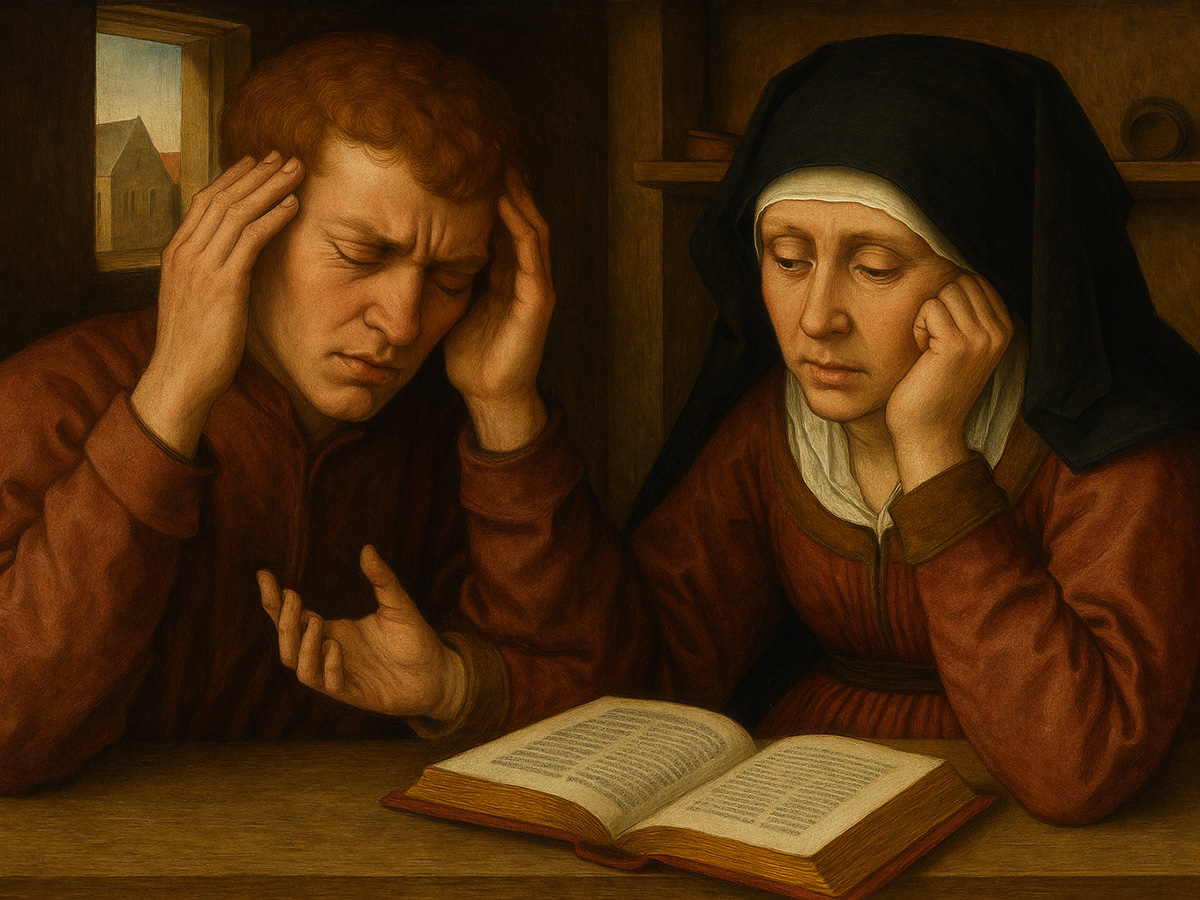
このような違いは、支援やセルフケアを考えるうえでとても重要な示唆を与えます。
男性の場合、若い時期には衝動性や感情の高まりに対処する力を身につけることが特に大切だと考えられます。
たとえば、強い感情がわいた時にどうやってクールダウンするか、距離をとる行動や深呼吸の習慣、また「やめよう」と思った瞬間に自分にかけるセルフトークなど、具体的な手段を練習することが効果的かもしれません。
これらは一度に身につくものではありませんが、トレーニングや支援者との対話の中で繰り返し実践することで、行動の衝動性を少しずつ調整できるようになります。
一方、女性では、年齢を重ねても困りごとの感じ方が変わりにくいため、「時間が経てば自然に落ち着く」という期待を前提にした支援では不十分です。
むしろ、不注意や忘れやすさへの環境調整――予定や持ち物を“見える化”する工夫、タスクを細かく分ける工夫、気が散る要因を減らす環境づくり――を、長期的に続けることが有効です。
さらに、感情の調整に関しても、気づく・言語化する・対処するという三段階のスキルを積み重ねていくことが、安定した生活を支える鍵になります。
この研究のもうひとつの特徴は、「日常生活の主観的な困りごと」を中心に据えた点です。
ADHDの研究では、客観的なテストの得点や脳画像のデータが注目されることが多いですが、実際の生活で「どのくらい困っているか」という体感こそ、支援の現場ではより重要です。
研究チームは、うつや不安の症状を統計的に調整しても、主要な結果が変わらないことを確認しており、今回の傾向が単なる気分の影響ではないことも示しています。
これは、ADHDの症状そのものが、年齢や性別によって異なるかたちで日常生活に影響していることを裏づける結果です。
もちろん、この研究にも限界はあります。
横断的な調査であるため、「年を重ねた結果そうなった」と因果を言えるわけではありません。
また、参加者の多くが自己報告による診断であり、臨床的に確定された診断ではない場合もあります。
さらに、女性が全体の大半を占めていたため、性別の比較は慎重に解釈する必要があります。
しかしそれでも、この結果はADHDの「一生のかたち」を考える上で重要な示唆を与えています。
つまり、男性と女性でADHD症状と日常生活の困りごとの結びつきが違うということは、「支援の地図」も異なるということなのです。

たとえば、男性では若い時期に「衝動のコントロール」を学ぶ機会を重視する一方、女性ではライフステージ全体を通して「不注意」や「感情の整理」を支える工夫を継続していくことが求められます。
とくに女性の場合、更年期などの身体的変化の時期に、注意力や記憶、感情の波が強まることがあります。
そこにADHDの特徴が重なると、本人が感じる困りごとが長く続くこともあるのです。
支援者は、「年齢とともに自然と落ち着くはず」と決めつけず、その人の生活状況や環境の変化に合わせて、実際の負担を減らす工夫を一緒に考えていく必要があります。
家事や仕事の分担、リマインダーの活用、周囲との調整など、日常の設計を柔軟に見直すことが、困りごとの軽減につながります。
また、感情のセルフケア――睡眠、運動、呼吸法、安心できる人との対話――を年齢を問わず継続することも大切です。
ADHDの症状は完全になくすことが目的ではなく、「どう付き合っていくか」を見つけていくことが中心です。
そのためには、自分の体調や感情の波を記録し、定期的に振り返ることも役に立ちます。
主観的な変化を可視化することは、将来の変化を先取りするサインにもなるからです。
研究チームは、こうした結果を通して、ADHDの支援に「性別」と「ライフステージ」という視点を加える重要性を訴えています。
従来は、年齢とともに症状が落ち着くと考えられることが多かったのですが、実際には、その変化の方向やスピードは人によって異なります。
とくに女性では、年齢を重ねても困りごとが続くケースが少なくなく、本人の努力不足ではなく、特徴そのものが持続するためだと理解する必要があります。
これは、本人の自尊心を守り、無理のない支援を考える上でとても大切な視点です。

最終的に、この研究が伝えているのは、ADHDという特性が「時間とともに薄れる」わけではなく、年齢や性別によってそのかたちを変えていくということです。
つまり、成長や加齢によって変わるのは「症状の強さ」ではなく、「症状とのつきあい方」なのです。
だからこそ、支援も「同じ方法を全員に当てはめる」のではなく、一人ひとりの生活のステージに合わせて調整する必要があります。
ADHDのある人が抱える日常の困りごとは、たとえ年齢を重ねても完全に消えるわけではありません。
けれども、適切な支援や工夫によって、その困難を少しずつ軽くし、自分らしいペースで生活できるようにすることはできます。
この研究は、そうした現実的な希望を示しているのです。
男性にも女性にも、それぞれの年齢のなかで「自分を理解し、支える方法」がある。
科学のデータの向こうには、そうした一人ひとりの物語が確かに存在しています。
(出典:Frontiers in Global Women’s Health DOI: 10.3389/fgwh.2025.1607464)(画像;たーとるうぃず)
困難は子どもの頃だけではない。
まず、それが広く知られる必要がありますね。
ADHDの「強み」と幸福。創造性と自発性が生むポジティブ効果
(チャーリー)





























