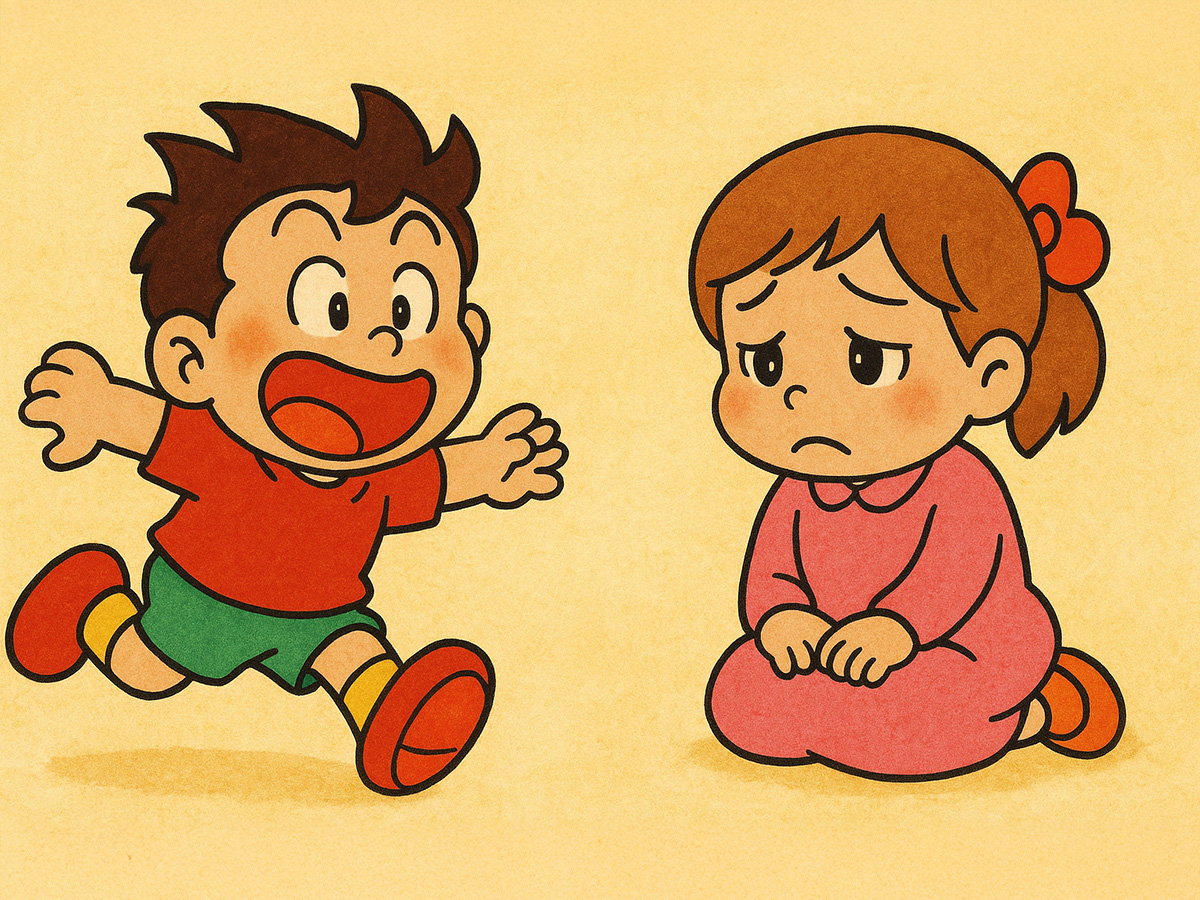
この記事が含む Q&A
- ADHDの不注意と不安障害の関係は性別や年齢によって異なるのですか?
- 女の子は不注意と不安の関連が強く、男の子は多動・衝動性が不安につながる傾向があります。
- どのような時期に支援や介入を行うと効果的ですか?
- 女の子には不注意への早期支援が、男の子には小学校低学年の多動・衝動性のコントロール支援が推奨されます。
- この研究の特徴は何ですか?
- 時系列の長期追跡と個人内変化を分析した点で、性別と年齢に即した因果関係の理解に貢献しています。
ノルウェーのノルウェー科学技術大学(Norwegian University of Science and Technology, NTNU)、セント・オラブ病院の児童青年精神科部門、そしてアメリカのワイオミング大学心理学部に所属する研究者たちによって行われた大規模な調査研究により、注意欠如・多動性障害(ADHD)と不安障害との関係について、年齢や性別によって異なる傾向があることが明らかになりました。
この研究は、ノルウェー国内の出生コホートを対象に、幼児期(4歳)から思春期後期(16歳)まで12年間にわたり、定期的に行われた診断面接データを分析したものです。
ADHDは、大きく「不注意」と「多動・衝動性」という2つの側面に分けられます。
そして、子どもたちの間では不安障害も比較的多く見られる問題です。
これまでの研究でも、ADHDと不安障害が併存する例は少なくないとされてきましたが、それぞれの側面がどのように不安と関係しているのか、またその関係が年齢や性別によってどう異なるのかは、はっきりとはわかっていませんでした。
本研究では、ノルウェーのトロンハイム市における出生コホート(2003〜2004年生まれ)の中から1,077人の子どもたちを対象に、2年ごとに7回の診断調査が行われました。
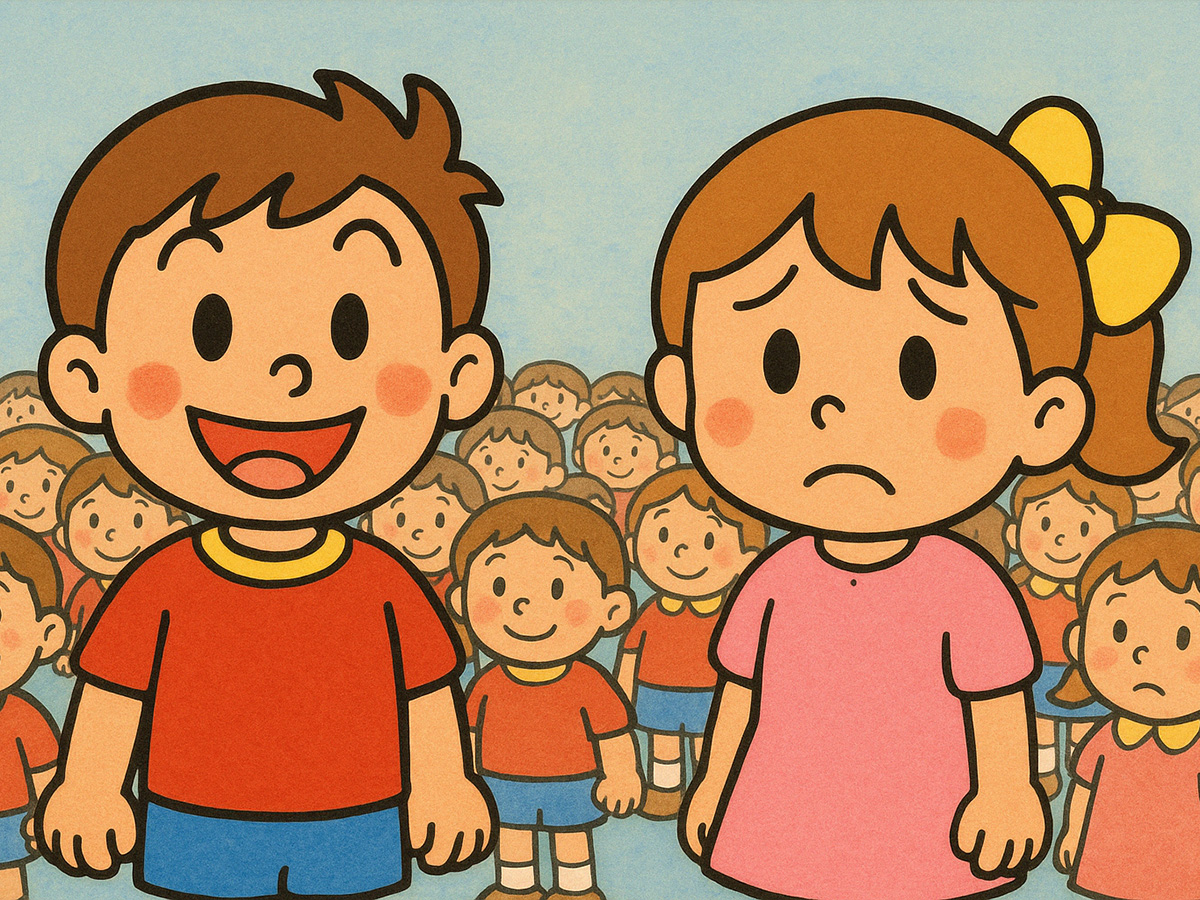
ADHDや不安症状については、子どもが4歳と6歳の時点では保護者への半構造化面接によって、8歳以降は子ども本人と保護者の両方に個別の面接を実施し、症状の有無や強さを詳細に評価しました。
評価には、年齢に応じた専門的な面接ツールが使われました。たとえば、4歳と6歳ではPreschool Age Psychiatric Assessment(PAPA)、8歳から14歳まではChild and Adolescent Psychiatric Assessment(CAPA)、16歳ではSchedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children(K-SADS-PL)を使用しました。
分析には、「ランダム切片交差遅延パネルモデル(RI-CLPM)」という、個人内の変化と個人間の違いを分離して解析できる統計手法が用いられました。
この方法により、長期にわたる時間的な影響を精密に評価することが可能になりました。

その結果、女の子と男の子とでは、ADHDのどの側面が不安と結びつくかに大きな違いがあることが明らかになりました。
女の子の場合、4歳から16歳までのほぼすべての時点で、「不注意」の症状が強いと、その2年後に「不安」の症状も増えるという傾向が確認されました。
さらに、思春期に入る12歳と14歳の時点では、逆に「不安」が高まることで、その後の「不注意」が増えるという双方向の影響も見られました。
一方、男の子の場合には少し異なるパターンが見られました。
とくに6歳と8歳の時点で「多動・衝動性」が高いと、その2年後に「不安」が増えるという関係が確認されました。
しかし、「不注意」と「不安」との間には、ほとんどの年齢段階で有意な関連は見られず、唯一10歳から12歳の期間でのみ、「不注意」がその後の「不安」を予測するという結果が得られました。
また、男の子においては「不安」が「ADHD」のどちらかの側面を予測するという傾向はほとんど見られませんでした。
このような性別の違いは、発達の過程や社会的な期待の影響を考慮することで、ある程度理解できます。
たとえば、女の子は学業や対人関係において「しっかりしているべき」「落ち着いているべき」という社会的期待を受けやすく、そうした期待のもとで「不注意」が目立つと、将来的に自己肯定感の低下や過剰な心配につながりやすく、不安を発症しやすくなる可能性が指摘されています。
また、思春期に入ると、ホルモンバランスの変化や人間関係の複雑化により、女の子は不安を感じやすくなり、そのことが「注意力の低下」につながることもあると考えられます。
今回の研究では、12歳や14歳の時点で不安の高まりが「不注意」の増加を引き起こしていたことが、それを裏付けています。

一方で、男の子の場合、「多動・衝動性」が学齢期に問題視されることが多く、そのストレスや失敗経験が積み重なることで、不安につながる可能性があります。
しかし、思春期以降は行動的な衝動性が減少していくことが多いため、そうした関連は次第に薄れていくと考えられます。
今回の研究は、ADHDの側面が一様に不安に関係するのではなく、「不注意」と「多動・衝動性」という異なる側面が、それぞれ異なる時期や性別で不安と関連していることを初めて詳細に示した点で、大きな意義があります。
とくに、「個人内の変化」に注目した分析によって、従来の研究では見えにくかった時間的な因果関係を明確にすることができました。
また、研究対象となった子どもたちの多くはノルウェー国籍で、地域の保健センターを通じた健康診査に基づくデータ収集が行われたため、地域住民にとって実態をよく反映した結果であるとも言えます。
この研究は、ADHDのある子どもたちに対して、性別や年齢に応じたよりきめ細かい支援が必要であることを示唆しています。
たとえば、女の子に対しては、幼い頃から「不注意」への対応を強化することで、将来的な不安の発症を防ぐことができる可能性があります。
また、思春期に不安を抱えやすい時期には、そのことがさらに「不注意」の悪化を引き起こす可能性があるため、早期の介入が重要です。
男の子の場合には、小学校低学年の段階で「多動・衝動性」を適切にコントロールできるように支援することで、不安のリスクを軽減することが期待されます。なお、「不安」が「ADHD」の症状を引き起こすという因果関係については、ほとんど確認されなかったため、予防や治療の際には主にADHDの症状に焦点を当てる方が効果的かもしれません。
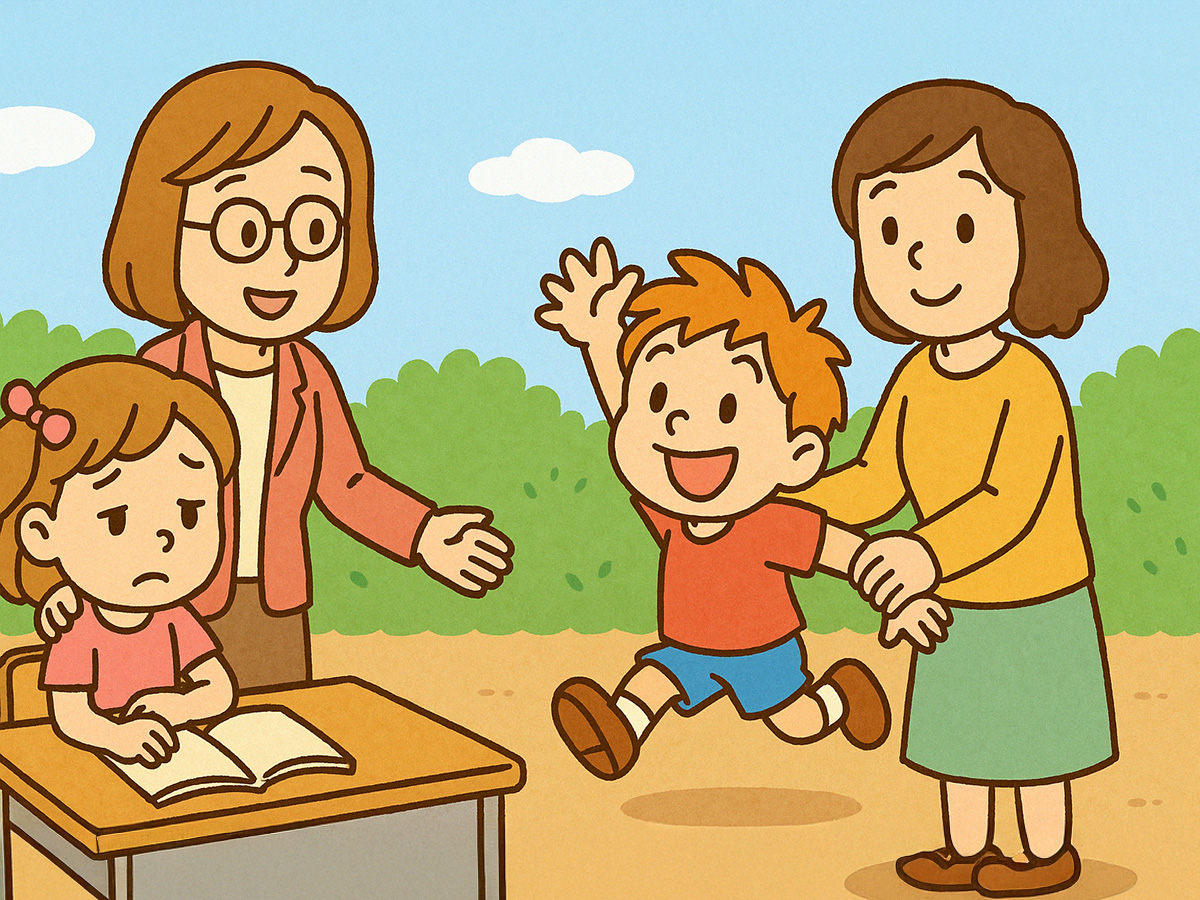
本研究は、ノルウェーの医療・保健制度の枠組みの中で、長期にわたり実施された信頼性の高い疫学的研究であり、今後の国際的な支援方針の形成にも影響を与える可能性があります。
ただし、本研究では、不安を「症状数」という連続的な尺度で捉えており、診断基準を満たす「不安障害」としての明確な診断とは異なる点に留意する必要があります。
また、4歳・6歳時点では保護者からの情報のみが用いられており、自己報告との違いがある可能性も考えられます。
それでもなお、性別と年齢に応じたきめ細やかな理解に基づく支援の重要性を示す本研究の意義は大きく、今後の臨床や教育現場における実践において、重要な指針となることでしょう。
(出典:Journal of Child Psychology and Psychiatry)(画像:たーとるうぃず)
この研究でわかったことを簡単にまとめると、
- 女の子では「不注意」が強いと不安が高まりやすく、そして思春期には不安が「不注意」をさらに悪化させる
- 男の子では「多動・衝動性」が小学校低学年で不安につながることがあるものの、年齢が上がるにつれてその関連性は薄れていく
なので、女の子には「不注意」への早期対応、男の子には「多動・衝動性」への小学校期での介入が、将来の「不安」のリスクを下げるために有効だと考えられます。
(チャーリー)




























