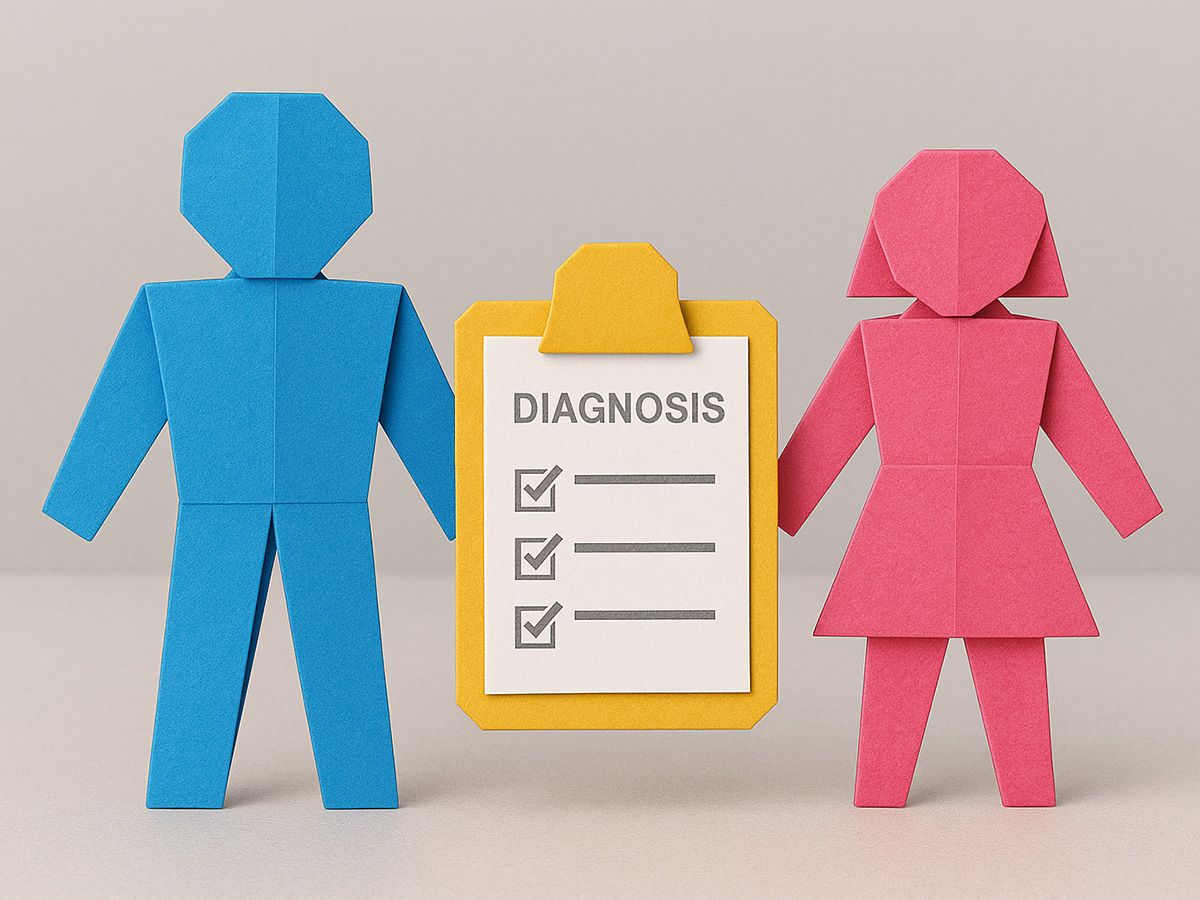
この記事が含む Q&A
- 男子は自分のADHD症状を少なく見積もる傾向がありますか?
- はい、男子は自己評価で症状の数が少なくなる傾向があります。
- 性別によるADHDの自己評価の違いは何ですか?
- 女子は自己評価で症状を正確に把握しやすく、診断でも高い評価が得られる傾向があります。
- ADHDの診断において、本人の声はどのように役立ちますか?
- 本人の声を丁寧に聞き取ることで、より正確な評価と適切な支援につながります。
注意欠如・多動症(ADHD)は、世界中で多くの子どもや大人に影響を与えている発達の特性です。
このADHDの診断や支援を進めるためには、本人の自己評価、親からの評価、そして医師や心理士による評価が使われることが多いですが、それぞれの評価がどのように違うのか、そして男女で違いがあるのかは、これまで十分にわかっていませんでした。
スウェーデンのウプサラ大学医学部、ストックホルム大学、カロリンスカ研究所、ストックホルム地域保健医療サービスらの研究チームは、ADHDと診断された15歳から18歳の男女159人を対象に、本人による自己評価、親からの評価、臨床家による評価を比較し、男女による違いがあるのかどうかを調べました。
研究に参加したのは男子58人、女子101人で、女子の参加者が多かったのは、女子のほうが自主的に参加を希望することが多かったためです。
ADHDの症状は、忘れ物が多い、集中が続かないなどの「不注意」と、落ち着きがなくじっとしていられない、衝動的に行動してしまうなどの「多動・衝動性」に分けられます。
今回の研究では、これらの症状について、本人が自分で記入する質問票、親が記入する質問票、そして臨床家が行う面接を通じて評価を行い、それぞれの評価がどのように一致しているのか、またどのような違いがあるのかを見ました。

その結果、男子は自分で評価した症状の数が、親や臨床家が評価した数よりも少ないことがわかりました。
つまり男子は、自分のADHDの症状を少なく見積もる傾向があったのです。
一方で女子の場合は、自分で評価した症状の数が、親や臨床家の評価とほとんど変わらず、自分自身の状態を正確に把握している可能性が示されました。
さらに、女子は男子よりも自己評価での症状の数が多く、臨床家の評価でも女子のほうが不注意の症状が多いと評価されていました。
しかし、親の評価では男女で大きな差はありませんでした。
このことは、女子が自分の困りごとを把握しやすいのに対して、男子は自分で気づきにくい可能性を示しています。
また、本人と臨床家の評価は、本人と親の評価よりも一致していることがわかりました。
これは、臨床家が診断の際に、親の話よりも本人の話を重視している可能性を示しています。
とく女子の場合は、臨床家との評価の一致度が高く、女子の自己申告が診断に大きな影響を与えていると考えられます。
症状の内容ごとに見てみると、「多動・衝動性」に関する評価は、本人、親、臨床家の間で比較的一致しやすい傾向がありました。
これは、多動や衝動的な行動は周囲からもわかりやすく、観察しやすいためです。
一方で「不注意」に関しては、本人と親、臨床家の間で評価が一致しにくくなっていました。
不注意の症状は、ぼんやりしてしまう、気が散ってしまうといった本人の内面的な状態が影響するため、外からは気づきにくく、評価が分かれることが多いのです。
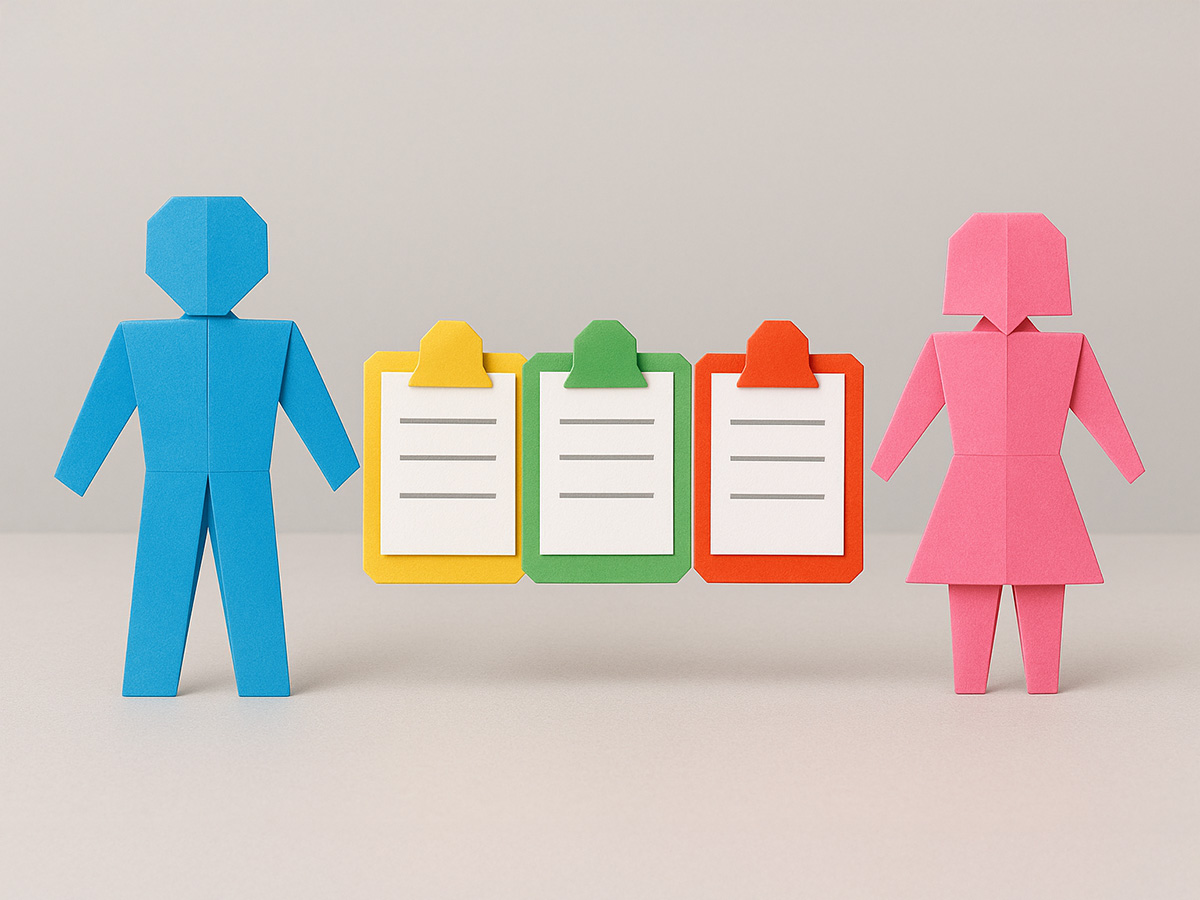
この研究では、ADHDの診断において、本人の声を聞くことの重要性が改めて示されました。
男子の場合、自分の困りごとを少なく見積もる傾向があるため、診断の際には周囲の大人が丁寧に話を聞き、本人が話しやすい環境をつくることが必要です。
一方で女子の場合は、自分自身で困りごとを正確に把握していることが多く、診断の際に本人の話を重視することが有効であると考えられます。
また、男子は女子よりもADHDの薬を使用している割合が高いこともわかりました。
しかし、薬の使用の有無を考慮しても、女子は男子よりも症状の評価が高くなる傾向があり、薬の使用だけが症状評価の違いを説明するわけではないことが示されました。
ADHDの診断は、本人、親、臨床家の複数の視点から情報を集めて行うことが重要ですが、特に本人の声を大切にすることが大切です。
不注意の症状は本人が自覚している場合も多いため、本人がどのように感じているのかを丁寧に聞き取ることが、診断の精度を高める鍵になります。
男子は自分の困りごとを少なく見積もる「ポジティブ錯覚バイアス」と呼ばれる傾向があることが知られています。
これは、自分の能力を高く評価し、困りごとを小さく見積もることで自分を守る心理的な働きと考えられています。
しかしこの傾向が強いと、困りごとに気づきにくく、支援を受ける機会を逃してしまう可能性があります。
一方で女子は、社会的な期待の影響もあり、自分自身の状態をより正確に把握しやすい可能性があります。

この研究の結果は、ADHDの診断や支援を進める際に、男子が困りごとを自覚しやすくなるように支援すること、女子の場合は本人の話を重視することの大切さを示しています。
また、不注意の症状は外からは見えにくいため、親や先生が気づかなくても、本人が困っている場合にはその声をしっかりと受け止めることが必要です。
ADHDは本人だけでなく、家族や学校生活にも影響を与える特性です。
しかし、本人が自分の状態を理解し、周囲の大人がその声を受け止めることができれば、より適切な支援につなげることが可能になります。
男子も女子も、自分自身の気持ちや困りごとを言葉にすることは簡単なことではありませんが、その声を大切にすることが、よりよい未来につながる第一歩になるのです。
この研究は、本人、親、臨床家の視点を比較することで、ADHDの診断や支援のあり方を見直すきっかけを与えてくれます。
ADHDの診断では、外からは見えにくい困りごとにも目を向け、本人の声を尊重することが、より適切な支援につながることが示されました。
そして、男子の困りごとを丁寧に聞き出し、女子の声を重視する姿勢が、診断や支援の場でますます求められることになるでしょう。
(出典:Journal of Psychiatric Research DOI: 10.1016/j.jpsychires.2025.05.026)(画像:たーとるうぃず)
男性のほうが、自分がADHDだとは考えない。
わかる気がします。
そうした傾向があることが正しく把握されることは、適切な支援につながりますね。
(チャーリー)





























