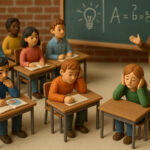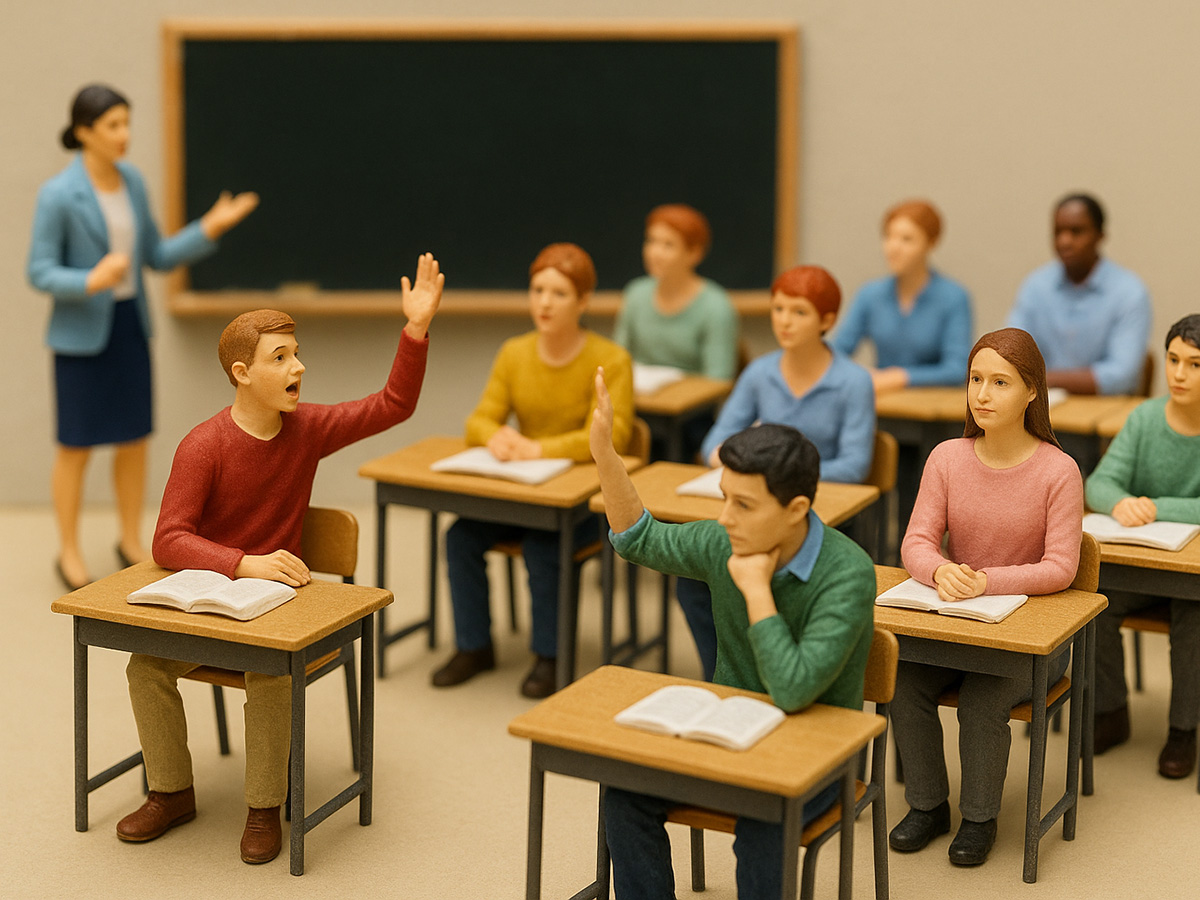
この記事が含む Q&A
- 静かな学生を歓迎することは自閉症の学生にどのように役立ちますか?
- 授業の冒頭で「静かに学んでいる学生も歓迎します」と伝えるだけで安心感が生まれ、声を出さない学びの形も認められるとされます。
- 仕組みを説明することの目的は何ですか?
- いつ・どのように・何をすればいいのかを明確に伝え、課題の意図を示すことで混乱を減らします。
- 神経発達の多様性を前提とすることはどういう意味ですか?
- 教室を特定の支援を受けている学生だけでなく未診断の学生にも配慮する、「誰にとってもやさしい教育」を目指す考え方です。
教室の中には、声を上げることが得意な学生もいれば、静かに考える時間を大切にしている学生もいます。
大学という場所では、意見を発言すること、議論すること、プレゼンテーションをすることが「積極的な学び」とみなされることが多いですが、それがすべての学生にとって心地よいとは限りません。
とくに自閉症の学生にとって、こうした“声を出す学び”のスタイルは大きなストレスになることがあります。
英国のオープンユニバーシティで教えるコラ・ベス・フレイザーによると、自閉症の学生の大学中退率は、他のどの障がいを持つ学生よりも高いといいます。
自閉症の学生のうち約三六パーセントが学業を途中でやめており、その割合は全体の学生よりも著しく高いのです。
これは、能力の問題ではなく、大学の環境が自閉症の学生にとってやさしく設計されていないことが大きな理由だとフレイザーは指摘します。
しかし、環境を「自閉症フレンドリー」にするために、大規模な改革を行う必要はありません。
フレイザーは、今すぐにでも誰でも実践できる三つの小さな工夫を紹介しています。
それは、「静かな学生を歓迎すること」「仕組みを明確に説明すること」「神経発達の多様性を前提に考えること」です。
どれも難しいことではありませんが、その影響はとても大きいといいます。

まず一つ目の工夫は、「静かな学生を歓迎すること」です。
多くの授業では、発言することやグループディスカッションへの参加が“良い学び方”とされます。
しかし、自閉症の学生にとっては、発言のタイミングをつかむことや、他人の話に割り込むことが非常に難しく感じられることがあります。
過去に「声を出しなさい」と言われ続け、プレッシャーや失敗の経験を積み重ねてきた学生もいます。
教員がその背景を知らずに「もっと発言して」と求めると、学生は安心を失い、学びの場から心を離してしまうことがあります。
そのため、フレイザーは授業のはじめに「静かに学んでいる学生も歓迎します」と伝えることをすすめています。
その一文があるだけで、自閉症の学生にとって授業はずっと安心できる場所になります。
言葉にすることで、「声を出さない=積極的でない」という誤解を解くことができ、学びの形に多様性があることをクラス全体に示すことができます。
また、口頭での説明だけでなく、必ず書面で同じ内容を示すことも大切です。
自閉症の学生は感覚刺激に敏感で、授業中の音や視覚的な情報に気を取られ、重要な指示を聞き逃すことがあります。
紙やメール、スライドなどで情報を提供しておくことで、学生は安心して自分のペースで確認できます。
この方法は自閉症の学生に限らず、英語を第二言語として学ぶ学生や、聞き取りが苦手な学生にも役立ちます。
教室に「声を出すことだけが学びではない」という空気をつくることが、最初の一歩なのです。
二つ目の工夫は、「仕組みを説明すること」です。
自閉症の学生は新しい手続きや流れに不安を感じやすい傾向があります。
授業の進め方や課題の提出方法、評価の基準などが曖昧なままだと、どう動いてよいかわからず、混乱や不安を抱えることがあります。
フレイザーは、どんなに小さな変更でも、必ず「いつ、どのように、何をすればいいのか」を明確に伝えることをすすめています。
たとえば、グループワークのルールや順番をはっきりさせること。
課題を出すときには、設問の意図を具体的に伝えること。「この課題では何を学んでほしいのか」「どのような力を評価しているのか」を明言することで、学生は課題に集中しやすくなります。
自閉症の学生は言葉を字義通りに受け取る傾向があるため、「自由に書いてください」と言われると方向を見失うことがあります。目的を言葉にすることは、学生に安心と理解を与えます。
こうした工夫は、すべての学生に利益をもたらします。
フレイザーはこれを「カーブカット効果」と呼びます。歩道の縁を車いすのために低くしたことが、ベビーカーや荷物を持つ人にも役立つように、自閉症に配慮した設計は他のすべての学生にとってもやさしい環境をつくるという考え方です。
つまり、自閉症支援の工夫は「特別な対応」ではなく、「全員にやさしい教育」そのものなのです。

三つ目の工夫は、「神経発達の多様性を前提とすること」です。
教室にいる学生は、一見同じように見えても、感じ方や考え方、集中の仕方が大きく異なります。
フレイザーは、教員が「特別な支援を受けている学生がいるかどうか」だけでなく、「まだ診断されていないが支援を必要としている学生がいる可能性」を想定することが大切だと述べています。
大学の中で支援登録をしている学生だけが支援を必要としているわけではありません。
診断を受けるには時間や費用、地域的な制約があり、必要なサポートにたどり着けていない学生も多いのです。
だからこそ、最初から教室を「神経発達の多様性を前提とした場」として設計することが求められます。
声を出さない学生も、ノートに静かに考えをまとめる学生も、それぞれに価値ある学びをしているという意識を教員がもつことが、安心できる教室の基礎になります。
このような設計があれば、学生がわざわざ「特別な配慮を求める」必要が少なくなります。
支援を申請すること自体が心理的な負担になることも多いため、最初から誰にとってもやさしい環境にしておくことは、学生の尊厳を守ることにもつながります。
自閉症の学生にとって「ここでは自分が特別ではない」と感じられることが、学びを続ける力になるのです。
フレイザーはまた、大学を卒業したあとの社会的課題にも触れています。
英国の調査によると、自閉症の卒業生のうち、卒業から十五か月後に正社員として働いている人の割合は、非自閉症の卒業生の半分ほどしかありません。
多くは契約職や無雇用の状態にあり、社会の中でも困難が続いています。
そのため、大学で「学びやすい」環境を整えることは、その先の「働きやすい」社会へとつながるといいます。
学びを通して自信を育み、社会の中で力を発揮できるようにするためには、まず大学が安心できる場所でなければなりません。

三つの工夫はどれも特別な支援策ではなく、教育をすべての学生にやさしくする基本の姿勢です。
「静かな学生を歓迎する」「仕組みを説明する」「多様性を前提とする」──この三つを意識するだけで、教室の空気は変わります。
教員にとっては小さな言葉や行動の違いですが、学生にとっては「理解されている」「ここにいていい」と感じられる大きな支えになります。
フレイザーは最後に、「神経発達の多様性を想定することは、特別な教育ではなく“正しい教育”である」と述べています。
教室には、言葉にできない不安や緊張を抱えながら学んでいる学生が必ずいます。
その存在を最初から想定し、やさしさを設計に組み込むことこそが、真の意味でのインクルーシブ教育なのです。
自閉症の学生が安心して学び続けられる環境は、他のすべての学生にとっても安心できる環境です。
そして、それは教員自身にとっても、教える喜びを取り戻す環境になります。
教育の現場を少しだけ変える三つの工夫が、誰にとってもやさしい未来をつくっていくのです。
(出典:英Times Higher Education)(画像:たーとるうぃず)
英国の大学では、積極的に求められ、きつく感じる学生も少なくないのでしょう。
もう、何十年も前ですが、私が(もちろん日本の)大学生だった頃は、そもそも講義中に発言を求められることはあまりなく、ゆるいものだったので。「静かな学生を歓迎する」という意識の必要性はまったくなかったですね。
求められること、であることは否定できませんが、学ぶ、将来につながる機会を奪ってしまったら本末転倒です。
(チャーリー)