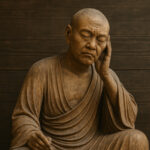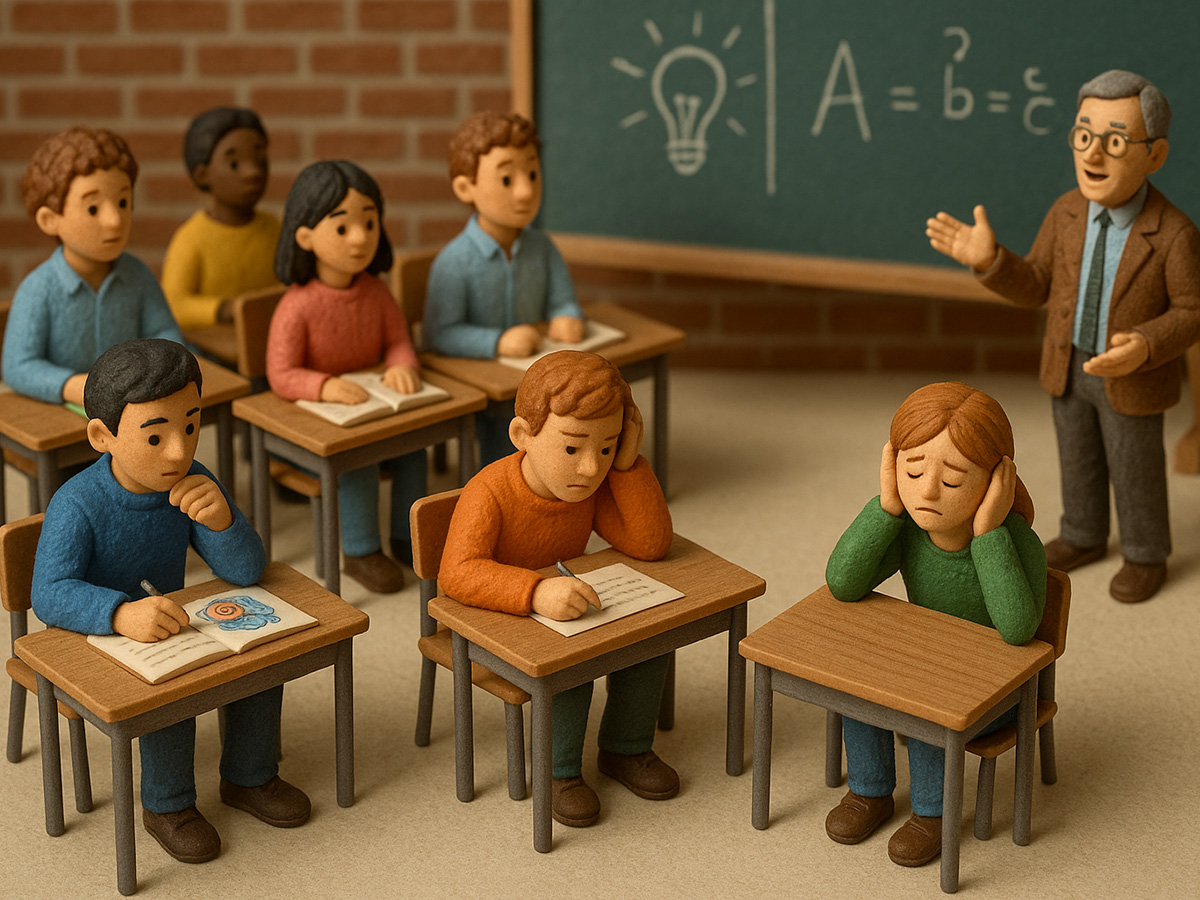
この記事が含む Q&A
- 自閉症の学生が大学で受けられる支援にはどんなものがありますか?
- 試験時間の延長、ノート取り補助、静かな環境での受験などの合理的配慮があり、アクセシブル・ラーニングセンターを通じて提供されますが、診断の有無で利用条件が異なる場合があります。
- 大学は神経多様性にどう対応すべきと考えられていますか?
- 教職員の協働や必修の研修、文化や個人に合わせた包括的な支援モデルを導入し、診断開示の有無に関わらず利用できる仕組みが求められています。
- 自閉症の学生が大学生活を充実させる具体的なアドバイスは何ですか?
- キャンパスのサービスやクラブを活用し、資金支援を探し、無理のないペースで学び、仲間や教授と関係を築き、静かな居場所を見つけることが有効です。
近年、自閉症と診断される人の数は増加しており、カナダでは子どもや青年の50人に1人が自閉症とされています。
そのため、大学やカレッジに進学する自閉症の学生も着実に増えています。
彼らは独自の強みを持ち込みます。
独創的な発想、集中して取り組む力、そして新しい視点から物事を考える能力です。
こうした力は学問の場にとって大きな価値があります。
一方で、研究は自閉症の学生が高等教育のキャンパスではまだ少数派であることを示しています。
非自閉症の学生に比べて卒業率が低い傾向があるのも事実です。
その背景には、支援の不足や感覚への配慮の欠如、そしてメンタルヘルスの課題など、構造的な壁があります。
こうした現状を受けて、カナダのヴィクトリア大学の研究チームは、自閉症の学生をどう支えるかを検討しました。
調査や既存研究のレビューに加えて、実際に大学生活を送るふたりの学生の経験を取り入れています。
ひとりは学部4年生で、自閉症や心理学、人類学に関心を持ち優秀論文を準備中です。
もうひとりは心理学を専攻して卒業し、その後も自閉症と高等教育に関する研究に関わり続け、レビュー論文の共著者にもなっています。

研究室では30分ほどのインタビューが行われ、大学での体験や新しく入学する学生への助言が語られました。
ふたりは実名での掲載に同意し、記事公開前に内容を確認しました。
自閉症を含む神経多様性のある学生は、大学で「合理的配慮」と呼ばれる支援を受ける資格があります。
試験時間の延長、ノート取りの補助、静かな環境での受験などです。
こうした仕組みはアクセシブル・ラーニングセンターなどを通じて提供されますが、利用には正式な診断が求められることが一般的です。
神経多様性への理解は広がりつつあるように見えますが、実際には課題が残っています。
カナダ会議委員会の調査によれば、大学で診断を開示している学生は半数に満たないのです。
しかし、開示した学生は学習や生活への満足度が高い傾向も示されました。
診断を受けるには高額な費用や長い待機時間が必要であり、そのため開示できない学生もいます。
したがって、診断の有無にかかわらず利用できる神経多様的な仕組みが不可欠です。
それにもかかわらず、カナダの大学で自閉症に特化したサービスを提供しているのはわずか6%です。
資金不足や教職員の研修不足が障壁になっています。
研究の多くは学生本人の体験に焦点を当ててきましたが、キャンパス全体をどう神経多様的に変えていくかは十分に議論されていません。
ふたりも「合理的配慮だけでは限界がある」と指摘しています。

カナダ会議委員会の調査では、大学職員や教員の約半数が「自分の大学の多様性やアクセシビリティの方針に神経多様性が反映されていない」と答えました。
そのため、神経多様性のある学生や教職員との協働、必修の研修、そして文化や個人に合わせた包括的な支援モデルの導入が提案されています。
こうした、学びも生活も含めて支える包括的な仕組みは、単なる配慮を超えて、学生が安心して学び続けるためのものです。
また、誰でもアクセスできる研修教材も存在します。
自閉症やユニバーサル・デザイン・オブ・ラーニングを学べるモジュールが公開されており、教職員が自ら理解を深めることができます。
少しずつですが、前進も見られます。
カナダのカルガリー大学では神経多様性支援オフィスが設置され、入学時の移行支援、メンター制度、教職員研修などが行われています。
ヴィクトリア大学では学生組合が運営する障害学生支援団体があり、予約制の休憩室を含むさまざまなサービスを提供しています。
さらに、2021年の調査結果を基に、全国の大学における自閉症特化の支援情報を集約したウェブサイトも作られました。
ふたりは、新しく大学に入る自閉症の学生への具体的なアドバイスも語っています。

まず、キャンパスのサービスやクラブ活動を活用することです。大学生活は学業だけではなく、人とのつながりによって豊かになります。
クラブに参加すれば「より本来の自分でいられる」と感じることもあるでしょう。
ただし、クラブやサークルを紹介する催しの場は人が多く音も大きいため、感覚的に負担となるかもしれません。
その場合は、学生センターのウェブサイトで活動を調べるのも良い方法です。
次に、資金面での支援を探すことです。
大学によっては補助機器のための資金制度があり、ノートパソコンやヘッドフォンなどをサポートしてくれます。
また、全国規模の障害学生支援団体は数百種類の奨学金情報を提供しており、大きな助けになります。
さらに、自分のペースで学ぶことを大切にしてください。
大学に入ると「決まった道を進まなければならない」と感じるかもしれませんが、授業数を減らして始めることも可能です。
実際に少ない科目から始め、慣れてからフルコースに移行するやり方もあります。
また、仲間や教授との関係を築くことも役立ちます。
自閉症学生のピアサポートグループでは「同じように生きている人と安心して過ごせる」と感じられるでしょう。
教授とつながることで、自分に合った学び方を一緒に考えてもらえることもあります。

最後に、感覚的に落ち着ける空間を探すことです。
カルガリー大学には神経多様性に配慮したスタジオがありますが、これは珍しい例です。
それでも図書館の静かな一角や小さな読書室など、安心して休める場所を見つけることはできます。
授業の合間にそうした場所を利用することで、気持ちを整え次の学びに備えることができます。
自閉症の学生にとって大学生活は挑戦の連続です。
しかし同時に、強みを発揮し可能性を広げる場でもあります。
自分に合った支援を利用し、仲間や教授と関係を築き、安心できる場所を見つけること。
それが学びを支え、卒業やその先の未来につながっていくのです。
(出典:THE CONVERSATION DOI: 10.64628/AAM.yh53c9hkq)(画像:たーとるうぃず)
「独創的な発想、集中して取り組む力、そして新しい視点から物事を考える能力です。
こうした力は学問の場にとって大きな価値があります。」
学問の場に限った話でもありません。
社会、人類にとってそうです。
ご活躍の機会が奪われることがますます減ることを心から願います。
(チャーリー)