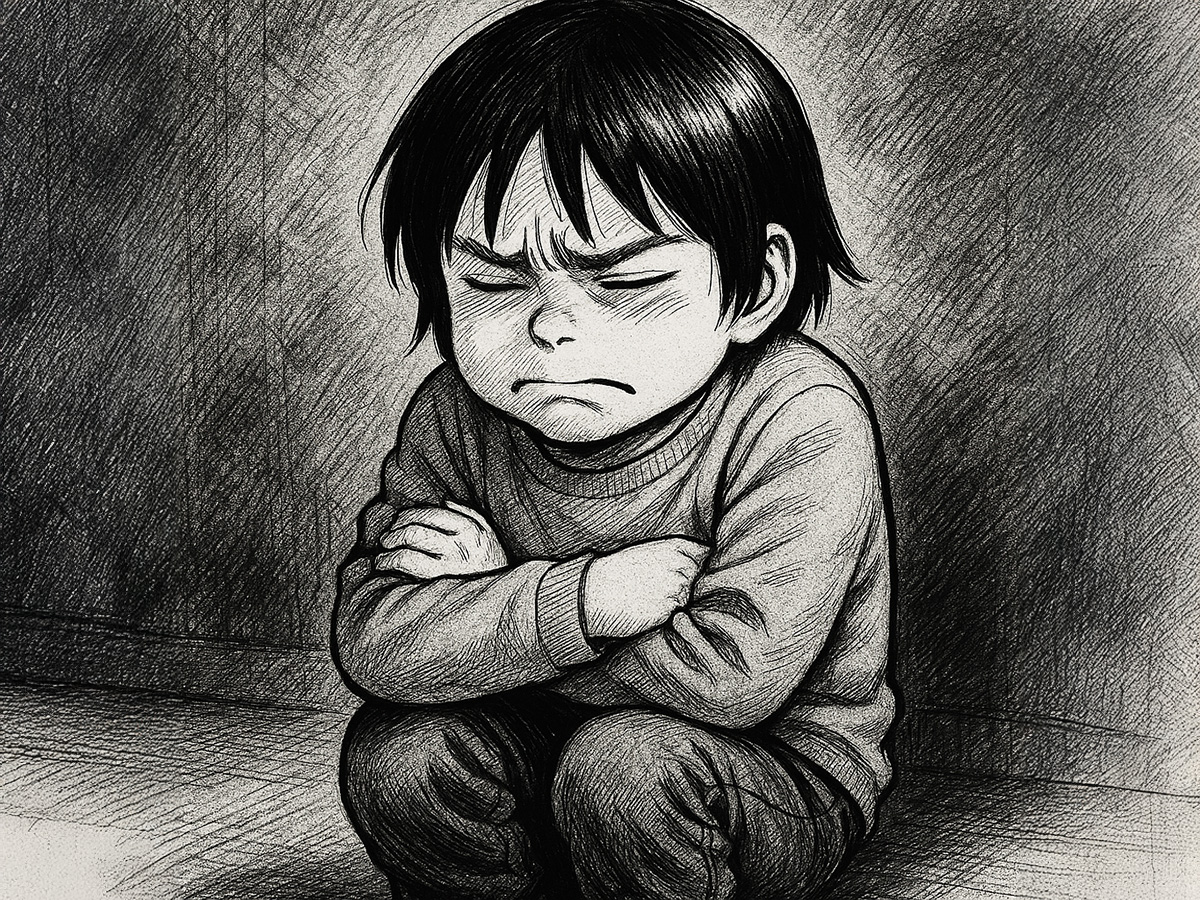
この記事が含む Q&A
- 自閉症の子どもたちの困りごとにはどんな背景が関係していますか?
- 不安障害、ADHD、そして実行機能の違いが深く関係しています。
- 不安障害やADHDの子どもたちにはどんな支援が効果的ですか?
- 認知行動療法やマインドフルネス、行動強化のプログラムが効果的とされています。
- 行動の背景を理解し、適切な支援を行うためにはどうすればよいですか?
- 行動の理由と脳の特性に早く気づき、個別に合ったサポートを考えることが大切です。
自閉症という言葉は、今では多くの人に知られるようになりました。
幼いころから、人とのやりとりやコミュニケーションが苦手だったり、同じ行動や習慣を強くくり返したり、身の回りの変化にとても敏感だったりする子どもたちがいます。
その一方で、実際に自閉症と診断された子どもたちと接するなかで、「それだけでは説明しきれない」生きづらさを抱えているケースが多いことも、保護者や支援者の間ではよく知られています。
たとえば、ちょっとした予定変更でパニックになったり、自分や他人を傷つけてしまう行動が続いたり、感覚の強い過敏さに悩まされたり、怒りがコントロールできずに大きな声で泣き叫ぶことがあったり。
こうした困りごとは、自閉症という診断名だけで説明できるものなのでしょうか。
ここに注目したのが、アメリカのデューク大学のカーペンターらの研究チームです。
彼らは、自閉症のある3歳から5歳の子どもたちを対象に、「不安障害」や「ADHD(注意欠如・多動症)」が自閉症の行動パターンにどう関係しているのか、さらに「実行機能」と呼ばれる脳の力がその間でどのように働いているのかを詳しく調べました。
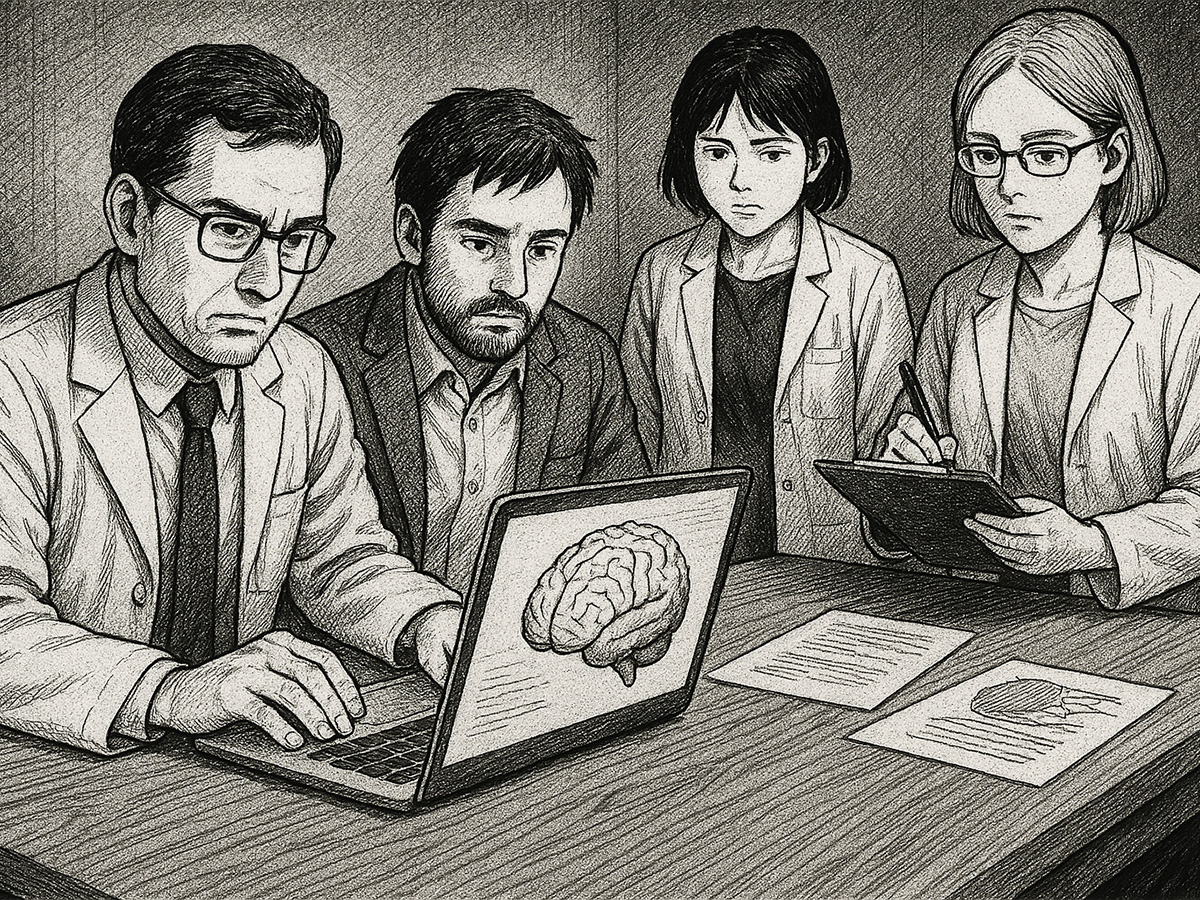
この研究に参加したのは、米ノースカロライナ州ダーラムのデューク大学自閉症脳発達センターで2015年から2017年に検査や面接を受けた、3歳から5歳11か月までの自閉症児69名です。
参加者は男児54名、女児15名と、やや男の子が多い構成となりました。
子どもたちの診断はアメリカ精神医学会の診断基準(DSM-5)で確認され、行動観察や保護者アンケート、知能検査などを組み合わせて、細やかに調査されました。
特に注目されたのは「不安障害」と「ADHD」です。
研究の結果、子どもたちのうち実に71%が不安障害(強い心配や恐怖、分離不安や社交不安など)を、61%がADHD(注意散漫、多動・衝動性)を、そして45%は両方を同時に抱えていたことがわかりました。
つまり、自閉症の子どもたちの半数近くが「不安」と「注意・衝動のコントロール」の両方で強い困難を感じていたのです。
こうした困りごとが、実際にどんな行動として現れてくるのか、研究チームは保護者へのアンケートや面接を通じて詳しく調べました。
自閉症の特徴である、社会的なやりとりの苦手さ、同じ行動や習慣への強いこだわり、感覚の過敏さ、そして自己傷害やパニック、怒りっぽさなどのさまざまな行動を、数値化して分析しました。
また、研究で重視されたのが「実行機能」という脳の力です。
実行機能とは、「目の前の課題や状況に合わせて気持ちや行動をコントロールする力」です。
たとえば「我慢して順番を待つ」「気持ちを切り替える」「感情を落ち着かせる」「必要なことを覚えておく」「計画を立てて動く」といった、日常生活でとても大切な能力です。
実行機能が弱いと、パニックを起こしたり、がまんできずにすぐ怒ったり、物事の順序が守れなかったりすることが増えます。

カーペンターらの分析によると、不安障害とADHDは、自閉症の行動パターンに異なるかたちで影響していました。
不安障害のある子どもは、特に「強いこだわり」や「儀式的な行動」「感覚過敏」が目立つ傾向がありました。
保護者からは「ちょっとした予定変更でパニックになる」「物の配置が変わると落ち着かなくなる」「音や触感などにとても敏感」といった声が集まりました。
不安障害のある子どもに共通していたのは、「気持ちや注意を切り替えることが苦手」という実行機能の弱さです。
たとえば、新しいことを始めるとき、急な変更があったときに自分で気持ちを整理できず、長時間泣き続けてしまったり、強いこだわり行動を見せたりします。
一方で、ADHDのある子どもたちでは、「衝動を抑える力(抑制)」が弱く、「自分を傷つけてしまう行動」や「怒りやすさ」「激しいパニック」が目立ちました。
たとえば「感情が高ぶると自分を叩いてしまう」「ちょっとしたことで大声を出して泣き叫ぶ」「思いついたことをすぐ行動に移してしまう」などです。
保護者は「我慢できずに行動してしまう」「すぐ怒ってしまう」と悩んでいました。
ADHDのない自閉症児と比べると、自己傷害や激しい怒りの爆発が明らかに多かったことも示されました。
さらに、不安障害とADHDの両方を持つ子どもは、「切り替え」と「抑制」の両方に困難を抱えやすく、複雑な困りごとが重なって現れやすい傾向がありました。
「新しい刺激に過敏に反応してパニックになり、さらに我慢できずに手が出てしまう」といった多層的な困りごとが見られることもありました。
このように、目の前の行動には必ず理由があり、その背景には「不安障害」「ADHD」、そして「実行機能」の違いが深く関係していることが、今回の研究から改めて確認されました。
行動だけを見て「わがまま」「努力が足りない」と決めつけるのではなく、「この子はなぜこうした行動をするのか」を理解しようとする姿勢が大切です。
研究では、こうした困りごとに対するサポートのヒントも提案されています。
不安障害が強い子どもには、注意や気持ちの切り替えを練習する「認知行動療法」や「マインドフルネス」などのトレーニングが役立つかもしれません。
たとえば、ゆっくり深呼吸をする練習や、イメージトレーニング、変化に少しずつ慣れる体験を積むことで、「切り替え」の力を高めることができます。
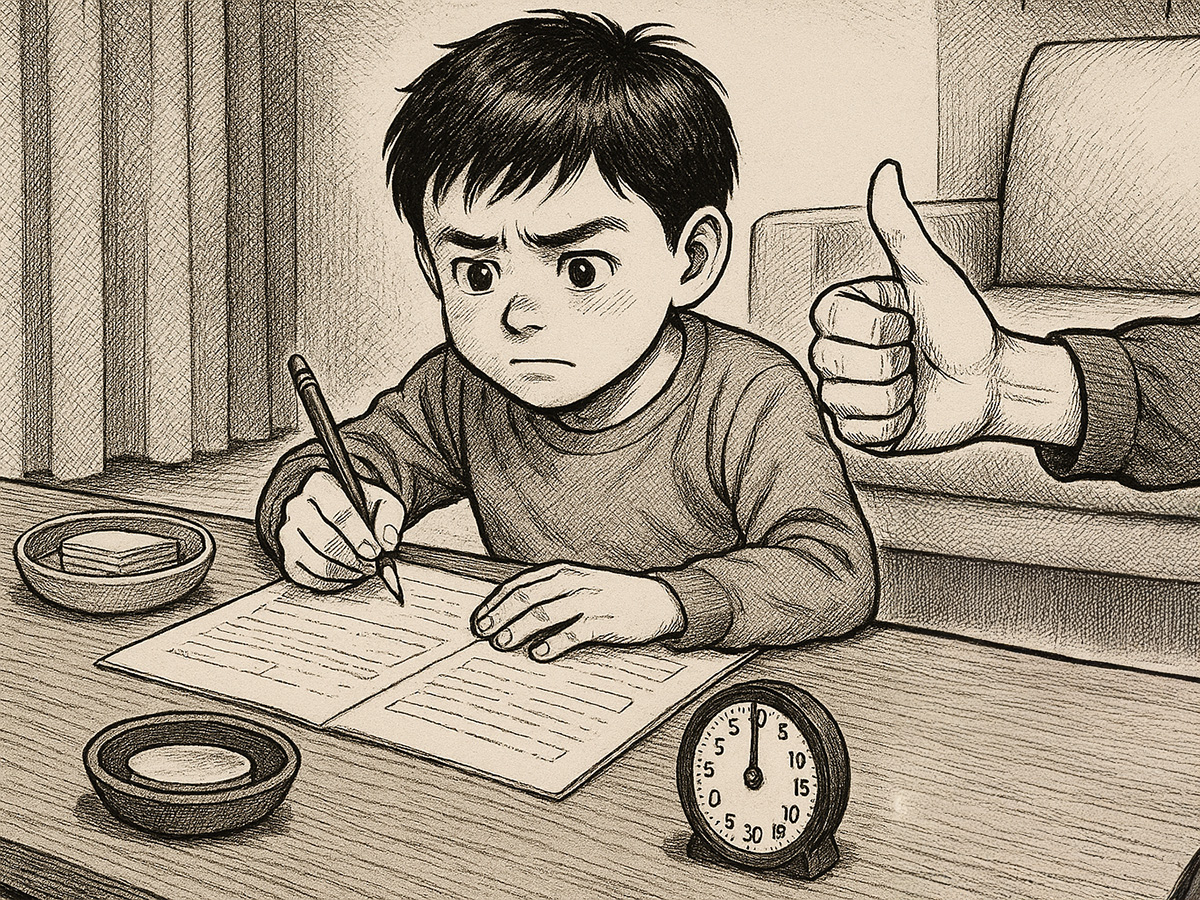
ADHD傾向の強い子どもには、短い課題を区切って取り組んだり、衝動をコントロールできたときに褒める、ごほうびを用意するなど、本人のやる気を高める工夫が有効です。
ゲームや遊びを通じて、順番を守る、がまんするなどの練習を少しずつ取り入れていくことも有効とされています。
また、不安障害とADHDの両方を持つ子どもには、「切り替え」と「抑制」両方の支援を個別に組み合わせることが大切です。
その子にとって一番困っている部分を早めに見極め、状況に合わせた支援を考える必要があります。
この研究は、「自閉症」という診断名だけにとらわれず、「不安障害」「ADHD」、そして「実行機能」という脳の力の違いにも目を向けることで、子どもたち一人ひとりの困りごとの理由をより深く理解できることを示しています。
たとえば「パニックになりやすい」「物事に強くこだわる」といった行動には、「不安と切り替えの苦手さ」が、「自己傷害や怒りっぽさ」には「衝動のコントロールの難しさ」が隠れていることがあります。
保護者や支援者の立場からは、子どもの困りごとの原因が見えづらいと、「なぜできないのか」「どうしてこの子だけこんなふうになってしまうのか」と悩むこともあるでしょう。

しかし、こうした行動には必ず理由があります。
脳や心の発達の違いによって、自分でもうまくコントロールできない困難を抱えている子どもたちがいることを理解することが、支援や寄り添いの第一歩になります。
今後は、こうした実行機能の違いに早い段階で気づき、個別に合ったサポートを考えていくことが大切です。
カーペンターらの研究チームは、「実行機能をターゲットとした早期介入プログラム」の開発や、子どもの発達を長期的に追う研究が今後ますます重要になると提案しています。
不安障害やADHD傾向のある子どもたちにとって、認知行動療法や作業記憶のトレーニング、マインドフルネス、行動強化のプログラムなどが役立つ可能性があり、これらの実践例が今後さらに広がることが期待されています。
自閉症の子どもたちがより豊かに、自分らしく生きていくためには、診断名にとらわれず、困りごとや脳の特性の違いに合わせた総合的な支援が必要です。
すべての子どもたちが、自分のペースで成長し、自信を持って生活できる社会の実現が、これからの発達支援や教育に求められています。
(出典:frontiers DOI: 10.3389/frcha.2025.1585507)(画像:たーとるうぃず)
「診断名にとらわれず、困りごとや脳の特性の違いに合わせた総合的な支援が必要」
よく見て、よく向き合って、少しでも困難が軽減し、親子楽しく生きていけるようにしていただきたいと思います。
(チャーリー)





























