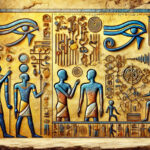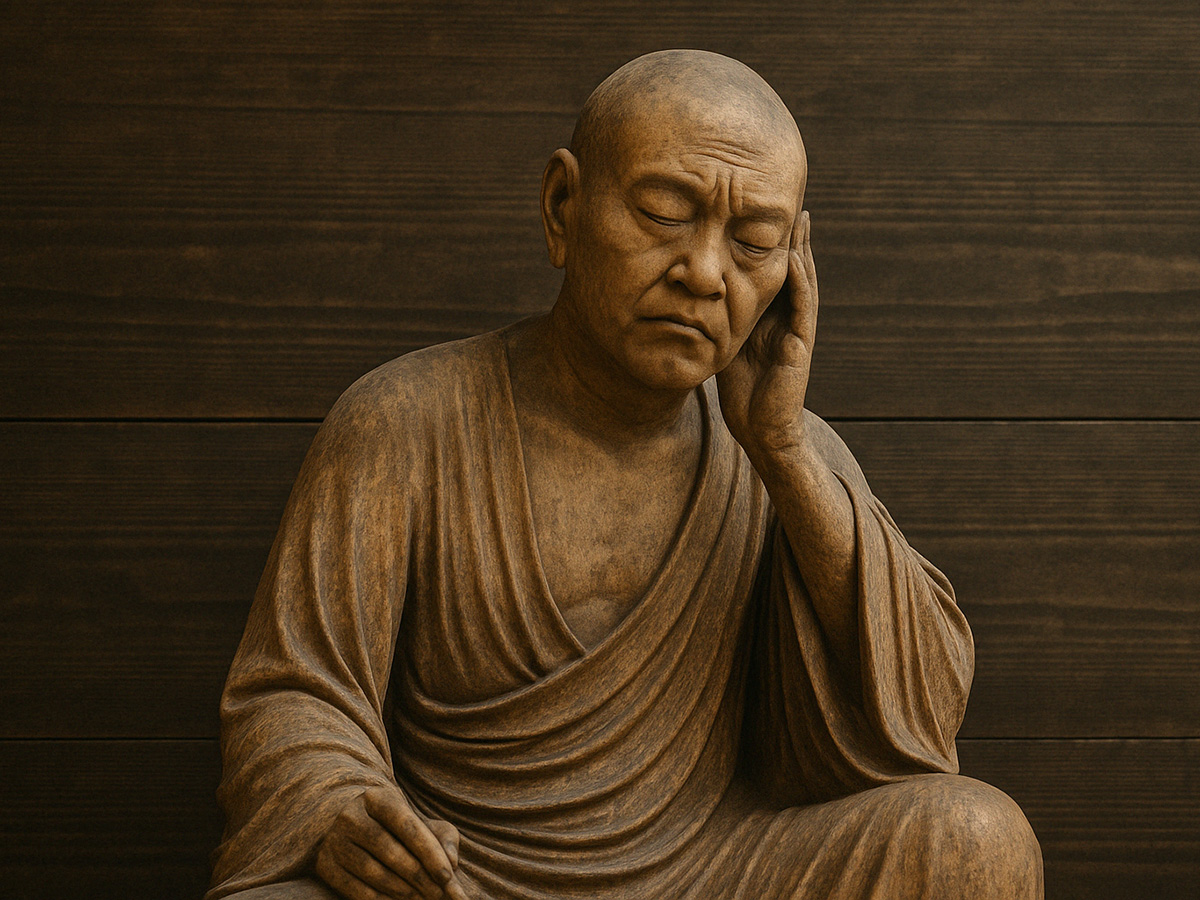
この記事が含む Q&A
- ADHDと慢性疼痛には関連があると言えますか?
- 最新の研究により、ADHDの傾向が強い人ほど慢性疼痛のリスクが高まることが示されています。
- どうすれば、自分や家族のADHDの可能性を見つけやすくなりますか?
- ADHDのスクリーニング検査を受けることで、症状の有無や傾向を把握しやすくなります。
- ADHAの薬が疼痛の軽減に効果的だと聞きましたが、その理由は何ですか?
- 神経伝達物質の働きの改善により、痛みの感じ方や過敏さが和らぐためです。
日本では近年、「慢性的な痛み(慢性疼痛)」に悩まされている人が増えてきています。
腰や首、肩などに原因のよくわからない痛みが長引くことで、日常生活に支障をきたし、精神的にもつらくなることがあります。
そしてこの慢性的な痛みに、実は「発達障害のひとつであるADHD(注意欠如・多動症)」が深く関係しているのではないかという新たな研究結果が報告されました。
この研究は、東京大学医学部附属病院と福島県立医科大学を中心に、複数の医療機関の研究者が協力して行ったもので、日本国内に住む20歳から64歳までの成人4,028人を対象とする大規模なインターネット調査の結果に基づいています。
調査の目的は、「ADHDやASD(自閉スペクトラム症)の傾向が、痛みの慢性化やその強さと関係しているのか」という点を明らかにすることでした。
ADHDは、落ち着きがなかったり、注意が散漫だったりといった特徴で知られる発達障害のひとつですが、その症状は子どもだけでなく、大人になっても持続することが少なくありません。
実際、幼少期にADHDの症状があった人のうち、40〜70%は大人になってもなんらかのかたちで症状が残っているとされています。
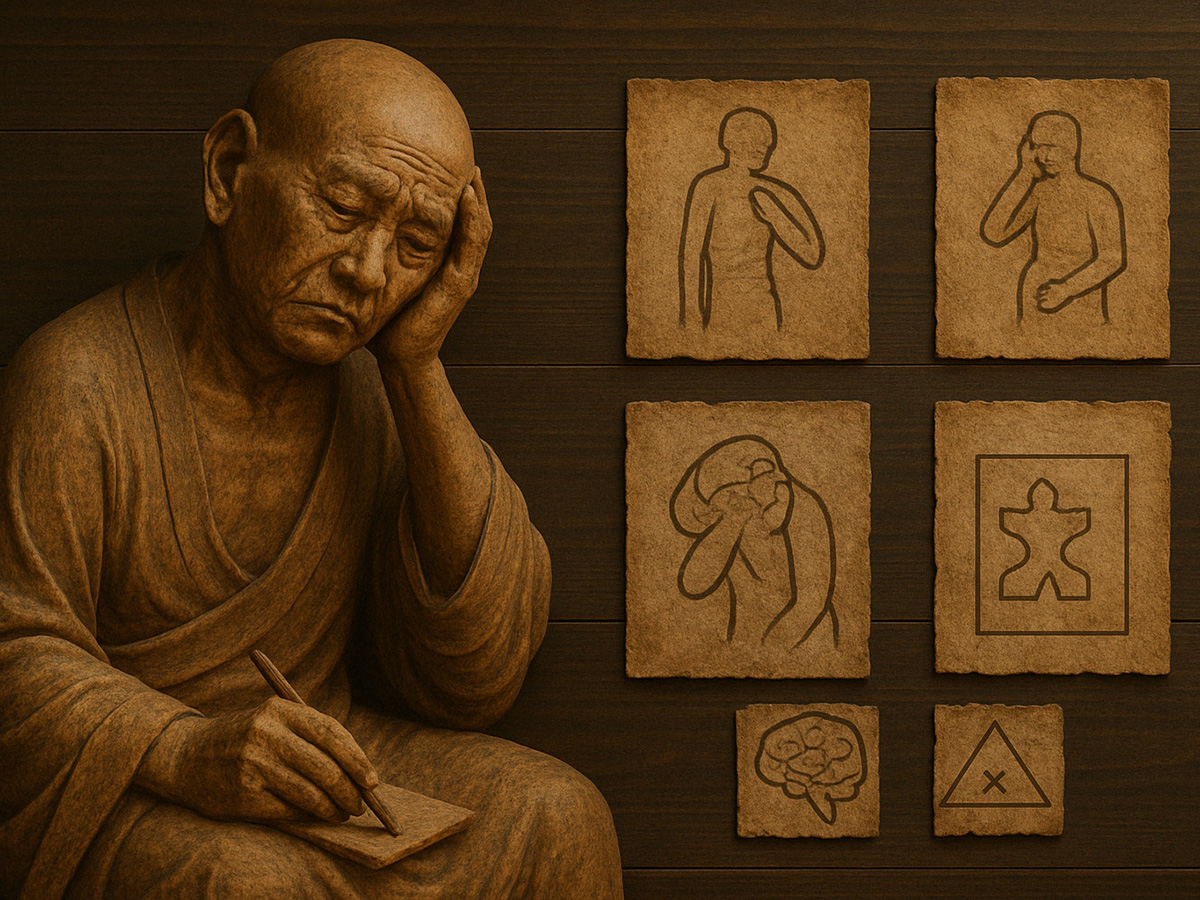
今回の調査では、まず過去4週間以内に「どこかしらに痛みを感じていた」成人を対象に、痛みの部位や程度、続いている期間、精神的な不調の有無、さらにはADHDやASDの傾向を測る心理検査を実施しました。
痛みの評価には、0(痛みなし)〜10(耐えられないほどの痛み)までの数値で答える方式を採用。
ADHDについては、世界保健機関(WHO)が開発した成人用のスクリーニング検査(ASRS)を使い、ASDについても50項目のチェックリストであるAQという検査が用いられました。
その結果、痛みが慢性化している(3か月以上続いている)人の割合は、全体の36.4%に上りました。
このグループでは、とくにADHDの傾向が強い人の割合が高いという傾向が明らかになったのです。
さらに、痛みの強さが増すほど、ADHDのスクリーニング検査で陽性になる割合が増えるという結果も出ました。
最も痛みが強いとされたグループでは、実に38.3%もの人がADHDの傾向があると判定されたのです。
一方で、ASDの傾向と慢性的な痛みの関連については、統計的に明確な関係は見られませんでした。
つまり、痛みと強く関連しているのは、ADHDのほうだったということです。
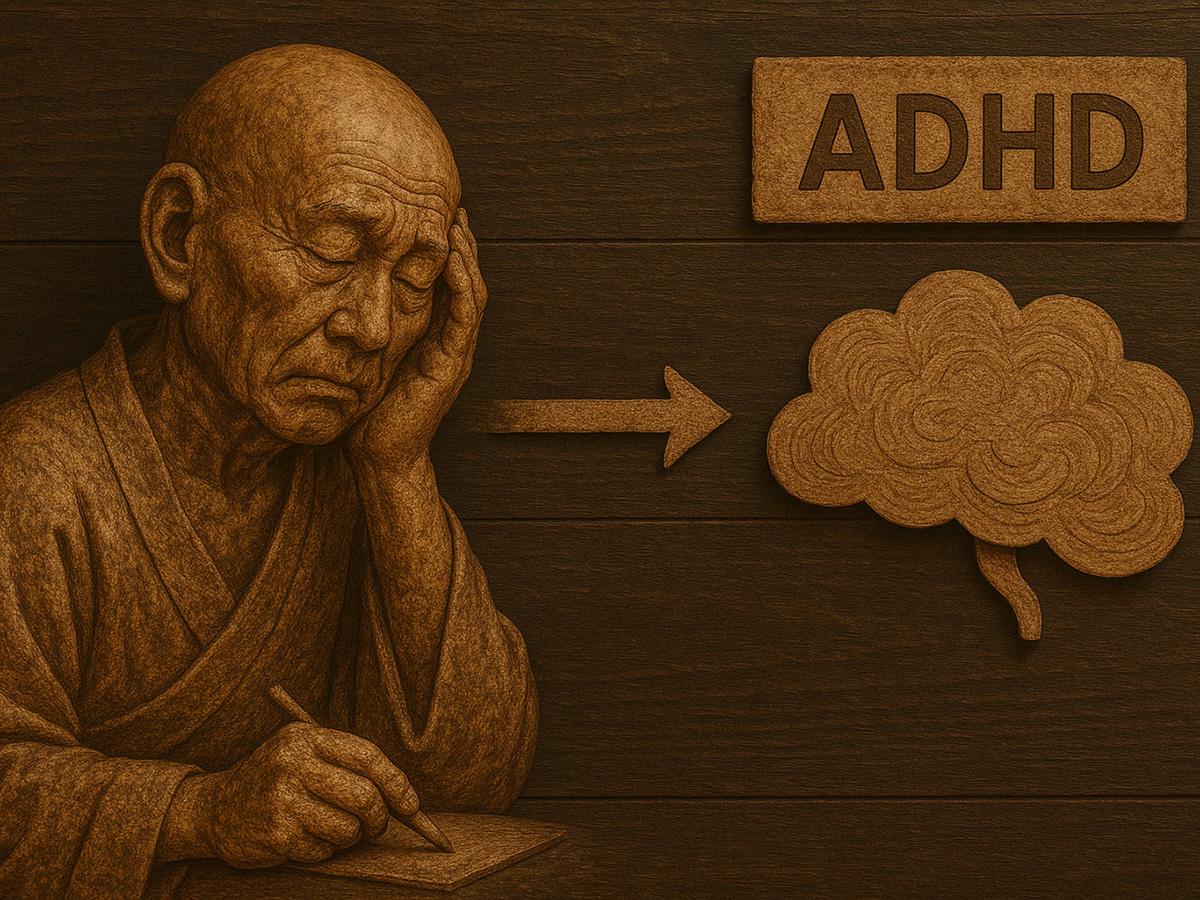
ADHDのある人がなぜ慢性疼痛を感じやすいのか。
その背景には、脳内の神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナリンの働きの違いがあると考えられています。
これらは、注意や感情のコントロールに加えて、痛みの感じ方にも深く関わっているのです。
ADHDの人は、この神経システムの機能に障害があることが多く、それが痛みへの過敏さを引き起こすとされています。
このことは、動物実験でも裏付けられています。
ADHDの症状を持つラットでは、脳の炎症や神経の過敏な反応が観察され、痛みを通常より強く感じやすい状態になっていたことがわかっています。
今回の研究では、さらに統計モデルを用いて、「ADHDの傾向があること」「精神的な不調(たとえばうつや不安)」「痛みの強さや慢性度」の3つの関係性を数値化しました。
その結果、ADHDの傾向があることは、精神的な不調を通じて痛みに影響を与えている可能性が高いことが明らかになりましたが、ADHD自体が痛みと直接的に関係している度合い(影響の強さ)は、精神的な不調よりも大きかったのです。
これは、従来の「慢性疼痛はうつや不安といったメンタルの問題が原因で起こる」といった見方を、ある意味で覆す重要な発見です。
そして実際に、ADHDの治療に用いられる薬(たとえばアトモキセチンやメチルフェニデートなど)は、慢性疼痛の軽減にも効果があるという報告がいくつかの臨床研究でも出てきています。
ADHDの症状を緩和することで、痛みの感じ方そのものが変化する可能性があるのです。
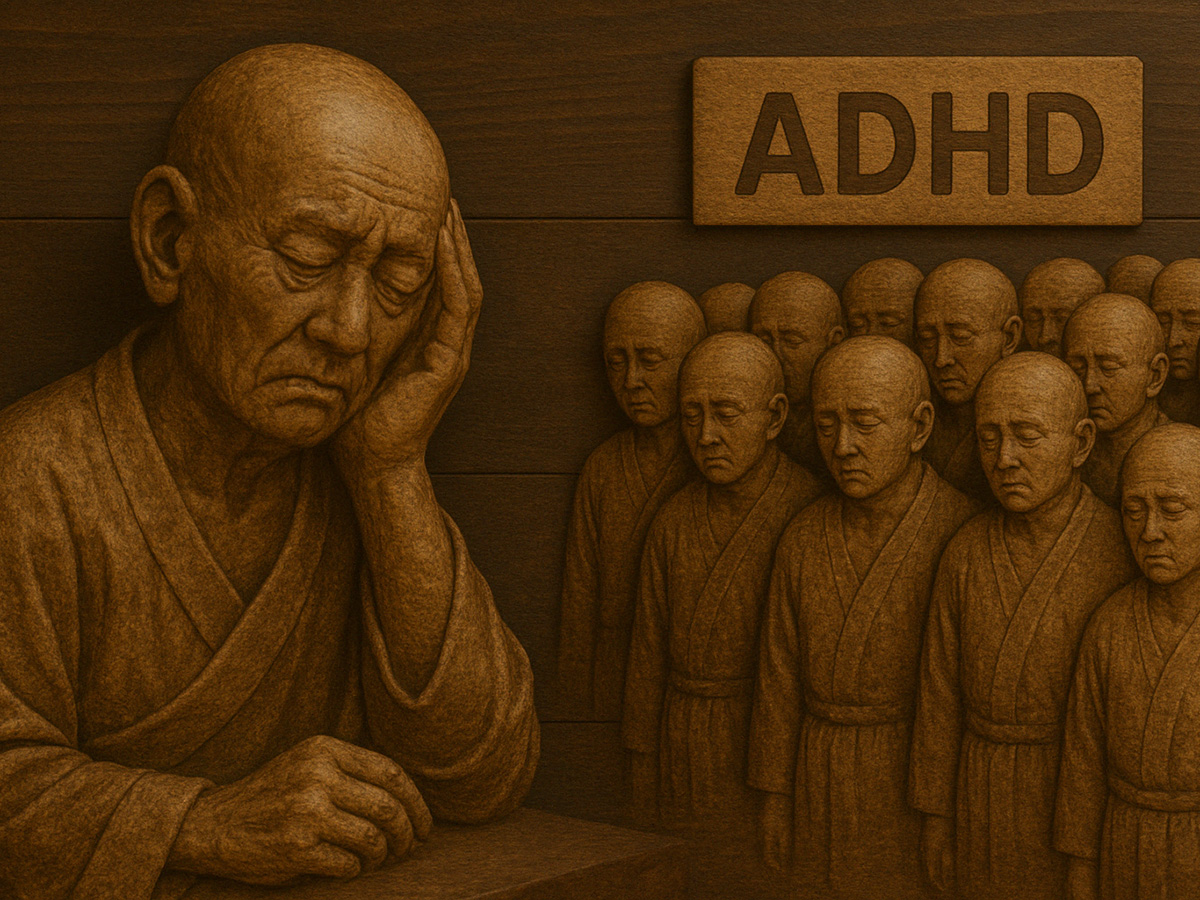
とくに注目されるのは、ADHDと診断されていないまま、長年にわたり痛みに苦しんでいる人たちが多く存在するという事実です。
研究者たちは、精神科の現場でさえ、成人ADHDは80%以上が見逃されている可能性があると指摘しています。
このような背景を踏まえ、研究チームは「慢性疼痛を抱えている人、とくに原因がわからない痛みが続いている人には、ADHDのスクリーニングを行うことが重要だ」と強調しています。
適切にADHDが見つかり、治療が行われれば、痛みの軽減だけでなく、日常生活の質(QOL)の向上、さらには医療費の削減といった社会的なメリットも期待できます。
ただし、この研究にはいくつかの限界もあります。
まず、調査はインターネット上で行われたため、パソコンやスマートフォンを利用できる人だけが対象になっており、回答者には健康に関心の高い層が多かった可能性があります。
また、ADHDやASDの傾向は、医師の診断によるものではなく、あくまでも自己申告によるスクリーニング検査に基づいたものです。
したがって、この調査で「ADHD傾向あり」とされた人が、実際に医師から診断を受けた場合にADHDと認定されるかどうかは、別の問題です。
さらに、痛みとADHDとの関係性が「どちらが原因でどちらが結果なのか」については、今回のような横断的調査だけでは明らかにはできません。
たとえば、痛みが長引くことで精神的なストレスが高まり、その結果としてADHDに似たような症状が現れてくるケースもありえます。
こうした因果関係を正確に理解するには、今後の縦断的(長期的)な研究が必要とされています。
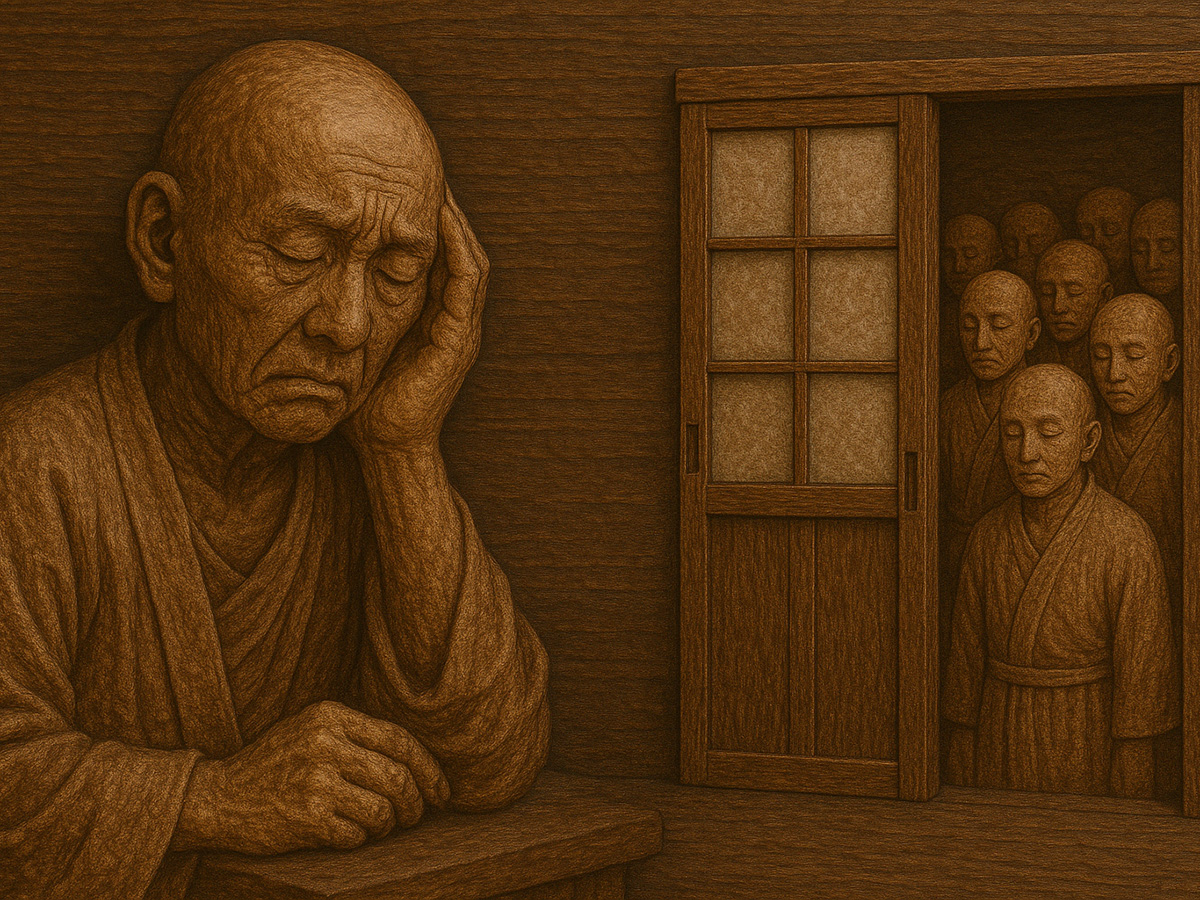
それでも今回の研究は、日本国内の大規模なデータをもとに、ADHDと慢性疼痛の関係性を具体的に明らかにしたという点で、非常に意義のあるものです。
実際に、ADHDの薬が慢性疼痛にも効くことが臨床で観察されていることからも、医療の現場で「痛みの原因」としてADHDに目を向けることの重要性が高まっています。
この研究は、医師や研究者だけでなく、職場の人事担当者や福祉関係者にとっても重要な意味を持つかもしれません。
なぜなら、これまで「原因不明の痛み」として片付けられていたケースの中に、ADHDという隠れた要因があったとすれば、それに気づけるかどうかで、本人の人生の質が大きく変わるからです。
痛みは、目に見えず、他人には理解されにくい苦しみです。
その背後に発達特性が潜んでいるとすれば、もっと多くの人が自分自身の状態を理解し、適切な支援につながる道を開くことができるでしょう。
今回の研究は、「痛み」と「発達特性」という一見無関係に思えるふたつの世界をつなぐ、新しい視点を与えてくれました。
そしてそこには、誰かの人生を少しだけ楽にする、大きなヒントが隠されているのかもしれません。
(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-95864-4)(画像:たーとるうぃず)
ADHDと「慢性的な痛み」に関係があるということは初めて知りました。
適切な支援につながることを願っています。
(チャーリー)