
この記事が含む Q&A
- ADHDの診断が増えていることは過剰診断といえるか?
- 診断増加は必ずしも過剰診断ではなく、支援へアクセスが広がる変化として捉えられています。
- 診断にはどんな意味がありますか?
- 診断は生活の困りごとを理解し必要な支援を受けるための入口であり、単なるラベルではありません。
- ADHDの支援にはどんな方法がありますか?
- 環境の工夫や生活リズムの改善など薬以外の対策も有効で、困りごとの程度や疲れ具合に応じて検討します。
ADHD(注意欠如・多動症)の診断を受ける人が増えています。
子どもだけでなく、大人になってから診断される人も少なくありません。
この傾向を見て、「診断されすぎではないか」「普通の性格の違いまで病気扱いされているのではないか」と感じる人もいます。
しかし、最新の研究では「ADHDの診断が増えていること=過剰診断」とは言えないことが示されています。
ADHDの特性は、注意がそれやすい、集中が続かない、衝動的に行動してしまうなどです。
こうした傾向は、誰にでも少しはあるものであり、その線引きは明確ではありません。
専門家はADHDを「あるかないか」ではなく、「どのくらい強く出ているか」という連続した特性として理解しています。
これまでの研究によると、ADHDの特徴を明確に満たす人は全体の5%ほどですが、実際に診断を受けている人は7〜11%にのぼります。
一見すると、診断される人の割合が多いように見えます。
しかし、それは「本来支援が必要だった人がようやく診断にたどりつけるようになった」ことを意味する場合もあります。
ADHDの症状は、環境によって変化します。
たとえば、小学校では困らなかった子どもが、中学校に進むと急に課題の量や複雑さに対応できなくなり、集中力の問題が目立つことがあります。
大人でも、職場環境の変化やストレス、睡眠不足などで症状が強く出ることがあります。
環境の変化によって特性が目立つようになるとき、支援が必要になります。
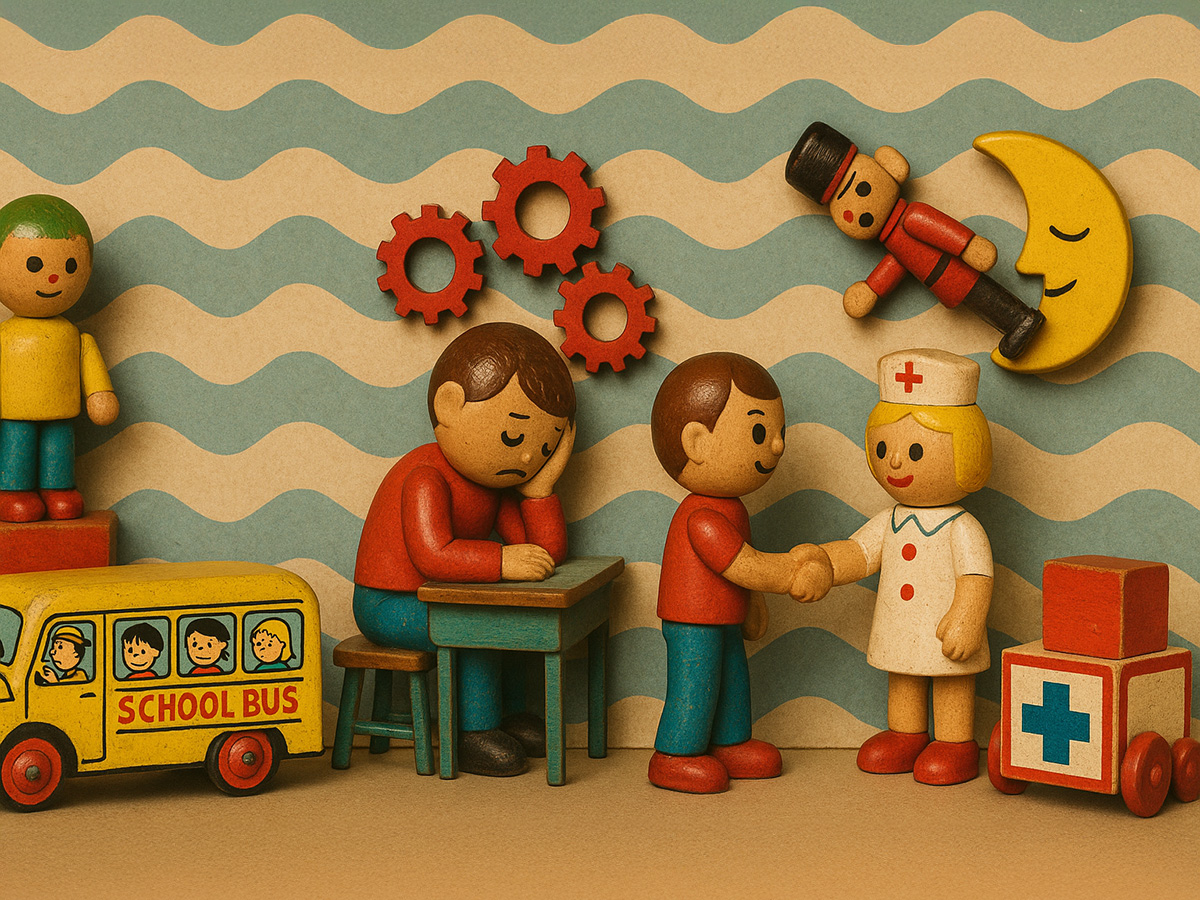
診断の増加には、こうした「これまで見過ごされてきた人たち」が含まれています。
以前は「性格」や「努力不足」とされていた人たちが、今では医学的な理解のもとに支援を受けられるようになっているのです。
これは過剰診断ではなく、支援へのアクセスが広がっているという変化です。
一方で、「過剰診断」の懸念もまったく根拠がないわけではありません。
ADHDの診断は、症状がどの程度、生活に支障を与えているかをもとに行われます。
そのため、生活のストレスや一時的な状況によって症状が強く見えると、実際にはADHDではない人が診断を受けてしまうこともあります。
しかし、研究では、そうした誤診の割合を示す確かな証拠は少なく、「ADHDの診断の多くは妥当である」と結論づけられています。
また、診断の数が増えていても、いまだに多くの人が診断を受けられずに困っています。
とくに、女性や成人、マイノリティの人々では、ADHDの特性が見逃されやすい傾向があります。
診断を受ける人が増えているという現象の裏には、「これまで届かなかった人にようやく支援が届き始めた」という事実もあります。

ADHDは「境界のあいまいな特性」です。
どこからが診断に値するかという線引きは、文化や教育制度、社会のあり方によっても変わります。
学校が求める集中の度合い、仕事で必要とされるマルチタスク能力、オンライン化による注意の分散など、社会の変化が症状を目立たせることもあります。
現代社会では、以前よりも「注意の切り替え」や「持続する集中力」が求められやすくなっています。
そのため、同じ特性でも昔より困りごととして表れやすい状況になっています。
研究者は、「診断が増えている」こと自体を問題とするのではなく、「どんな人が支援にたどりつけているか」「どんな支援が行われているか」をていねいに見ていく必要があると指摘しています。
ADHDの診断は、その人の生き方を制限するためではなく、困りごとを理解し、必要な支援を受けるための入り口です。
ADHDの支援には、薬だけでなく、環境の工夫や生活リズムの改善も含まれます。
たとえば、静かな環境で作業できるようにする、スケジュールを視覚的に整理する、睡眠時間を一定に保つなどの工夫が効果的です。
軽い症状の場合、薬を使わなくても支援がうまく機能することもあります。

研究者たちは、「支援を受けるかどうか」は症状の強さだけで決めるべきではないと述べています。
日常生活にどれだけ困りごとがあるか、どれだけ本人や家族が疲れているかを基準に考えることが大切です。
軽い症状でも、環境の変化やストレスの影響で、生活が難しくなることがあります。
そのようなときは早めの相談や支援が役立ちます。
ADHDの診断を受けたからといって、その人が「異常」になるわけではありません。
特性を理解し、自分のやり方を工夫することによって、生活をより楽にすることができます。
診断はラベルではなく、助けを受けるための手段です。
診断数の増加を「過剰」と決めつけてしまうことは、支援が必要な人を再び見えなくしてしまう危険があります。
むしろ、社会全体がADHDという特性をより正確に理解し、支援のあり方を柔軟にしていくことが求められます。
ADHDは、決して「流行の診断」ではありません。
人が変化の多い社会で暮らすようになり、集中や自己管理が難しくなる環境が増えたことで、困りごとが表面化しているのです。
その意味では、診断が増えることは、「より多くの人が支援にアクセスできるようになった」という社会の成熟を示しているとも言えます。
診断の数ではなく、一人ひとりの生活の質に目を向けること。
過剰かどうかを論じる前に、どんな人が支援を必要としているのかを理解すること。
それが、ADHDをめぐる本当の課題です。
(出典:THE CONVERSATION DOI: 10.64628/AAI.xf6eseewt)(画像:たーとるうぃず)
支援を必要とする方に適切な支援が届くようになる。
そうであれば、増えることは決して悪いことではありません。
(チャーリー)





























