
この記事が含む Q&A
- ADHDの子どもに対して、短い運動は学校での力発揮を支え、運動後だけでなく翌朝まで認知機能の向上が見られると報告されていますか?
- はい、運動サーキット後に三つの認知テストの成績が改善し、翌朝まで効果が続いたと説明されています。
- どんな運動が効果的とされていますか?
- 楽しく体を動かしながら頭を使う「遊びの要素を含む」運動が効果的とされ、教室でも30分程度のサーキットが例として挙げられています。
- 研究の規模や今後の課題は何ですか?
- 参加者は27名と小規模で、効果を確認するためにはさらなる調査が必要だと述べられています。
世界で最も多く診断されている子ども向けの神経発達症のひとつであるADHD(注意欠如・多動症)について、子どもたちが学校で少しでも力を発揮しやすくなる方法を探る研究がイギリスのノーザンブリア大学の研究チームによって行われました。
ADHDは世界中で広く見られ、3〜12歳の約8%、12〜18歳の約6%に影響するとされています。
数字だけを見るととても多くの子どもたちが関わっていることがわかりますが、その一人ひとりには日々の生活の中での困りごとや、頑張っている姿があります。
学校は、子どもたちにとって大事な学びの場であると同時に、ADHDの特性を持つ子どもたちにとっては挑戦が多い場所でもあります。
静かに座って話を聞く、指示をよく理解する、注意を切り替える、衝動を抑える。
こうした場面の連続が授業の中心であり、そのどれもがADHDのある子にとっては少し負担が大きくなりやすいのです。
そのため、行動が目立ってしまったり、授業の理解が追いつかなくなったり、登校への意欲が下がってしまったりすることがあります。
もちろん本人は“やる気がない”わけではありません。
周囲が思う以上に、日々の学校生活は集中と疲労の連続で、努力が続いていることも多いのです。
今回の研究は、そのような子どもたちが学校の中で少しでも安心して力を発揮できるための、新しいヒントを示しています。
それは特別な器具や長時間のトレーニングを必要とするものではなく、短くて楽しい「ちょっとした運動」でした。
しかも、その効果は“運動した直後だけ”ではなく、“次の日の朝まで”続いていたのです。
この「翌朝まで続く」という点は、これまでの研究ではほとんど報告されておらず、とても大きな発見となっています。
研究チームは、ADHDの診断を受けた9〜11歳の子ども27人に参加してもらい、同じ子どもが二つの違う体験をするという方法を取りました。
ひとつは「運動をする日」、もうひとつは「運動をしない日」です。
この二つの体験を比較することで、どのような変化が起きるのかをていねいに調べました。

まず、子どもたちは30分間の「運動サーキット」を行いました。この運動は、ただ走ったり跳んだりするものではありません。
身体を動かしながら同時に頭を使うよう工夫されていて、学校でもできるほどシンプルで楽しい内容でした。
いくつかのステーションが教室や体育館の中に用意され、子どもたちは順に回ります。
たとえば「サイモン・セズ」という遊びでは、指示をよく聞き、正しいタイミングで動く必要があります。
「〇〇して」と言われたら動き、「〇〇して」と言われなかったら動かない。
衝動的に動いてしまいやすい子どもたちにとって、この遊びは“じっと聞く力”と“考えてから動く力”の両方を必要とします。
また、別のステーションでは2人組になり、バスケットボールを交互の手でつきながら友だちにパスをします。
右手と左手を切り替えながらボールを扱うことや、相手の動きを見てタイミングよくパスをすることは、体の協調と注意力、そして瞬間的な判断をすべて使う活動です。
これらの活動は、激しい運動というよりも「楽しく体を動かしながら、頭も一緒に働かせる」タイプのものです。運動の得意・不得意に関わらず誰もが参加でき、しかも友だちと声をかけ合いながら自然に取り組める、そんな工夫が詰まっていました。
もう一方の体験は、比較のために用意された「休息だけの時間」です。子どもたちは教室の席に座ったまま、特に運動はせずに過ごします。
この体験が“運動をしなかった場合”の状態となり、後で調査結果を比べるための基準になります。
運動と休息の二つの体験を行ったうえで、子どもたちはパソコンを使って三つの認知テストを受けました。
テストはそれぞれ、「運動の前」「運動のすぐ後」「運動の翌朝」に行われました。
休息の場合も同じタイミングでテストを行い、差を比べます。
こうすることで、「運動が認知の働きにどのような影響を与えたのか」を細かく調べることができるのです。
三つのテストのうち、ひとつめは「ストループ・テスト」と呼ばれるものです。
これは衝動を抑える力を見るテストで、ADHDのある子どもたちがしばしば困難を感じやすい部分です。
たとえば“青”という色の文字が赤で表示されるなど、視覚と意味が食い違う刺激を見たときに、自動的に反応してしまいそうになる衝動を抑えて正しく判断できるかを測るものです。
このテストは、日常生活での「ちょっと待つ」「すぐに動かない」といった行動に関係する力を見るため、学校でも家でも役に立つ視点を与えてくれます。
ふたつめのテストは「スタンバーグ課題」と呼ばれ、短い時間の記憶を扱います。
画面に一瞬だけ数字や記号が表示され、それが後で出てきたときに「さっき見たものかどうか」を答えるテストです。
これは短期記憶や作業記憶と呼ばれる力に関わっていて、授業中に先生の話を理解したり、説明を聞いたうえで行動に移したりする場面で役立つ要素です。
三つめのテストは「視覚探索テスト」です。
画面の中に多数の図形や記号があり、その中から指定されたものを素早く探し出すテストです。
注意を向ける力や、情報を整理して把握する力が必要になります。
ADHDのある子どもは、情報が多い環境で注意を向ける対象を絞ることが難しいことがあるため、このテストはそうした特徴を理解するうえでも重要なものです。

結果は非常に興味深いものでした。
運動サーキットの後、子どもたちは三つのテストすべてで、休息だけの日よりも良い成績を示したのです。
しかもただ正解が多くなっただけではなく、反応が少し“ゆっくり”になっていました。
この「ゆっくり」という変化は、単なる遅さではなく、「急がずに、ていねいに考えてから答える」という方向への変化です。
ADHDのある子どもの多くが、“思わず動いてしまう”“すぐ答えてしまう”という衝動的な反応で困ることがある中、この変化は非常に意味のあるものでした。
焦らずに考えて正確に答えられるというのは、学校生活の中で大切なスキルであり、授業の理解や友だちとのやり取りにも良い影響を与える可能性があります。
さらに驚くべきことに、この効果は翌日の朝まで続いていました。
運動をした日の翌朝に行われたテストの結果でも、子どもたちは休息だけの日よりも良い成績を出していたのです。
この「翌日までの効果」は、これまでほとんど研究されてこなかった部分であり、今回の研究が示した最も大きな発見のひとつです。
学校生活では、昨日の疲れが残って集中しづらい朝の時間帯はとくに重要です。
朝の授業の理解がスムーズになることは、その日の学習全体にも影響します。
こうした背景を考えると、今回の発見は教師や保護者だけでなく、子ども自身にとっても大きな希望を持てるものだと言えます。
もちろん、この研究は参加者が27人と少なく、さらなる調査が必要であることは研究チームも明確に述べています。
しかし“少ない時間の、楽しい運動”が、子どもたちの認知の働きを改善し、その効果が翌日まで続いたという結果は、これまでにない大切な示唆を与えてくれます。
さらに研究チームは、こうした一回限りの運動の効果はこの研究だけに限られたものではないと指摘しています。
他の研究でも、遊びの要素が入った運動、つまり“ゲームのような運動”がADHDのある子どもの認知機能に特に良い影響を与えることが報告されています。
短時間の運動でも効果があるという点は、学校現場にとって非常に導入しやすい特徴です。
特別な道具を使わず、教室や体育館でも簡単に行えることから、教師が授業の合間に取り入れることも可能です。
また、持久的な運動、たとえば20〜45分ほどのランニングやサイクリングでも、衝動を抑える力や考えを切り替える力が高まることが示されています。
研究チームのレビューでは、「体を動かしながら頭も使う運動」のほうが記憶や注意力に対する効果が大きいという報告もあります。
このように、どれが“絶対に正しい”というよりも、複数の運動が子どもたちの脳の働きを支える力を持っていることが、研究全体から見えてきます。
しかし現実には、ADHDのある子どもは運動習慣を続けることが難しいという調査結果もあります。
最近の研究では、ADHDのある子どもは同年代の子に比べて21%も運動ガイドラインを満たしにくいと報告されています。
背景には、やる気が出にくい、できると思えない、自信が持てない、環境が刺激的すぎて落ち着かないといった感情面の課題もあります。
学校や家庭で「やればできる」と励ましても、その言葉がプレッシャーになってしまうこともあります。
しかし今回の研究は、「運動の量」を求めるのではなく、「楽しい」「参加しやすい」活動が効果を持つ可能性を示しているため、無理のない範囲で取り入れる道筋が見えています。
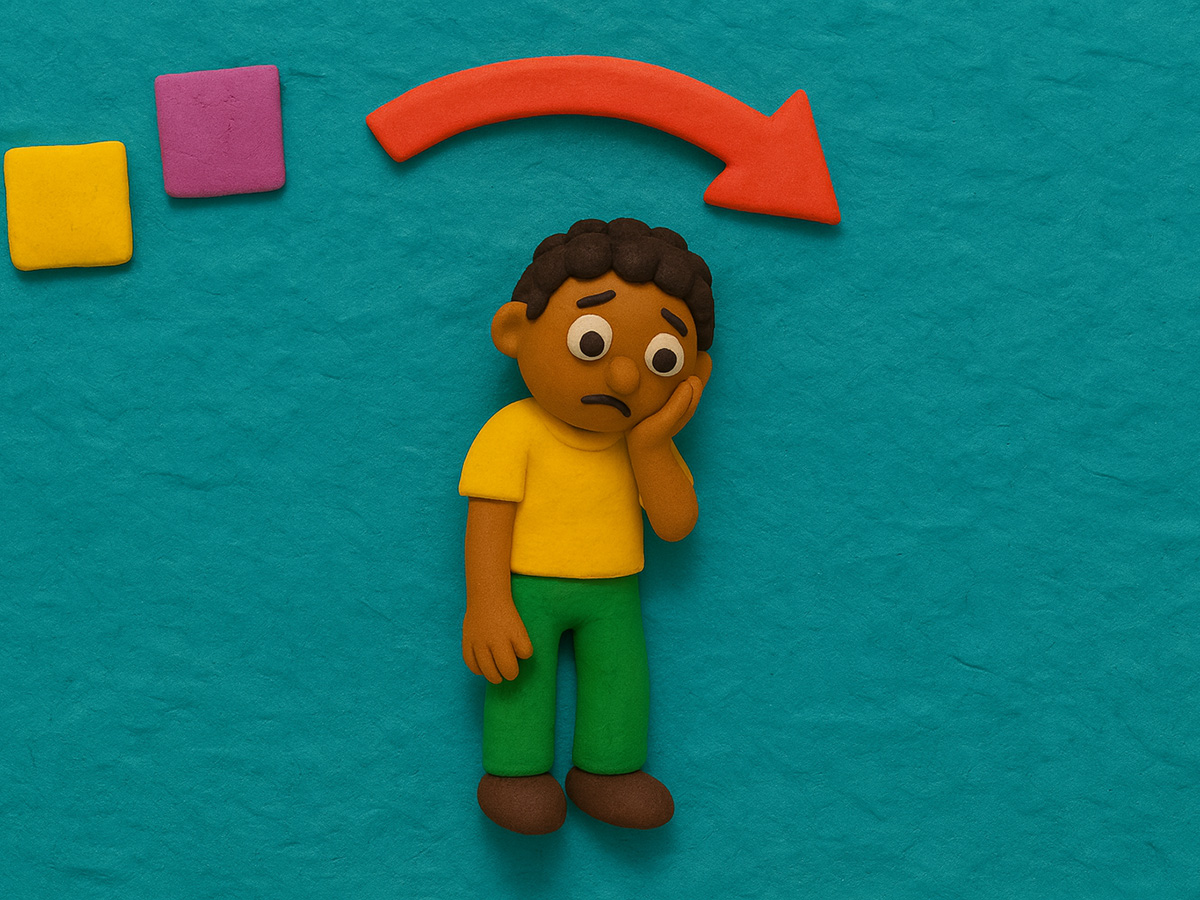
大事なのは、運動がADHDの特性そのものを消すわけではないということです。
けれど、子どもが自分の力を発揮しやすくなったり、授業の理解がスムーズになったり、衝動を抑えやすくなったりすることで、日常が少し楽になる可能性があります。
これは本人にとっても周囲にとっても、安心して学校生活を送るための大きな助けになるでしょう。
今回の研究を行ったノーザンブリア大学の研究チームは、これらの結果から「短くても、楽しい運動が、翌日まで子どもを支えることができる」と強調しています。
運動は特別な薬や機器と違い、学校でも家庭でも取り入れられるものです。
子どもが笑顔で取り組める運動なら、習慣にもつながりやすく、学びの環境もより良いものになる可能性があります。
ADHDのある子どもたちは、決して“できない”わけではありません。
少しの工夫や環境の調整によって、本来の力がもっと自然に出せるようになります。
今回の研究は、そうした工夫のひとつが「楽しく体を動かすこと」であることを、ていねいに示したものです。
翌日まで効果が続いたという事実は、学校の中での小さな取り組みが、子どもたちの毎日に確かな変化をもたらす可能性を伝えてくれます。
子どもたちが自分らしく学び、安心して力を発揮できるためには、体も心も“ほぐれる”時間が必要です。
今回の研究は、そのためのヒントをやさしく教えてくれています。
短い運動、友だちとの遊びのような活動、少しの達成感。
それだけで、昨日よりも今日、今日よりも明日を、穏やかに過ごせる手がかりがあるのかもしれません。
(出典:THE CONVERSATION DOI: 10.64628/AB.55ddgeumn)(画像:たーとるうぃず)
「ちょっとした運動」で、次の日まで「安心して学校生活を送るための大きな助けになる」。
うまく取り入れたいですね。
(チャーリー)




























