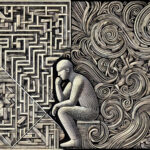この記事が含む Q&A
- 自閉症の子どもの将来の知的障害や言葉の発達は早期に予測できますか?
- 遺伝情報と発達行動を組み合わせた予測モデルにより、一定の精度で予測が可能です。
自閉スペクトラム症(ASD)と診断された子どもたちをもつ親の多くが抱える最も切実な問いは、「この子は将来、どのように育つのだろうか?」ということです。
とくに気になるのは、知的障害(ID)を伴うかどうか、そして、言葉を話せるようになるのか、人と関わる力が育つのか、独立して生活できるようになるのかといった、日常生活の基本に関わる力についてです。
このような不安に対し、医療や教育の現場ではできるだけ早く、その子に合った支援を届けることが望まれています。
しかし現実には、多くの場合、「もう少し様子を見ましょう」と言われ、支援の手が遅れてしまうことも少なくありません。
その背景には、「この子が将来どうなるのか」を予測するための、信頼できる手がかりが不足しているという現実があります。
今回、カナダやイギリスを中心とする国際研究チームが、自閉症と診断された子どもたちが将来的に知的障害を伴うかどうかを、できるだけ早い段階で予測できるようにするための研究を行いました。
その成果は、アメリカの医学専門誌「JAMA Pediatrics」に発表され、大きな注目を集めています。
この研究では、発達の節目となる行動(たとえば、一人歩きや言葉の出始めなど)と、遺伝子情報の両方を組み合わせて予測モデルをつくることで、子どもの将来像をより早く、より正確に見立てる可能性があることが示されました。
研究を主導したのは、カナダ・モントリオールのCHUサント・ジュスティーヌ小児病院のヴィンサン=ラファエル・ブルク医師、ゾエ・シュミロヴィッチ博士らです。
また、イギリス・ケンブリッジ大学のバロン=コーエン博士やワリエル博士ら、自閉症研究の第一人者たちも参加しています。
研究チームは、アメリカとカナダで収集された3つの大規模な自閉症研究データベースを使用しました。
対象となったのは、遺伝子検査の結果と発達の情報がそろっている自閉症の子ども5,600人以上。全体の約2割が、後に知的障害の診断を受けていました。

彼らは、以下のような情報を予測モデルに取り込みました:
- 一人歩きを始めた月齢
- 初めての言葉が出た月齢
- 言葉の後退(話せていた言葉が急に使えなくなる)の有無
- トイレの習得時期(おしっこ、うんち)
- 知的能力に関係する多遺伝子スコア(PGS)
- 自閉症に関係する多遺伝子スコア
- 稀な遺伝子の欠失・重複(CNV)
- 新たに生じた遺伝子変異(de novo)で、重要な遺伝子を損なう変異
モデルの性能を示す数字として、AUROCという指標があります。
これは0.5なら「当てずっぽう」と同じで、1.0に近いほど「完璧な予測」です。
今回の研究で開発されたモデルは、AUROC 0.653というスコアを記録しました。
これは医療現場で十分に活用できる水準とは言えませんが、「現状のままよりはずっとマシ」と言えるレベルです。
また、ある特定の遺伝子の組み合わせを持つ子どもたちについては、「この子は将来、IDを伴う可能性が高い」と予測する力がとくに強くなっていました。
そのような子どもたちをモデルが正しく予測できた確率(PPV)は、最大で55%に達しました。
つまり、「この子はIDを伴う」と予測された場合、その半分以上は本当にIDを伴っていたということです。
ただし、このモデルが「IDを伴わない」と予測した場合に、実際にIDを伴わなかった割合(NPV)は、最大でも89%程度にとどまりました。
これは、予測ミスを完全には防げないという現実も示しています。

興味深いのは、遺伝子情報だけでは予測の力が弱く、発達の遅れがあってはじめて、遺伝情報の意味が強まるという点です。
たとえば、発達の節目が遅れている子どもに対して、ある種の遺伝的な変異が見つかった場合には、「その遅れはただの個人差ではないかもしれない」という判断がしやすくなります。
また、逆に発達の遅れがあまり見られない場合でも、遺伝子に注目することで、「将来IDを伴う可能性は低い」と推測できることもあります。
研究チームは、さらに詳しく分析を進め、「言語の発達」「社会性」「日常生活の適応力」といった細かな能力ごとの予測にも挑戦しました。
その結果、ある種の遺伝的変異は「言葉の理解」に、別の変異は「運動スキル」に、またある変異は「日常生活の適応力」に影響しやすいことも明らかになりました。

これらの知見は、個々の子どもの支援方針を立てるうえで、きわめて重要なヒントになります。
たとえば、ある子には「言葉のトレーニング」を早くから重視した方がよいかもしれないし、また別の子には「身体の動かし方」や「トイレの練習」を丁寧に進めることがカギになるかもしれない、というふうに。
もちろん、今回の研究には限界もあります。
たとえば、発達の節目に関するデータは、保護者の記憶に頼った部分が多く、記録の正確さにばらつきがある可能性があります。
また、研究に参加したのは主にヨーロッパ系の家族であり、他の人種や文化的背景を持つ家庭にはこのモデルが当てはまらない可能性もあります。
それでも、この研究が示した方向性は、自閉症の診断から支援へとつながる「橋渡し」として、大きな意義を持つといえるでしょう。
「将来が不確かだから、何もできない」ではなく、「確実ではないけれど、ある程度の見通しがある」ことで、早期から適切な支援を考えることができる。
この変化は、子どもたちの人生だけでなく、家族の不安やストレスを軽減し、支援する側にとっても貴重なガイドになります。
今後、さらに多くのデータが蓄積され、多様な背景を持つ子どもたちを対象にした予測モデルが整備されれば、「自閉症」という診断がもたらす不確かさは、徐々に「道しるべ」へと変わっていくのかもしれません。
(出典:JAMA Pediatrics)(画像:たーとるうぃず)
うちの子もちょっとおかしいなと思った、2歳頃に相談しても、「様子をみましょう」でした。
しばらく「様子をみましょう」で、自閉症や知的障害と診断をされたのは、すっかり言葉もなくなってしまった4歳頃でした。
早期療育をより行うには、こうした新しい推定方法が必要です。期待しています。
(チャーリー)