
この記事が含む Q&A
- 障害のあるきょうだいの診断をどう理解すればよいですか?
- 診断は家族や本人の理解を深めるものであり、向き合い方が関係性に大きく影響します。
- きょうだいの心の状態や関係性に良い影響を与えるにはどうしたらよいですか?
- 家族全体の診断受容と理解を促進し、きょうだいへの支援やコミュニケーションを重視することが重要です。
- 兄弟姉妹間の関係を良くするためのポイントは何ですか?
- 相手の違いを認め合い、信頼と親密さを築きながら、嫉妬や対立を和らげる努力が効果的です。
障害のある人のきょうだいとして育つこと。それは、子ども時代から大人になるまで、人生のさまざまな場面で心のあり方に影響を与えるものです。
イタリアのサレント大学による最新の研究では、障害のあるきょうだいの「診断」に対して、親やもう一人のきょうだいがどのように受け止め、向き合ってきたかが、家族の関係性、とくにきょうだい関係に大きく関わっていることが明らかになりました。
この研究は、典型的に発達しているきょうだい、「障害のないきょうだい」たちの心の状態に焦点をあてたものです。
障害のあるきょうだいを持つ障害のないきょうだいが、その障害の診断にどう向き合い、どのように受け止めているのか。
その心のプロセスと、きょうだい関係の質(たとえば親しさ、けんかの頻度、嫉妬心、自分の感情を抑える傾向、不安など)とのつながりを探りました。
調査には、イタリア全国の365組の親子が参加しました。
親と、その障害のある子のきょうだいのペアです。
障害のないきょうだいの年齢は18〜39歳で、調査時点ではすでに成人している人たちです。
対象となった障害には、自閉スペクトラム症、知的障害、ADHDなどの神経発達症だけでなく、視覚障害や身体麻痺といった身体障害も含まれています。
この研究では、2024年の春から秋にかけて、イタリア国内でオンライン調査を実施しました。
調査対象となったのは、障害のある子どもをもつ親と、その子どものきょうだい(18〜39歳の障害のないきょうだい)です。
親子合わせて365組のペアが参加し、それぞれが専用のアンケートに回答しました。
調査ではまず、親に対しては「診断をどれだけ受け入れているか」を測るために、「診断への反応質問票」という42項目からなるアンケートを使用しました。
この質問票では、「私は子どもの障害に対する気持ちが以前と比べて変わったと感じている」「子どもの困難と同時に、強みや達成にも気づけるようになった」などの肯定的な項目と、「自分の子どもに起きたことに怒りを感じる」「障害について考えるのがやめられない」といった否定的な項目が含まれており、5段階で回答する形式です。
これによって、どの程度診断を受け入れているか(受容スコア)を数値化しました。
同じく障害のないきょうだいにも、内容を自分の兄弟姉妹にあわせて調整したバージョンの質問票を用意し、「私はきょうだいの障害について家族や他の人と共有できている」「きょうだいは困難にもかかわらずよく頑張っていると感じる」などの肯定的項目と、「将来的にきょうだいが自立できるとは思えない」「きょうだいに起きたことに怒りを感じる」といった否定的項目について5段階評価で答えてもらいました。
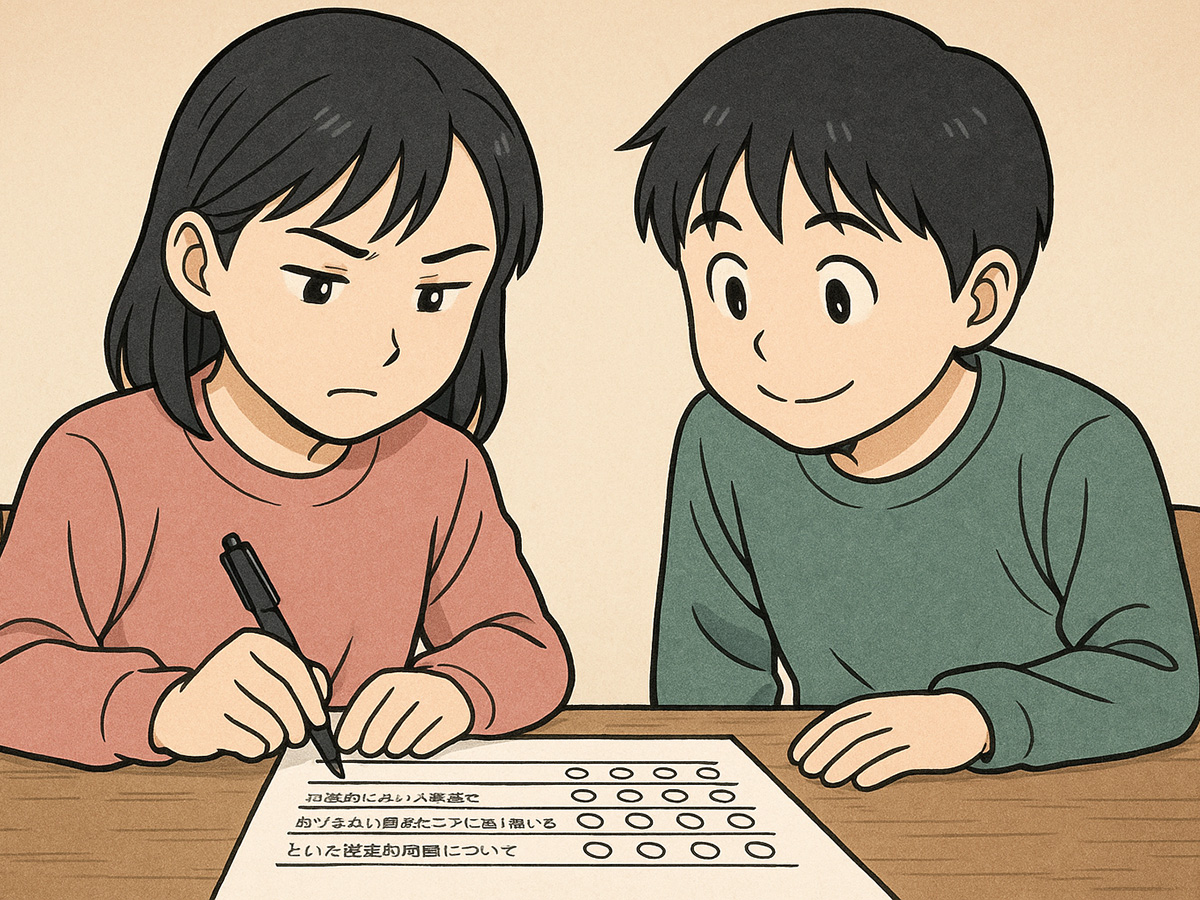
また、障害のないきょうだいとの関係の質を測定するために、「きょうだい関係体験スケール(Siblings’ Experience Quality Scale)」という別の質問票も使用しました。
ここでは、以下の5つの側面について23項目の質問が用意されました。
- 親密さ(例:「私はきょうだいに『大切だよ』と伝えることがある」)
- 対立(例:「きょうだいの行動にイライラすることがある」)
- 嫉妬(例:「親の態度に対して、きょうだいに嫉妬を感じたことがある」)
- 自己抑圧(例:「親に心配をかけたくないので、自分の気持ちを隠してしまう」)
- 将来への不安(例:「きょうだいが家庭の外で幸せに暮らせるか不安がある」)
さらに、兄弟姉妹の障害の重さを評価するために、「バーテル指数」という日常生活動作の支援の必要度を測る尺度も用いました。
食事、着替え、洗面などの6項目について、どの程度自立しているかを5段階で回答する形式で、合計点が高いほど障害の重さが大きいことを意味します。
得られたデータをもとに、研究者たちは統計解析を行い、次のような重要な結果を導き出しました。
まず、「親の受容スコアが高いと、障害のないきょうだいの受容スコアも高くなる」という相関が見られました。
つまり、親が障害をどれだけ現実として受け入れているかが、きょうだいの考え方にも影響を及ぼしているということです。
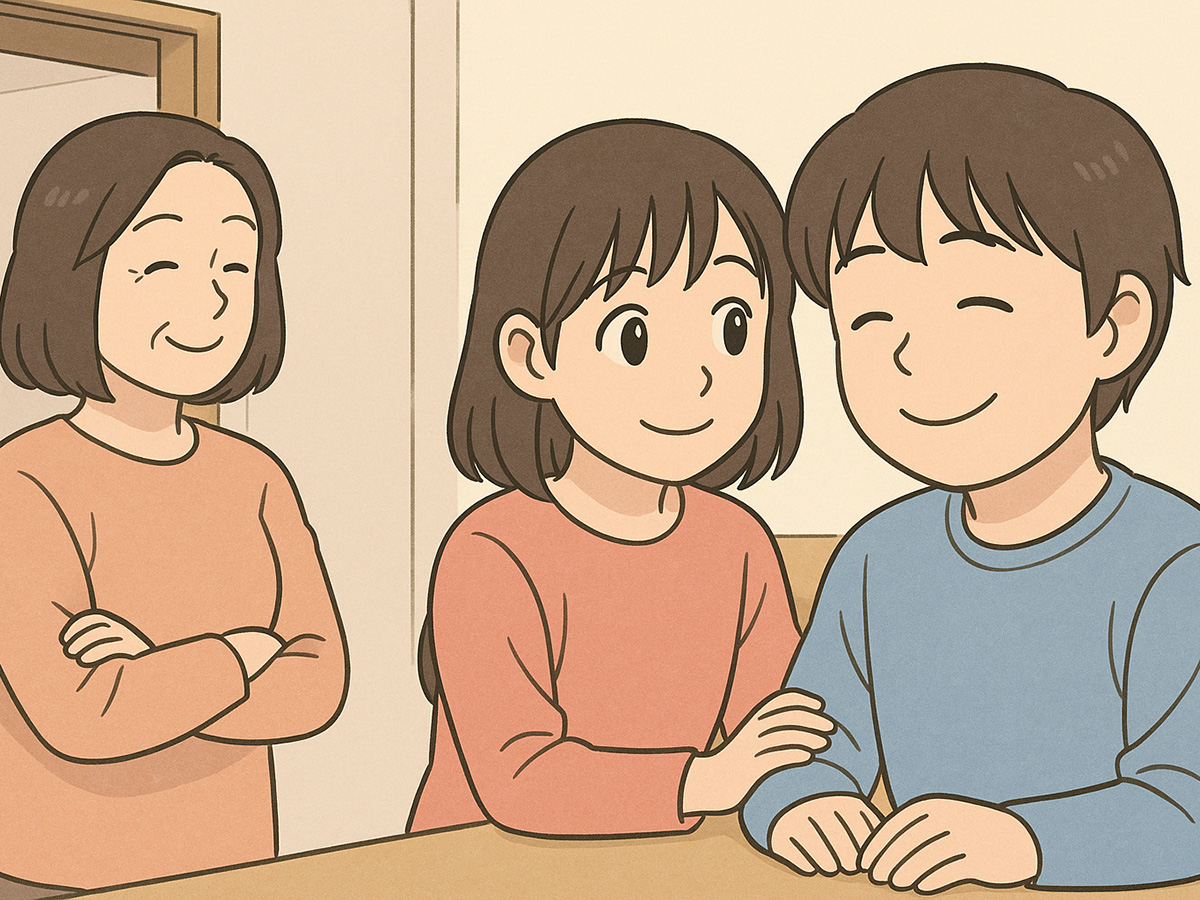
また、障害のないきょうだいの受容スコアが高い人ほど、兄弟姉妹との関係で以下のような傾向が見られました。
- 親密さが高い(仲が良い、信頼関係がある)
- 対立が少ない(けんかや摩擦が少ない)
- 嫉妬が少ない(親の愛情に対する不満が少ない)
- 自己抑圧が少ない(自分の感情を押し殺すことが少ない)
- 将来への不安が少ない(きょうだいの今後について前向きに捉えている)
とくに「嫉妬」と「将来への不安」に関しては、障害のないきょうだいの受容度が高いことで強く改善されることが明らかになりました。
加えて、年齢や性別、生まれ順による違いもありました。
- 年下のきょうだいの方が、障害をより受け入れている傾向が強く見られました。
- 女性の障害のないきょうだい(姉妹)は、きょうだいとの関係に親密さを感じる一方で、「親に迷惑をかけてはいけない」と考え、自己抑圧の傾向が強いことも示されました。
- 障害の重さが強い場合には、きょうだいの受容スコアは下がりやすい一方で、親密さは保たれ、むしろ嫉妬が少ない傾向も確認されました。
このようにして、診断の受容度がきょうだい関係のあらゆる側面に影響を及ぼすことが、具体的な数値とともに実証されました。
研究の統計モデルも良好な適合度を示し、信頼できる結果と評価されています。
このような結果から研究者たちは、障害の診断を受けた家族の支援においては、親だけでなく、きょうだいにも焦点を当てた支援が必要だと提言しています。
とくに、きょうだいがどのように診断を理解し、受け止め、将来の役割をどう意識しているのかに注目することで、家族全体の健康と安定を支えることができるとしています。
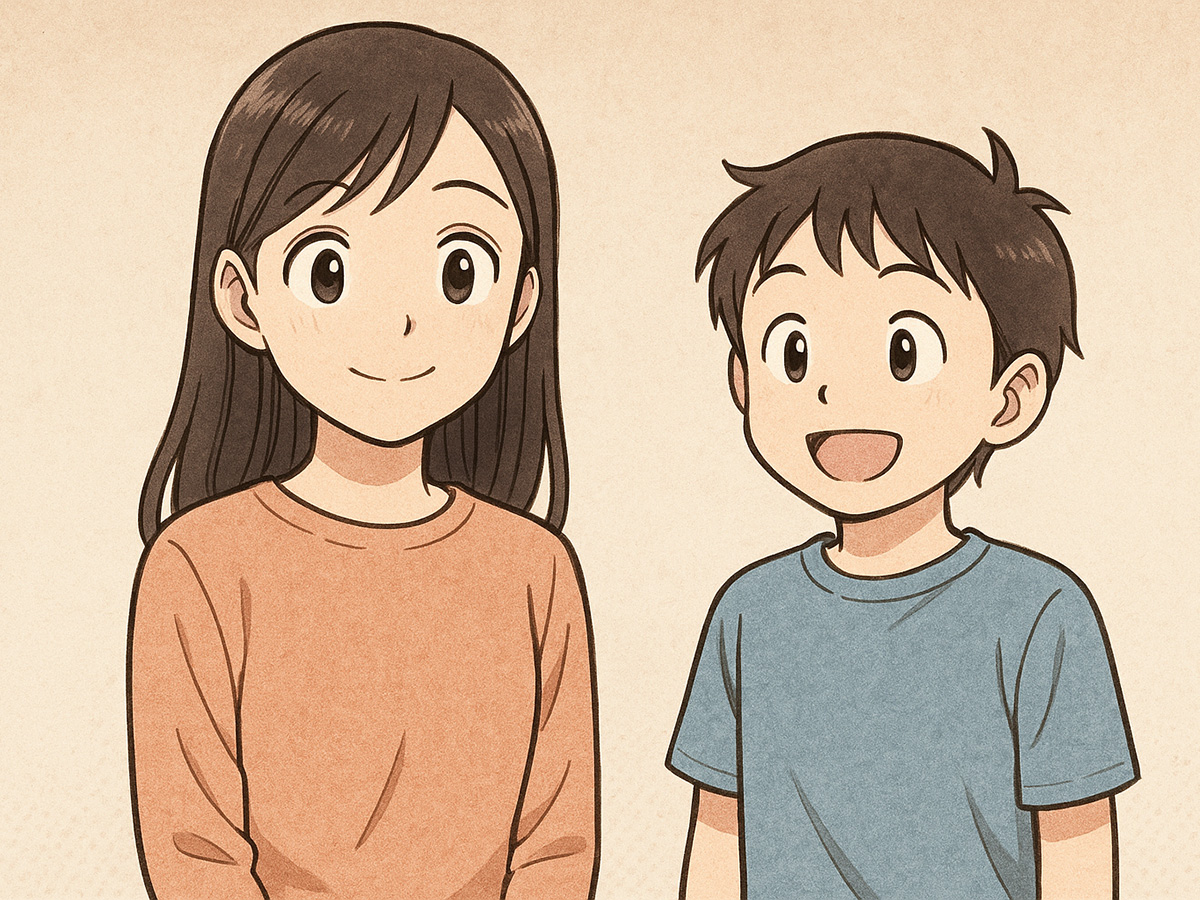
また、今後の研究では、きょうだいの精神的な健康や長期的なケア責任への影響も調査対象にする必要があるとしています。
障害のないきょうだいの「診断の受容」は、単に心理的な適応にとどまらず、家族の未来を左右する重要な要素であることが浮き彫りになりました。
この研究は、障害を持つ人の家族に対する支援をより包括的なものにするための一歩といえるでしょう。
きょうだいの存在とその心理に光を当てた点で、実践的にも大きな意味を持つ研究です。
きょうだいという存在は、人生の中で最も長く続く関係のひとつです。
その関係が、互いの違いを認め合い、理解と支え合いに満ちたものになるために、社会や支援者ができることはまだまだ多くあります。
「障害があるかどうか」ではなく、「その人をどう見ているか」「家族としてどう向き合っているか」が、関係を左右する大きな要素です。
そしてその見方は、親から子へ、子からきょうだいへと、確かに受け継がれていくのです。
(出典:Frontiers DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1551953)(画像:たーとるうぃず)
うちの子は、一緒に遊んだりすることも、話したりすることもできないので、ちいさな頃にきょうだいがよく「つまらない」と言っていたのを思い出します。
それでも、ずっと優しくしてくれ、障害のあるうちの子もニコニコしながらよくきょうだいの顔を見ています。
未診断の自閉症が原因である可能性。疎遠になった「きょうだい」
(チャーリー)




























