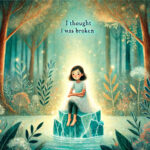この記事が含む Q&A
- ADHDを持つシングルマザーと子どもの関係を深める要因は何ですか?
- 共に生きる経験、オープンな対話、ADHDを理解の力として受け止めることが関係を強くします。
- 「相互理解の連鎖」とはどのような循環を指しますか?
- 母が自分の特性を理解して子を受け入れ、子が自己受容を育み母親への理解を生む循環です。
- どんな支援が有効と提案されていますか?
- 欠けた部分を補う支援ではなく、共感・正直な対話・自分を理解する知恵などの強みを活かす支援が有効とされています。
南アフリカの家庭の多くは、母親ひとりが支えています。
統計によると、その割合はおよそ七割にもなります。
そんな中、自分自身がADHD(注意欠如・多動症)を持ちながら、同じADHDをもつ子どもを育てている母親たちがいます。
彼女たちは毎日を全力で生きながらも、社会の中で理解されることが少なく、その経験は語られることがほとんどありません。
南アフリカ・ステレンボッシュ大学の研究チームは、そうした母親たちの声に耳を傾けました。
研究のタイトルは「ADHDを持っていてよかった(It’s a Blessing that I Have ADHD)」。
その言葉どおり、彼女たちは自分のADHDを“祝福”として語っています。
自分の特性を受け入れ、子どもの特性と重ね合わせ、日々の生活を支え合う姿がそこにはありました。
研究に参加したのは、ADHDの診断を受けた七人のシングルマザーたちでした。
彼女たちはいずれも、5歳から17歳のADHDの子どもを育てています。
離婚や別居を経験し、経済的にも社会的にも支援が少ない中で暮らしていました。
それでもインタビューでは、どの母親も明るい笑顔を見せ、自分と子どもの関係を誇らしげに語っていました。

調査は、質問を決めすぎず会話のように進める聞き取り調査と、母親たちが自ら書いた振り返りの文章を分析する形で行われました。
研究チームは、心理学者ブロンフェンブレンナーの「生態学的発達モデル(バイオエコロジカル・モデル)」を理論の土台としました。
このモデルは、人の発達を「個人と環境の相互作用」としてとらえる考え方です。
母親と子どもが互いに影響し合いながら成長していくプロセスを、科学的に理解するための枠組みとして用いられました。
研究の結果、母親たちの語りの中には、共通した三つのテーマが見えてきました。
ひとつは、「共に生きる経験が親子の絆を育てていること」。
ふたつめは、「オープンで正直な会話を通じて関係を築いていること」。
そして三つめは、「ADHDを弱点ではなく、理解の力として受け止めていること」
でした。
母親たちは、自分の子どもを「大変な子」ではなく、「自分と似た子」として見ていました。
「息子が泣きながら“ぼくはどこにも居場所がない”と言ったとき、私も同じ気持ちを抱いてきたことを思い出しました。
だから“わかるよ”と心から言えたんです。」
そう語る母親がいました。
彼女たちは、子どもの混乱や衝動、集中の難しさを「理解できる」と言います。
それは同情ではなく、共感(エンパシー)です。
ある母親はこう話していました。
「共感は“かわいそう”とは違う。
私は“わかる”と言えるから、助けてあげられる。」
自分が同じように苦しみ、同じように失敗してきたからこそ、子どもの気持ちを想像できる。
この“共に生きる感覚”が、親子の絆を特別なものにしていました。
母親たちはまた、子どもに対して「怒りやすい自分」も正直に話していました。
「私もイライラする。だけど、それが私のADHDなんだって説明するようにしている。」
その正直さが、かえって子どもの理解を生みました。
「ママが怒っても、ぼくはわかってる。ママもADHDだから。」
そう言って笑ったという息子の言葉を、ある母親はうれしそうに語っていました。
母親だけでなく、子どもたちもまた、母親の特性を理解しようとしていたのです。
「お互いに忘れっぽいけど、それも私たちの一部なの。」
母親のその言葉は、欠点を責めるのではなく、共に受け入れる強さを感じさせます。

このような関係を支えていたのが、「オープンな対話」でした。
母親たちは、子どもと本音で話し合うことを何より大切にしていました。
「私たちは、よく謝り合うんです。
私が怒ったら、“ごめんね、ママも落ち着けなかった”と言う。
息子も“ぼくも遅れちゃってごめん”と言う。
それで、また一緒に笑う。」
ある母親は、話しにくいことを手紙でやりとりしていると話しました。
「言葉にできないことは紙に書いてベッドに置いておく。
私はその手紙を読んで、返事を書いておくんです。」
そんなやり方で、信頼を育てていました。
また、話題にタブーを設けないという姿勢も共通していました。
「思春期のことも、恋愛のことも、正直に話します。
大切なのは“恥ずかしがらずに話せる親”でいること。」
このような対話は、衝動的に言ってしまうことの多いADHDの性質を、
「率直でオープンな関係を作る強み」として生かしているものでした。

この研究では、母親のADHDが“負の要因”だけではなく、“保護要因”として働く場合があることが明らかになりました。
つまり、母親が自分のADHDを理解し、それをもとに子どもと共感的に関わることで、関係が安定しやすくなるのです。
過去の研究では、ADHDの親は家庭内が混乱しやすく、子どものしつけが一貫しにくいとされてきました。
しかし、この研究の母親たちはむしろ、自分の特性を活かして、子どもとより深くつながっていました。
「私がADHDだからこそ、彼の世界がわかる。
それが私の強みなんです。」
ある母親はそう言い切っています。
研究チームは、この関係を「相互理解の連鎖」と呼んでいます。
母親が自分の特性を理解し、子どもを受け入れる。
それが子どもの自己受容を育て、さらに母親への理解を生む。
この“理解の循環”こそが、ADHD親子の関係を支える大きな力だと考えられました。
また、この循環は「時間とともに育っていく」とも指摘されています。
母親と子どもが互いの行動に共通点を見つけることで、笑い合い、支え合う関係へと変わっていく。
その変化のプロセスが、まさに発達そのものだと研究者たちは述べています。
一方で、母親たちは数多くの課題も抱えていました。
忘れ物や予定の管理の難しさ、経済的な負担、そして社会的な偏見。
「ADHDの親はだらしない」「シングルマザーは大変だ」といった周囲の見方は、彼女たちを苦しめていました。
それでも彼女たちは、そこに“誇り”を見いだしていました。
「私たちは“足りない家庭”じゃない。
お互いを理解して支え合う家庭なんです。」
母親たちは、ADHDを「問題」ではなく「個性の一部」として受け止め、その特性を通じて子どもと成長していました。

この研究は、南アフリカにおけるADHD支援にも新しい視点をもたらしました。
これまでの支援は、主に「欠けた部分を補う」ことを目的としてきました。
しかし研究チームは、「資源(アセット)」を活かす支援――つまり、すでにその人が持っている力を伸ばす支援――が大切だと提案しています。
共感できる力、正直に話せる関係、自分を理解する知恵。
それらは、特別な治療ではなくても親子を支える大きな資源です。
支援者や専門家がこうした「強み」に注目することで、
母親たちは「問題のある人」から「強さを持つ人」へと見られるようになります。
それは、社会の偏見を少しずつ変えていく力になるでしょう。

研究の最後で、チームはこう述べています。
「母と子の関係そのものが、支えであり、保護要因である。」
相互の共感と理解は、生活の混乱を超えて親子を結びつける。
そして、その結びつきは、社会が想像するよりもずっと強い。
この研究は、「シングルマザー」と「ADHD」という二つのラベルの裏にある豊かな現実を明らかにしました。
それは、困難を抱えながらも前向きに生きる母親たちの物語であり、同時に“人を理解する力”の物語でもあります。
この研究論文タイトルの「ADHDを持っていてよかった」という言葉には、深い意味があります。
それは、苦労を否定するものではありません。
むしろ、その苦労の中にあるつながりと成長を肯定する言葉です。
自分の特性を通して、子どもの気持ちを感じることができる。
その瞬間、ADHDは“障害”ではなく、“共感の言語”になります。
この研究は、ADHDをめぐる親子関係を「弱さの連鎖」ではなく、「理解の連鎖」として描き直しました。
母親たちの声は静かで、しかし力強いものでした。
「ADHDを持つ母親だからこそ、ADHDの子どもを理解できる」――その言葉には、愛と誇りが込められていました。
(出典:Interchange DOI: 10.1007/s10780-025-09549-y)(画像:たーとるうぃず)
南アフリカのADHDのシングルマザーとADHDの子。
すごく限定された研究の対象なので、最初はなんだか遠い話のように思えましたが、
まったくそんなことはない、日本に限らず、世界のどこであっても、普遍的な大切な研究結果でした。
(チャーリー)