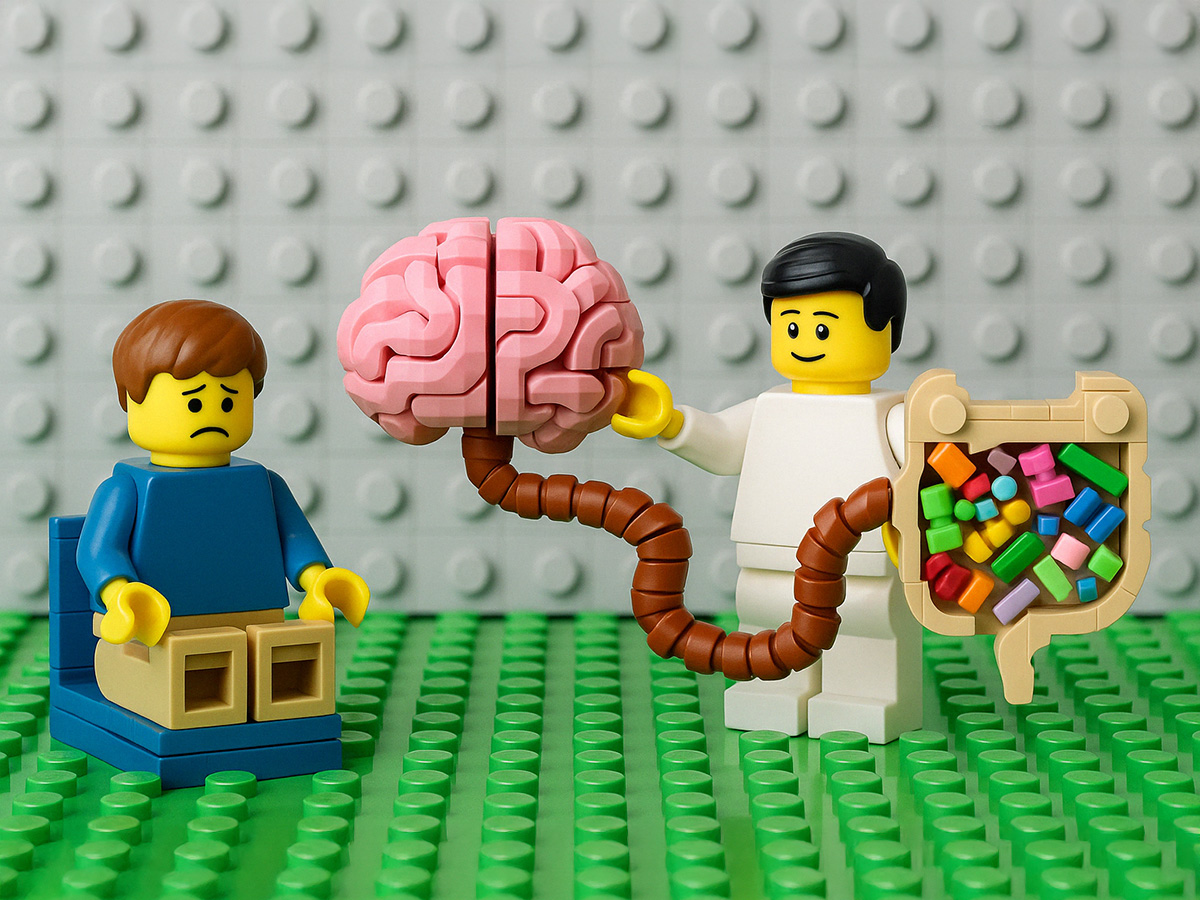
この記事が含む Q&A
- 自閉症スペクトラム障害と腸内環境の関係について何が明らかになっていますか?
- 腸内のトリプトファン代謝物の一つであるキニュレネートが少ないことと、脳の感情・感覚処理に関わる部分の活動の低下が関連しています。
- 自閉症の子どもたちはどのような腸内代謝物が不足しているのでしょうか?
- 主に、脳を守る働きがあるキニュレネート(KA)が、自閉症の子どもたちでは少ないことがわかっています。
近年、自閉症スペクトラム障害(ASD)の症状と腸内環境との関係が次第に明らかになってきています。
米南カリフォルニア大学の研究チームは、8歳から17歳までの自閉症スペクトラム障害を持つ43人の子どもたちと、同年代の自閉症を持たない41人の子どもたちを対象に、腸内細菌が作り出すトリプトファンというアミノ酸に関連した代謝物と脳の活動、自閉症の症状との関連性を調べました。
これまで、腸内細菌が作る代謝物が自閉症に関連している可能性が指摘されていましたが、具体的にどのような仕組みで脳に影響を与えるのかはわかっていませんでした。
今回の研究ではとくに、「トリプトファン」というアミノ酸から腸内細菌が作る代謝物質に注目し、これらが脳の働きや行動にどう影響を与えるのかを詳しく分析しました。
研究に参加した子どもたちは、腸内細菌が作る代謝物の量を調べる検査(便の代謝物分析)や、社会的・感覚的な刺激に対する脳の反応を測定する機能的磁気共鳴画像法(fMRI)、さらには行動評価を受けました。
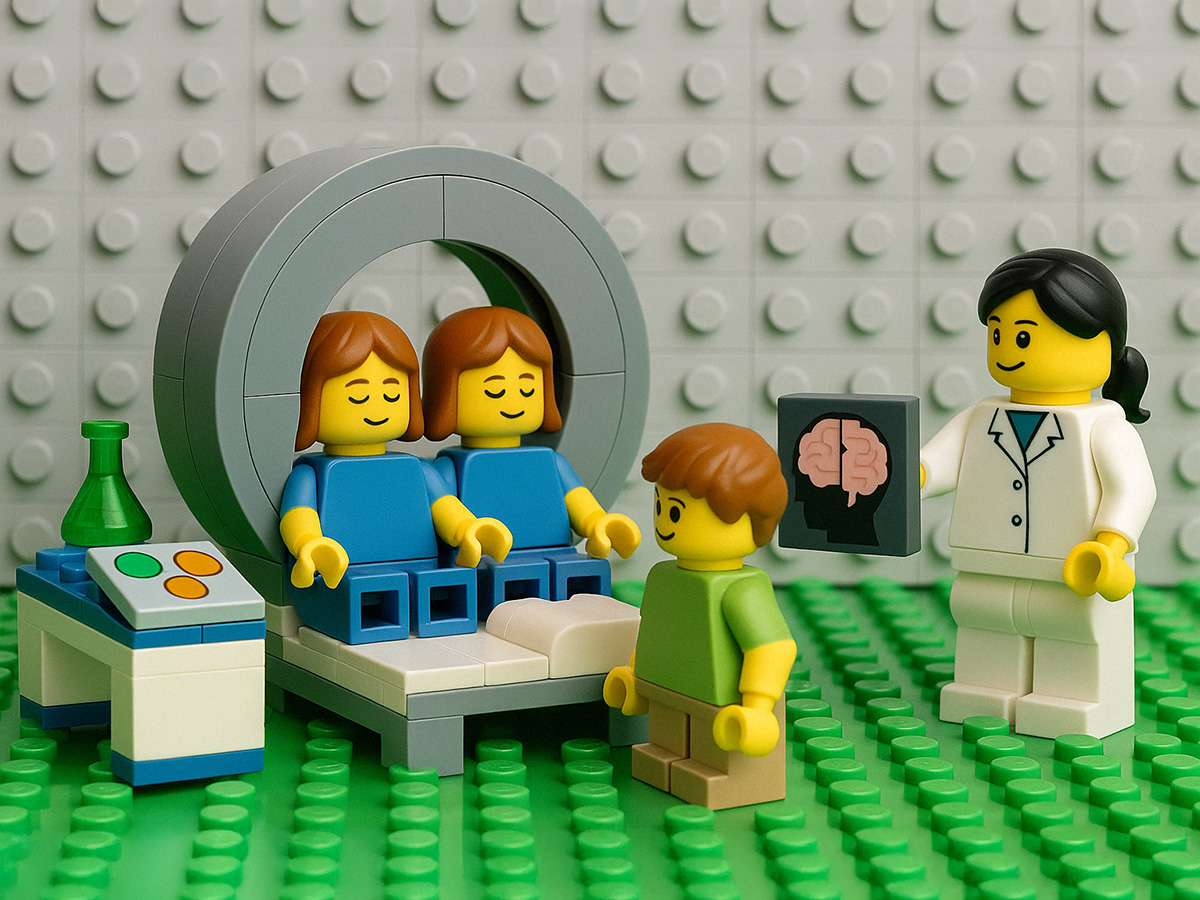
その結果、自閉症の子どもたちは自閉症を持たない子どもたちに比べて、「キニュレネート(KA)」という代謝物の量が明らかに少ないことがわかりました。
このキニュレネートという物質は、通常、脳を守る働きを持つ重要な代謝物です。
さらに、この代謝物が少ないことが、自閉症の子ども特有の脳活動の違いとも関係していることがわかりました。
とくに脳の「島皮質(インスラ)」や「帯状皮質」と呼ばれる部位の活動が、腸内の代謝物の量と強く関連していることが確認されました。
これらの脳の部位は、自閉症でよく知られているように、感情や感覚の処理に深く関わっています。
また、「インドール乳酸(インドレラクテート)」や「トリプトファンベタイン」といったトリプトファン関連代謝物が、中部島皮質(ミッドインスラ)や中帯状皮質(ミッドシングレート)という脳部位の活動と強く結びついていることも明らかになりました。
これらの脳の部位の活動は、自閉症の症状の重さや特定の感覚に対する敏感さ(例えば、嫌悪感を強く感じる傾向)にも関係していました。
さらに、脳のこれらの活動が腸内代謝物と自閉症の行動特性との関係をつなぐ役割を果たしている可能性も示されました。
つまり、腸内の代謝物がまず脳の特定の部分の活動に影響を与え、その結果、自閉症特有の行動が現れるという可能性があるのです。
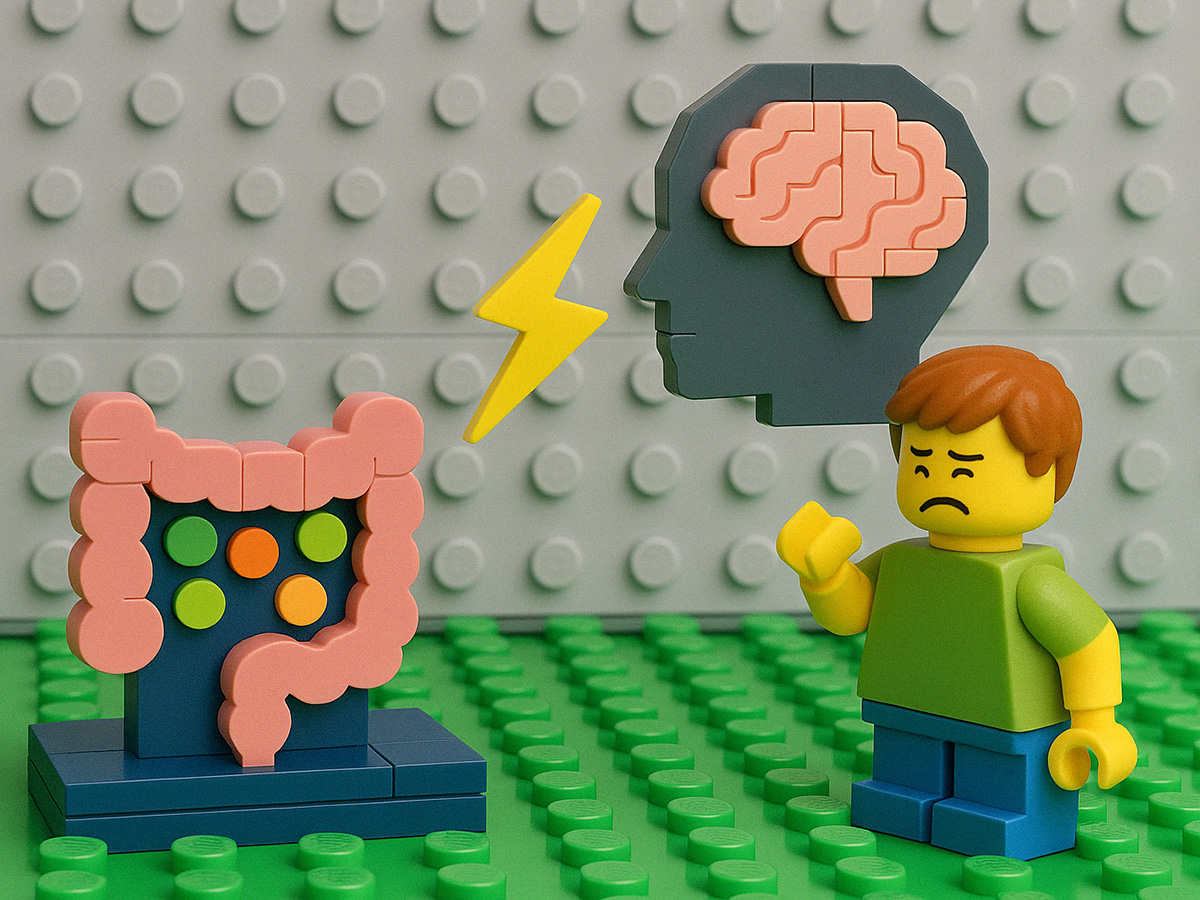
研究チームは、自閉症の子どもたちがよく抱える腹痛や便秘などの消化器症状が多いことから、腸内環境の乱れが脳に影響を与えている可能性を指摘しています。
ただし、今回の研究では消化器症状の有無にかかわらず、キニュレネートが少ないことが確認されました。
これは消化器症状が直接の原因であるとは限らないことを示しています。
この研究は、脳と腸の関係が自閉症の症状形成に深く関わっていることを示す重要な手がかりを提供しています。
ただし、今回の研究は特定の時点のデータを収集したものであり、腸内の代謝物が自閉症の症状や脳活動を直接引き起こすことを証明してはいません。
研究者たちは、長期間の追跡調査や腸内環境を整える治療など、さらなる研究が必要だと述べています。
今回の研究成果は、自閉症を持つ子どもたちの治療や支援に新たな可能性を示しています。
腸内環境を整えることで自閉症の症状が改善される可能性があり、今後の研究や新しい治療法の開発が期待されています。
(出典:Nature Communications DOI: 10.1038/s41467-025-58459-1)(画像:たーとるうぃず)
1.自閉症の子どもたちは自閉症を持たない子どもたちに比べて、「キニュレネート(KA)」という代謝物の量が明らかに少ない
2.感情や感覚の処理に深く関わる脳の活動が、それと強く関連している
3.つまり、腸内の代謝物がまず脳の特定の部分の活動に影響を与え、その結果、自閉症特有の行動が現れるのかもしれない
そんな研究の結果です。
(チャーリー)





























