
この記事が含む Q&A
- 自閉症と統合失調症の共通点と違いを理解することで、診断名にとらわれず実際の困りごとに目を向けることが重要だと分かるのはなぜですか?
- 共通する社会的やりとりの難しさなどを挙げ、診断名よりも困りごとに着目することが支援の質を高めると説明されています。
- 予測モデルの目的は何ですか?
- 自閉症のADOS-2と統合失調症のPANSSを組み合わせて診断の誤りを減らす新しい予測モデルを作ることです。
- 研究が提案する実践的な支援のポイントは何ですか?
- 段階的な練習や個別支援設計、デジタル・フェノタイピングの活用など、負担を減らし実生活の支援につなげる方法が示されています。
自閉症と統合失調症という二つの状態は、長い間、まったく別のものとして語られてきました。
自閉症は子どものころから特性が見られる発達のあり方で、ことばや感覚、そして人とのやりとりに独自の傾向が出やすいことで知られています。
統合失調症は青年期から成人期にかけて現れることが多く、幻覚や妄想といった症状が有名です。
こうして並べてみると、両者はまるで違う領域にあるように見えます。
しかし実際には、驚くほどの共通点があることが研究によって明らかになってきました。
ときには外から見える行動だけでは区別がつかず、誤診につながることもあります。
このような課題に取り組むために、アメリカのセントラル・コネチカット州立大学心理学部、スペインのバルセロナ大学附属ホスピタル・クリニック、アメリカのハートフォード・ホスピタルにあるオリン神経精神医学研究センターとメアリー・W・パーカー・オーティズム・センター、そしてイェール大学医学部精神科に所属する研究者たちが、両者の共通点と相違点を整理した解説をまとめました。
彼らが目指したのは、診断の線引きを超えて、共通する部分と違いを明らかにし、それぞれの理解と支援をより深めることです。
両者に共通するものの一つは、社会的なやりとりに関する難しさです。
研究の中では「ソーシャル・コグニション」と呼ばれますが、これは相手の表情や声から気持ちを読み取ったり、行動の意図を推測したりする力のことです。
自閉症でも統合失調症でも、この部分に苦手さを持つ人がいるため、周囲からの理解が得にくかったり、誤解を受けたりすることがあります。

こうした誤診のリスクを減らすための研究も紹介されています。
たとえば、自閉症の観察評価であるADOS-2と、統合失調症の症状を測定するPANSSを組み合わせ、新しい予測モデルを作った取り組みがあります。
従来は統合失調症の「陰性症状」、つまり感情の表れが乏しいことや意欲の低下といった特徴がADOS-2で自閉症の特性と誤って評価されることがありました。
そのため、本当は統合失調症であるのに自閉症と診断されてしまうことがあったのです。
この新しいモデルでは、ADOS-2の中から特定の項目を組み合わせて活用することで、診断をより正確に行えるよう工夫されています。
また、認知機能を比べた研究もあります。
認知機能とは、計画を立てる力、注意を切り替える力、短期的に情報を覚えておく力など、生活に欠かせない頭の働きのことです。
自閉症と統合失調症を比べると、エグゼクティブ・ファンクションと呼ばれる「頭の中の司令塔」のような働きに大きな重なりが見られました。
ただし短期記憶の一部では違いが出ることもありました。
これらの知見は、診断名ごとに支援を分けるのではなく、実際に困っている機能に応じて支援を設計できることを示しています。
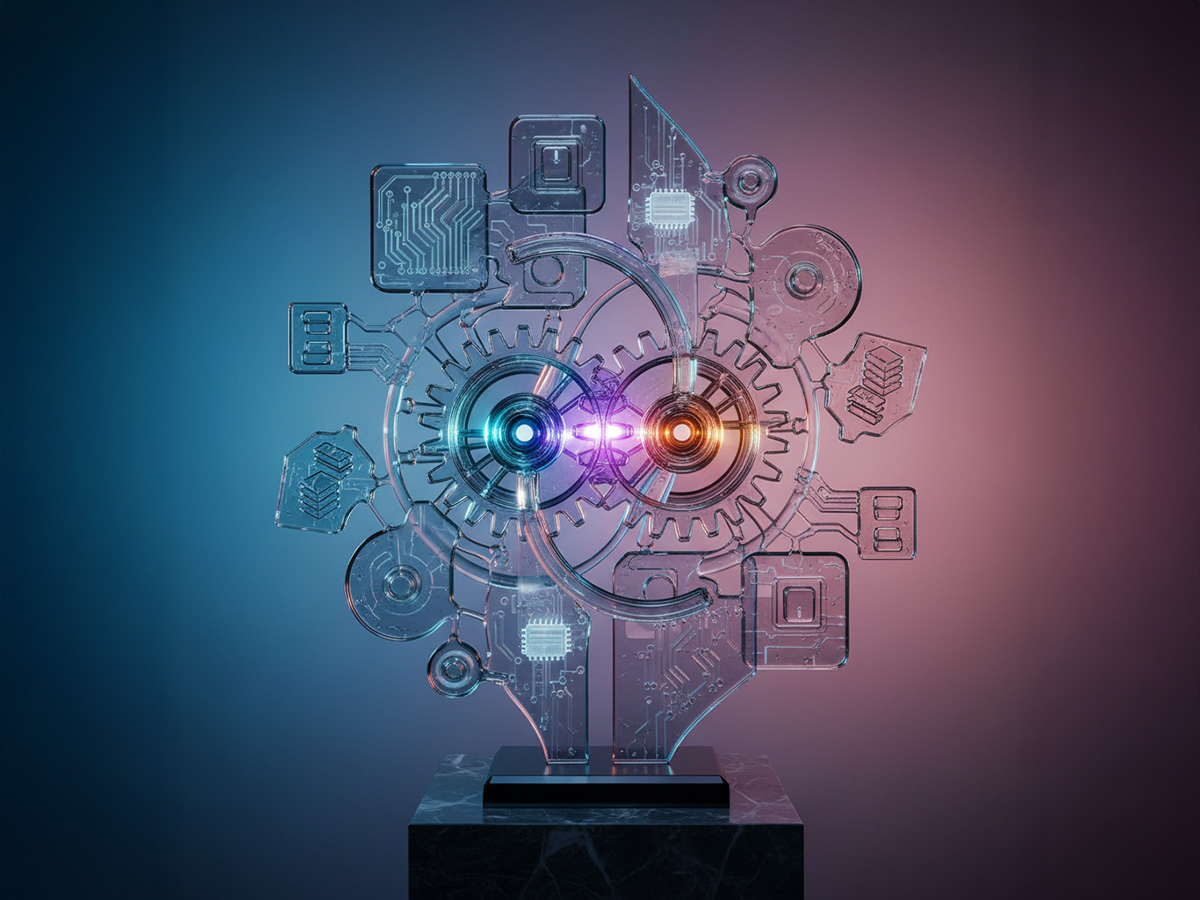
さらに、自閉症の子どもの感情処理を調べた研究では、社会的な情報が入り込むと混乱しやすいことが示されました。
顔の表情や声の調子などが加わると、注意を保つことが難しくなり、情報が増えるにつれて困難が増すのです。
研究者たちは、この知見をもとに「段階的な練習」を提案しました。
たとえば、バーチャルな顔から始めて現実の顔に移り、一人から複数の顔へと少しずつ広げていく方法です。
この工夫によって、過度の負担を避けながら力を育てていくことができます。
体の中の仕組みに注目した研究もありました。
その一つが「テロメア」です。
テロメアは染色体の端にある部分で、よく「体の寿命を示す時計」とたとえられます。
加齢やストレスで短くなっていくとされますが、自閉症の人ではテロメアが短くなりやすく、細胞の酸化ストレスと呼ばれるダメージと関係していることが示されました。
これは、早期診断や支援の新しい手がかりになるかもしれません。
治療の最適化を目指す研究としては、初めて精神症状が出た人に対し、遺伝情報、生活習慣、環境要因、脳の画像データなどを組み合わせて薬の効果を予測する大規模研究も進められています。
機械学習を用いて、一人ひとりに合わせた「精密医療」を実現しようとする取り組みです。
従来の一律的な処方から脱し、個人に適した治療を提供する道を開こうとしています。

また、腸内細菌の研究も注目されています。
統合失調症の人では腸内細菌に乱れがあることが一貫して示されていますが、その乱れの内容は多様でした。
自閉症については研究がまだ少なく、腸と脳のつながりが両者にどう影響しているのかを比較することが今後の課題とされています。
呼吸器疾患との関係も調べられました。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)と統合失調症の間に遺伝的な関連が示されましたが、そのつながりは喫煙や体重、うつなどを介していることがわかりました。
自閉症に関しては研究が少なく、喘息との関係についても結論が出ていません。
今後はより多様な人々を対象にした大規模研究が必要とされています。

全体を通して強調されているのは、「診断名にこだわりすぎない」ことです。
共通点と違いを同時に見つめることで、誤診を減らし、早期にサインをとらえ、その人に合った支援や治療につなげられる未来が描かれています。
さらに、大規模で長期的な研究や、スマートフォンやウェアラブル機器を用いて日常の行動をリアルタイムで測定する「デジタル・フェノタイピング」といった新しい技術を取り入れることも提案されています。
自閉症の当事者や家族、支援者にとって、この解説が伝えるメッセージは二つあります。
第一に、診断名で決めつけるのではなく、実際に困っていることの中身を丁寧に見ること。
第二に、段階を踏んで負担を減らし、小さな変化を記録して支援に活かすこと。
これらは研究の中で示された方向性であると同時に、日常生活の支援にすぐ応用できる実践的なヒントでもあります。
(出典:Frontiers in Psychiatry DOI: 10.3389/fpsyt.2025.1694809)(画像:たーとるうぃず)
「ときには外から見える行動だけでは区別がつかず、誤診につながることもあります」
まず、それを知っておかなければなりません。
自閉症であり、統合失調症もかかえる方もいます。
(チャーリー)





























