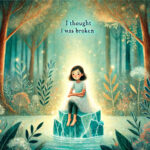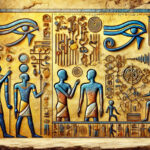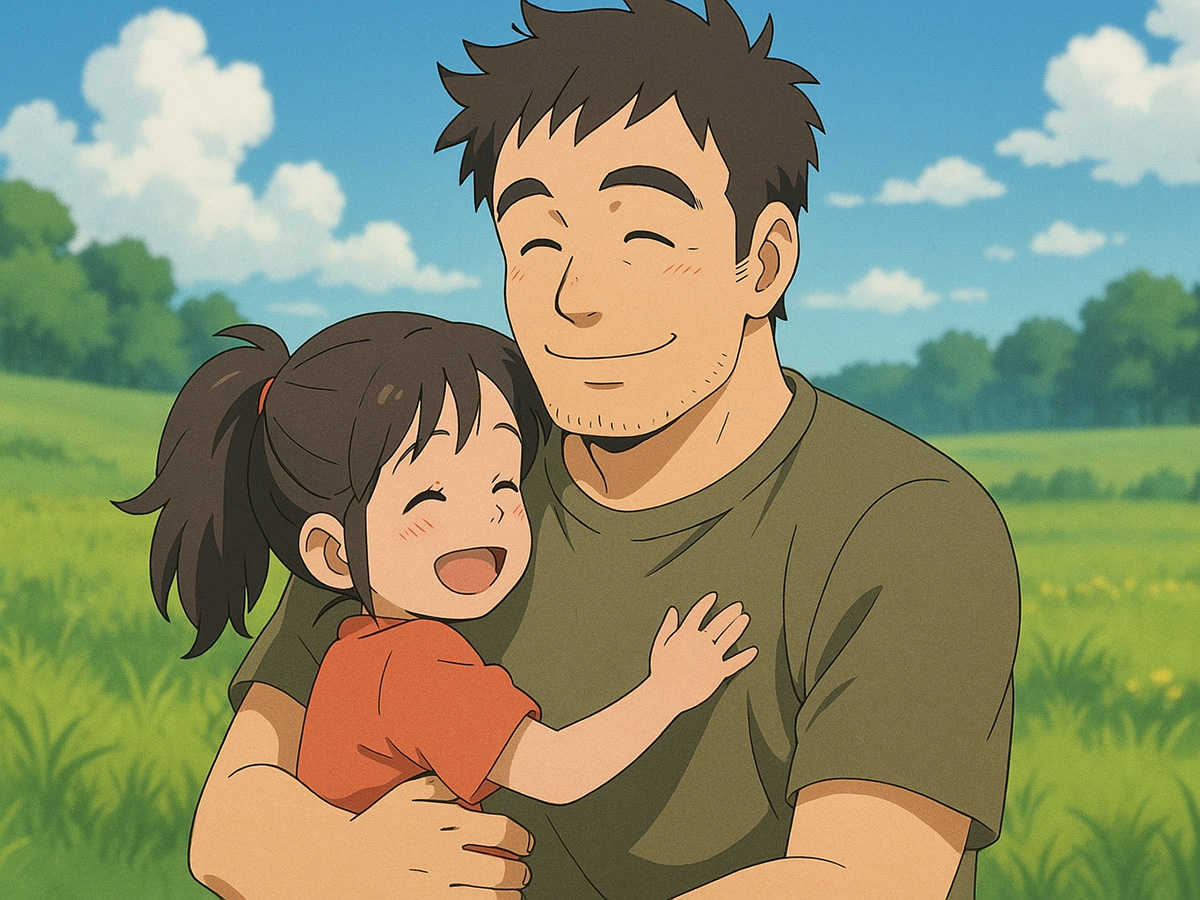
この記事が含む Q&A
- 子ども時代のポジティブな経験が自殺リスクに影響しますか?
- はい、子ども時代に安心感やつながりを感じた経験は自殺リスクを低減させます。
- ASDやADHDの若者にとってポジティブな環境づくりはどのように役立ちますか?
- 支えられた記憶が精神的なレジリエンスを高め、困難に耐える力となります。
- 大人ができる子ども支援の具体的な方法は何ですか?
- 子どもたちに話しかけやすい存在になり、安心できる経験を共に積むことです。
日本では若者の自殺が深刻な社会問題となっています。
世界的に見ても日本の若者の自殺率は高く、とくに思春期から青年期にかけてのメンタルヘルスへの支援が重要視されています。
そんな中、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)の傾向を持つ若者たちが、他の若者よりも高い自殺リスクを抱えていることが多くの研究からわかってきました。
発達特性によって生きづらさを抱えやすくなる彼らにとって、どんな環境や経験がそのリスクを和らげることにつながるのか。
その答えの一端を、日本の大規模な調査が明らかにしました。
この研究は、明治学院大学などの研究チームによって実施されたものです。
日本全国の16歳から25歳の若者5,000人以上を対象に、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)の傾向と、彼らの子ども時代の経験、そして自殺に関する考えや行動との関係を分析しました。
とくに注目されたのが、「ポジティブな子ども時代の経験(Positive Childhood Experiences:PCEs)」と呼ばれるものです。
PCEsとは、子どもが家庭や地域、学校などの中で経験する「安心感」や「つながり」、「支えられている感覚」を指します。
たとえば、「家庭で感情を安心して表現できた」「困ったときに大人や友達に助けてもらえた」「近くに信頼できる大人がいた」「楽しく過ごした思い出がある」といった経験です。
これらは一見、当たり前のようにも思えるものですが、家庭の事情や社会的な孤立、発達特性による誤解などにより、得られない子どもも少なくありません。
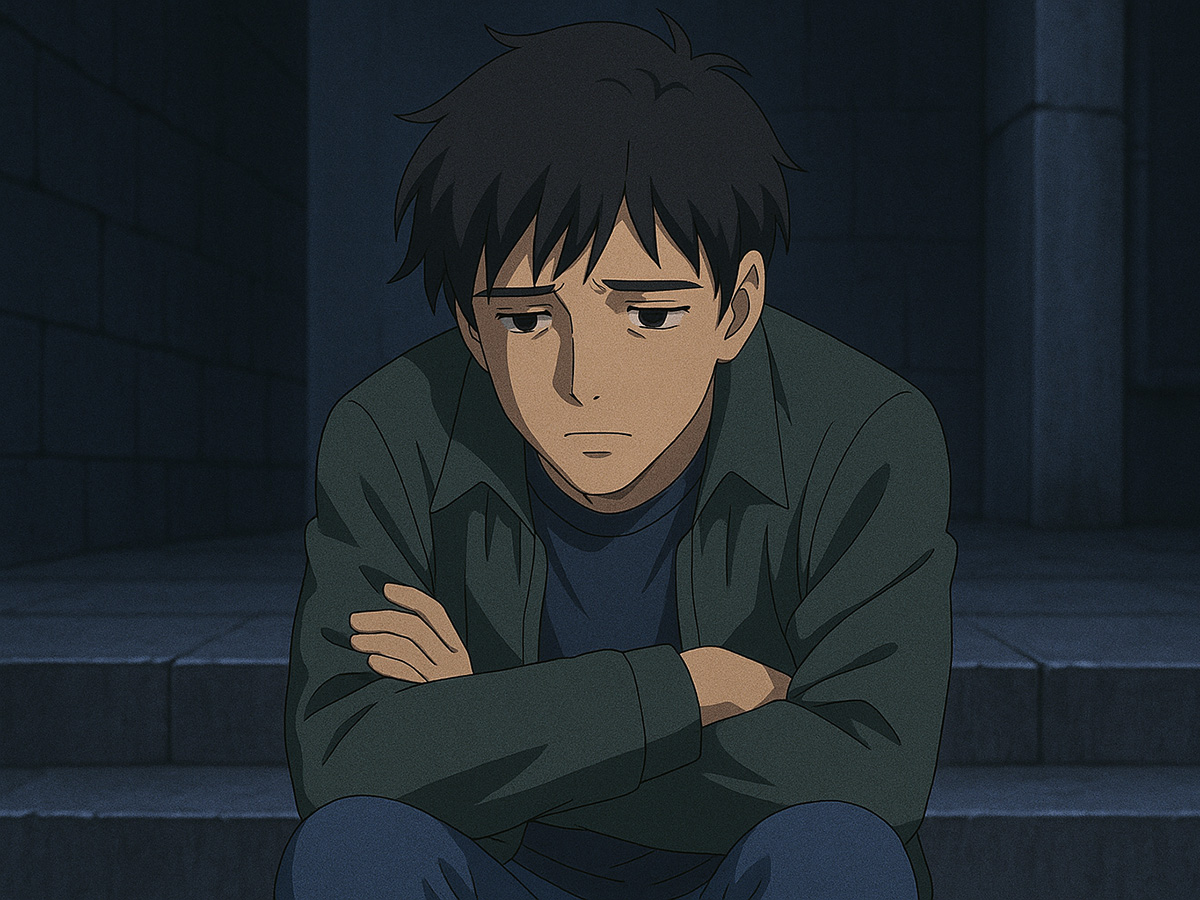
研究の結果、ASDやADHDの傾向が強い若者ほど、自殺念慮(死にたいと思ったことがある)や自殺未遂の割合が高いことが明らかになりました。
これは過去の研究とも一致するもので、社会との摩擦や不理解、孤立、自己肯定感の低さなどが重なり、精神的な負担が大きくなることが背景にあると考えられます。
しかし、それと同時に、ASDやADHDの傾向がある若者でも、子ども時代にPCEsを多く経験していた場合、自殺念慮や自殺未遂の割合が低くなることがわかりました。
つまり、発達特性そのものが直接自殺リスクを高めるのではなく、それにどう対処できる環境があるかが重要であることを、この研究は示しています。
とくにADHD傾向のある若者においては、PCEsの効果がより顕著に見られました。
ADHDでは、感情のコントロールが難しかったり、衝動的な行動に出やすかったりするため、周囲からの否定的な対応を受けやすい傾向があります。
その結果、自己評価が下がりやすく、孤独感を抱えることも少なくありません。
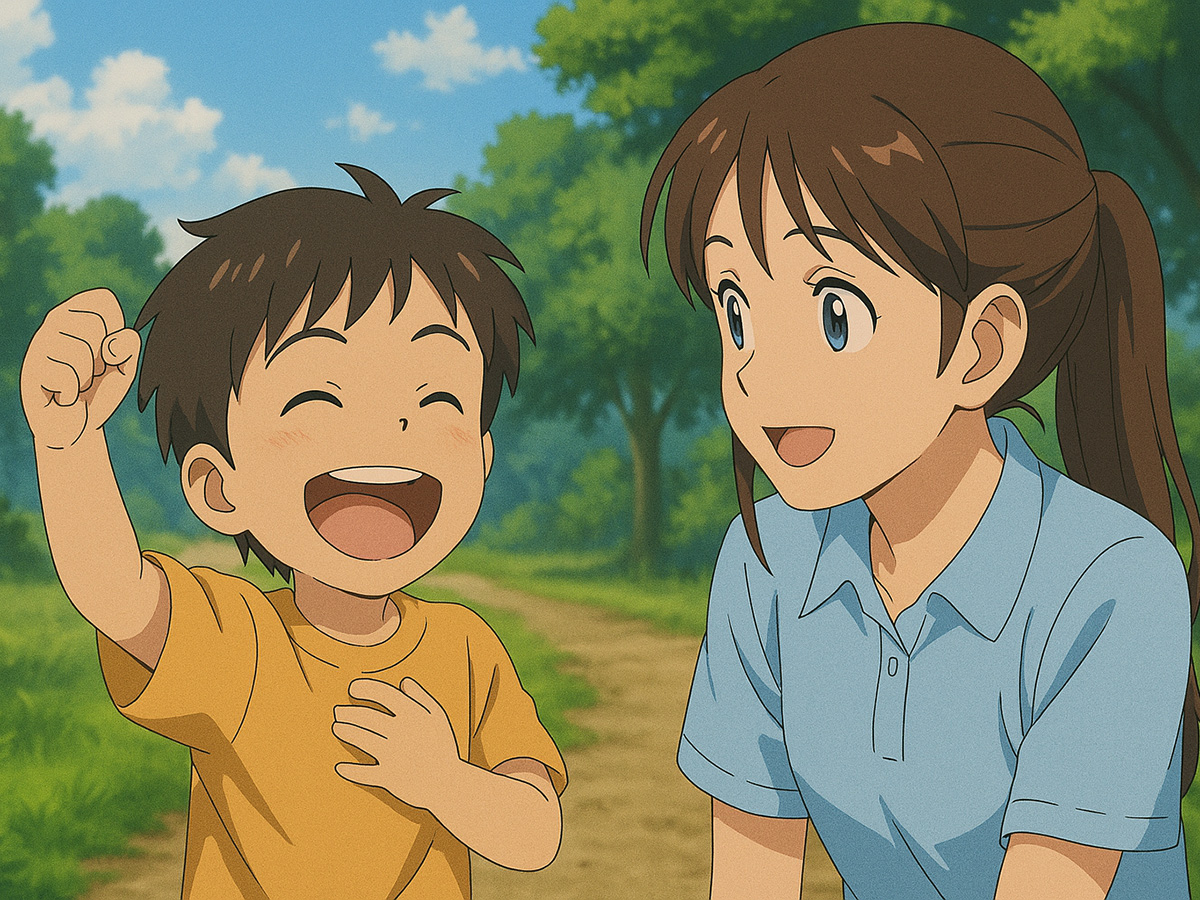
そんな中で「味方がいる」「感情を安心して出せる」「楽しいと思える時間があった」という経験は、人生に対する信頼や希望をつなぎとめる大きな力になります。
この調査では、PCEsの項目として、具体的に以下のようなものが取り上げられています。
- 感情を家庭で安心して話せた
- 困ったときに支えてくれる大人がいた
- 周囲の大人が努力を認めてくれた
- 安心して過ごせる地域や場所があった
- 楽しい思い出を共有できる人がいた
- 大人から関心を持ってもらえた
- 友達とのつながりがあった
- 成長や進歩を応援してくれる存在がいた
- 家庭の中に安全感があった
- やりたいことに挑戦できた
こうした経験が多かった人ほど、自殺関連のリスクが低かったのです。
研究者たちは、「支えられた記憶」が、その後の困難な状況にも耐える心理的なレジリエンス(回復力)を育てる可能性があると指摘しています。
興味深いのは、ASD傾向のある若者においては、ADHD傾向ほど強くPCEsの影響が出ていなかったことです。
これは、ASDの特性が社会的な相互理解や感情共有に関わるものであるため、PCEsが他者との関係性を通じて形成される以上、その受け取り方に個人差が出やすい可能性があると考えられます。
つまり、同じような「支援的な関わり」があっても、それをどれだけポジティブな経験と感じられるかは、個々の認知や感受性によって変わるということです。
また、研究は日本という社会文化的背景をもとに行われており、親子関係や教育観、地域のつながり方なども含めて考察されています。
たとえば日本では、感情を表に出すことが苦手とされがちで、家族間でも「気持ちは察するもの」といった文化があります。
これはときに、子どもが内面を話す機会を失ったり、孤独感を深めたりする原因にもなります。
そんな中で、子どもが「言葉にしてもいい」「話しても受け止めてもらえる」と感じられる環境をどれだけつくれるかが、非常に大きな意味を持つのです。
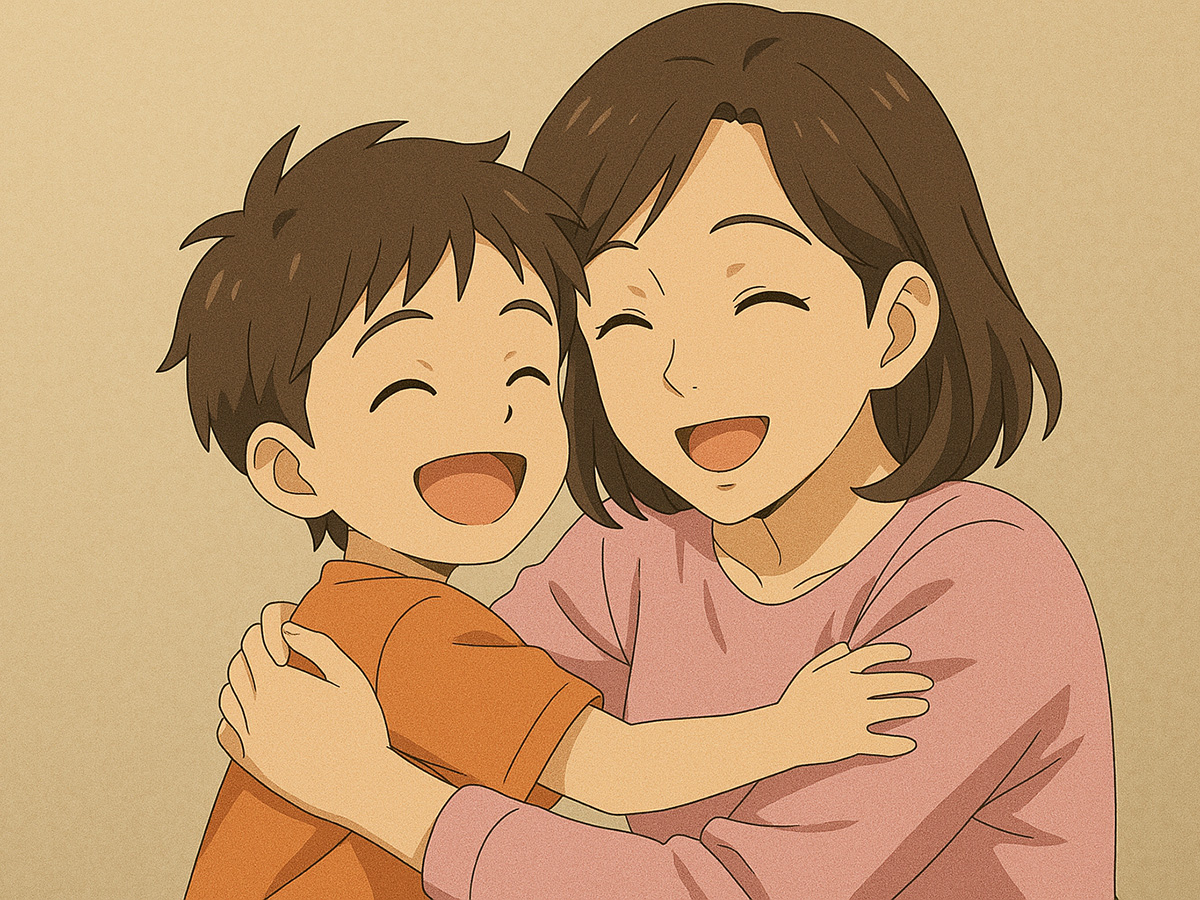
この研究から得られる教訓は、実にシンプルです。
すべての子どもたちが、「安心して過ごせる」「気持ちを受け止めてもらえる」「応援してくれる人がいる」と実感できるような環境を、できるだけ早い段階で整えてあげること。
そうした経験の積み重ねが、将来の深刻な危機を防ぐ防波堤となるのです。
とりわけ、ASDやADHDといった発達特性を持つ子どもたちは、社会とのちょっとした「ズレ」によって、自己否定に陥りやすい傾向があります。
「できないこと」「失敗したこと」に目が向けられがちだからこそ、逆に「楽しかった記憶」「認めてもらえた経験」がどれほど大切かが浮き彫りになります。
実際、研究チームの一人は「子どもの発達支援を考えるとき、スキルの向上や訓練だけでなく、感情的な安全基地をつくることの意義をもっと重視すべきだ」と述べています。
つまり、療育や教育の中でも、「支援されることそのものが、自尊心や生きる力につながる」という視点が必要なのです。
もちろん、すべての子どもが完璧な家庭環境で育つわけではありません。
親自身がメンタルヘルスの課題を抱えていたり、経済的に厳しかったりすることもあります。
だからこそ、家庭だけに責任を押し付けるのではなく、地域や学校、医療・福祉の現場が連携しながら、子ども一人ひとりの「小さな安心」を支えていくことが、社会としての課題といえるでしょう。
たとえば、学校で「相談できる先生」がいる、地域に「居場所」と感じられる場所がある、周囲の大人が「ちゃんと見ていてくれる」と感じられる――そんな小さな積み重ねが、子どもたちの中に「自分は大丈夫」という感覚を育てていくのです。
研究者たちは今後、こうしたPCEsの具体的な促進方法をさらに検討していくとしています。
また、同様の調査を他の国や地域でも行うことで、文化的背景の違いがどう影響するかを比較していくことも計画されています。
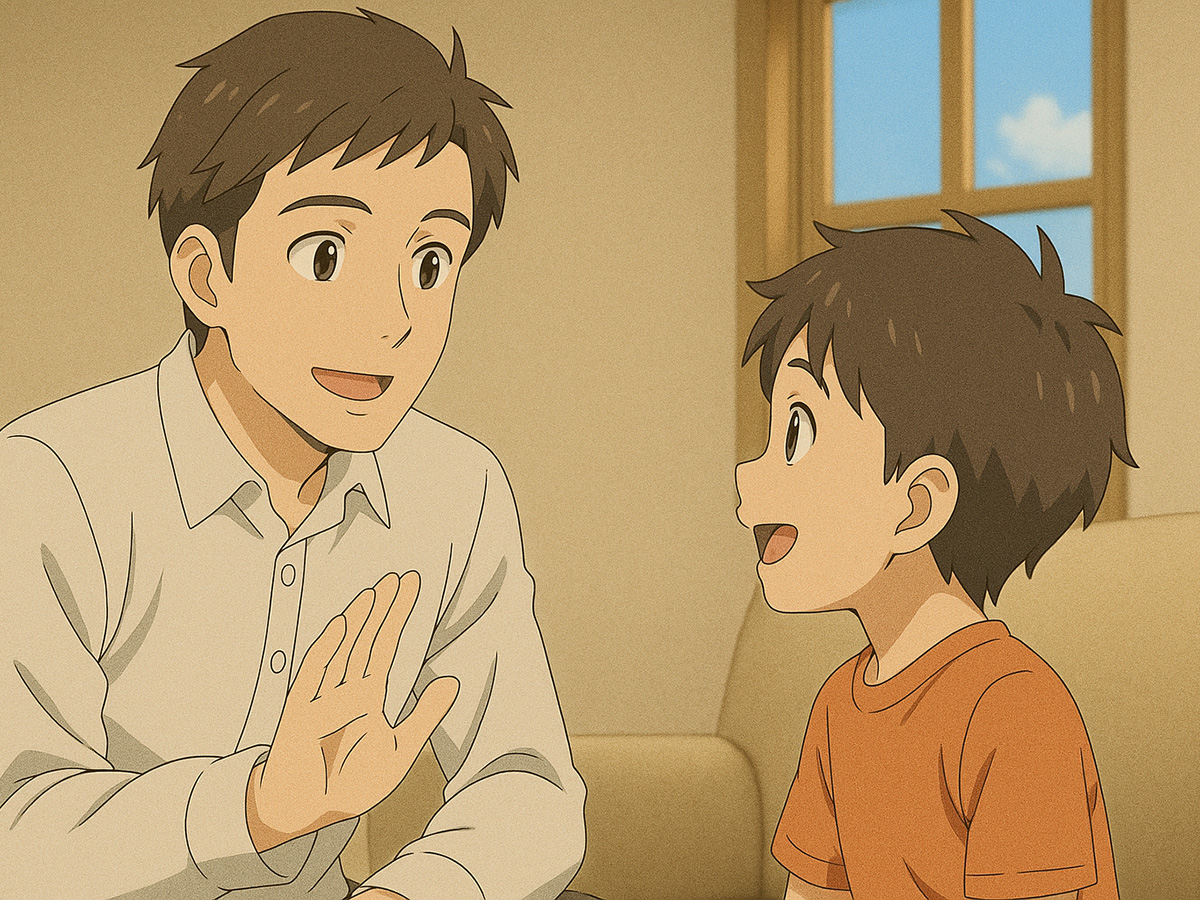
私たち大人にできることは何でしょうか。
それは、子どもたちが「話しかけやすい」と感じられる存在になること。子どもの言葉に耳を傾け、「大丈夫だよ」と伝え続けること。
そして、小さな成功体験や喜びを、一緒に感じ、覚えておくことです。
どれも特別な知識や資格が必要なことではありません。
ただ、その一つひとつが、子どもたちの未来に確かに影響を与える「ポジティブな経験」となりうるのです。
自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症の傾向がある若者にとっても、それは変わりません。
「わかってもらえた」「支えてもらえた」という記憶は、困難に立ち向かう力になります。
そしてそれは、彼らが将来、自分以外の誰かを支える側になったときにも生きてくるはずです。
今回の研究が明らかにしたのは、発達特性と自殺リスクという重たいテーマの中にも、「希望」が確かに存在するということでした。
その希望を、ひとりでも多くの子どもたちに手渡していく社会を、私たちは選ぶことができるのです。
(出典:frontiers DOI: 10.3389/fpsyt.2025.1566098)(画像:たーとるうぃず)
【電話やチャットで気軽に相談できる窓口があります。悩みや不安を感じたら】
厚生労働省 相談先一覧ページ
「感情的な安全基地」
こうした若者、子供たちに限った話ではありません。
大人でもそうです。
たとえば、もっともパフォーマンスが高い職場環境に必要なのは、言葉は違えども同様の「心理的安全性」です。
Googleが研究発表した「プロジェクト・アリストテレス」が有名です。
相手を尊重し、まずは受け入れてみようと考える。(受け入れられないこともある)
それが、より幸せな世界につながるものと私は思います。
自閉症スペクトラムの人の自殺リスクはそうでない人の3倍。研究
(チャーリー)