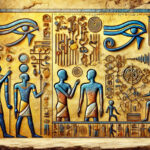この記事が含む Q&A
- くすぐりの感覚は発達障害にどのように関係していますか?
- 自閉症スペクトラム症の方は、くすぐりへの反応が敏感すぎたり反応しなかったりすることがあります。
- なぜ自閉症の子どもはくすぐられたときに反応が違うのでしょう?
- 脳の予測と反応の仕組みが働きにくいことが原因と考えられています。
- くすぐり遊びは発達や社会性にどのような影響がありますか?
- くすぐり遊びは、親子や社会的なつながりや愛着、コミュニケーションの促進に役立ちます。
オランダのラドバウド大学ドンダース脳・認知・行動研究所と、スウェーデンのカロリンスカ研究所を中心にした研究チームによってまとめられ、科学誌『サイエンス・アドバンシズ』に掲載された論文では、「くすぐり」というとても身近な感覚が、実は脳や心、そして自閉症スペクトラム症(ASD)をはじめとする発達の特性に、どれほど深く関係しているのかを世界中の研究をもとに紹介されています。
「くすぐったい!」という感覚は、誰でも子どものころから経験したことがあるものです。
たとえば、家族や友だちと遊ぶとき、脇の下や足の裏をくすぐられて笑いが止まらなくなったり、体をよじってしまったりすることはありませんか。
しかし、この「くすぐり」がなぜ起きるのか、どんな意味があるのか、科学的にはすべては明らかになっていません。
論文では、「くすぐり」には大きく分けて二つのタイプがあると説明しています。
一つは、虫が皮膚をはったときのようなゾワゾワする「クニスメーシス」という感覚です。
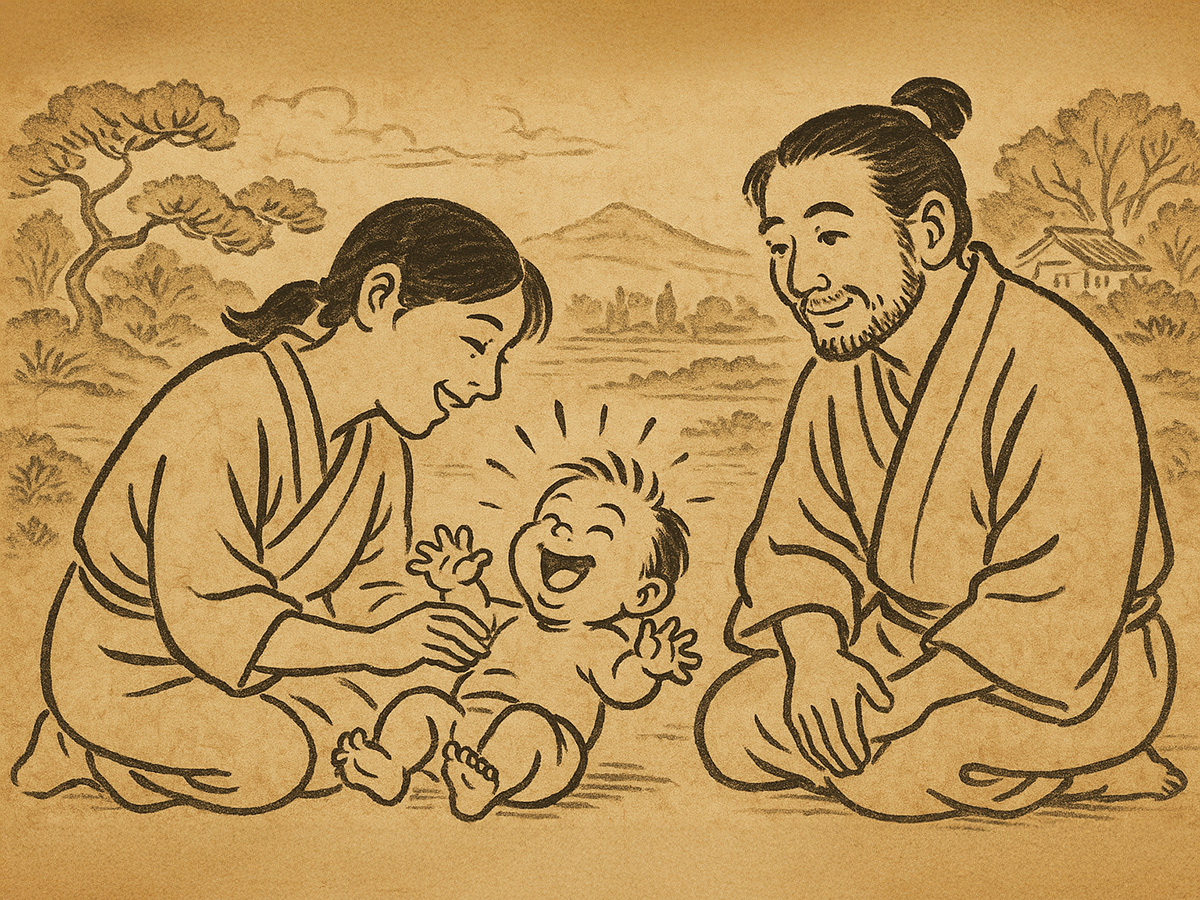
もう一つは、思わず笑い出してしまうような強い「ガルガレーシス」という感覚です。
このガルガレーシスは赤ちゃんのころから見られ、お母さんやお父さんが赤ちゃんをくすぐると、赤ちゃんは声をあげて笑ったり、体をくねらせたりします。
このようなくすぐり遊びは、親子のふれあいや愛着、そして社会性や心の発達にとって大切なものだと考えられています。
この論文が注目しているのは、くすぐりに対する人それぞれの反応の違いです。
自閉症スペクトラム症のある子どもたちは、定型発達の子どもと比べて、くすぐりに対してとても敏感だったり、逆にほとんど反応しなかったりすることがあります。
イギリスのロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの神経学研究所の研究では2006年、アスペルガー症候群を含む自閉症スペクトラム症の人を対象に、くすぐったさの感じ方を調べました。
その結果、自閉症スペクトラム症の人は、普通の人と比べて「くすぐったい」と感じやすい傾向があることがわかりました。
とくに「自分で自分をくすぐる」ときと「他の人からくすぐられる」ときでは、感じ方が大きく違うことがわかりました。
自分で自分をくすぐってもあまりくすぐったくないけれど、人にくすぐられるととてもくすぐったいのです。
これは「自分の動きは脳で予測できるけれど、他人の動きは予測できない」という脳の仕組みと関係があると考えられています。
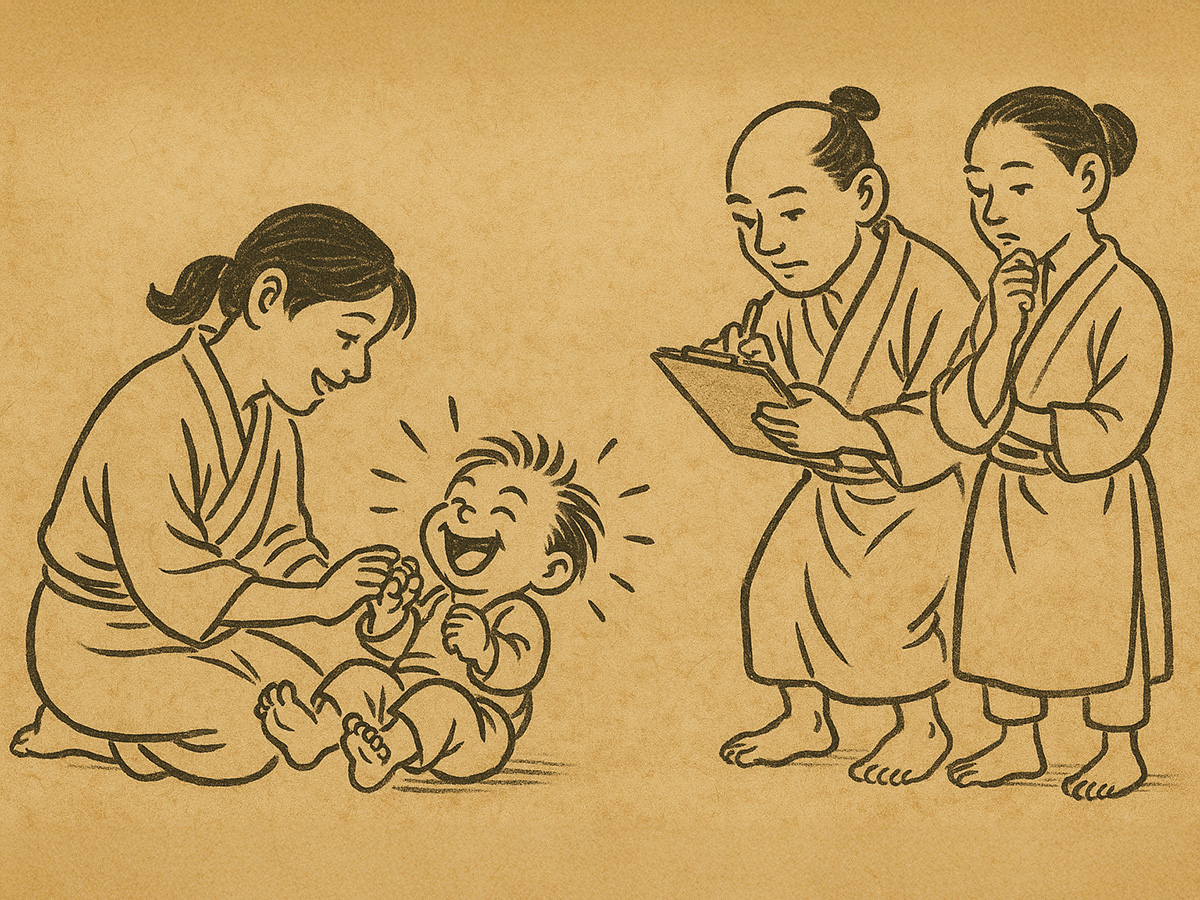
日本でも、2023年に関西医科大学の研究チームが、幼児とその保護者を対象に親子のくすぐり遊びと自閉症傾向の関係を研究しました。
親子でくすぐり遊びをしている様子をビデオで観察し、笑い声や体の動き、「無反応」や「回避」など、さまざまな行動を細かく調べました。
その結果、自閉症の特性が強い子どもほど、くすぐり遊びの中で「笑わない」「反応が少ない」といった傾向があることが明らかになりました。
反対に、定型発達の子どもはくすぐり遊びで前向きな表情や体の動きが多く見られました。
なぜ、自閉症スペクトラム症のある子どもは、くすぐりへの反応が違うのでしょうか?
脳には「自分の行動は自分で予測できる」「他人からの刺激は予測できない」というしくみがあります。
自閉症のある人は、ときにこの“予測のしくみ”がうまく働かないことがあり、くすぐりなど予想外の刺激に過剰に反応したり、まったく反応しなかったりすることがあるのです。
自分では自分をくすぐってもあまり感じないのに、他人にくすぐられると敏感に反応する理由も、ここにあると考えられています。
また、なぜ脇の下や足の裏など特定の場所だけがくすぐったいのか、なぜ人によって感じ方がこんなに違うのか、科学でもまだ答えが見つかっていない不思議な点がたくさんあります。
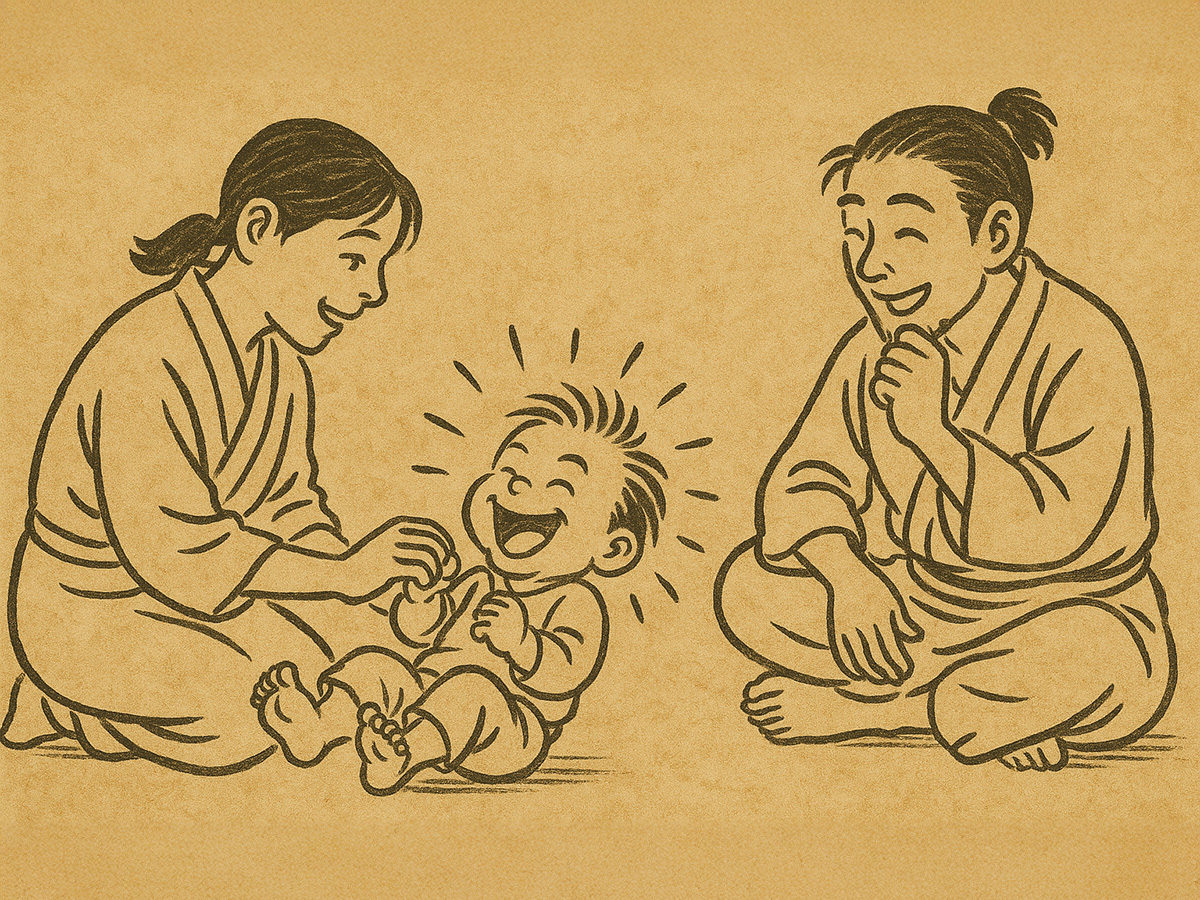
自閉症の人の中には、「くすぐられるのが本当に苦手」「触られるだけで不快に感じる」人もいれば、「くすぐりは楽しい」と感じる人もいます。
皮膚や神経の違いだけでなく、脳が刺激をどのように感じてどう処理しているのか、そういった“感じ方のしくみ”も関係していると考えられています。
くすぐりをきっかけに起こる「笑い」や「遊び」が、親子や友人どうしの距離を近づけ、信頼や愛着を深めるなど、社会性の発達にもつながっていることが指摘されています。
自閉症や発達障害のある子どもたちとのふれあいでも、「くすぐり」や「体に触れる」ことでどんな反応があるかを丁寧に観察し、その子どもなりの感じ方や気持ちに目を向けることがとても大切です。
「笑っているから楽しい」「笑わないから嫌い」と単純に決めつけず、本人の心や感覚を尊重する姿勢が、よりよい関係や支援につながるのです。
「なぜ笑うのか?」「なぜくすぐったいのか?」という問いに対し、いまも世界中の研究者たちがさまざまな方法で答えを探しています。
私たちの日常のなかで、子どもとふれあいながら、こうした問いに思いをめぐらせることは、支援や教育の現場だけでなく、私たち自身の「人と人とのつながり」を考えるきっかけにもなるのではないでしょうか。
くすぐりの研究は、そんな大切なヒントを与えてくれています。
(出典:Science Advances)(画像:たーとるうぃず)
うちの子は、小さな頃から「くすぐり」は大好きのようです。
私がほっぺや手のひらをくすぐると、笑ったり、笑わなくてももっとしてくれとせがんだりします。
楽しいコミュニケーションの一つになっています。
(チャーリー)