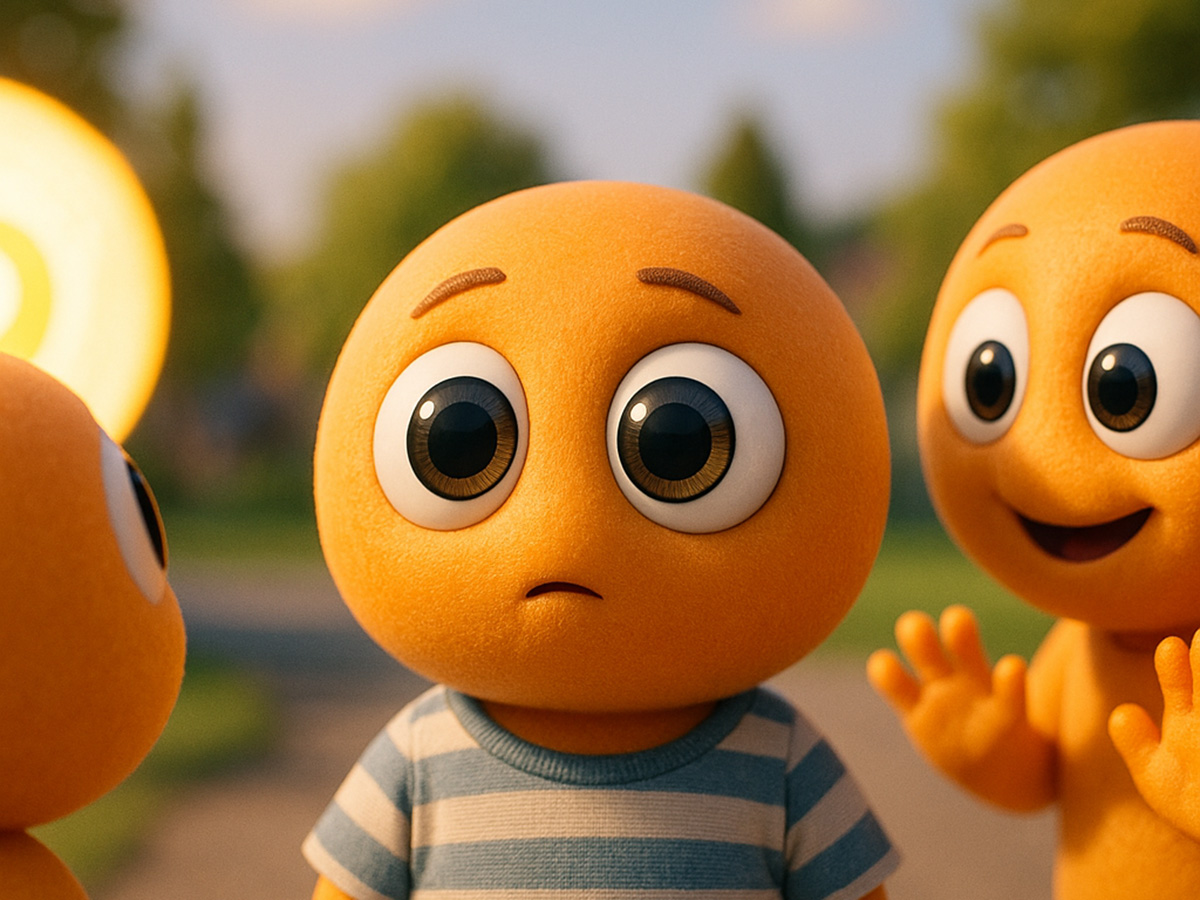
この記事が含む Q&A
- 視覚認知が自閉症児の日常生活の参加と関係するという研究結果は何を示していますか?
- 視覚認知の得点が高いほど家庭・学校・地域での参加度が高い傾向があり、正の相関が示されました。
- この研究の限界は何ですか?
- 一施設での小規模研究で他国・多様性への一般化は難しく、聴覚・触覚など他の感覚は扱われず、併存診断の子は除外されています。
- 因果関係の断定はされていますか?
- いいえ、関連は示されても因果関係は分からず、前後関係や第三の要因は不確定です。
トルコのヘルスサイエンス大学の研究チームは、自閉症の子どもにとって「視覚の力」が日常生活の中でどのように影響しているのかを明らかにしようとしました。
多くのご家族や支援者にとっても実感があるように、自閉症の子どもは光や模様といった刺激に強く反応する一方で、人の表情や目線といった細やかな情報には気づきにくいことがあります。
そうした「見え方のアンバランス」が、家庭や学校や地域での行動や参加にどう関わるのかを科学的に調べることが、この研究の狙いでした。
調査は2023年から2024年にかけて、イスタンブールの特別支援・リハビリテーションセンターで行われました。
子ども本人には口頭で説明を行い理解できる範囲で同意を得たうえで、保護者には書面で同意書に署名してもらい、調査はすべて対面で実施されました。
対象は7歳から10歳までの自閉症の診断を受けた子どもたちです。
61人が参加しました。
平均年齢は8.21歳で、男の子が37人(約61%)、女の子が24人(約39%)でした。
条件としては、子どもと家族が自発的に参加を了承すること、簡単な指示を理解できる程度のコミュニケーション力を持つこと、特別支援センターに通っていることが必要でした。
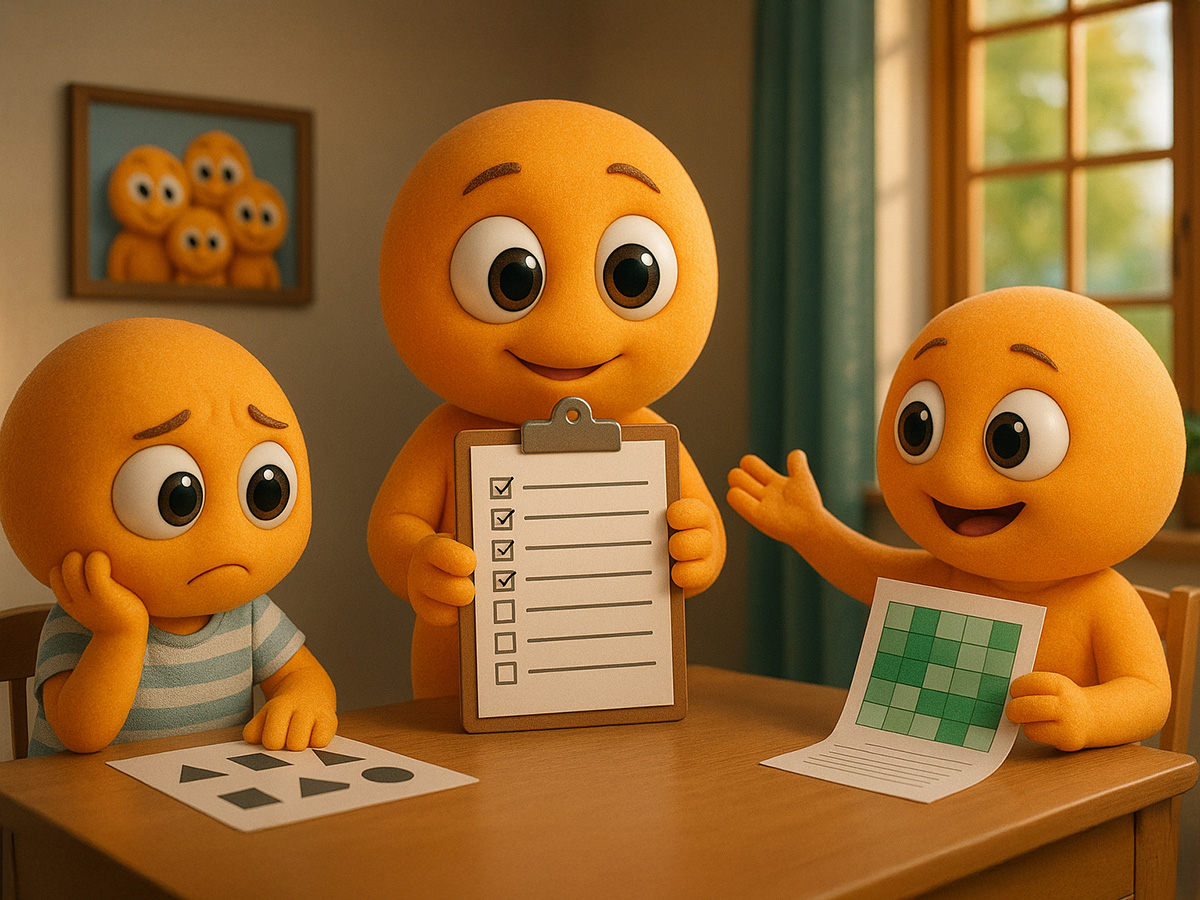
研究では三つの方法で情報を集めました。
一つ目は年齢や性別、きょうだいの数、学年、保護者の学歴や就業状況、家庭の収入や家族の形態(核家族、拡大家族、離別家庭)などの社会的背景です。
二つ目は「運動動作を伴わない視知覚検査(MVPT-4)」で、これは手を使わずに「見る力」を測る検査です。
黒い図形を白い背景に示し、複数の選択肢から正しいものを選ぶ形式で、45問あります。
測定するのは「空間関係をとらえる力」「形を見分ける力」「背景から対象を見分ける力」「全体像を推測する力」「見たものを覚える力」の五つです。
正解で1点、不正解や無回答は0点とし、合計点を出します。20〜30分ほどで終わる検査で、信頼性が確かめられています。
三つ目は「子ども・若者の参加スケール(CASP)」で、これは家庭、学校、地域、生活全般において子どもがどの程度活動に参加できているかを保護者に尋ねるものです。
20の質問があり、それぞれ0から4までの段階で答えてもらいます。
合計点は0から100の範囲になり、点が高いほど参加の度合いが大きいことを示します。
結果として、視覚認知の得点が高い子どもほど家庭や学校、地域での参加度が高いことが明らかになりました。
統計的にも強い関連が示され、「参加度」の変化の55.8%は視覚認知と家族の形態の二つで説明できることがわかりました。
具体的には、視覚認知の得点が1点上がると参加度が0.617点上がり、また核家族の子どもは離別家庭の子どもより平均で3.1点高いという結果でした。
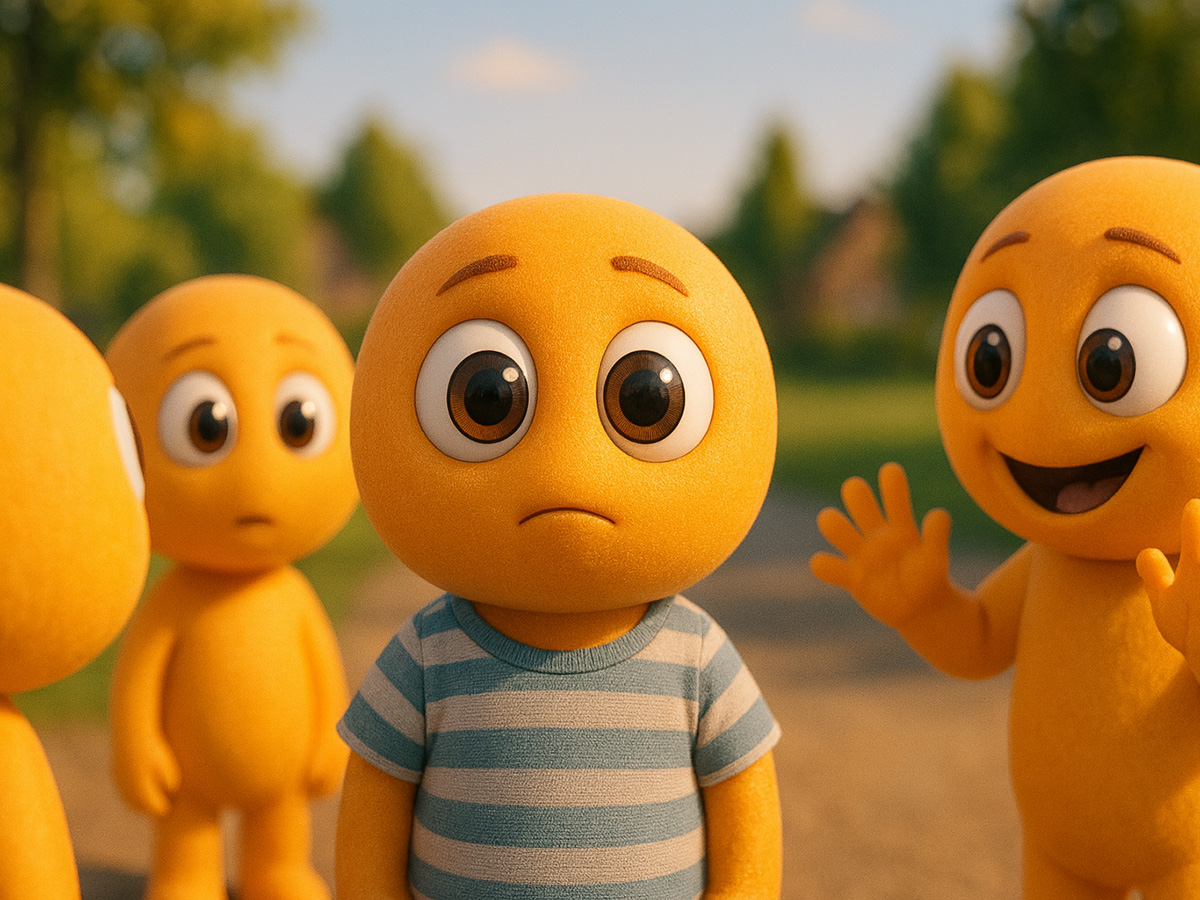
性別による違いも見られました。
男の子は家庭と学校での参加が高く、女の子は家庭生活や地域活動により多く関わっていました。
年齢や学年、きょうだいの数、家庭の収入、保護者の学歴や就業の有無では、大きな差は見られませんでした。
一方で、離別家庭の子どもは視覚認知も参加度も低い傾向がありました。
これは家族の支えが子どもの参加に強く関わることを示しています。
相関分析の結果でも、視覚認知と参加度の間には有意な正の関係があることが示されました。
家庭、学校、地域のすべての場面で、視覚認知が高い子どもはより多くの活動に参加していました。
視覚認知が最も大きな影響を持つことが明らかになりました。
研究チームは、これらの結果を「視覚認知が社会参加に強く関わっている」と解釈しましたが、因果関係を断定するものではないとしています。
つまり「見る力」が強いから参加が広がるのか、それとも参加の経験が「見る力」を育てているのかは、この研究からは決められません。
また第三の要因、たとえば全般的な認知力や家庭からの支えが両方に影響している可能性も考えられます。
そのため、今後は長期的に子どもを追跡する研究や、視覚認知に働きかける支援を導入して前後の変化を測定する研究が必要だとしています。
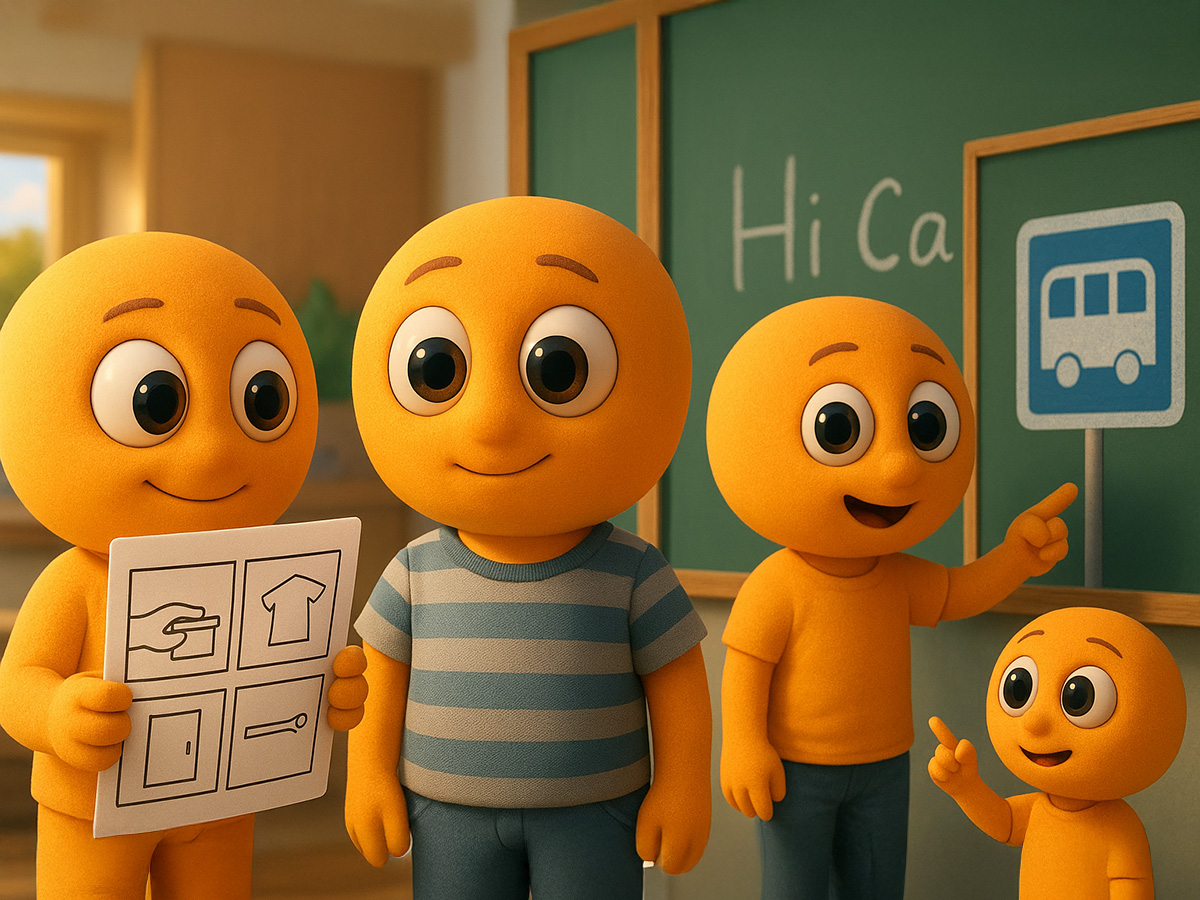
限界として、この研究は一つの施設で行われた小規模なものであり、他の国や文化にそのまま当てはめることはできない点が挙げられます。
また、聴覚や触覚など他の感覚は扱っていません。
さらに、併存する診断や補助具を持つ子どもは除外されているため、より多様な自閉症の子どもを反映していない可能性もあります。
それでも、この研究の意義は大きいものです。
自閉症の子どもにとって「見る力」が日常生活の参加と結びついていることをデータで示した点は、支援の方向性を考えるうえで重要です。
たとえば、家庭では片づけや着替えの手順を絵や写真で示す、学校では板書を見やすく整理する、地域ではサインを単純化する、といった工夫が考えられます。
こうした工夫はすでに実践されているところもありますが、今回の研究はその重要性を裏付ける科学的な根拠を提供しました。
まとめると、この研究は自閉症の子どもにとって「視覚認知」と「日常生活への参加」が深く関わり合っていることを示しました。
因果関係は今後の課題ですが、見え方を整えることが日常の行動を広げる可能性を示唆しています。
ご家族や支援者にとっては、今日からでも「見やすさ」を意識した工夫を取り入れることが、子どもの生活を前に進める第一歩になると感じられるでしょう。
(出典:PLOS One DOI: 10.1371/journal.pone.0330457)(画像:たーとるうぃず)
「視覚認知が社会参加に強く関わっている」と解釈しましたが、因果関係を断定するものではない。
つまり「見る力」が強いから参加が広がるのか、それとも参加の経験が「見る力」を育てているのかは、この研究からは決められません。
たしかにうちの子も小さな頃に見えていないのではないかとメガネも作ったのですが、そのときに眼科のお医者さんに言われたのは、
- 見えないから関心がない。
- 関心がないから見ないために見えない。
この悪循環を早く止めましょうとのことでしたが、うちの子はメガネを嫌って、かけることはほとんどありませんでした。
幸い、大きくなった今は、見えていないという感じはありません。
(チャーリー)





























