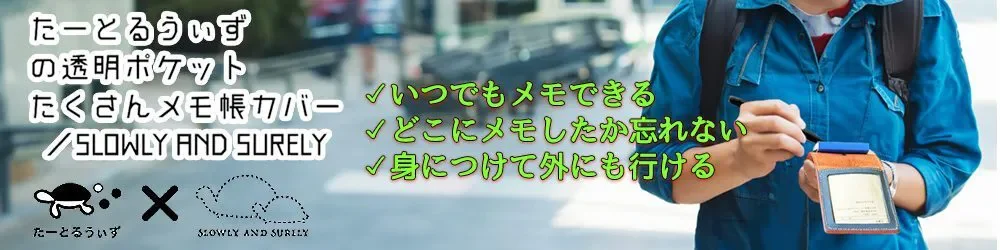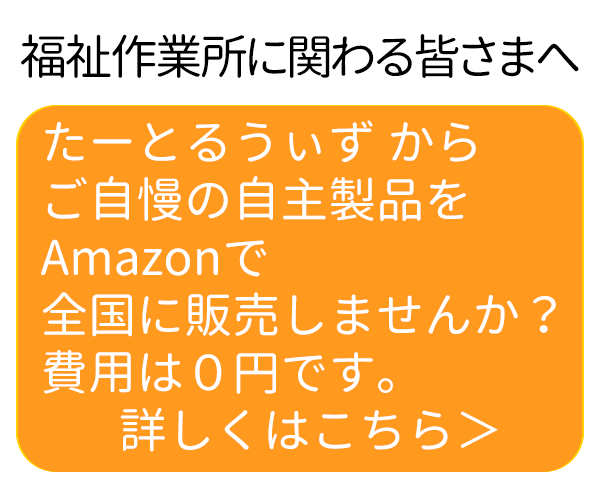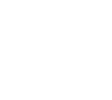この記事が含む Q&A
- 自閉症の理解で「生活の質」モデルと「ニューロダイバーシティ」はどう関係する?
- 両者は医学モデルを超え、社会参加と自己決定を支援する統合を目指す点で重なる一方、緊張関係も指摘されています。
- 呼び方の違いが示す意味とは何ですか?
- 支援場面では「自閉症のある人」という表現が使われやすく、自己表現の場面では「自閉症者」という認識が大切にされる場合があり、場面によって使い分けるべきです。
- 研究の代表性と参加の課題は何ですか?
- 知的障害を伴う人など声が反映されにくい層の参加を増やし、全自閉症者の声を研究に反映させることが課題です。
近年、自閉症は「できないこと」や「欠けているもの」を基準に理解される存在から、
「どのように生きているのか」「どのような支えがあれば、その人らしく暮らせるのか」を中心に考えられる存在へと、大きく捉え直されつつあります。
スペインのサラマンカ大学コミュニティ包摂研究所(Institute for Community Inclusion, INICO)を中心とした研究グループは、この変化の流れの中で、二つの重要な考え方に注目しました。
ひとつは、障害分野で長年使われてきた「クオリティ・オブ・ライフ(生活の質)」モデルです。
もうひとつは、自閉症当事者の自己主張や社会運動から生まれた「ニューロダイバーシティ」という考え方です。
この研究は、自閉症のある人を、支援ニーズの軽い人から重い人まで含めて捉えたうえで、この二つの考え方がどこで重なり、どこですれ違い、どうすれば統合できるのかを検討したミニレビューです。
非言語の自閉症者、知的障害を伴う自閉症者、精神的な困難を併せ持つ人たちも含めて議論している点が大きな特徴です。
まず論文は、自閉症がきわめて多様な特性をもつ状態であることを前提に話を進めます。
認知のあり方、コミュニケーションの形、感覚の感じ方、日常生活の適応の仕方は、人によって大きく異なります。
そのため、「自閉症とは何か」を一つの型で定義するのではなく、「その人にとっての良い人生とは何か」「どのような条件があれば社会に参加できるのか」を考える視点が重要になると述べています。
クオリティ・オブ・ライフの考え方は、国連の障害者権利条約とも深く結びついて発展してきました。
この枠組みでは、生活の質は単なる客観的な指標だけでなく、本人が自分の人生をどう評価しているかという主観的な側面も含めて考えられます。
支援とは、その人の特性と環境との相互作用の中で、社会参加や自己決定を可能にするための仕組みとして位置づけられています。
一方、ニューロダイバーシティの考え方は、自閉症を「治すべき障害」ではなく、人間の自然な多様性のひとつとして捉え直します。
ここでは、自己受容、帰属感、本来の自分でいることが、ウェルビーイングの中核に置かれます。
自閉症はアイデンティティの一部であり、誇りや社会的権利と結びつくものとして語られます。

論文は、この二つの考え方が、どちらも医学モデルを超えようとしている点では共通していると指摘します。
しかし同時に、いくつかの緊張関係も浮かび上がると述べています。
その一つが、呼び方をどう考えるかという点です。
支援や制度を考える分野では、これまで「自閉症のある人」という言い方が多く使われてきました。
これは、その人を一人の生活者として捉えたうえで、必要な支援や環境を整理しやすくするための考え方です。
一方で、ニューロダイバーシティの考え方では、「自閉症者」という呼び方が大切にされることがあります。
自閉症は後から付け加えられた特徴ではなく、ものの感じ方や考え方を含めた、その人らしさそのものだと考えるからです。
日本語では、この二つの言い方に大きな意味の違いを感じにくいかもしれません。
しかし、海外では、自閉症をどう理解し、どう扱ってきたかという歴史の中で、呼び方そのものが「自分をどう位置づけるか」を示す意味を持つようになってきました。
この違いは単なる表現の好みではなく、「誰のために」「どの文脈で」言葉が使われるのかという問題と深く関わっています。
論文は、どちらか一方を絶対視するのではなく、支援の場面と自己表現の場面では、言語の役割が異なることを認める必要があると論じています。

もう一つの重要な論点は、代表性の問題です。
ニューロダイバーシティ運動は、言語的に表現力の高い自閉症成人によって牽引されてきました。
その結果、知的障害を伴う人や、日常生活で多くの支援を必要とする人の声が、研究や社会的議論の中で十分に反映されていない可能性が指摘されています。
実際、論文が紹介している先行研究では、自閉症アイデンティティに関する研究の参加者のうち、知的障害を伴う人は極めて少数でした。
これは、「自閉症の誇り」や「自己肯定」という議論が、すべての自閉症者に同じ形で当てはまるわけではないことを示唆しています。
応用や臨床の視点から見ると、この問題はさらに複雑になります。
支援やサービスへのアクセスは、現在でも診断を前提とする場合が多く、診断を受けること自体が大きな壁になっている人も少なくありません。
そのため、自己診断や自己同一化が広がっている現状も論文では取り上げられています。
しかし、診断を完全に不要なものとみなす立場には、慎重な検討が必要だとも述べられています。
なぜなら、自閉症は非常に幅の広い特性と支援ニーズを含んでおり、支援がなければ日常生活が著しく困難になる人も多いからです。
メンタルヘルスの問題や自殺リスクの高さといった現実も、論文は明確に示しています。
クオリティ・オブ・ライフの枠組みでは、支援はアイデンティティを脅かすものではなく、社会参加を可能にする手段と捉えられます。
一方で、ニューロアファーマティブな立場からは、支援が「普通にさせるための矯正」になってしまう危険性にも注意が向けられています。
論文は、重要なのは「支援が必要かどうか」ではなく、「どのような支援が、本人の尊厳と自律を守りながら提供されるか」だと述べています。
自己管理だけに頼る支援は孤立を招くおそれがあり、逆に画一的な支援は能力を過小評価する危険があります。

研究の視点においても、同様の課題が指摘されています。
長年行われてきた遺伝研究や脳研究は、自閉症の原因解明には一定の知見をもたらしましたが、日常生活の質を直接改善する成果にはつながりにくかったと論文は述べています。
一方、自閉症当事者や家族が重視している研究テーマは、生涯にわたる支援、メンタルヘルス、社会理解、教育や雇用へのアクセスなど、より生活に密着したものです。
しかし、こうした優先事項は、研究資金や研究計画に十分反映されてこなかった現実があります。
クオリティ・オブ・ライフのモデルは、こうした研究の方向性を再調整する枠組みとして有効だと論文は評価しています。
ただし、多くの研究が代理回答に依存しており、本人の声が直接反映されていないという課題も同時に指摘されています。
そのため、近年は参加型研究や共同研究の重要性が高まっています。
ただし、支援ニーズの高い自閉症者が、研究のすべての段階に本当に参加できているかという点は、今後の大きな課題として残されています。

こうした議論を踏まえ、論文は六つの統合的な原則を提示しています。
- ウェルビーイングは自己受容だけでなく、支援の質にも依存する
- 言語は文脈と本人の選好を尊重して使われるべき
- アイデンティティは変革的な力を持ち、診断は排除的であってはならない
- 支援はアイデンティティの敵ではなく、参加のための手段
- 介入は正常化を押しつけず、成長と帰属を支えるもの
- そして研究は、すべての自閉症者を知識の担い手として包摂する必要がある
最後に示されているのは、「相互依存」という考え方です。
人は誰もが他者の支えの中で生きており、違いは社会を豊かにする一方で、環境によっては脆弱性にもなり得ます。
自閉症を、アイデンティティ、ニーズ、支援、文脈の相互作用として捉えること。
それが、より公正で包摂的な社会へ向かうための鍵であると、この研究は示しています。
(出典:Frontiers in Psychiatry DOI: 10.3389/fpsyt.2025.1756323)(画像:たーとるうぃず)
ひとくくりにラベルを貼るのではなく、
その人を見て、その人を尊重する。お互いに。
(チャーリー)