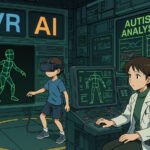この記事が含む Q&A
- 自閉症やADHDについて、職場でどんな誤解がまだ残っていると指摘されていますか?
- 自閉症を知っていても「知的障害がある」という誤解や、ADHDの特徴の一部を誤って結びつける誤解が存在します。
- 職場での受け止め方はどうでしたか?
- 一緒に働くことへの安心感は高い一方、職場環境は整っていないと感じる人が多く、平均3.8点の評価にとどまりました。
- 研究が勧める職場づくりの具体的な方策は何ですか?
- 静かな作業スペースやノイズキャンセリング、勤務時間の柔軟化、コミュニケーションの明確化、メンタリング、ユニバーサルデザインの導入が挙げられています。
自閉症やADHDをもつ人が、社会の中でどのように受け止められているか。
とりわけ職場という場での理解や支援は、本人だけでなく家族や支援者にとっても大きな関心事です。
スペイン・マドリードのインファンタ・レオノール大学病院とコンプルテンセ大学、そして製薬企業アストラゼネカとその子会社アレクシオン、さらにPsiKids神経発達ユニットが協力して行った研究は、この問題を深く探るために実施されました。
対象となったのは、スペイン国内でアストラゼネカやアレクシオンに勤める社員たち。2024年7月に行われたアンケート調査に、1168人に案内が送られ、そのうち880人が回答しました。
回答率は75%を超え、非常に高い数字です。それだけ社員たちも関心を持ち、自分の考えを伝える必要を感じていたのだと言えるでしょう。
回答者の年齢は主に30代から50代で、平均は43歳。
女性が62%を占め、全体の3分の2近くが修士や博士といった大学院レベルの学歴を持っていました。
つまり、この調査は比較的高学歴で意識の高い集団を対象にしているのです。
それでもなお、ADHDや自閉症についての誤解は残っていることが示されました。
「自閉症を知っていますか?」という問いには98%が「はい」と答えました。
「ADHDを知っていますか?」にも99%が「はい」と答えました。
名前そのものはほとんどの人が知っていたのです。
ところが、次に「具体的な特徴を選んでください」と聞くと、状況は変わります。
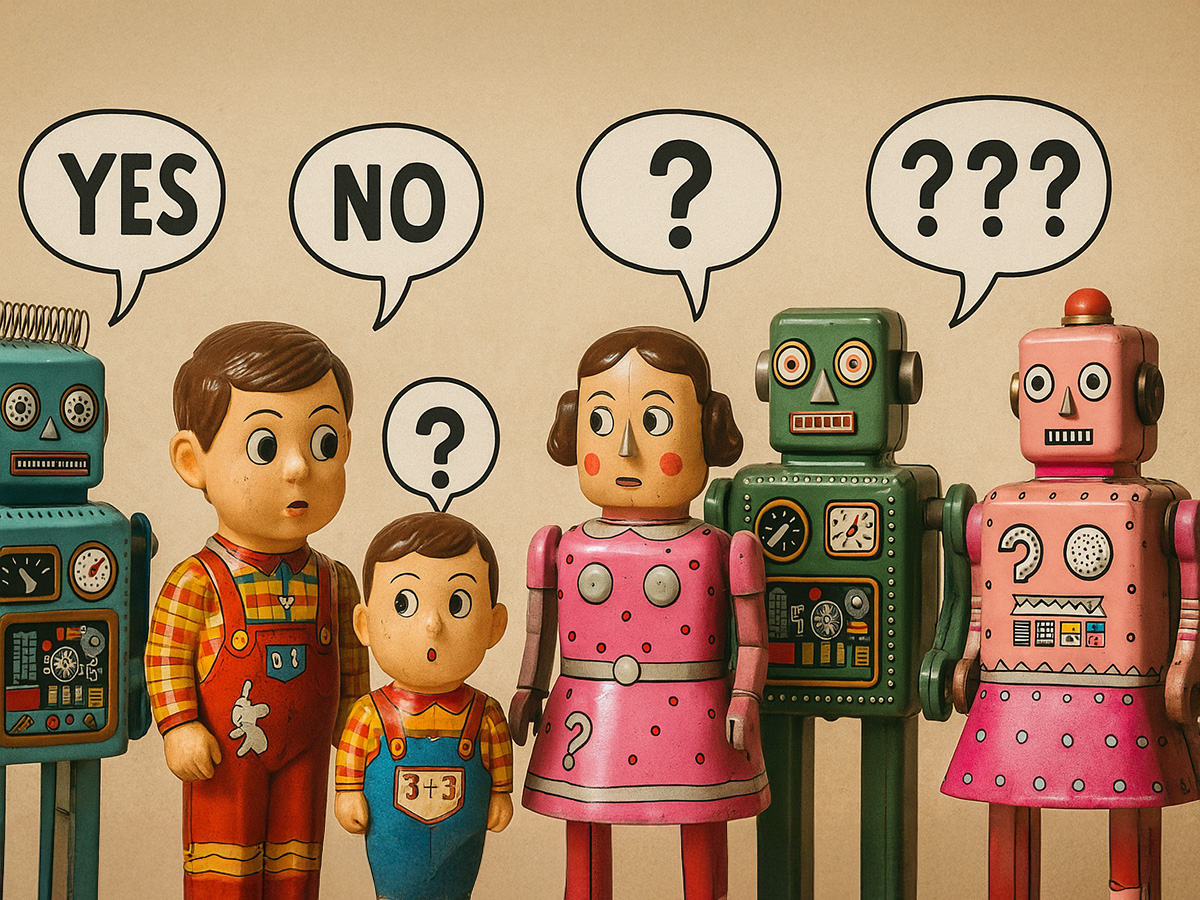
たとえば自閉症の特徴として「友達をつくるのが難しい」「非言語的なコミュニケーションが苦手」「繰り返し行動をする」といった項目は9割近い人が正しく選びました。
しかし「知的障害」を自閉症の特徴だと答えた人が20%いました。
つまり5人に1人は「自閉症=知的障害がある」と思い込んでいたのです。
ADHDについても同じように、注意の持続が難しい、多動性や衝動性があるといった項目は多くの人が正しく答えましたが、こちらも約2割が「限定された興味を持つ」という特徴をADHDだと誤って答えました。
本来それは自閉症に関連する説明であり、ADHDの中心的な特性とは異なります。
この誤解は、当事者や家族にとっては身に覚えのある経験かもしれません。
「あなたは自閉症だから必ず知的障害があるはずだ」と言われたり、「ADHDなら同じことばかりに固執するのでは」といった思い込みを受けたりすることは少なくありません。
今回の調査は、そうした誤解がいまだに広く存在していることを数字で裏づけたのです。
一方で、「一緒に働くことに抵抗があるか」という問いに対しては、社員たちの回答は比較的ポジティブでした。
0から10の尺度で「一緒に働くとしたらどのくらい安心できるか」を尋ねたところ、ADHDの人に対しては平均7.4点、自閉症の人に対しては7.1点でした。
どちらも10点満点の中では高い数字です。
つまり、多くの人は「働くこと自体に不安はない」と感じているのです。
ところが、同じ社員たちに「職場の環境は十分に整っていますか?」と聞くと、結果は厳しいものでした。
6割以上の社員が「整っていない」と答え、平均スコアは3.8点にとどまりました。
気持ちはあっても、実際の環境が追いついていない。
そのギャップが浮き彫りになったのです。
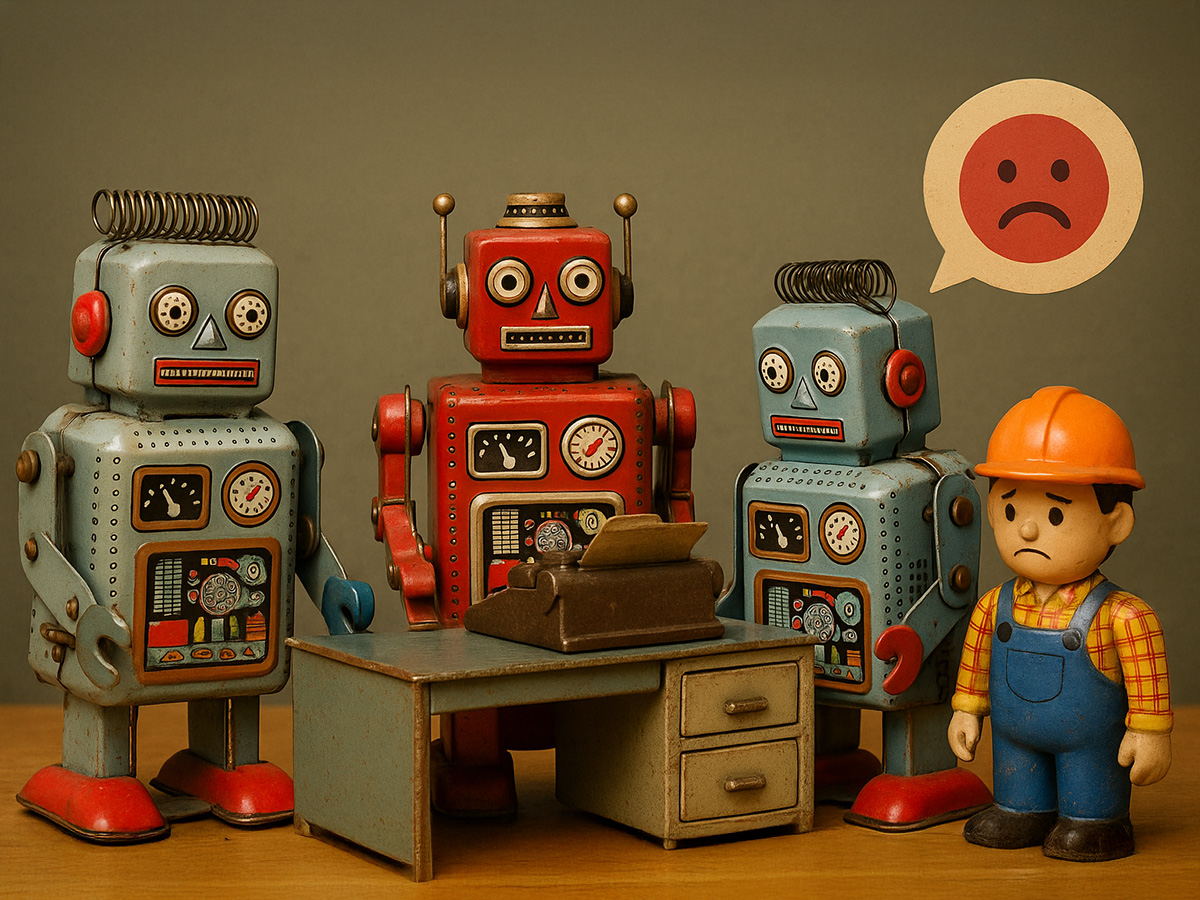
さらに「社会全体は発達障害についてどのくらい理解しているか」という問いでは、8割近くが「理解していない」と答えました。
平均スコアは3.0点。
社会の知識不足を多くの人が肌で感じていることがわかります。
社員が自閉症やADHDについて学んだ情報源は、「友人や家族から」が最も多く77%にのぼりました。
次に「インターネット」が63%、「医療専門職」が50%、「マスメディア」が49%でした。
職場での公式研修を通じて学んだという人は少なく、学びの多くは日常生活の中で得られていたのです。
そして「今後どのような教育を望むか」という問いに対しては、「学校での講演会」が88%と圧倒的に支持されました。
次いで「ソーシャルメディア」(68%)、「ワークショップやセミナー」(58%)、「患者団体からの情報提供」(48%)が挙げられました。
社員たちは、自分だけが特別に研修を受けるのではなく、社会全体に広がる形で教育や情報提供が行われることを強く望んでいることが見えてきます。
研究チームはまた、ADHDや自閉症を持つ人の強みに注目しています。
細部に気づく力、パターンを見抜く力、複雑な問題を解決する力。これらはしばしば軽視されますが、企業にとっては大きな資産です。
調査の結果、社員の多くはこうした強みに気づいていないことも浮かび上がりました。
困難の側面だけを見てしまうと、可能性を活かせないまま終わってしまいます。
論文では、職場で実際に役立つ工夫として、静かな作業スペースの提供やノイズキャンセリング機器の利用、勤務時間の柔軟化、コミュニケーションの明確化、メンタリング制度の導入などが挙げられています。
これらは神経発達症のある社員だけでなく、すべての社員にとって働きやすさを高める工夫にもつながるとされています。
また、研究チームは「ユニバーサルデザイン」の発想を推奨しています。
特定の社員のために特別な配慮をするのではなく、最初から誰にとっても利用しやすい制度や環境を設計する。
この考え方があれば、当事者が自分の特性を告白しなければ支援を受けられないという状況を減らせるのです。
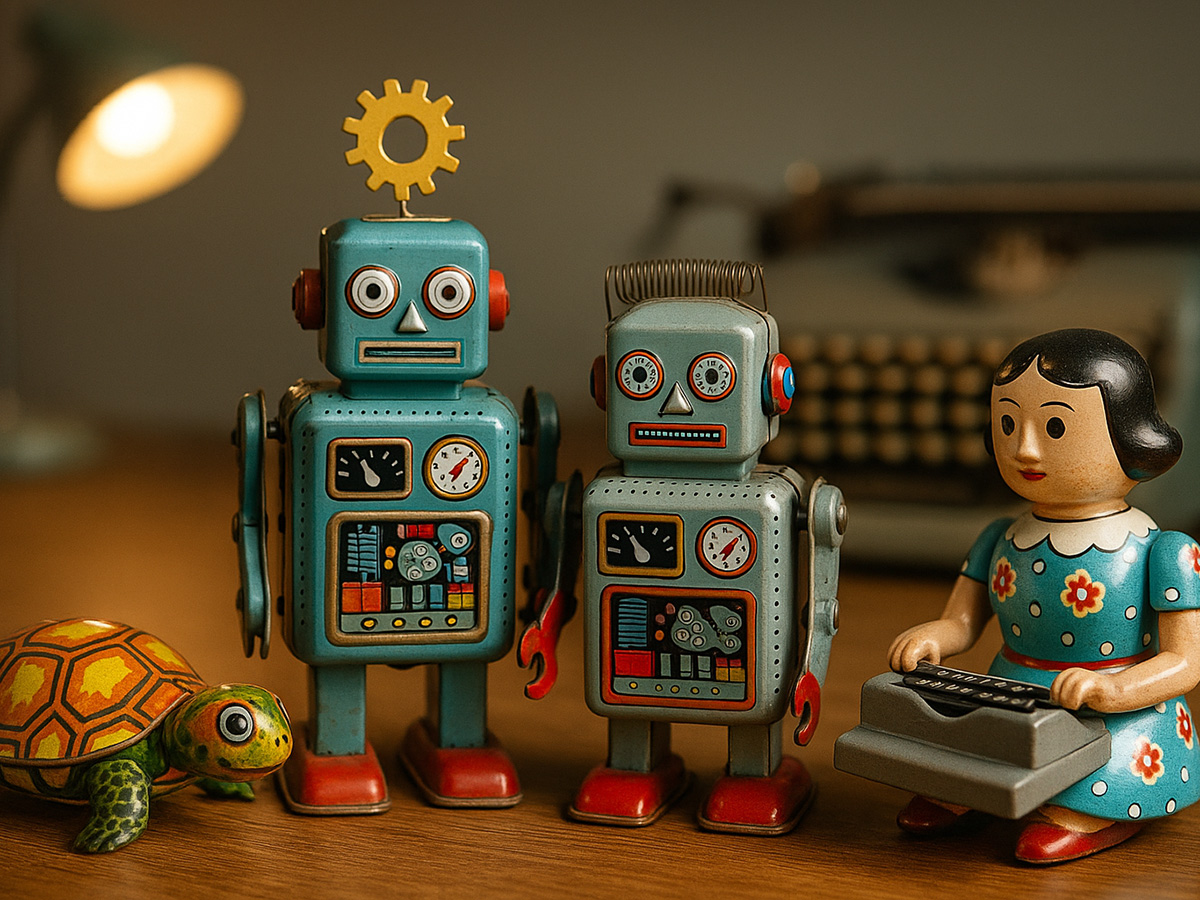
今回の研究には限界もあります。
対象となったのは製薬業界の大企業で、多くが高学歴の社員でした。
そのため、必ずしも社会全体を代表しているわけではありません。
しかし、高学歴の集団でさえ誤解が残っているという事実は、社会全体ではさらに大きな課題があることを示唆しています。
研究チームは今後の方向性として、教育プログラムの効果を追跡する長期研究や、他の業種や国を対象とした調査を挙げています。
この研究は第一歩にすぎません。
まとめると、この調査はこう語っています。
「知っている」と答える人は多いが、理解には誤解が残る。
「一緒に働ける」と感じる人は多いが、環境はまだ不十分。
強みに目を向けることで、当事者も企業も社会も恩恵を受ける。
自閉症やADHDをもつ人、その家族、そして支援者にとって、この知見は大きな意味を持ちます。
誤解と現実のギャップを知ることは、より良い社会づくりの出発点になるからです。
(出典:Nature scientific reports DOI: 10.1038/s41598-025-17470-8)(画像:たーとるうぃず)
「強み」を正しく理解し、発揮できるように。
それが、競争力の源泉となります。
(チャーリー)