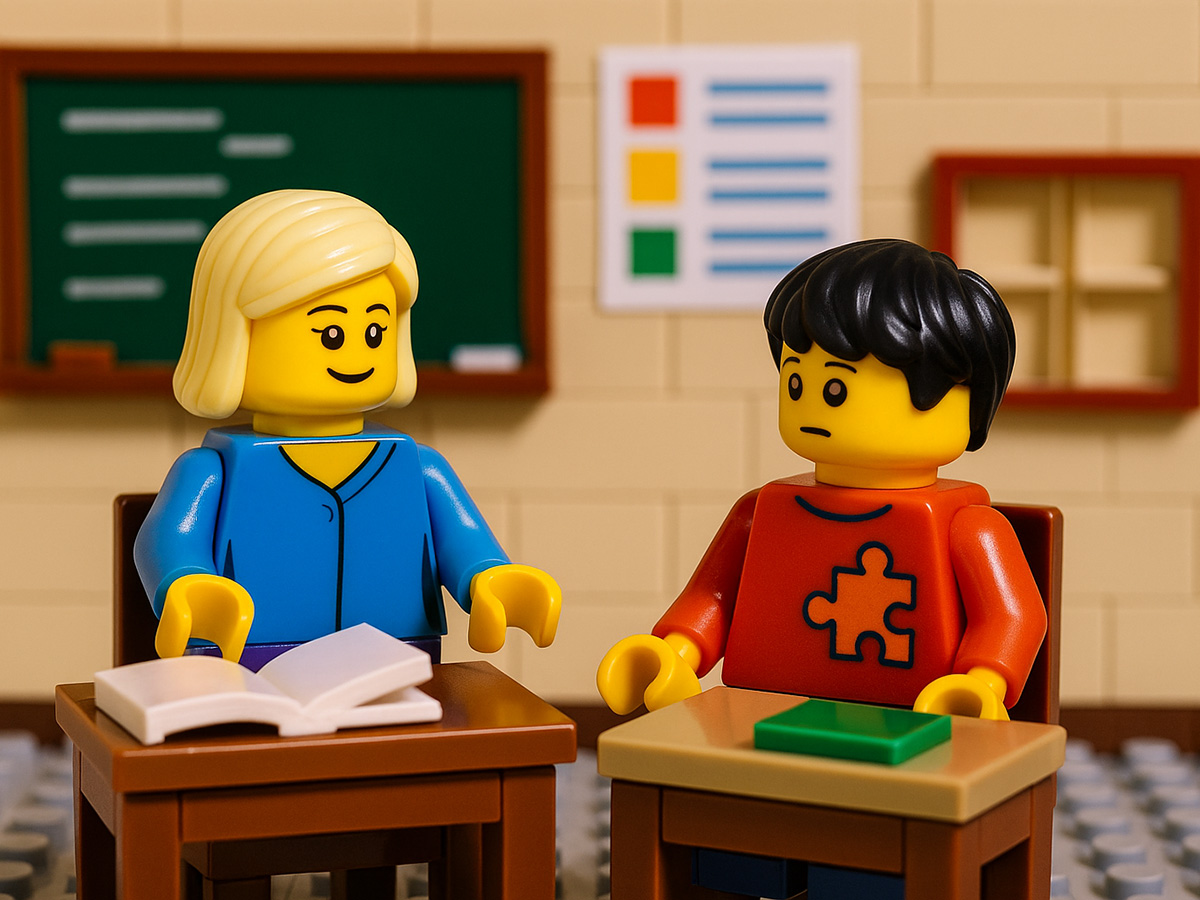
この記事が含む Q&A
- インクルーシブ教育における教師の態度は子どもの学習と社会的発達に影響を与えるのですか?
- はい、前向きな態度は支援の実現を促す一方、否定的な態度は孤立や困難を招く可能性があります。
- 教師の態度を左右する要因は何ですか?
- 知識・訓練・経験・自己効力感・文化・性別の6つが影響すると報告されています。
- 教師のASDに対する態度を改善するにはどうすれば良いですか?
- 教育課程でのASD・インクルーシブ教育の充実、現職研修、学校全体の支援体制づくり、教育政策とリソース整備、そしてメディア理解の促進が提案されています。
自閉スペクトラム症、いわゆるASD(Autism Spectrum Disorder)を持つ子どもたちが、通常学級でともに学ぶ機会が世界的に増えています。これは「インクルーシブ教育」と呼ばれ、障害のある子どもも障害のない子どもも、同じ教室で学び、育つことを目指す教育のかたちです。
このような取り組みは、子どもたちにとって社会的なつながりを育む大切な場となりますが、現場でその実現を担う教師たちにとっては、大きな課題を抱えることにもつながっています。
スペイン・バレンシア大学の研究チームは、このインクルーシブ教育を進める上で欠かせない「教師のASDに対する態度」について、世界中の研究を整理し、分析する系統的レビューを行いました。
対象となったのは、2015年から2020年の間に発表された英語の実証研究16本です。
このレビューでは、教師たちの態度がどのような傾向にあるのか、そしてその態度を左右する要因には何があるのかを明らかにしています。
教師の態度とは、ASDのある子どもを通常学級で受け入れることについて、どのように感じ、どのような姿勢で関わろうとしているかを指します。
この態度が前向きであれば、教育現場においてインクルーシブ教育はより成功しやすくなります。
反対に、態度が否定的であれば、ASDのある子どもが孤立したり、学習面や社会的な発達で困難を感じやすくなってしまいます。

研究チームが調べた16本の論文のうち、教師の態度が「肯定的」であったと報告したものは、わずか4本でした。
6本は「中立的」または「混在」(肯定と否定が入り混じった)と評価され、1本は「否定的」な態度を示していました。
残りの5本は、国や条件の違いによって差があることを報告していました。
では、なぜ教師によって態度が異なるのでしょうか。
研究では、次の6つの要因が影響を与えるとされています。
1つ目は、「知識」です。
ASDについての理解が深い教師は、行動の意味や対応方法をより適切にとらえることができるため、肯定的な態度を示す傾向があります。
たとえば、あるアメリカの研究では、ASDの専門的な訓練を受けた教師は、そうでない教師よりも積極的に子どもと関わろうとする姿勢が見られました。
2つ目は、「訓練(教育)」です。
特別支援教育の訓練を受けている教師は、一般教育のみを受けた教師よりも、ASDのある子どもの受け入れに対して前向きであることが多いと報告されています。
実際、初等教育や保育を専門とする教師の養成課程では、インクルーシブ教育に関する内容がより多く含まれているため、そうした教師の方が前向きな態度を持つことが確認されています。

3つ目は、「経験」です。
ASDのある子どもと接した経験があるかどうかが、態度に大きく影響します。
たとえば、過去にASDの子どもを受け持ったことのある教師は、不安よりも理解や自信を持って接することができる傾向があります。
逆に、経験がない教師は、誤解や不安から否定的な印象を持ちやすくなります。
4つ目は、「自己効力感」、つまり「自分ならうまく教えられる」という自信の有無です。
自己効力感が高い教師は、多少の困難があっても前向きに取り組むことができ、結果としてより肯定的な態度を持つ傾向があります。
5つ目は、「文化」です。
国によって、教育制度や社会の価値観が異なるため、ASDに対する教師の態度にも差が見られます。
アメリカ、オーストラリア、イギリスなどでは比較的肯定的な態度が多く、中国、マレーシア、サウジアラビアなどでは中立的または否定的な態度が多く報告されています。
これは、各国のインクルーシブ教育に対する政策の違いや、障害に対する社会的な認識が影響していると考えられます。
6つ目は、「性別」です。
一部の研究では、女性教師の方が男性教師よりもASDに対して肯定的な態度を持つ傾向があるとされていますが、すべての研究で一貫した結果が得られているわけではありません。
また、この研究レビューでは、教師の態度を調べるために使われた方法にも注目しています。
多くの研究が「リッカート尺度」と呼ばれるアンケート方式で調査を行っていますが、この方法には「社会的望ましさバイアス」が入りやすいという問題があります。
つまり、実際の本音とは違い、「正しいと思われる答え」を選んでしまう傾向があるということです。
これを避けるためには、インタビューや観察、あるいは間接的に態度を測定する手法も検討すべきだと指摘しています。
では、どうすれば教師のASDに対する態度を改善できるのでしょうか。
研究チームは、次のような対策を提案しています。
まず、教師養成課程でASDやインクルーシブ教育に関するカリキュラムを充実させることが重要です。
実習やボランティアなどを通じて、実際にASDのある子どもと接する機会を持つことで、理解と自信を深めることができます。
また、現職教師に対しても、定期的な研修や学び直しの機会を提供することが求められます。
とくにASDに関する知識や対応スキルの習得は、教師自身の負担感を減らし、より前向きな態度を育てるうえで大きな効果を持ちます。
さらに、学校全体としてインクルーシブな文化を築くことも大切です。
校長や管理職が積極的に支援を行い、全教職員が協力して子どもたちを支える体制を整えることで、個々の教師にかかる負担を軽減し、前向きな態度を維持しやすくなります。
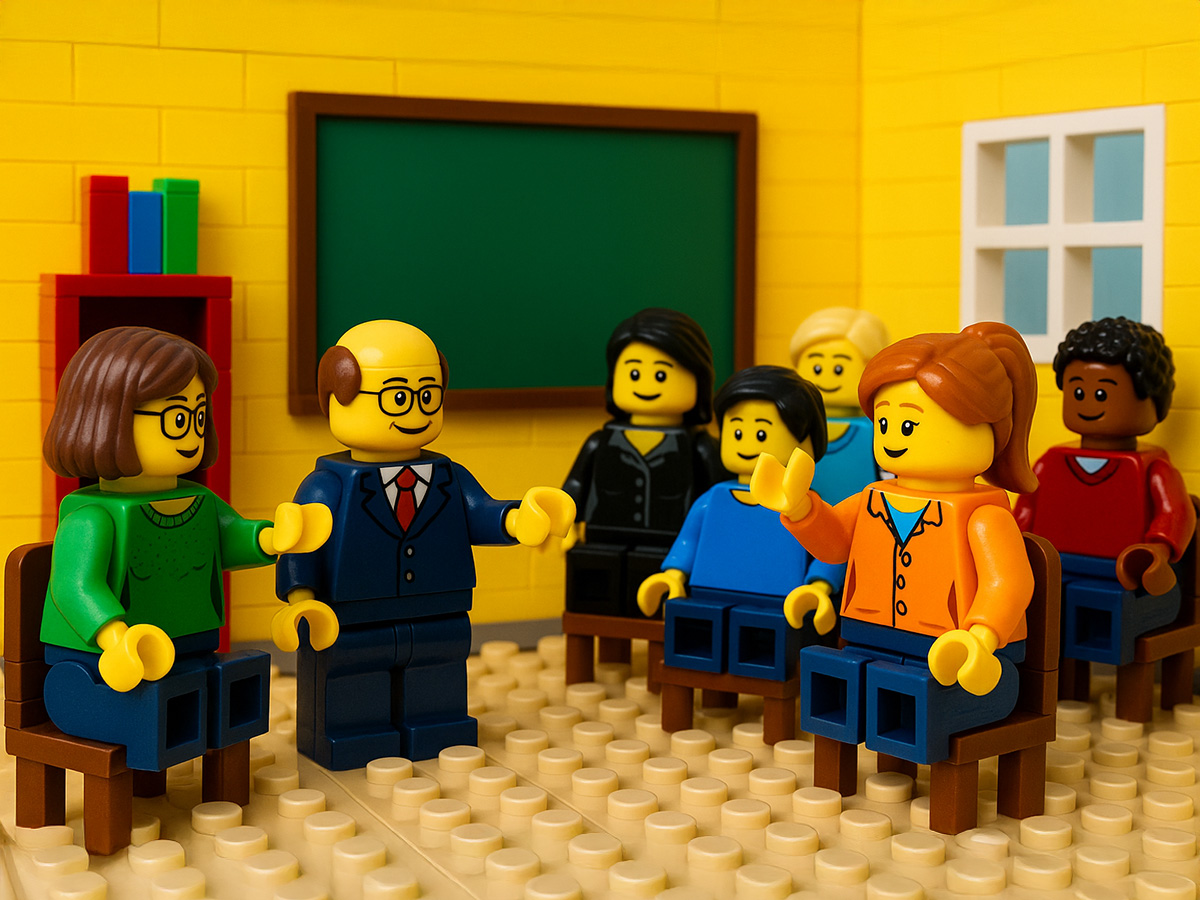
加えて、国や地域レベルでの教育政策も見直しが必要です。
インクルーシブ教育を推進するには、法律や方針だけでなく、現場で実行可能な予算や人材、施設といったリソースの整備が不可欠です。
そうでなければ、教師がいくら前向きな態度を持っていても、実際の実践が困難になってしまいます。
最後に、研究チームは、将来的にはメディアの影響についても研究すべきだと述べています。
テレビドラマや映画、SNSなどで描かれるASDのイメージが、社会全体、そして教師個人の認識に大きな影響を与えるからです。
事実と異なる描かれ方がされれば、誤解や偏見を生む可能性があります。
反対に、ASDを正しく理解し、共感を呼ぶような表現が広まれば、教師を含む社会全体の態度も変わっていくはずです。
このように、ASDのある子どもたちをよりよく理解し、支援していくためには、教師の態度を育て、支えるための多面的なアプローチが求められます。
訓練と経験、文化的理解と制度的支援。これらすべてが連携しながら進んでいくことで、子どもたちの学びと成長の場はより豊かになっていくのです。
(出典:ResearchGate)(画像:たーとるうぃず)
うちの子についていえば、重度自閉症で知的障害もあり話すこともできないため、ずっと特別支援学校でした。
インクルーシブでないからこその、それぞれの子どもにあった手厚い支援があり、ずっと幸せに学び、過ごすことができました。
しかし程度が違えば、インクルーシブであるほうがいいのかもしれません。
ですが、そこにいる先生がもしそれに否定的であれば、それは無理なことでしょう。
自閉症の子にインクルーシブ教育が就職や進学に良い影響。米研究
(チャーリー)




























