
この記事が含む Q&A
- 食べ物を食べたがらない子どもは脳の特性に関係していることがありますか?
- はい、研究では摂食障害の子どもたちの脳構造に特有の違いがあることが示されています。
- EO-ANとARFIDの子どもたちの脳にはどのような違いがありますか?
- EO-ANは脳の皮質が薄く、中枢や感情の調整領域が小さくなっている一方、ARFIDは感覚処理に関係する領域に特徴的な変化が見られます。
- 摂食障害の脳の違いを理解することは子どもへの支援にどのように役立ちますか?
- それぞれの脳の特性に応じたきめ細やかな支援を行うための理解と手助けになり得ます。
食べ物を食べたがらない子どもは、決してめずらしくありません。
でも、その「食べない」理由が、「ただの好き嫌い」や「少食」ではなく、こころや脳の特性に深く関係しているとしたら、どうでしょうか。
カナダのSickKids(トロント小児病院)とトロント大学、フランスのパリ精神医学・神経科学研究所およびパリ・シテ大学による研究チームが、思春期前に発症する2つの摂食障害について、それぞれの子どもの脳構造をくわしく調べました。
ひとつは「Early-Onset Anorexia Nervosa(EO-AN)」と呼ばれるもので、体重への強いこだわりから、極端に食事を制限してしまう障害です。
もうひとつは「Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder(ARFID)」といい、体重や体型とは無関係に、食べ物への強いこだわりや不安から、特定の食品しか食べられなくなる傾向が特徴です。
それぞれ異なる理由で食べられなくなる子どもたちの脳に、どのような違いがあるのかを調べたのです。
対象となったのは、EO-ANの子ども124人、ARFIDの子ども50人、そして健康な子ども116人(定型発達、TD)です。
研究ではMRI画像を使って、脳のさまざまな部分の厚みや体積を測定しました。
この調査によって、「どうして食べられないのか?」という問いに対し、脳の“かたち”という新しい視点からの答えが見えてきました。

まず注目されたのは、EO-ANの子どもたちの脳の表面が広い範囲で“薄く”なっていたことです。
脳の表面には「皮質(ひしつ)」と呼ばれる部分があり、しわのように折り重なっていて、感覚や思考、記憶などを司っています。
EO-ANの子どもでは、この皮質が特に「頭のてっぺんからうしろ側」にかけての広い範囲で薄くなっていました。
具体的には、「上頭頂葉(じょうとうちょうよう)」「楔前部(けつぜんぶ)」「舌状回(ぜつじょうかい)」などの場所です。
これらは、自分の体の感覚や、見たり動いたりすることに関係する部分です。
また、脳の“内側”にある重要な中枢──たとえば「視床(ししょう)」「扁桃体(へんとうたい)」「被殻(ひかく)」「淡蒼球(たんそうきゅう)」といった領域──の大きさも、健康な子どもたちよりやや小さくなっていることがわかりました。
これらの場所は、感情や衝動の調整、感覚のフィルターのような役割を担っています。
さらに、脳の中を流れる液体(脳脊髄液、CSF)の量は増加していました。
これは、脳の“実質”が減ったぶん、その隙間を埋めていると考えられます。
これに対して、ARFIDの子どもたちの脳構造はEO-ANとは違う特徴を見せていました。
ARFIDでも、脳の全体的な大きさや、皮質の「面積」、灰白質の「体積」は、健康な子どもよりやや小さめでした。
しかし、皮質の厚さはほとんど変わっていなかったのです。
唯一、変化が見られたのは「右の帯状回峡部(たいじょうかいきょうぶ)」という場所です。
ここは、お腹がすいた・苦しい・気持ち悪いなど、自分の体の内側の状態を感じ取る「内受容感覚(interoception)」に関係する領域です。
この結果から、研究チームは、ARFIDの子どもたちは脳の“感覚センサー”のような場所にちがいがある可能性を指摘しています。
実際、ARFIDの子どもたちの多くは「食べること自体がつらい」「味やにおい、食感が気持ち悪い」と感じており、それがこの脳の特徴と関係しているかもしれません。

また、研究チームは、EO-ANとARFIDのなかでも特に体重が低い子どもたちどうしを比べることで、「やせているから脳が変わっているのか?」「それとも病気の種類によって変わっているのか?」を検討しました。
その結果、同じくらい体重が少なくても、EO-ANの子どものほうが圧倒的に多くの脳の変化が見られたのです。
これは、「低体重がすべての原因ではない」ことを示しています。
さらに、EO-ANの子どもたちでは、「BMI(体格指数)が正常に近づくほど、皮質の厚さも戻る」ことが確認されました。
これは、栄養状態が脳の厚みにも影響を与えている証拠です。
一方、ARFIDでは、BMIと脳構造との間に明確な関連は見つかりませんでした。
つまり、ARFIDにおける脳の変化は、「やせているから」ではなく、より根本的な感覚処理の特性と関係していると考えられます。
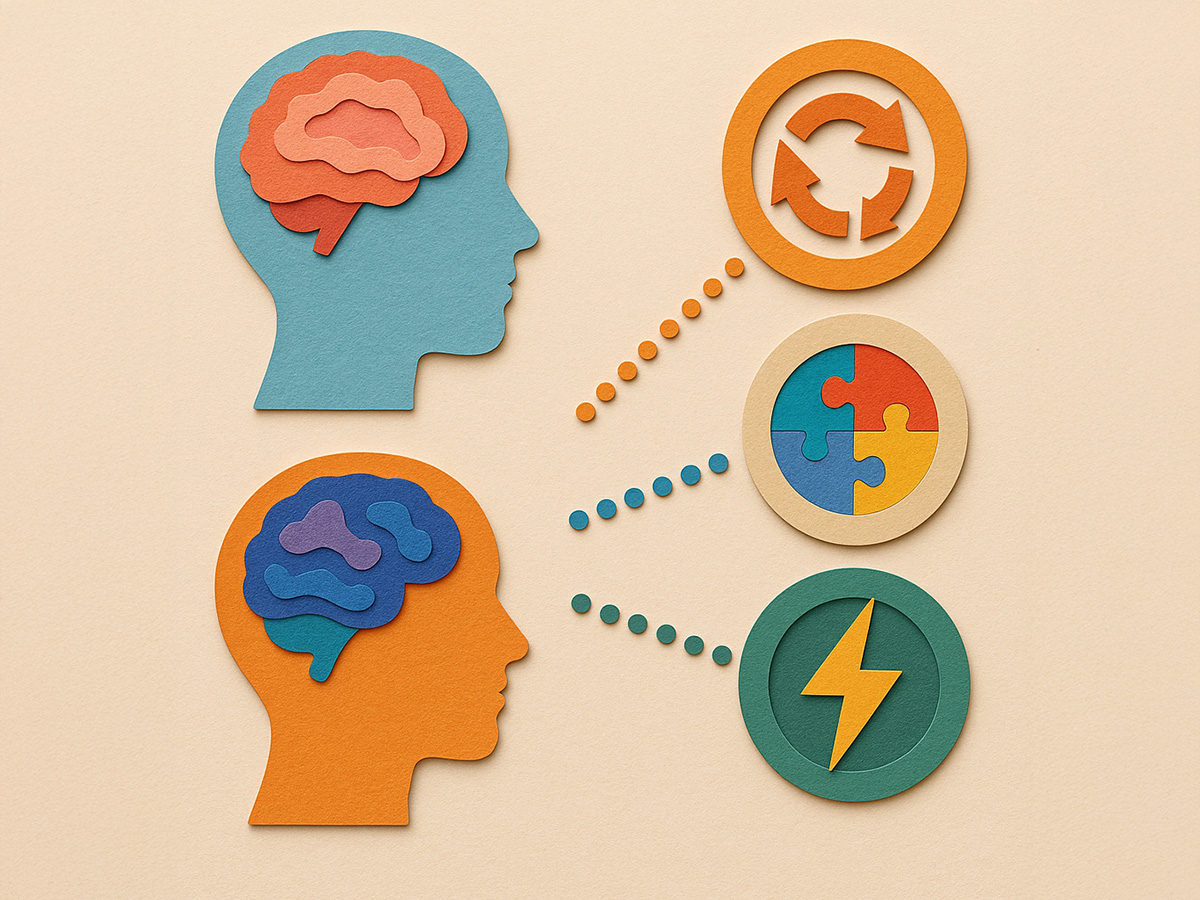
この研究のもうひとつの特徴は、「ARFIDやEO-ANの脳の特徴が、他の神経発達症とどのくらい似ているか?」を調べている点です。
比較対象となったのは次の3つ:
- ASD(自閉スペクトラム症)
- ADHD(注意欠如・多動症)
- OCD(強迫症)
これらの脳構造パターンは、ENIGMAという国際的な脳画像データベースから得られたものです。
結果は次のようになりました:
- EO-ANは、OCDと中程度の相関があった
- EO-ANは、ASDおよびADHDとは関連がなかった
- ARFIDは、ASDと弱いながら有意な相関があった
- ARFIDは、ADHDとは関連がなかった
つまり、EO-ANの脳は「強いこだわりや不安」に関係するOCDと近く、ARFIDの脳は「感覚や内側の感覚処理のちがい」に特徴があるASDと部分的に似ている、ということがわかりました。
ADHDについては、EO-ANともARFIDとも脳構造のパターンに共通性は見つかりませんでした。
このように、摂食障害の子どもたちの脳の変化は、「やせているかどうか」だけでは説明できないことが明らかになってきました。
EO-ANの子どもは、「やせたい」「太るのがこわい」といった強い思い込みが行動を支配し、脳にもその影響が現れている可能性があります。
一方、ARFIDの子どもは、「食べることそのもの」がつらい感覚体験になっており、脳の感覚処理や内側の感覚に関係する場所に変化が見られます。

この研究の意義は、こうした脳のちがいを明らかにすることで、それぞれの子どもに合った支援の必要性を伝えている点にあります。
たとえば、ASDと診断された子どもが食べ物に強いこだわりを示したとき、それはARFIDの一部かもしれません。
反対に、「食べない」ことで著しくやせていても、本人が「太るのがこわい」と言っているなら、それはEO-ANに近い状態かもしれません。
どちらの場合も、ただの偏食やわがままではなく、「脳の感じ方そのものがちがう」という理解が求められます。
食べることは、体と心の両方にかかわる深い営みです。
子どもが「食べられない」と感じるとき、そこには目に見えない理由があるかもしれません。
今回の研究は、そうした理由を「脳」という視点から見せてくれました。
「どうしてこの子は食べられないのか?」
その問いに、正面から向き合おうとする大人たちにとって、大きな手がかりとなる研究です。
(出典:Nature DOI: 10.1038/s44220-025-00447-x)(画像:たーとるうぃず)
摂食障害をかかえる自閉症の子どもは多くいます。
摂食障害の「脳」を見る研究からも、その関連が裏付けられたと言えるでしょう。
(チャーリー)





























