
この記事が含む Q&A
- 水泳によるADHD児の抑制機能の改善と脳ネットワークの変化を検証した?
- 8週間、ADHDの子ども20人が週3回30分の中強度水泳を実施し、フランカー課題と安静時fMRIで反応抑制と脳内ネットワークの変化を確認した。
- rIFGの内的ネットワーク強化と右下頭頂小葉との結合増加がみられた?
- 運動後、rIFGの内的結合とrIFG—右下頭頂小葉の結合が強まり、前頭葉ネットワークが抑制機能を支える基盤となった。
- この研究の意味と今後の課題は?
- 有酸素運動が抑制機能と脳ネットワークを変える可能性を示す一方、対象数が40人で短期間、長期効果や学校生活への影響は今後の研究課題です。
ADHDの子どもたちにとって、「止めたいのに止まらない」という体験は、日常の中で何度も訪れます。
授業中に思わず立ち上がってしまう。
宿題をしようと思っても、気がつくと他のことに夢中になっている。
そんな「抑制のむずかしさ」は、本人の努力不足ではなく、脳の働きの特徴によるものだとわかっています。
けれども、その脳の働きが「鍛えられる」かもしれないとしたらどうでしょうか。
今回、中国の南通大学附属・常州児童病院などの研究チームが発表した研究は、そんな希望を科学的に示しました。
「水泳によるADHD児の抑制機能の改善」です。しかもその効果を、脳の内部ネットワークの変化として確認したのです。
研究チームが行ったのは、とてもシンプルで現実的な試みでした。
6歳から10歳のADHDの子ども20人が、週3回、1回30分の中強度(最大心拍の60〜69%)で水泳を8週間続けました。
家庭でも実践できるプログラムで、心拍は保護者がフィットネストラッカーを使って見守ります。
特別な施設も必要なく、無理のない範囲で行える運動です。
比較対象として、同年齢の定型発達の子ども20人も協力しました。
全員が研究の倫理審査を経て、保護者の同意を得ています。
プログラムの前後で、2つのテストが行われました。
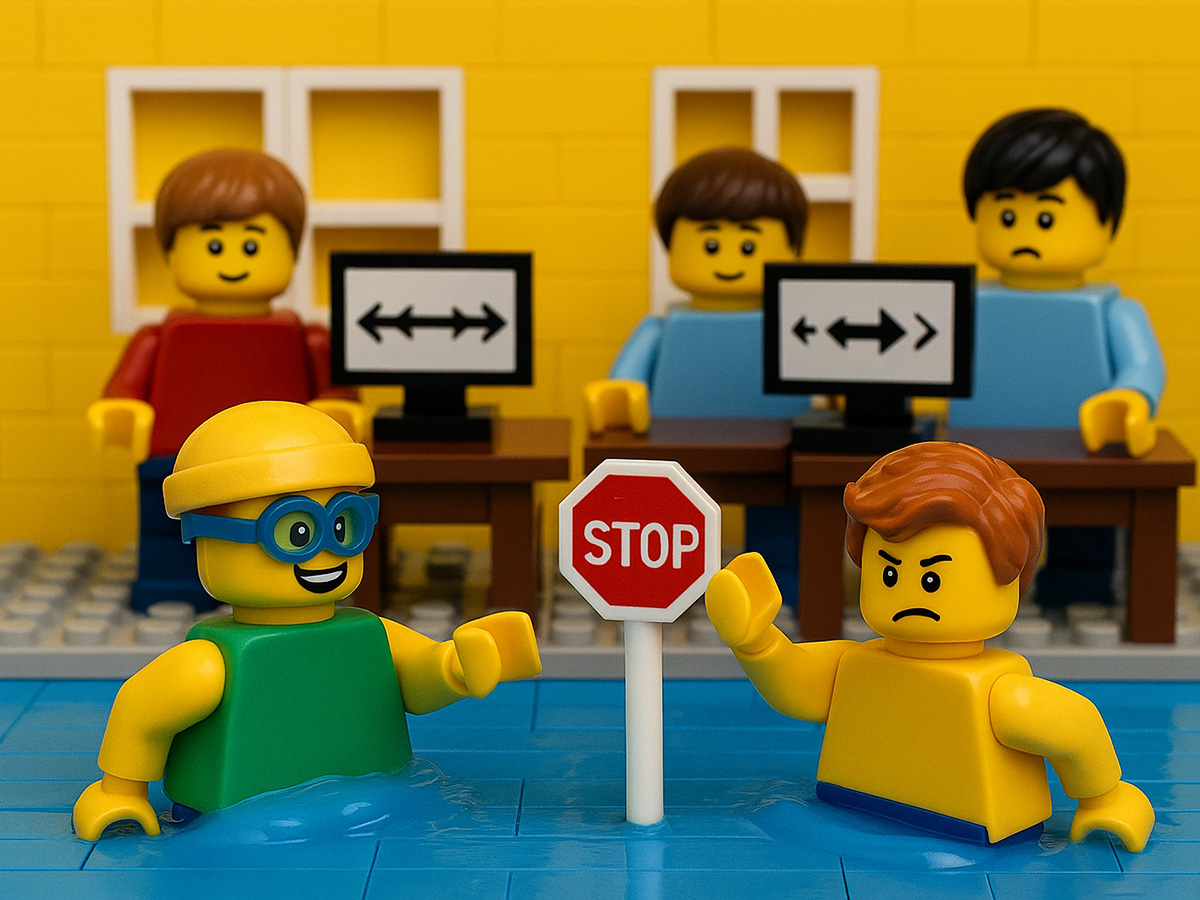
ひとつは「フランカー課題」と呼ばれる反応抑制テスト。
もうひとつは「安静時fMRI(機能的磁気共鳴画像)」による脳ネットワークの測定です。
フランカー課題とは、矢印が並んだ画面を見て、中央の矢印の向きを答えるというものです。
たとえば「← ← → ← ←」のように周囲の矢印が惑わせてくる中で、子どもは一瞬で中央だけを見て反応しなければなりません。
これは「注意を集中させ、不要な反応を止める力(インヒビション)」を測る代表的な課題です。
結果は明確でした。
8週間の水泳のあと、ADHDの子どもたちは反応が速く、正確になっていました。
反応時間は平均で21.29ミリ秒から14.57ミリ秒へと短縮し、正答率は0.868から0.924へと上がっていました。
単に慣れたというよりも、「迷わずに、正しく反応を止める」力が増していたのです。
この変化は脳の中でも確認されました。
研究チームが注目したのは「右下前頭回(rIFG)」という領域です。
rIFGは、私たちが「出かかった反応を止める」ときに中心的な役割を果たす場所で、ADHDの神経科学研究でもたびたび注目されてきました。
運動前と比べて、運動後のADHDの子どもでは、rIFGの中でのネットワーク(内的結合)が明らかに強まりました。
さらに、rIFGと右下頭頂小葉との結びつきも強くなっていました。
この2つの領域の協調は、注意の切り替えと反応の抑制を支える神経回路の要であり、まさに「行動を止める力」を脳レベルで支える基盤です。
さらに、rIFGと小脳後葉とのつながりは弱まっていました。
この変化は、「不要な補助的経路が減り、前頭葉ネットワークがより効率的に働くようになった」可能性を示すと研究者たちは解釈しています。
つまり、水泳によって「ブレーキをかける脳の配線」が整えられたのです。
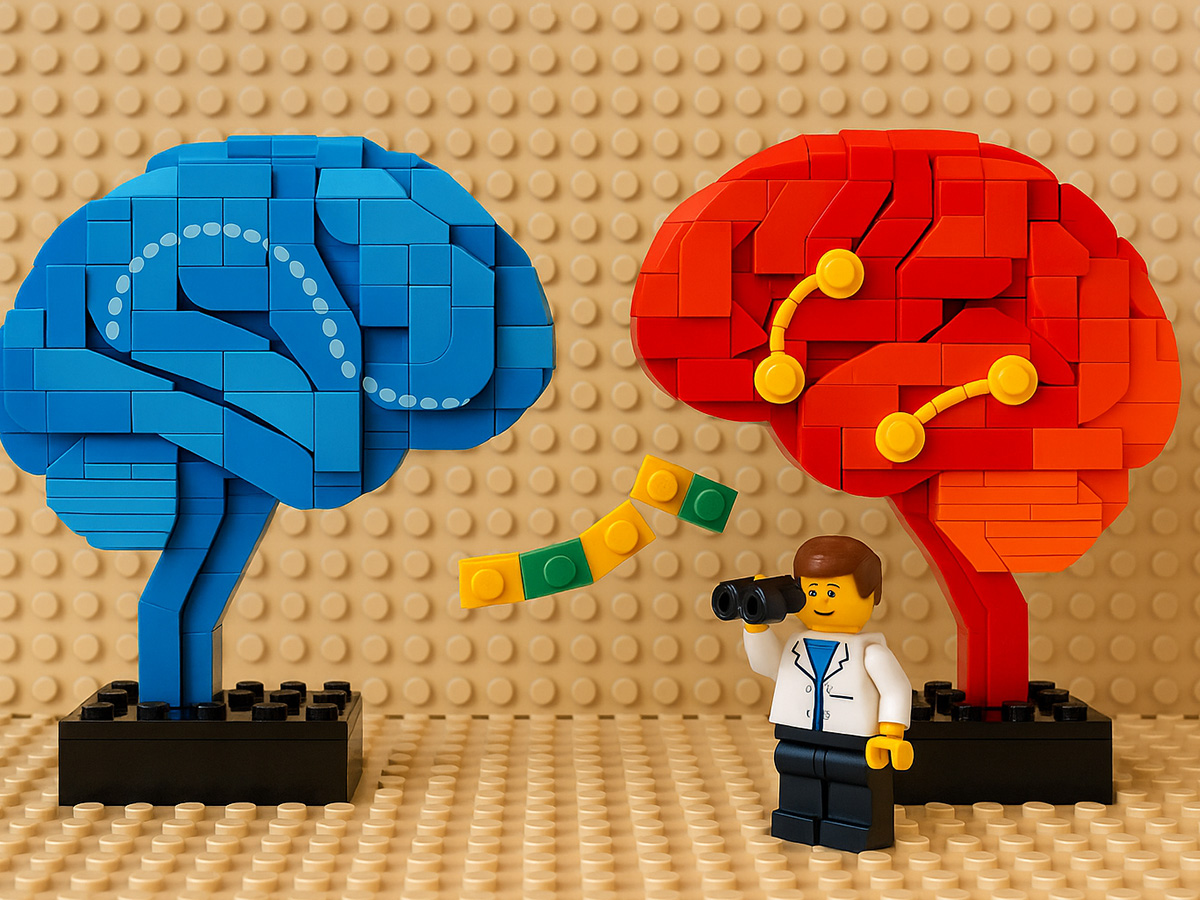
この変化が行動の改善と対応していることも確認されました。
rIFGの内的ネットワークが強いほど、反応時間は短く、正答率は高いという相関が見られました。
つまり、脳のネットワークの強化が、実際の「止められる力」に直結しているのです。
また、研究チームは3つの群――運動前のADHD、運動後のADHD、定型発達――を比較しました。
運動後のADHDは、運動前のADHDよりもrIFG内の結合が強く、rIFGと右下頭頂小葉の結合も増していました。
そして、このrIFG内の結合に関しては、運動後のADHDはもはや定型発達の子どもとほとんど差がありませんでした。
つまり、「水泳によって脳の活動が定型発達に近づいた」と言えるのです。
rIFGは「行動のブレーキ」、右下頭頂小葉は「注意の方向転換」、小脳は「運動の調整」を司ります。
これらの領域の連携の仕方が変わったことは、「考える」「感じる」「動く」がより統合された状態になったことを意味します。
脳の中で、不要な反応を抑えるためのネットワークが効率よく動くようになった――それがこの研究の最大の成果でした。
今回の水泳プログラムの工夫は、「実生活でも取り入れやすい」という点にあります。
30分の中強度運動を週3回というのは、学校の体育や家庭での運動習慣にも組み込みやすいレベルです。
保護者がスマートウォッチで見守りながら、子どもが楽しく泳ぐ。
その積み重ねが脳の働きを変える可能性があるのです。
この成果は、単に「体を動かすことがいい」という一般論にとどまりません。
運動によって「どの脳のネットワークがどう変わるか」という具体的な神経基盤を示した点で、ADHD支援の科学的な裏づけとして重要です。
しかも、それが薬や機械ではなく、遊びに近い「水泳」という自然な活動で得られるという点が大きな意味を持ちます。
一方で、研究チームは限界も正直に述べています。
参加者数が40人と少なく、8週間という短期間での変化を見ているため、長期的な効果や再現性については今後の研究が必要です。
また、今回は「認知課題」と「脳のネットワーク」に焦点を当てており、学校生活や家庭での実際の困りごとがどの程度改善されるかまでは検討していません。
この点は、次のステップとして臨床的な評価が求められます。
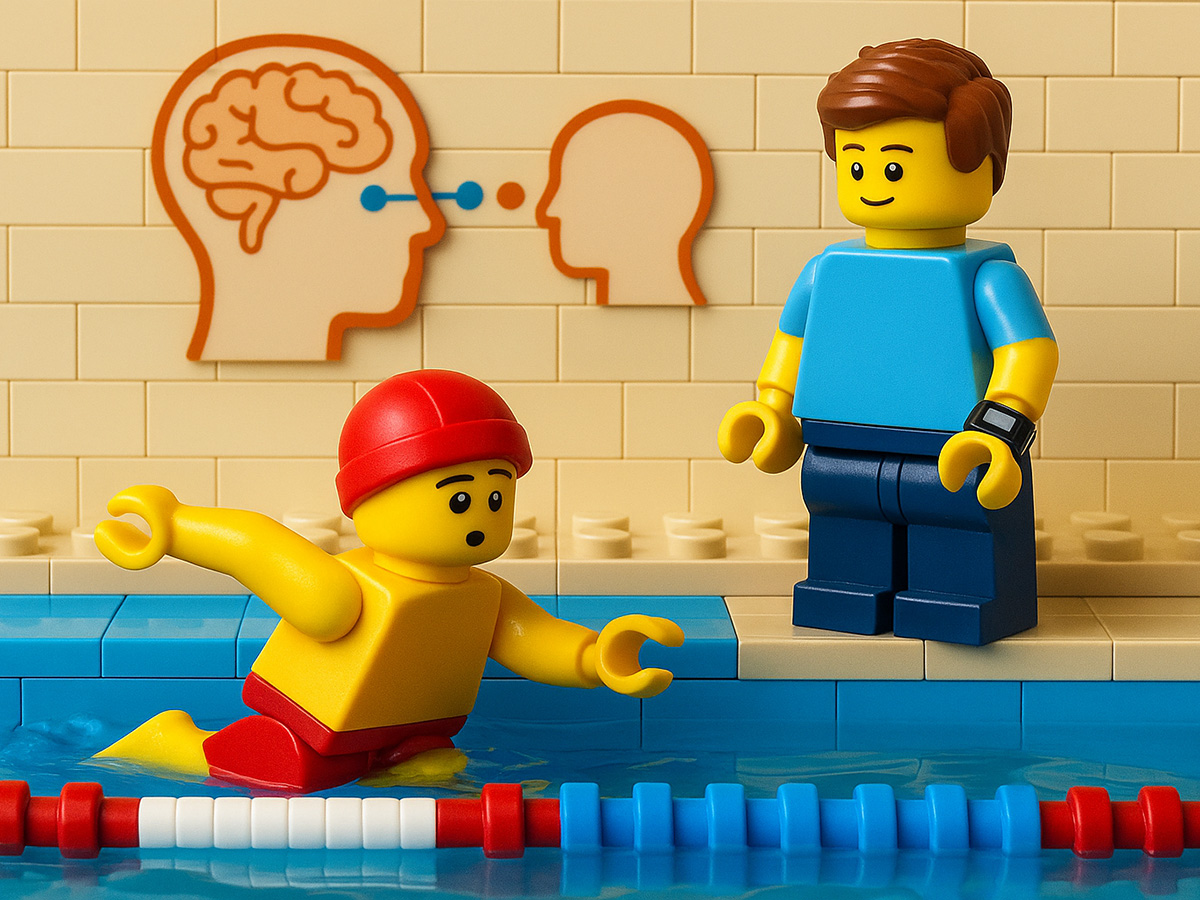
それでも、今回の研究が伝えるメッセージは明確です。
ADHDの子どもたちにおける「止める力(抑制力)」は、適度な運動によって確かに変えられる。
その変化は一時的な気分や集中の問題ではなく、脳の神経結合というレベルで確認できる。
これは、日常の支援や教育にとって非常に大きな希望です。
研究チームは論文の最後でこうまとめています。
「ADHD児における抑制機能の改善は、右下前頭回の内的ネットワークと、右下前頭回―右下頭頂小葉の機能的結合の変化と関連している」
つまり、脳の中の「抑制ネットワーク」が活性化し、その結果として行動のコントロール力が上がったということです。
ADHDの子どもたちは、日常の中で「やめようと思っても体が先に動いてしまう」場面を多く経験します。
それは、努力や意志の弱さではなく、抑制に関わる脳の回路が十分に働いていないためです。
今回の研究は、その回路を「遊びのような運動」で助けられることを示しました。
水泳という活動は、全身を使い、呼吸と動きをリズミカルに保つ運動です。
浮力によって体の感覚がやわらぎ、水の抵抗によって自然にペースが調整されます。
これらは、感覚刺激の調整や身体意識の安定にもつながると考えられます。
ADHDの子どもにとっては、安心して動ける環境でありながら、自然に「抑制の練習」を積み重ねられる場でもあります。
さらに、水泳のような有酸素運動は、ドーパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスを整えることが知られています。
これらは注意・動機づけ・感情調整を司る重要な物質で、ADHDの症状に関係しています。
脳のネットワークと化学的なバランスの両方から、運動が働きかけている可能性があるのです。
日常の中で実践できる支援とは何か。
この研究が提示する答えはとてもシンプルです。
「体を動かすことが、心を整える」
そして、「楽しく続けられる運動が、脳の働きを助ける」ということです。

子どもにとって、水の中は特別な空間です。
音がやわらぎ、体が軽くなり、自由に動ける。
その中で、自分のペースを感じながら体をコントロールする。
その体験の中に、脳を整える力が隠れているのかもしれません。
科学が明らかにしたのは、そんな当たり前のようでいて見過ごされがちな「体と心のつながり」です。
ADHDの支援を考えるとき、薬や特別なトレーニングだけでなく、こうした自然な活動が子どもを支えることを思い出すことが大切です。
水泳が難しい場合でも、同じ中強度の有酸素運動――たとえば自転車、なわとび、リズム運動など――でも、似た効果が期待できる可能性があります。
重要なのは、続けられること。そして、子どもが「楽しい」と感じることです。
体を動かす喜びが、少しずつ脳の中に「止める力」を育てていきます。
今回の研究は、その第一歩を科学的に証明しました。
子どもたちの脳が、水の中で静かに変わっていく。
それは「努力」ではなく、「楽しさ」が生んだ変化でした。
(出典:BMC Pediatrics DOI: 10.1186/s12887-025-06196-1)(画像:たーとるうぃず)
「重要なのは、続けられること。そして、子どもが「楽しい」と感じること」
ここが本当に重要な点です。
(チャーリー)





























