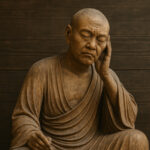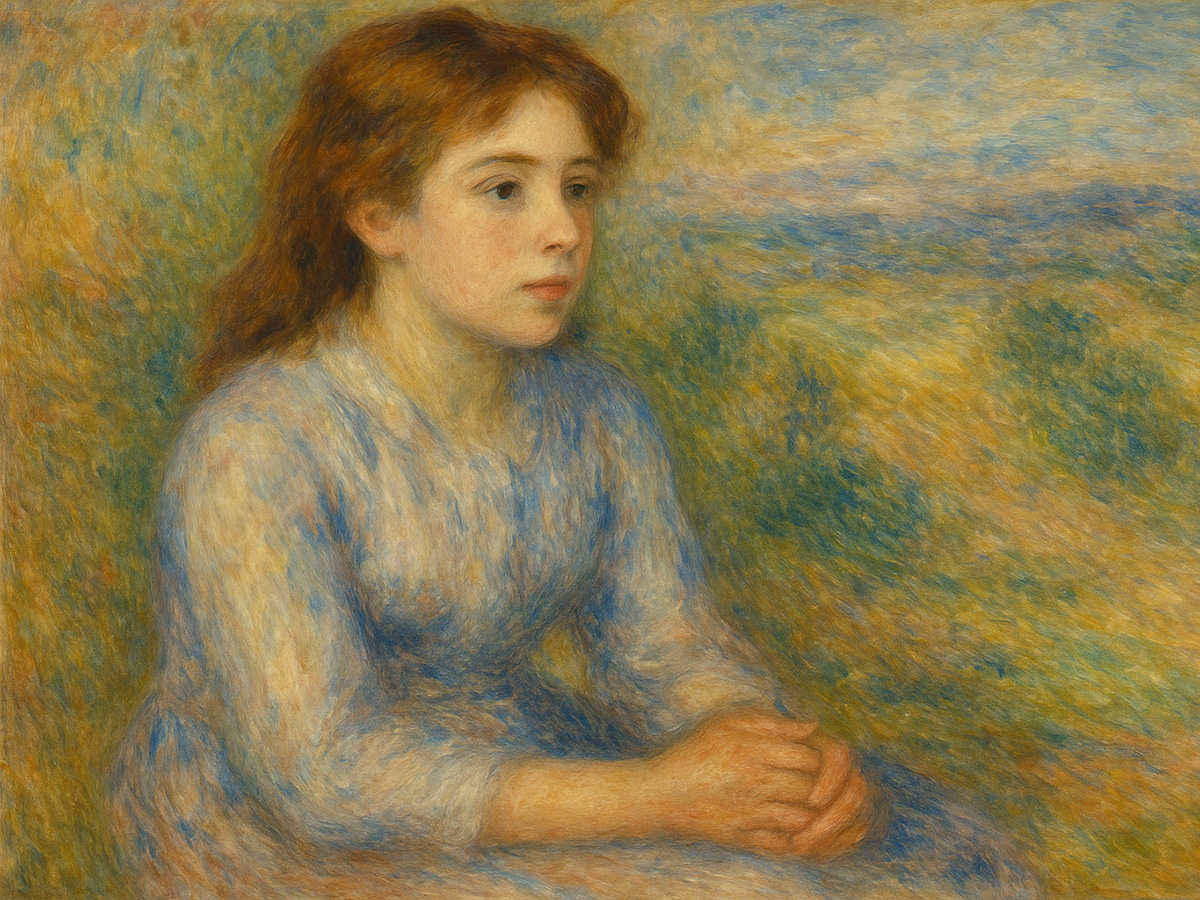
この記事が含む Q&A
- 自閉症の人は自分の人生の物語をどのように語る傾向があるのですか?
- つながりや因果関係の表現が弱く、淡々とした語り方をしやすい傾向があります。
- 自閉症の人の人生物語にはどのような特徴が見られますか?
- ネガティブな出来事を語ることが多く、締めくくりや展望が少ないことが特徴です。
- どのような支援が自閉症の人の自己理解や語り方の改善に役立ちますか?
- 出来事のつながりを一緒に振り返る練習や、ポジティブな出来事への意識付けが効果的と考えられます。
自分とは何か。人生とはどうつながっているのか。
私たちは日々の出来事を経験し、それを「自分の物語」として語ることで、自分らしさや人生の意味を見つけていきます。
しかし、自閉スペクトラム症(ASD)のある人にとっては、その「物語をつむぐ」ことが、実は大きな課題となることがあるのです。
フランスのリール大学とストラスブール大学の研究チームは、自閉症の成人が自分の人生をどのように語るのかを調べ、その特徴を明らかにしました。
これまでの研究では、自閉症の人が特定の出来事を思い出すときの特徴や、感情の表現の仕方については多くの知見がありましたが、「人生全体をどのように語るのか」という視点からの調査は、ほとんど行われていませんでした。
今回の研究では、22人の自閉症の成人と、22人の非自閉症の成人に、自分の「人生の物語」を語ってもらいました。
具体的には、これまでの人生で「とても大事だった7つの出来事」を選び、それらを含めて「自分はどのような人生を歩んできたのか」を20分ほどかけて語ってもらうというものです。
研究チームは、この語りを「どのくらい話がつながっているか」「出来事同士がどのように関係づけられているか」という観点から分析しました。
この語りのつながり具合を、専門的には「ナラティブ・コヒーレンス(語りのまとまり)」と呼びます。

その結果、自閉症の人の人生物語には、いくつかの特徴があることがわかりました。
まず、自閉症の人は、物語の「全体的なつながり」が弱い傾向が見られました。
とくに、「ある出来事が自分にどんな影響を与えたのか」「その結果、自分がどう変わったのか」といった「因果関係」を語る部分が少なかったのです。
これは、人生を一本の流れとして説明するのが難しい、ということを意味しています。
また、物語の始まりや終わり方にも違いが見られました。
非自閉症の人は、自分の人生物語を「誕生」から始めることが多く、語りの最後には「今までの経験をふり返ってまとめる」「これからどうなりたいか展望を語る」といった形で締めくくる傾向がありました。
しかし、自閉症の人は、物語を「自分がはっきり覚えている最初の記憶」から始めることが多く、終わり方も淡々としていて、ふり返りや展望が少ないことがわかりました。
一方で、物語を構成する「細かい部分」については、非自閉症の人と大きな差はありませんでした。
出来事をどのくらい詳しく語れるか、自分がその出来事でどれだけ主体的だったかといった点では、両者に違いはなかったのです。
興味深いことに、自閉症の人が選んだ「大事な出来事」は、全体的に「ネガティブ」なものが多いという特徴もありました。
悲しかったこと、つらかったこと、困難な体験が、自閉症の人にとっての「自分を語るうえで欠かせない出来事」として選ばれやすかったのです。
しかし、そうした出来事が「自分にどんな影響を与えたのか」については、あまり語られませんでした。
「その出来事が自分の性格や考え方をどう変えたのか」といった部分を言葉にするのが難しいという傾向が見られたのです。

では、なぜこのような違いが生まれるのでしょうか。
研究チームは、自閉症の人が持つ「認知スタイル」が関係していると考えています。
自閉症の人は、物事を細かく観察し、部分的な情報を重視する傾向があります。
これを「弱い中枢的統合」と呼びます。
細部には強いのですが、全体をまとめあげることが苦手なのです。
そのため、自分の人生を「一本の物語」として語ることが難しくなりがちです。
また、自閉症の人は「他人の視点を想像する」のが難しいと言われています。
人生物語を語るときには、「相手がどんな話を聞きたいか」「どんな順番で話すとわかりやすいか」を考えながら語る必要があります。
しかし、自閉症の人は、自分の中での思考や感覚に集中しやすく、他人に合わせた語り方をするのが難しいことがあります。
さらに、自閉症の人は「過去の出来事をふり返って、その意味を考える」「未来の自分を想像する」といった思考も、独特のスタイルを持っています。
これらは「エピソード記憶」や「自己認識」に関わるもので、自閉症の人が日常生活で感じている困難ともつながっています。
今回の研究では、語りのまとまりを支える「自己理解」や「自己評価」の低さも関係していることが示唆されました。
自閉症の人は、一般的にうつ症状や自己評価の低さを抱えやすいことが知られていますが、こうした心理的要因が、人生物語のネガティブさや因果関係の語りづらさに影響している可能性があります。
とはいえ、自閉症の人が「大事な出来事」をしっかりと選び、自分にとって意味のあるものとして認識していることも確認されました。
問題は、それをどう語るか、どうつなげていくかという「語り方」の部分にあります。
研究チームは、この結果をもとに、いくつかの支援の方向性を提案しています。
まず、自閉症の人が自分の人生を語るときに、「出来事同士のつながり」を一緒に考えるサポートが有効だと考えられます。
たとえば、「この出来事があったから、次にこうなった」「この経験が自分にどんな影響を与えたか」を振り返る練習をするのです。
また、自閉症の人が「ポジティブな出来事」にも目を向けるように促すことで、自己理解や自己肯定感を育む支援ができるとされています。

さらに、自分の物語を語ることは、対人関係のスキルアップにもつながります。
自閉症の人にとっては、「自分のことを適切に伝える」ことが大きな課題になることがありますが、人生物語を語る練習は、そのまま「相手にわかりやすく伝える力」を養うことにもなります。
今回の研究は、自閉症のある人が持つ「語り方の特徴」を明らかにしただけでなく、支援の新たなヒントを示しました。
自己理解を深め、他者との関係をよりよくするための「物語をつむぐ力」。
それを育てるための方法を考えることが、これからの課題となるでしょう。
この研究は、フランスのリール大学(Université de Lille)、ストラスブール大学(Université de Strasbourg)、そしてそれぞれに関連する研究機関である国立科学研究センター(CNRS)、国立保健医学研究所(INSERM)が共同で行いました。
研究の中心となったのは、メリッサ・アレ(MÉLISSA C. ALLÉ)氏をはじめとする研究チームです。
参加者は、フランス・コルマールにある自閉症支援センターや、ストラスブール大学病院の精神科で診断を受けた成人でした。
診断は、DSM-5という国際的な基準に基づいて行われ、知的障害のない自閉症の人たちが対象となりました。
この研究は、まだサンプル数が少ないため、今後はより多くの人を対象にした調査や、女性の自閉症の人にも焦点を当てた研究が求められています。
しかし、今回の結果は、自閉症のある人が「自分を語る」ことの難しさと、それに対する支援の方向性を考えるうえで、非常に重要な一歩となりました。
自分の人生を語るという行為は、自分自身を理解し、他者とつながるための大切な営みです。
その営みの中で、自閉症の人が感じている困難や特性を理解し、寄り添うこと。それが、これからの社会に求められる支援のあり方なのかもしれません。
(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-00178-0)(画像:たーとるうぃず)
これまでにない視点から、わかった特徴。
こんなことがあるのですね。たしかに想像できます。
よりよい理解、支援につながっていくことを願います。
(チャーリー)