
この記事が含む Q&A
- 発達障害のセルフチェックは自己理解のきっかけになりますか?
- はい、自己の行動や感覚を振り返る手助けとなります。
- セルフ診断だけで発達障害と確定できますか?
- いいえ、専門家による詳細な評価と診断が必要です。
- 長期間困りごとが続く場合、どうしたらよいですか?
- 専門家や支援者に相談し、適切な支援や環境調整を検討してください。
「わたしって発達障害なのかな?」と不安になることはありませんか。
インターネットで「発達障害 セルフチェック」「ADHD 診断」と検索すると、忘れ物が多い、片付けが苦手、人の話を最後まで聞けない、マルチタスクが苦手、音や光に敏感――そんな項目がずらりと並んでいます。
それらに「当てはまる」「当てはまりすぎて怖い」と感じる人も多いでしょう。
けれど、その不安の裏にはバーナム効果という心の働きが関係しています。
バーナム効果とは、誰にでも当てはまりそうな曖昧で一般的な記述を「自分にだけ当てはまる」と思い込む心理現象のことです。
たとえば血液型性格診断では、「A型は几帳面だけど頑固」「B型は自由だけどマイペース」「O型はおおらかだけど大雑把」「AB型は個性的だけど二面性がある」といった説明を誰もが一度は目にしたことがあるでしょう。
よく読むと多くの人に当てはまる内容なのに、「これはわたしそのものだ」と感じてしまいます。
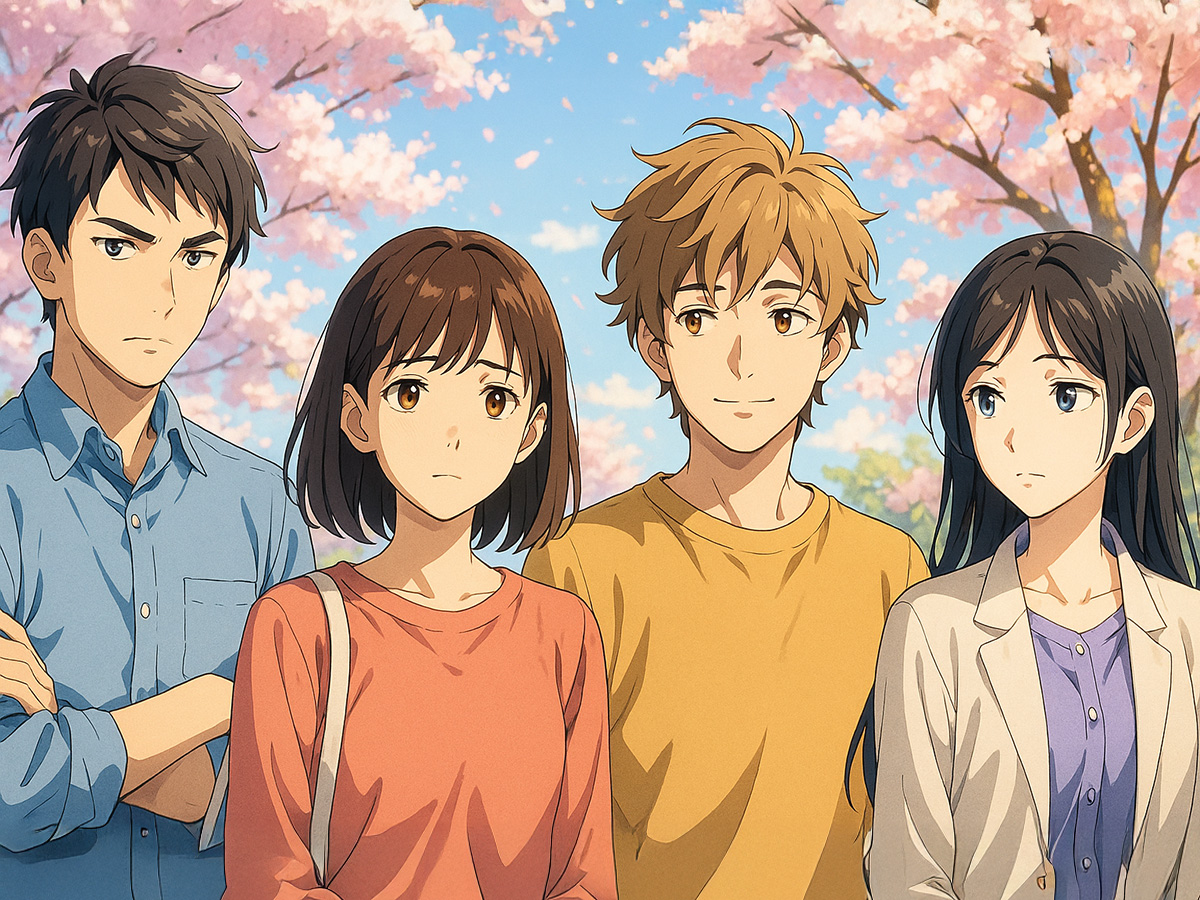
発達障害の自己診断チェックリストにも、同じことが起こります。
セルフチェックの項目には、「うっかりミスが多い」「忘れ物をする」「空気が読めない」といった、一度は誰もが経験したことのある困りごとが多く含まれています。
それでも、自分に当てはまる項目が目立つと、「やっぱり私は発達障害かもしれない」と強く思ってしまいがちです。
最近の研究でもSNSを舞台にした自己ラベリングの実態が明らかになっています。
2025年に『Autism Research』誌に発表された研究【1】では、RedditなどのSNS上で「診断を受けていないが、自閉症やADHDだと感じている」と自己表明する投稿が多く見られることが示されました。
しかし、その投稿の多くは正式な診断を経ていない「感覚的な自己認識」に基づいており、バーナム効果の影響を受けている可能性が指摘されています【1】。
また、2025年3月に『Frontiers in Psychology』で報告された系統的レビューでは、セルフチェックはあくまで「自己理解を深めるきっかけ」に過ぎず、正式な診断には医師や臨床心理士など専門家による詳細な問診や心理検査、必要に応じて複数回の面談が必要であると結論づけられています【2】。
セルフチェックの結果だけで「私は確かにADHDだ」と決めつけることはできず、専門的評価によって生活上の困りごとがどの程度持続し、複数の場面で支障を来しているかが重視されます。

実際に2025年5月の『JAMA Psychiatry』レビュー【3】では、成人ADHDの評価を受けた人々のうち、自己診断時に想定していた困難領域と、専門家による診断後に明らかになった主要な困りごとが異なるケースが多いと報告されています。
ある人はセルフチェックで「集中力の欠如」が主な問題と感じていたものの、診断後には「対人関係のストレスの深刻さ」が大きな困難として浮上した例もありました【3】。
このように、自己診断と正式診断の間にはギャップが存在します。
では、セルフチェック自体は無意味なのでしょうか。
決してそうではありません。
セルフチェックは、自分の行動や感覚を振り返る大切なきっかけになります。
「なぜ私は忘れ物が多いのか」「どうして会話が続かないと感じるのか」を自問することで、自分の得意・不得意を自覚し、対処法を考える第一歩が踏み出せます。
ただし、チェック項目に当てはまったからといって即「発達障害だ」と決めつけるのではなく、「どのような場面で困っているのか」「困りごとの程度はどれくらいか」を冷静に見極めることが重要です。

日常生活や職場・学校での支障が複数の場面に継続して起きている場合や、精神的・身体的な負担が大きい場合には、専門機関への相談を検討してください。
実際、『Frontiers in Psychology』のレビューでは、専門家による診断とサポートによって自己理解が深まり、学校や職場での合理的配慮が得られることで、当事者の生活の質が大きく向上する事例が多数報告されています【2】。
また、『Molecular Autism』の研究でも、診断後の支援プログラムや環境調整が本人の幸福感や適応感を高める効果が示されています【1】。
バーナム効果を知ることは、「当てはまっている気がする」という曖昧な思い込みに振り回されず、本当に必要な支援を見極める判断力を養うことにつながります。
血液型診断や星座占いを「自分の性格を知る楽しみ」として気軽に受け止めるように、セルフチェックも「自分を振り返るツール」として活用しましょう。

そしてもし、日常生活での困りごとが長期間続き、つらさを感じることがあれば、一人で抱え込まずに家族や友人、支援者、専門家に話をしてみてください。
「気づくこと」「知ること」「助けを求めること」――これらは、自分らしく生きるために欠かせないステップです。
(チャーリー)
(画像:たーとるうぃず)
(出典:
【1】
Autism Spectrum Disorders Discourse on Social Media Platforms: A Topic Modeling Study of Reddit Posts. Autism Research. 2025年6月5日公開.
DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aur.70066
【2】
Evaluating Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD): A Systematic Review of DSM-5 Diagnostic Criteria and Considerations for Adult Assessment. Frontiers in Psychology. 2025年3月公開.
DOI: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2025.1466088/full
【3】 Thompson L., Ramirez M., Chen Y. ほか.
Increased Prescribing of ADHD Medication and Real-World Outcomes Over Time. JAMA Psychiatry. 2025年5月公開.
DOI: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2835661
)




























