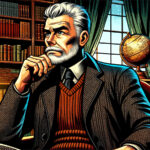この記事が含む Q&A
- 不器用さ(DCD)とは何ですか?
- 発達性協調運動障害と呼ばれ、運動や手先の作業が苦手で、必ずしも診断を受けていなくても自覚や日常生活への影響がある状態です。
- 研究の結論は何を示していますか?
- 不器用さは心の健康に直接影響するのではなく、ADHDや自閉症の困りごとを強めることで間接的に影響する可能性があると考えられています。
- 学校ではどう支援できると提案されていますか?
- ADHDや自閉症の困りごとを自己申告した学生に絞って不器用さを検査するターゲット型の方法や、試験時間の延長・ノートテイカー・パソコン利用などの支援が現実的とされています。
大阪大学の研究チームが、新入生を中心とする大学生を対象に「不器用さ」と心の健康との関わりを調べた研究を発表しました。
この「不器用さ」とは、医学的には「発達性協調運動障害(DCD)」と呼ばれることがある状態です。
小さい頃から体の動きがぎこちなく、運動や手先の作業が苦手である特徴を指します。
必ずしも診断を受けているわけではなくても、「自分は不器用だ」と感じることが日常生活に影響している人がいます。
この研究の大きなポイントは、不器用さとADHDや自閉症に関する困りごと、そして心の健康との間に、どのような関係があるのかを明らかにしようとしたことです。
ADHDは注意がそれやすい、落ち着きにくい、計画を立てて行動するのが難しいといった特徴を持つ発達特性です。
自閉症は、人との関わり方や感覚の受け取り方に特徴があり、周囲とのずれから生きづらさが生まれることがあります。
いずれも大学生活に大きな影響を与える可能性がある特性です。
大阪大学では毎年、学生に健康調査を行っています。
研究チームはその調査の後に、オンラインで任意参加のアンケートを案内しました。
1万6000人以上の学部生・大学院生に案内が届き、584人が回答しました。そのうち不完全な回答や条件に合わないものを除き、最終的に527人が分析の対象となりました。
調査には、不器用さの程度を測る質問票のほか、ADHDや自閉症に関する簡単な質問、さらに気分の落ち込みや不安など心の状態をたずねる項目も含まれていました

結果をみると、不器用さの傾向が強い学生は全体の7%程度にのぼりました。
この学生たちは、ADHDや自閉症に関連する困りごとを強く感じている割合が高く、心の健康にも悩みを抱えているケースが多いことが分かりました。
具体的には、「集中が続かない」「気分が落ち込みやすい」といった回答が、不器用さの高い学生に目立ったのです。
研究チームは、この結果をもとに、不器用さが心の健康に直接影響しているのではなく、ADHDや自閉症の困りごとを強めることで間接的に影響しているのではないかと考えています。
不器用さがあると授業の準備やレポート作成などで時間がかかり、集中力を保つのが難しくなります。
そのために学業の負担が増し、心の健康に影響が出るという流れです。
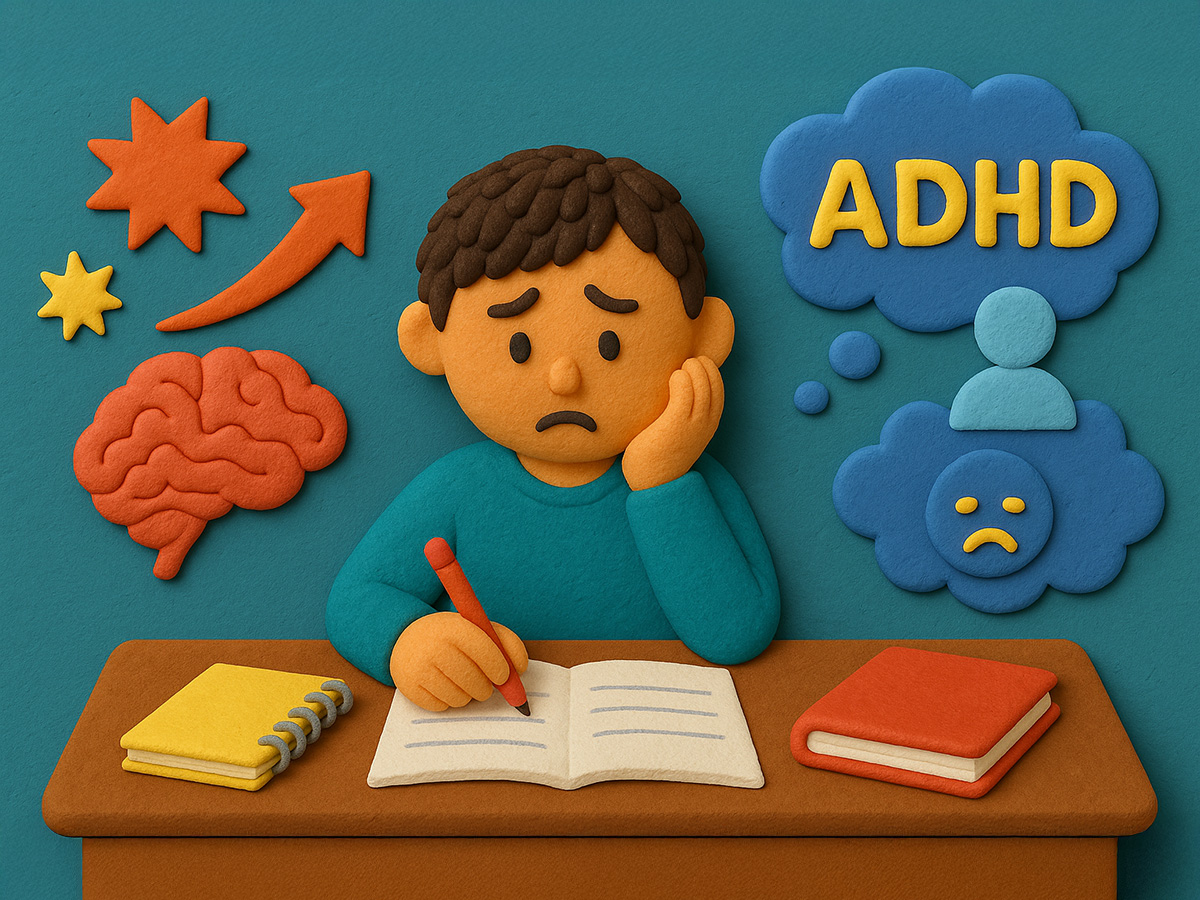
研究者たちは、大学生活の入り口で「すべての学生に一律で不器用さの検査をする」のではなく、「ADHDや自閉症の困りごとを自己申告した学生」に絞って不器用さのチェックを行う方法が現実的だと提案しました。
この「ターゲット型」の方法なら、支援が必要な学生を効率的に見つけ出し、試験時間の延長や学習支援などにつなげることができるからです。
この研究にはいくつかの制約もあります。
調査対象は大阪大学の学生に限られており、回答率は決して高くありません。
また、不器用さの質問票は海外で作られた基準をそのまま使っているため、日本の学生にそのまま当てはまるかどうかは慎重に考える必要があります。
さらに調査は横断的、つまりある一時点だけのデータに基づいているので、因果関係を断定することはできません。
それでもこの研究の意義は大きいといえます。
不器用さを「ただの運動のぎこちなさ」と片づけず、ADHDや自閉症の特徴や心の健康と重なり合うものとして理解しようとした点に新しさがあります。
当事者や保護者にとっても、学業の困難や気分の落ち込みの背景に不器用さが関わっているかもしれない、という視点を与えてくれます。

大阪大学の研究チームは今後、多くの大学で同様の調査を行い、より幅広い学生の実態を明らかにすることを目指しています。
また、不器用さをもつ学生がどのような場面でつまずきやすいのかを、聞き取り調査などを通して明らかにし、具体的な支援策につなげたいとしています。
支援の一例としては、試験時間の延長やノートテイカー(授業内容を文字にして支援する人)の配置、パソコンの利用などが海外では導入されています。
日本でもこうした支援が広がれば、不器用さを抱える学生が安心して学べる環境につながる可能性があります。
今回の成果は、学生の多様な特性を理解し、学びやすい環境を整えることが心の健康にも結びつくことをデータで示したものです。
大阪大学の研究チームは、この知見をもとに今後も支援のあり方を探っていく姿勢を示しています。
(出典:brain sciences DOI: 10.3390/brainsci15080895)(画像:たーとるうぃず)
運動が極端に苦手で、体育が大嫌い。
そんな人にとっては、本当に深刻な問題になっていることです。
DCDについて、正しく、広く、理解されてほしいと思います。
とくに学校の先生、とりわけ体育の先生には。
(チャーリー)