
この記事が含む Q&A
- スクリーンを長く見ると発達にはどう影響する可能性があるのですか?
- 研究は一概には結論づけず、長時間がADHDリスクを下げる可能性がある一方で知能の発達には不利になる可能性が示唆されています。
- なぜこの研究でADHDと知能の影響が両立して見えるのですか?
- 「スクリーンの使い方や体質の解釈」を含む視点が加えられており、受け身の長時間視聴をそのまま因果とするデータではないからです。
- 家庭でスクリーンとの付き合い方をどう工夫すれば良いですか?
- 視聴時間だけでなく「どこが楽しかった?どう工夫できそう?」と話し合い、学校では受け身だけでなく自分で考え作る活動を取り入れるのが有効と提案されています。
子どもがふだん、どのくらいスクリーンを見ているか。
これは多くの家庭にとって気になるテーマです。
とくにADHDや自閉症、知的障害などの発達にかかわる子どもを育てる親や、支援をしている人にとっては、とても大切なことです。
「長く見せると集中力が乱れるのでは?」「社会性の発達に影響があるのでは?」と心配する声もあれば、「画面を見ていると落ち着く」「楽しみが見つかる」といったプラスの体験を語る声もあります。
でも実際にスクリーンを見ることが発達にどう関係しているのかは、はっきりしていませんでした。
今回、中国の研究チーム(杭州臨平婦幼保健医院、浙江大学医学院付属児童病院、蘭州大学 公衆衛生学院)が行った大規模な調査は、この疑問に新しい光を当てています。
研究で調べたのは「レジャー・スクリーンタイム」、つまり楽しみとして画面を見る時間と、発達にかかわる六つの状態との関係です。
対象になったのは、ADHD(注意欠如・多動症)、自閉症、知的障害、学習障害、言語の障害、トゥレット症です。
使われたデータはヨーロッパ系の約70万人分。そのうち25万6千人分のデータがスクリーンタイムに関する解析に使われました。

ここでポイントになるのが「メンデル無作為化」という方法です。
これは、生まれたときに偶然決まる「遺伝的なちがい」を手がかりにして、ある習慣や行動が結果にどうつながるのかを調べるやり方です。
たとえば「スクリーンを長く見やすい体質」と関係する遺伝のちがいを持つ人と、そうでない人を比べて、ADHDなどの状態がどれくらい出やすいかを調べるのです。
さらに研究チームは、「ADHDなどの状態になりやすい体質の人が、結果としてスクリーン時間を長くしているのではないか」という逆の可能性も調べました。
この逆方向の検証では、六つすべての状態について強い証拠は見つかりませんでした。
つまり「特性があるからスクリーン時間が長くなる」というよりも、「スクリーンを長く見やすい体質が発達や行動に影響する」と考えたほうが自然だという結論です。
その結果、大きく二つのことがわかりました。
ひとつは、スクリーンを長く見やすい体質の人ほど、ADHDのリスクが下がる傾向があったことです。
数値にすると、スクリーン時間が1単位増えるごとに、ADHDの可能性はおよそ0.68倍に下がるという結果でした。
もうひとつは、知能の発達に不利な傾向が見えたことです。
知的障害そのものの遺伝データが十分でなかったため、「子どもの知能」に関するデータを代わりに使ったのですが、スクリーンを長く見やすい体質の人は、知能の発達に不利になる可能性があるという結果が出ました。リスクは1.66倍に高まっていました。

つまり、「スクリーンを長く見やすい体質の人はADHDのリスクは下がるが、知能の発達にはマイナスがあるかもしれない」という両面が示されたのです。
一方で、自閉症、学習障害、言語の障害、トゥレット症については、はっきりした関連は見つかりませんでした。
これは「スクリーンタイムがすべての発達障害に影響するわけではない」ということを示しています。
ここまでが、研究から直接得られた結果です。
ただし論文には「なぜこんな違いが出たのか」を理解するための研究チームの解釈も書かれています。
ADHDのリスクが下がった理由については、「スクリーンを使った活動の中には、工夫や挑戦を伴うものがあり、それが集中や達成感につながるかもしれない」と研究チームは考えています。
一方で、知能の発達に不利な結果が出た理由については、「ただ受け身に長時間スクリーンを見続けることが、学びや体験の機会を減らしてしまうのではないか」と説明しています。
ここで大切なのは、これらは研究チームが結果を理解するために加えた視点であって、研究データそのものから直接導かれた事実ではないということです。
つまり「結果」と「解釈」は分けて理解する必要があります。
もちろん、この研究にも限界があります。
参加者はヨーロッパ系の人に偏っていること、知的障害の代わりに「子どもの知能」を使っていること、スクリーンの内容(ゲーム、動画、SNSなど)を区別していないことなどです。
それでも、逆方向の検証を含めて大きな矛盾がなかったことから、この結果は「方向性の手がかり」として重要な意味を持つと考えられます。
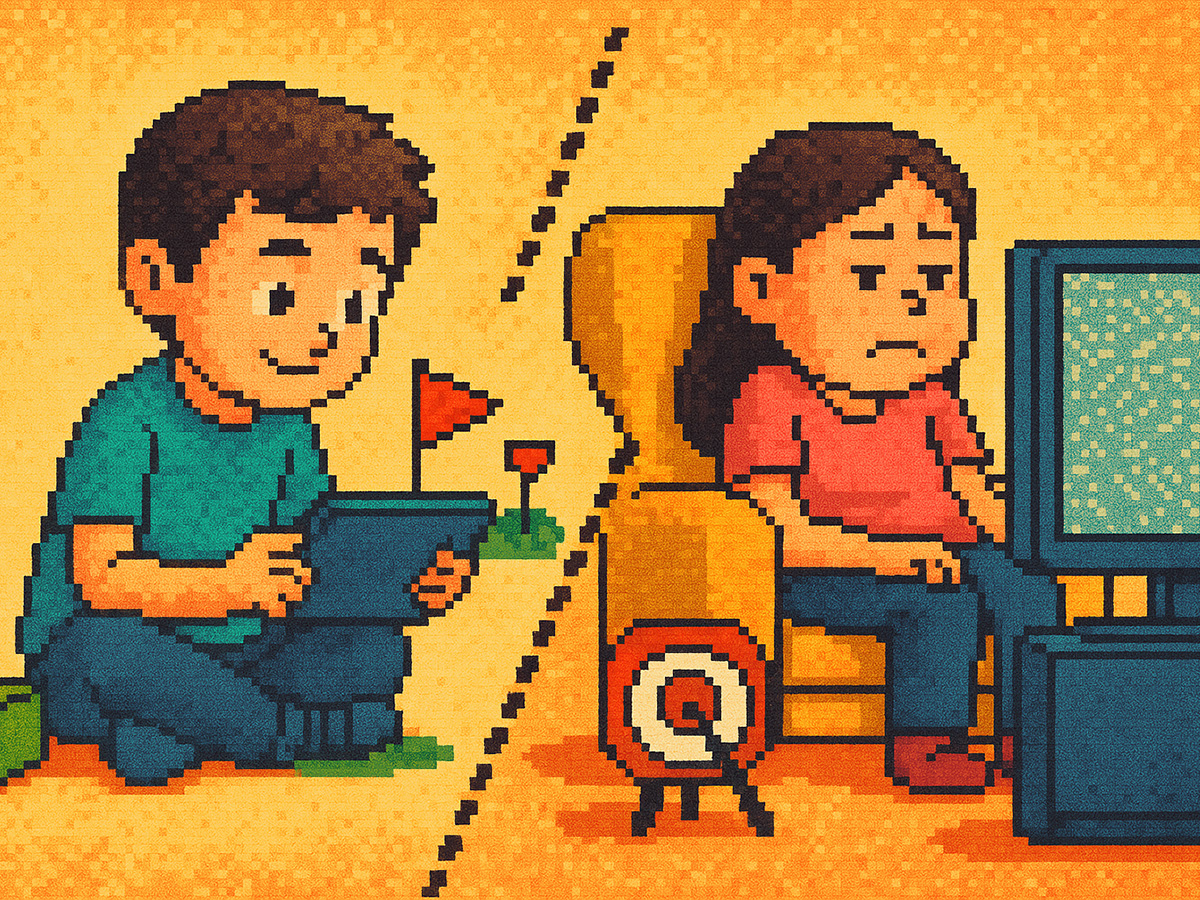
今回の研究が伝えるのは、「スクリーンは一律に良い悪いと決められるものではない」ということです。
ADHDのリスクを下げるように働く可能性もあれば、知能の発達に不利に働く可能性もある。
大切なのは「どのように、どれくらい使うか」という点です。
家庭では、ただ見せるだけでなく「どこが楽しかった?」「どう工夫できそう?」と話し合ってみる。
学校では、受け身に情報を受け取るだけでなく、自分で考えたり作ったりする活動を取り入れる。
そうした小さな工夫で、スクリーンとのつき合い方は大きく変わります。
この研究は「スクリーンを長く見やすい体質とADHDや知能との関係」に注目し、ADHDのリスクが下がる一方で、知能の発達には不利な影響があるかもしれない、という結果を示しました。
自閉症やその他の発達障害とは関係は見られませんでした。
スクリーンは敵にも味方にもなりえます。
その可能性を理解し、子どもの特性や家庭のリズムに合わせて、賢くつき合っていくことが、子どもと家族の安心と成長につながっていくのです。
(出典:Brain and Behavior DOI: 10.1002/brb3.70884)(画像:たーとるうぃず)
この研究の結論は
・スクリーンを長く見る体質の人はADHD(状態)の人が少ない
であり、スクリーンを長く見る「行動」がADHDのリスクを減らす、とは言っていません。
ここは注意です。
ですが、研究チームの考察、
「「スクリーンは一律に良い悪いと決められるものではない」ということです。
ADHDのリスクを下げるように働く可能性もあれば、知能の発達に不利に働く可能性もある。
大切なのは「どのように、どれくらい使うか」という点です。」
はまったく同感です。
(チャーリー)





























