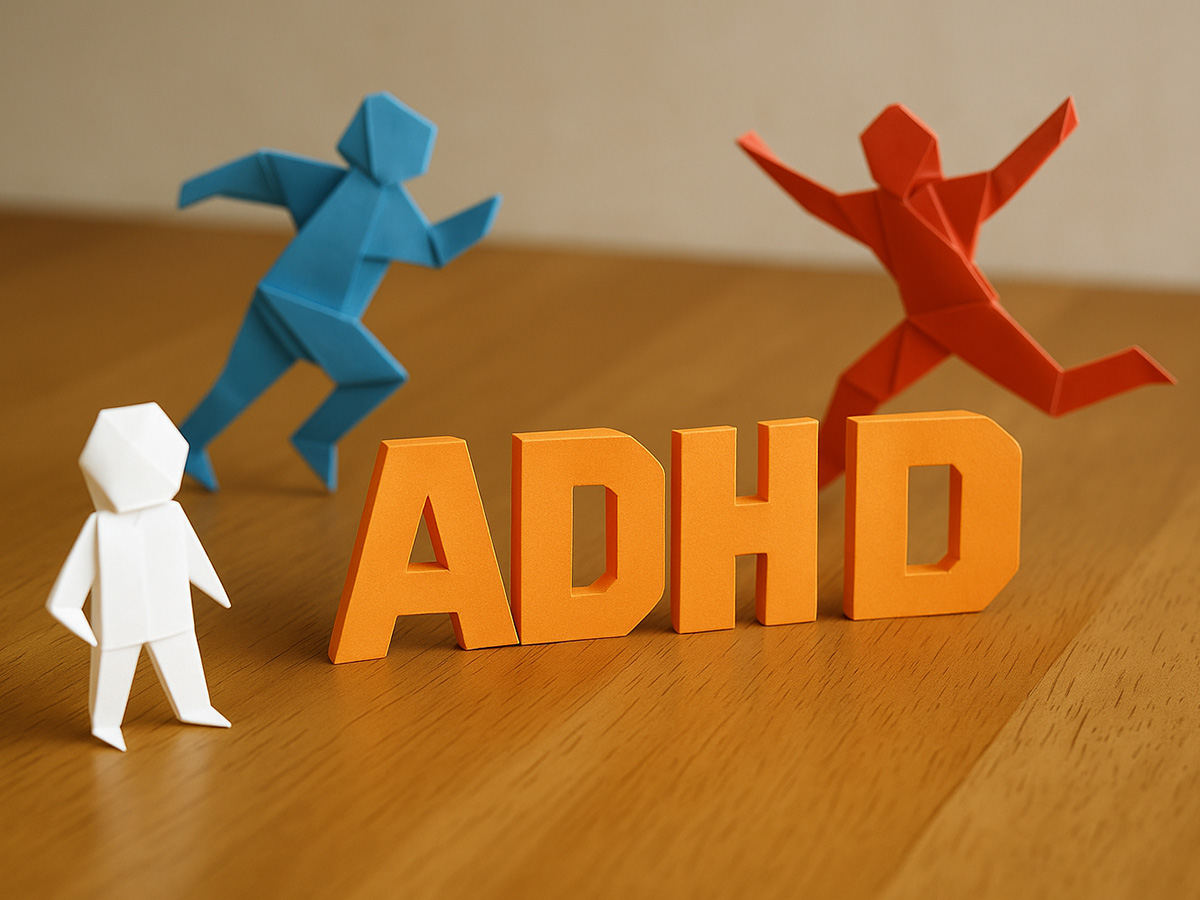
この記事が含む Q&A
- ADHDの診断率は本当に増加しているのでしょうか?
- 公式データでは大きな増加は見られず、認知や診断基準の変化が背景と考えられます。
- 社会のADHDに対する理解が深まることは良いことですか?
- はい、適切な支援や理解に繋がるため、社会全体の共感と支援の促進に役立ちます。
- 社会の変化がADHDの患者数にどのように影響していますか?
- 診断基準や認識の変化により、以前は見逃されていたケースも支援対象になっています。
ADHD(注意欠如・多動症)は、近年、世界中で大きな注目を集めている特徴のひとつです。
子どもだけでなく大人でもADHDと診断される人が増えているという声があり、SNSやニュースでも「診断が急増」「薬が不足」「支援の順番待ちが長い」といった話題が目立ちます。
しかし、実際にADHDの人が急激に増えているのか、それとも社会の見方や仕組みが変わったことで表に出てきただけなのか、多くの人が疑問を感じています。
ここ数年で、ADHDの診断や支援を求める人の数は著しく増えました。
たとえばイギリスでは、ADHDの相談や評価を待つ人のうち、4人に1人が1年以上待っているという状況があります。
10人に1人は2年以上も順番待ちをしているケースもあります。
欧米では治療薬の処方数も過去最高に達し、薬そのものが不足しがちになっています。
こうした背景には、社会のADHDに対する理解の広がりや、受診のハードルが下がったことが関係していると考えられています。
イギリスのキングス・カレッジ・ロンドン(King’s College London)にある精神医学・心理学・神経科学研究所(Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, IoPPN)の研究者たちは、ADHDの診断や支援を求める人の増加と、その背景にある実態をより詳しく明らかにするため、世界各国の最新データを徹底的に分析しました。
ADHDの診断にはDSM-5やICD-11という国際的な診断基準が使われます。
これらの基準は、子どものころから複数の場面で特徴的な症状が続いているかどうかを重視しています。
診断基準は年々見直されていて、たとえばDSM-5では思春期や大人の診断がしやすいように、必要な症状の数が減らされたり、症状の出現年齢の上限が12歳まで引き上げられたりしました。
このような基準の変化によって、これまで見逃されていた人も診断されやすくなっています。
世界中の子どもにおけるADHDの割合は、だいたい5~7%前後とされてきました。
思春期や大人では3~4%前後と推定されています。
これらの数字は、診断方法や調査の仕方によって大きく異なる場合があります。
とくに近年は、社会の認識や支援の在り方が変化し、「以前なら診断されなかったような人」も支援につながるようになりました。
2020年以降、ADHDの有病率や発症率に関するデータを世界各地で集めて比較した結果、最も信頼性が高いとされる北米やスウェーデンの医療記録によるデータでは、アメリカの子どもで約9.6~10.5%、カナダの1~24歳で7.5%、スウェーデンの0~17歳で3.2%という数字が出ています。
大人では、スウェーデンの調査で1.4%という結果が得られています。
こうした数字は、ここ十数年で大きな変動があったとは言いがたい範囲に収まっています。
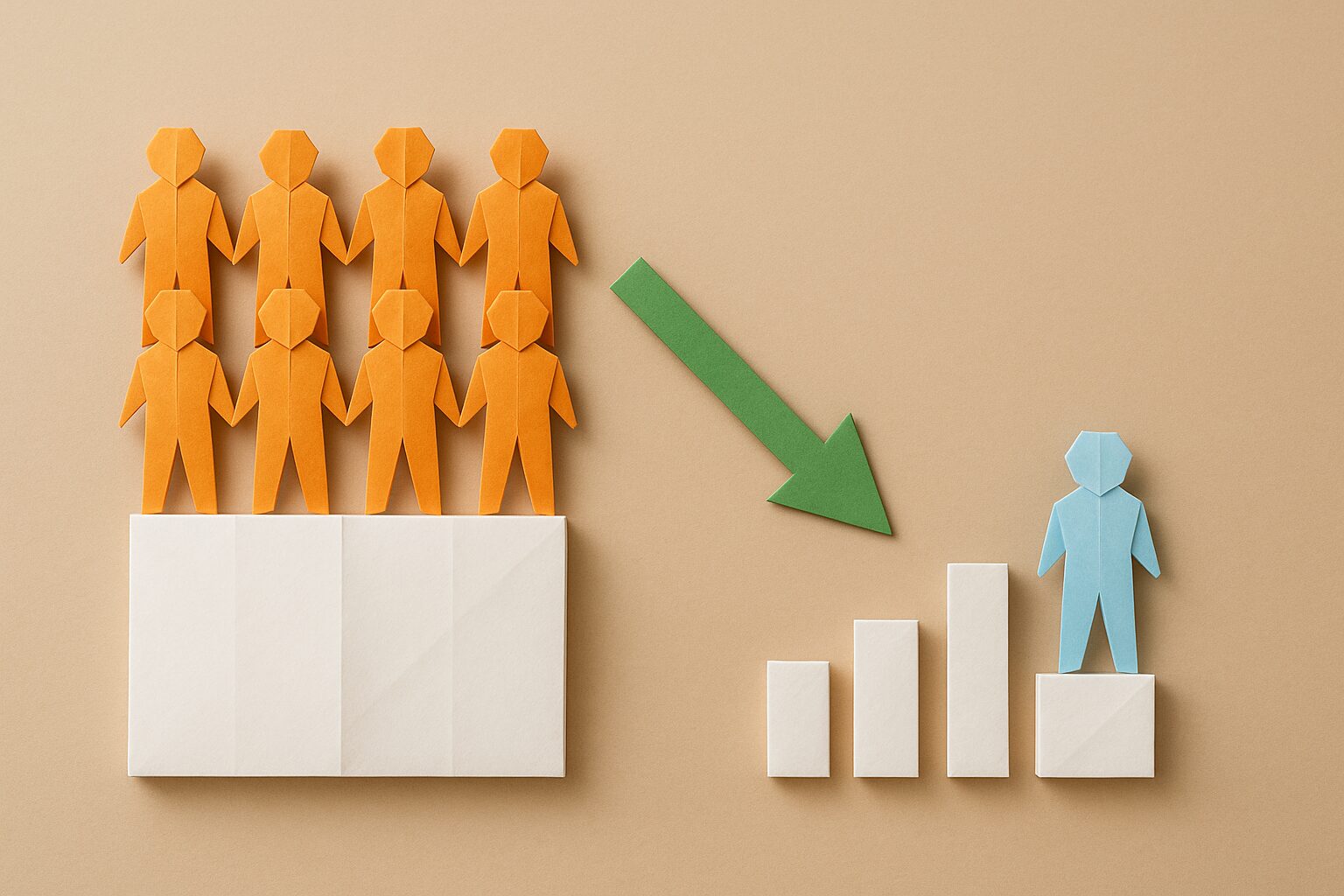
一方で、インターネット調査や自己申告式のアンケートに頼った場合には、ADHDの割合が極端に高く出ることもあります。
たとえば、中国の農村では2%、サウジアラビアでは52.5%という例まであります。
しかし、こうした自己申告型の調査は診断の信頼性や対象集団の偏りなど多くの課題を含んでおり、数字の幅も非常に大きくなりがちです。
医療記録など公式な診断データにもとづく調査では、カナダで2014年から2021年にかけて診断率が1.4倍になったという報告や、スウェーデンでは2018年から2020年の間に0.2%から0.3%に微増したという例があります。
ただし、アメリカでは2018年から2021年まで診断率がわずかに上下したものの、全体として有意な増加は認められませんでした。
コロナ禍の影響については、パンデミック直後に受診控えや医療現場の混乱で一時的に診断や薬の処方が減少しましたが、その後、従来の水準に戻り、場合によってはコロナ前より増えた地域もあります。
コロナ禍の生活環境の変化が子どもや大人のADHD症状を悪化させ、支援を求める人が増えたという報告もあります。
とはいえ、これらの変化が「社会全体でADHDの人が増えた」ことを意味しているわけではありません。
年齢ごとの違いも明らかになっています。
アメリカの大規模調査では、12~17歳の方が4~11歳よりも診断率が高くなっているという傾向が見られました(2021~2022年の調査で12~17歳が14.2%、4~11歳が7.5%)。
これは以前よりも思春期や大人のADHDが社会的に注目され、より認識されやすくなってきたことが背景にあると考えられます。

ADHDの診断には、医師による正式な評価だけでなく、親や教師によるアンケートや自己記入式のチェックリストなどさまざまな方法が使われています。
医師による診断はより信頼性が高いものの、受診までのハードルが高く、すべての人が専門機関につながっているわけではありません。
アンケート調査は広範囲に情報を集められるメリットがある一方で、診断の過剰推定やサンプルの偏りといった課題もついてまわります。
支援を求める人が増えたことで、医療や教育の現場では診断待ちの期間が長くなっています。
受診を希望する人がどれほど多いのか、実際にどの程度の人がADHDと診断されるのかについては、現時点で信頼できる大規模なデータが限られています。
診断まで数年待つという状況は、ADHDに限らず自閉症など他の発達特性でも同様に見られます。
社会全体の需要増加が医療現場に負担をかけているのは確かですが、これが必ずしもADHDの有病率そのものの増加を意味しているわけではありません。
世界中でADHDの割合が大きく異なる理由として、使われる診断基準や調査方法の違いがあります。
たとえば北米では、医療記録や公式な診断データを使った調査が多く、数字も安定しています。
アジアやアフリカでは自己記入型のアンケート調査が主流で、数字の幅が大きくなりやすい傾向があります。
こうした違いが、国や地域ごとのADHD有病率の推定値に大きく影響を及ぼしています。
また、診断基準自体が研究や国によって異なり、DSM-IVやDSM-5、ICD-10など複数の基準が混在しています。
年齢による症状の変化や、いつからADHDと診断されたかといった違いが十分に考慮されていない場合も多く、調査間の比較や数値の一貫性を損なう要因となっています。
医療や教育現場から、ADHDに関するリアルタイムなデータの提供や、診断希望者・待機者・診断件数の透明な公開が求められています。
しかし、データの公開にはさまざまな課題があり、実際の状況把握は難しいままとなっています。
論文や統計データが発表されるまでのタイムラグもあり、最新の現状を反映したデータが研究として世に出るまで時間がかかります。

社会の関心が高まったことで、ADHDの診断を受ける人や支援を希望する人が増えましたが、最も信頼できるデータを見ると、2020年以降のADHDの割合は大きな増加を示していません。
子どもではおおむね3~10%、大人では1~2%程度の範囲で推移しており、国や調査方法によって数字が異なります。コロナ禍をきっかけに一時的な変動はあったものの、社会全体で急増していると断言できる証拠は現在のところ見当たりません。
社会全体でADHDが注目されるようになった背景には、診断基準の変化や情報発信の増加、支援制度の充実など、さまざまな要因が重なっています。
実際に支援が必要な人が適切につながるためにも、診断や支援の仕組みそのものの見直しや、より質の高いデータに基づいた社会政策が今後ますます重要になっていくと考えられます。
ADHDという特徴をめぐる社会の理解と関心は、今後も高まり続けていくでしょう。
しかし、数字や流行に振り回されるのではなく、個々の背景や社会の仕組みに目を向けながら、冷静に実態を見つめていく姿勢が大切です。
新たな研究やデータの蓄積によって、より実態に即した支援や理解が進むことが期待されます。
(出典:Journal of Affective Disorders DOI: 10.1016/j.jad.2025.119427)(画像:たーとるうぃず)
ADHDの診断を求める人は増加しているものの、本当にADHDである人は増えているとは言えない。
ということです。
ADHDの人が増えているという印象は、社会的な認知の変化や診断を受けやすくなっとことが理由。
自閉症と同様ですね。
(チャーリー)





























