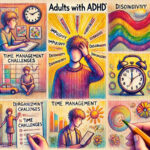この記事が含む Q&A
- 自閉症やADHDの人の時間感覚障害はどのような影響を及ぼしますか?
- 約束忘れや遅刻、自己肯定感の低下など、日常生活に支障をきたすことがあります。
- 時間感覚障害の改善策にはどんなものがありますか?
- デジタル時計や視覚タイマー、ポモドーロ・テクニック、外部リマインドなどが効果的です。
- これらの時間感覚の特性は、脳のどの部分が関係しているのですか?
- 前頭前野の活動が弱いため、「今何時か」「あとどれくらい」などの見通しが立てにくくなります。
「ちょっと時間が経つのが早すぎる」「気づくと約束の時間を過ぎていた」。
こうした経験は誰にでもありますが、ADHD(注意欠如・多動症)や自閉症の人では、ほぼ毎日のように起こり、生活に大きな支障をきたすことがあります。
最近の研究では、この現象を「時間感覚障害(タイム・ブラインドネス)」と呼び、時間そのものを感じ取る力が弱いことが原因だと考えられています。
時間感覚障害とは、時計が示す時間と自分が体感する時間がずれてしまう状態です。
「5分だけ休もう」と思っていたのに実際は30分過ぎていたり、「まだ1時間ある」と思ったら締め切りまで数分しか残っていなかったりする――こうしたズレが続くと、仕事や学業、人間関係で「だらしない」と誤解されるだけでなく、自己肯定感の低下にもつながります。

ADHDの時間感覚については、2023年に発表された、過去10年間の394本の研究をまとめたレビュー(出典①)があります。
このレビューによると、ADHDの人は「時間推定」「時間再現」「時間生成」「時間識別」の4つすべての課題で中等度以上の誤差を示し、数秒〜数分という短いスケールでもズレが起きることが示されています。
レビューの対象は世界各国の複数の研究で、特定の国や研究チームに限られた結果ではありません。
自閉症の人にも同様の傾向があることが報告されています。
2018年に発表された、時間の長さを識別する課題を行いながら脳を撮影した研究(出典②)では、ADHD、自閉症、そして両方を併存するグループともに、前頭前野の活動が弱いことが確認されました。
前頭前野は「計画」「注意の制御」「ワーキングメモリ」を担う領域で、ここが十分に働かないと「今は何時頃か」「あとどれくらいで次の予定か」という見通しを立てにくくなるのです。
また、2018年の別の研究(出典③)では、強い感情を伴う刺激があるとADHDの子どもはむしろ時間感覚が良くなることが示されています。
研究では、ポジティブあるいはネガティブな画像を見せたところ、ADHDの子どもは時間を正確に区別できるようになりました。
ドーパミンなど報酬系の神経が一時的に活性化し、前頭前野の働きを補うためではないかと考えられています。

自閉症については感情刺激と時間感覚の関係を調べた研究が少なく、今後の課題とされています。
近年は治療的アプローチも試みられています。
2024年にイギリスの研究グループが発表した研究(出典④)では、経頭蓋直流電流刺激(tDCS)で前頭前野に弱い電流を流し、ADHDの若者の「時間再現」「時間識別」課題を改善することに成功しました。
1回の刺激でも効果が見られたため、複数回のセッションでどこまで改善が持続するかが注目されています。
こうした個別の実験だけでなく、2024年に発表された大規模な統合解析(メタアナリシス)(出典⑤)も進んでいます。
このメタアナリシスは824件の効果量を統合し、ADHDの人では全年代で中等度以上の時間知覚のズレが一貫して存在すると結論づけました。
著者らは「時間知覚の測定は臨床評価に取り入れる価値がある」と述べ、診断補助や支援計画に活用できる可能性を示唆しています。
発達障害どうしの重なり(併存)も重要です。
ADHDと自閉症の併存率は50%以上と報告され、両方の特徴を併せ持つ人ほど時間盲による生活上の困難が大きくなる傾向があります。
時間管理がうまくいかないと、遅刻や締め切り遅延が重なり、学業成績や職場での評価に直結します。結果としてストレスが増え、さらに注意力が落ちるという悪循環にも陥りやすいのです。
こうした悪循環を断ち切るために、日常生活で取り入れられる具体的な対策があります。

1.時間を「見える化」する大きなデジタル時計や視覚タイマーを使う
ADHDや自閉症の方は、頭の中だけで「今、何時だろう」「あとどれくらいで出かける時間?」と考えるのが苦手です。そのため、
・数字が大きくて見やすいデジタル時計
・残り時間がパッと見てわかる視覚タイマー(たとえば赤い色やパネルがだんだん減るもの)
を部屋や机の上に置きましょう。
たとえば、「あと10分」と思っても感覚だけだとすぐ忘れてしまいますが、視覚タイマーなら赤い部分が消えるのを見ながら「もう半分過ぎた」「あと2分」など一目でわかります。
スマホアプリにも視覚タイマーの機能がありますので、外出先や作業中にも便利です。
2.25分作業+5分休憩を繰り返すポモドーロ・テクニックで区切りを作る
「ポモドーロ・テクニック」は、タイマーを使って25分だけ集中し、その後5分間休憩する、というサイクルを繰り返す方法です。
ADHDや自閉症の方は、気づくと何時間も同じことをしてしまったり、逆に集中できずにダラダラしてしまったりしがちです。
この方法を使うと「今は集中の時間」「今は休む時間」と、メリハリをつけて行動できます。
タイマーをセットしたら、その間は他のことをせず、終わったらしっかり休み、また次の25分を始める…これだけで作業効率が上がる人が多いです。
ポモドーロ用のタイマーアプリやキッチンタイマーでもOKです。

3.好きな音楽やガムなど軽い刺激でドーパミンを程よく上げて集中を保つ
ADHDの人は「退屈」や「刺激が少ない状態」だと集中力が急に落ちてしまうことがあります。
そこで、
・好きな音楽を流しながら作業する
・ミントガムやタブレットを噛む
・アロマや手のひら用の小さなグッズで触覚刺激を感じる
など、五感にちょっとした刺激を与えると集中しやすくなります。
ただし、刺激が強すぎると逆に気が散るので、「自分にとってちょうどいい刺激」をいくつか見つけておくと良いでしょう。
4.予定には必ずバッファ(移動時間+10分など)を入れる
「バッファ」とは、予定の前後に“余裕時間”をつけ足すことです。
ADHDや自閉症の人は、「ギリギリで間に合う」と思っていたのに実際には少し遅れてしまったり、予想外のことに時間をとられて遅刻してしまうことがよくあります。
たとえば、
・10時に到着したいなら、9時50分に着くつもりで行動する
・移動や準備に想定より10分多く時間をとる
などです。
バッファを入れることで、「あれ?間に合わない!」という焦りを減らし、落ち着いて行動できるようになります。

5.家族や同僚にリマインドしてもらうなど外部アカウンタビリティを活用する
「アカウンタビリティ」とは、他の人に進捗や結果を“伝える責任”のことです。ADHDや自閉症の人は、自分一人だけで時間やスケジュールを守るのが難しいことがよくあります。
たとえば、
・出かける時間になったら家族に「もう出る時間だよ」と声をかけてもらう
・大事な締め切りの前に、同僚や友達から「そろそろ提出日だけど大丈夫?」とメッセージしてもらう
などです。
「人に伝える」「見てもらう」ことで、自分でも意識しやすくなり、計画通りに動ける確率がぐんと上がります。
最近はリマインダー機能付きのアプリや、家族間で予定を共有できるカレンダーも増えているので、うまく活用しましょう。
どの対策も「自分の特性に合うやり方」を探すのが大切です。失敗しても自分を責めず、ちょっとずつ“できる工夫”を積み重ねてみてください。
タイム・ブラインドネスは、意志の弱さや怠けではなく、脳の情報処理の特徴に根ざした現象です。
ADHDや自閉症のある人の「時間にルーズ」は、本人の努力不足ではなく神経生理学的な特性だという視点が広まりつつあります。
今後、tDCSのような神経刺激やデジタルツールの発展とともに、時間盲への支援はさらに選択肢が増えるでしょう。
私たち一人ひとりがこの特性を理解し、具体的なサポートを行うことで、当事者が本来の力を発揮できる社会に近づいていきます。
体内時計が正しく機能しないことが自閉症、睡眠障害の原因。研究
(チャーリー)
(画像:たーとるうぃず)
(出典:
① Barkley R. A. ほか. “Time Perception in Adult ADHD: Findings from a Decade—A Review”. Journal of Neuropsychology, 2023. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9962130/
② Zelaznik H. N. ほか. “Neural Correlates of Duration Discrimination in Young Adults with Autism Spectrum Disorder, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Their Comorbid Presentation”. Frontiers in Psychiatry, 2018. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2018.00569/full
③ Nazari M. A. ほか. “Emotional stimuli facilitate time perception in children with attention‑deficit/hyperactivity disorder”. Journal of Neuropsychology, 2018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27566601/
④ Munz M. T. ほか. “Transcranial direct current stimulation improves time perception in ADHD”. Scientific Reports, 2024. https://www.nature.com/articles/s41598-024-82974-8
⑤ Metcalfe K. B. ほか. “Time‑Perception Deficits in Attention‑Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta‑Analysis”. Developmental Neuropsychology, 2024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38145491/
)