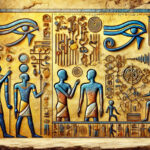この記事が含む Q&A
- 「自閉症」と「すごく繊細な人」は同じものなのでしょうか?
- いいえ、「自閉症」と「繊細な気質」は本質的に異なるもので、前者は神経発達の差異です。
- なぜ「自閉症」と「繊細な気質」が混同されてしまうのでしょうか?
- 感受性が高い自閉症の人が存在し、類似点が見られるため混同されやすいからです。
- 「HSP(非常に繊細な人)」の特徴と自閉症の違いは何ですか?
- HSPは気質の一つで刺激に敏感なことの表現であり、自閉症は言語や社会性など広範な神経発達の違いに基づきます。
「自閉症」と「すごく繊細な人」は、同じものなのでしょうか?
最近では、「自分は感受性が強くて生きづらい。だからきっと自閉症かもしれない」と感じる人や、「自閉症はただの繊細さなんじゃないの?」という声も耳にします。
2021年、イギリスの研究者たちは『自閉症と“すごく繊細なこと”は同じではありません』と発表しています。
多くの人の関心を集めた、そのメッセージは今も色あせていません。
──「自閉症」と「繊細な気質」は、まったく別のものなのです。
では、どうしてこの2つが混同されてしまうのでしょうか?
その理由を一緒に考えてみましょう。
まず、「すごく繊細な人」とは、どんな人なのでしょうか。
心理学ではこれは「環境感受性」とも呼ばれています。まわりの刺激や出来事にどれだけ強く反応するかという、人の生まれつきの傾向です。

これは「気質(テンパラメント)」という、生まれ持った性格の土台のようなもので、人によって異なります。
「内向的」「協調的」「誠実」「開放的」「神経質」といった特徴と同じように、「繊細さ」も気質のひとつなのです。
この「敏感な気質」をもつ人は、まわりの環境からの影響を受けやすい傾向があります。
たとえば、まぶしい光や騒がしい音、人の表情や気配に敏感な一方で、自然の美しさや人の優しさに強く感動するような面もあります。
これは決して「弱さ」ではなく、むしろ「良い環境にいると、大きく力を発揮できる」タイプだといえるでしょう。
この「感受性の強さ」は、白黒ではっきり分かれるものではありません。
すべての人が多かれ少なかれ持っている特性であり、程度の差があります。
研究によると、人口の約30%の人が「すごく繊細」、40%が「中程度」、30%が「あまり繊細ではない」とされています。
一方で「自閉症」は、生まれつきの神経のタイプであり、診断基準を満たすかどうかによって判断される「ニューロタイプ(神経発達のあり方)」です。
先進国では、人口の1〜2%ほどが自閉症に該当するとされています。

それでは、なぜ「自閉症」と「すごく繊細な人」が混同されてしまうのでしょうか。
理由のひとつは、「感受性の強い自閉症の人」が実際に存在するからです。
たとえば、自閉症の人でも「外向的」な人もいれば「内向的」な人もいます。
それと同じように、「すごく繊細な」自閉症の人もいれば、そうでない人もいます。
つまり、「自閉症」であり「すごく繊細な人」である人は、自分の感じ方をふり返ったときに、「私はHSP(Highly Sensitive Person:とても繊細な人)かもしれない」と思うことがあります。
このような体験の重なりが、「HSP」と「自閉症」の違いを深く知らない人たちに、「この2つは同じでは?」という誤解を生むのです。
さらに混乱を招いているのが、「HSP(すごく繊細な人)」という言葉の広まりです。
HSPという言葉は、「感受性の強さには個人差がある」ということを伝えるために広まり、多くの人が「自分もそうかもしれない」と気づくきっかけになりました。
しかし、その一方で、HSPというラベルがまるで「決まった性格タイプ」のように語られるようになってしまいました。
インターネット上では、「HSPの人はこういう性格です」「HSPだからこう感じるのは当然」といった説明があふれ、もともとの科学的な意味から離れてしまっていることもあります。
こうした状況のなかで、「HSPは自閉症の軽い形なのでは?」という誤解も生まれています。
実際、自閉症の人が最初は「自分はHSPなんだ」と思い込み、後になって「やっぱり自閉症の特徴のほうがしっくりくる」と気づくケースもあります。
このような混乱が、「すごく繊細な気質」と「自閉症」を誤って結びつけてしまっているのです。
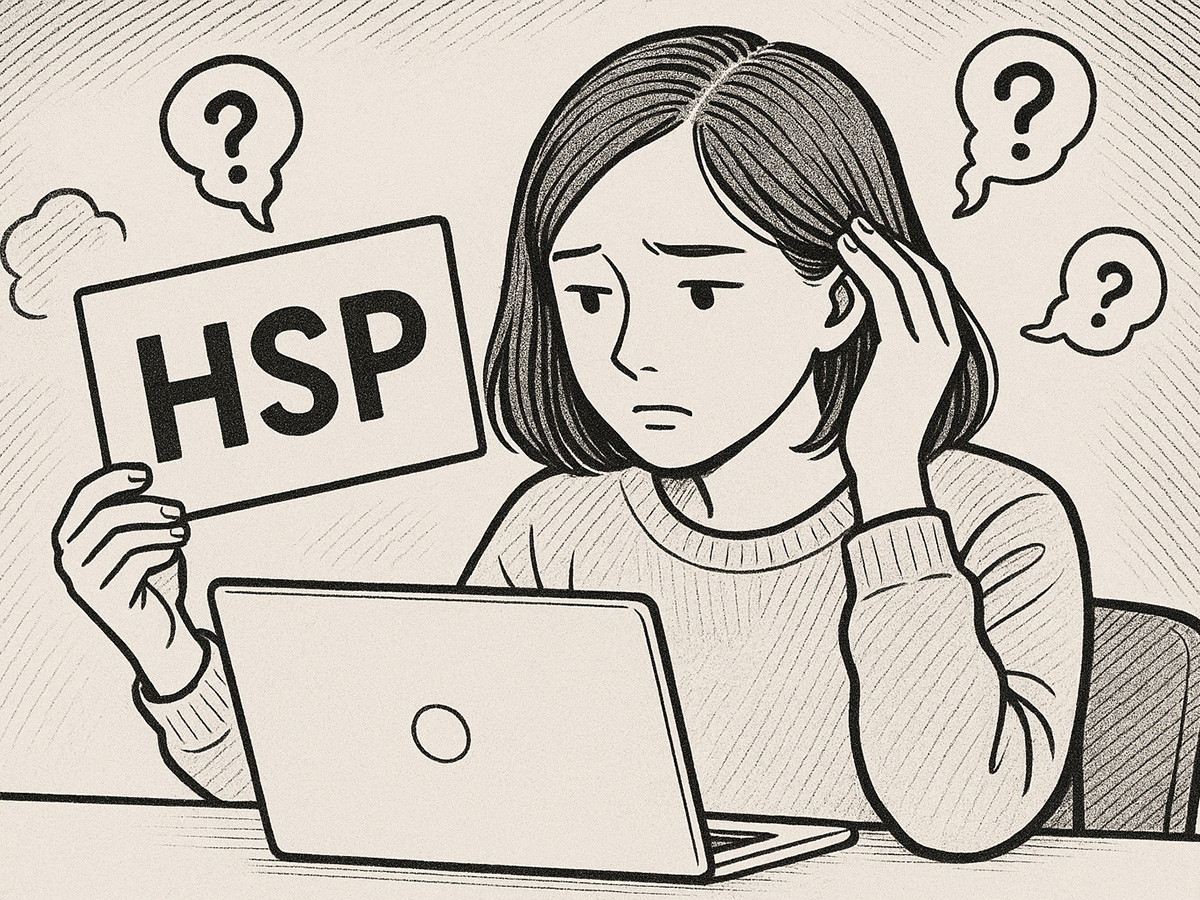
たしかに、見た目には似ている部分もあります。
たとえば、音がうるさく感じる、光がまぶしすぎる、服のタグが気になる、人混みがつらい──こうした感覚のつらさは、「繊細な人」にも「自閉症の人」にもよく見られます。
しかし、そこにある背景は違います。
すごく繊細な人は、刺激に対して反応しやすいという「気質」の特徴からこうした体験をします。
あくまで「感じ方」の強さの問題であり、それ以外の面に大きな違いはありません。
それに対して、自閉症では「刺激に対して強すぎる反応」や「逆にほとんど反応しない」場合があり、その特性は人によってさまざまです。
また、感覚の面だけでなく、「言葉の使い方」「人との関係の築き方」「日常のこだわり方」にも明確な違いがあります。
たとえば、自閉症の人は、言葉を使うときにも独特の感覚を持っていることがあります。
言葉の音やリズムを楽しんだり、同じフレーズを繰り返したり、詩のように言葉を遊ぶような使い方をすることもあります。
昔はこうした違いを「社会性が低い」と見なすことが多かったのですが、近年の研究では「自閉症の人どうしなら、とてもスムーズにやり取りできる」という事実が注目されています。
つまり、自閉症の人と非自閉症の人のあいだには、コミュニケーションのスタイルの「すれ違い」があるのです。

一方で、「繊細な人どうし」が言葉の使い方でうまくかみ合わない、ということはあまり見られません。
また、自閉症の人には「同じことを繰り返すのが好き」「ひとつのことに強く集中する(ハイパーフォーカス)」といった特徴もあります。
こうした特性は、「すごく繊細な人」にはあまり見られないものです。
「すごく繊細な人」は、人間の気質のひとつであり、環境の変化や刺激に敏感に反応するという傾向をもっています。
ただし、それは言葉の使い方や社会性、こだわりの強さなどには直結しません。
一方で、「自閉症」は、感覚だけでなく、言語、社会的ふるまい、興味の持ち方など、広い範囲にわたる神経発達の違いです。
この2つを混同してしまうと、それぞれの人が持っている違いや個性が見えにくくなってしまいます。
たしかに「似ている部分」はありますが、「本質的な違い」を正しく知ることが大切です。
その違いを尊重し、理解を深めること──それこそが、よりよい共生社会の第一歩なのではないでしょうか。
(出典:米Psychology Today)(画像:たーとるうぃず)
必要とされる方に、適切な支援が届くためには、正しい理解が不可欠です。
(チャーリー)