
この記事が含む Q&A
- ADHDのある女子高校生は、どのように自己アイデンティティを向き合っていますか?
- 社会的期待や学校の役割に応じて抑えたり演じたりしながら、自己理解を模索しています。
- ADHDの診断は女子にとってどのような意味を持つのでしょうか?
- 違和感の説明と安心感をもたらす一方、ラベル付けや社会的期待による葛藤も伴います。
- 学校環境や社会制度は、ADHDの女子の自己表現にどのように影響していますか?
- きめ細かいサポートや多様な役割を認めることで、彼女たちが自分らしく学べる場を創る必要があります。
ADHDのある女子高校生たちは、学校という舞台でどのように「自分らしさ」と向き合っているのでしょうか。
スウェーデンのウメオ大学社会学部、ストックホルム大学心理学部、そしてウプサラ大学医学部小児・思春期精神医学部門の研究チームが行った共同研究が、思春期の女子たちが経験する「アイデンティティのゆらぎ」と、その背景にある社会的な期待や制度の影響に迫りました。
研究に参加したのは、ADHDの診断を受けた15歳から18歳の女子10人です。
彼女たちの語りからは、日常の中で自分を抑えたり、合わせたり、演じたりすることの苦労と、その中で自分自身を見つけようとする複雑なこころの動きが浮かび上がりました。
この研究では、社会の期待を内面化した「ワタシ(Me)」と、本来の自分である「ワタシ(I)」という心理学的な枠組みを用いながら、彼女たちの「アイデンティティ・ワーク」、つまり「自分とは誰か」を探る過程を読み解いていきます。
まず明らかになったのは、学校や人前では「落ち着いた、静かな、良い生徒」としてふるまおうとするあまり、元々の性格や行動パターンを押し殺してしまうという体験です。
たとえば「本当はもっとおしゃべりで、元気で、じっとしていられないのに、それを出すと迷惑がられる気がして抑えてしまう」と語る女子もいました。
クラスの中で浮かないよう、他人のふるまいを観察してまねる「カモフラージュ」を行うことも少なくありません。
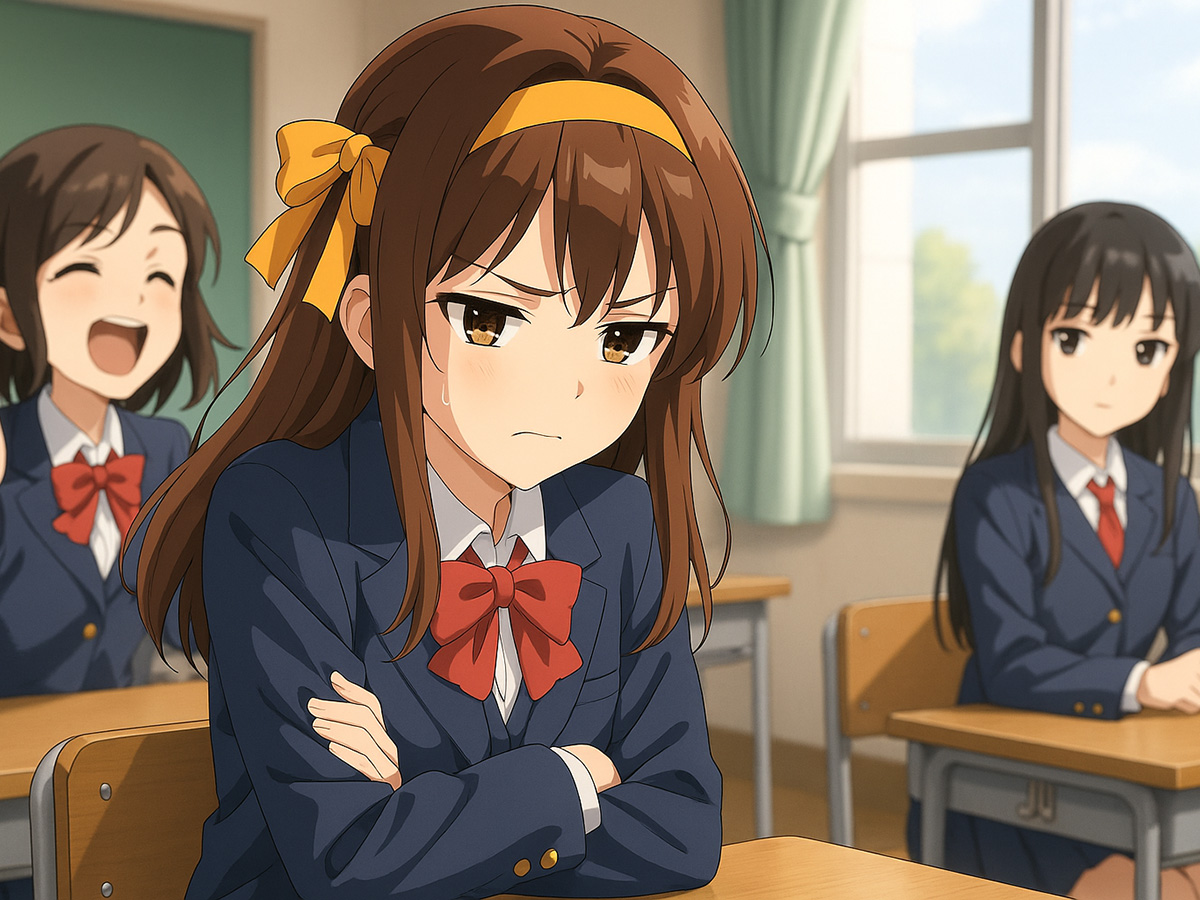
ある女子は、「学校で一日中がんばって演じて、家に帰るとぐったりして動けない」と話します。
別の女子は「人といるときはずっと緊張していて、本当の自分を見せられない。まるで“タマゴの殻の上を歩いているみたい”」と表現しました。
ADHDの女子にとって、こうした自己抑制は日常的に必要とされるものです。
しかし、それは決して自然なことではなく、心身に大きな負担をかけているのです。
一方で、抑えるだけではなく、ADHDの特性をうまく活かそうとする姿勢も見られました。
たとえば「フィルターがなく、ズバズバ言ってしまう性格」を、年齢が上がるにつれて「面白い」と受け取られるようになったことで、自信につながったという女子もいました。
しかしそれでも、周囲の評価や社会の期待は常に彼女たちの中に影響を与えています。
「もっと女の子らしく、やさしく、穏やかにふるまいたい。そうじゃない自分が嫌になる」と葛藤を語る声もありました。

また、ADHDという診断そのものが、彼女たちにとっては二重の意味を持ちます。
多くの女子にとって、診断は「自分の感じていた違和感に説明がついた」という安堵でもあり、「普通じゃない」とラベルを貼られたような戸惑いでもあります。
ある女子は、「ADHDってもっと男の子っぽいイメージがあった。じっとできないとか、物を投げるとか。だから自分には関係ないと思っていた」と話しました。
このように、「ADHD=やんちゃな男の子」というステレオタイプが、女子の気づきや診断を遅らせる要因にもなっています。
学校での困難も、彼女たちのアイデンティティに大きく関係しています。授業中にじっとしていられない、課題に集中できない、提出物を忘れてしまう──。
こうした行動は、学校という場で求められる「良い生徒像」とは相容れません。
それでも周囲は、「できない」彼女たちに対して、「もっとがんばれ」「将来それじゃ困る」といった期待を突きつけてきます。
「学校ではずっと人と比べられて、劣っている気がする」と語る女子や、「昔はできたのに、だんだん求められることが増えて、ついていけなくなった」と語る女子もいました。

診断をきっかけに処方されることの多い薬もまた、彼女たちのアイデンティティに影響を与えます。
たとえば、「薬を飲むと集中できるけど、自分じゃない感じがする」「友だちは『薬を飲むとつまらなくなる』って言う」など、薬が「よい生徒」を演じるための道具になっているように感じているのです。
別の女子は、「薬を飲んでいないと成績が下がるけど、飲むと自分が自分じゃなくなる。どっちを選べばいいのかわからない」と語りました。
こうした「学校での役割を果たす自分」と「ありのままの自分」との分裂感が、アイデンティティ・ワークに大きな緊張をもたらしているのです。
研究チームは、「学校がADHD診断のきっかけになることが多いが、その背景には“望ましくない行動”への対応として、診断が求められている現状がある」と指摘します。
もちろん、薬がすべて悪いというわけではありません。
多くの女子が「薬で集中できるようになった」「授業についていけるようになった」とも述べています。
しかし、それはあくまで「成績を上げる」ためであり、「自分らしく生きる」ためではないという点に注目が必要です。
この研究が示しているのは、「ADHDのある女子の困難は、単に個人の問題ではなく、社会や学校の構造とも深く結びついている」ということです。
たとえば、小規模なクラスや柔軟な学習環境、早期のラベリングを避ける制度的な見直しなど、医療以外のアプローチが模索されるべきだと述べられています。

「良い生徒」という役割をただ一つに定めるのではなく、もっと多様な「舞台」や「役割」が存在する学校であれば、ADHDのある女子たちが自分らしさを保ちながら学べる環境が生まれるかもしれません。
今回の研究は10人という少人数の聞き取りに基づいており、統計的な一般化はできません。
しかし、彼女たちの生の声を通して、「ADHDであること」と「女子であること」が交差する地点でのアイデンティティ形成の難しさと可能性を丁寧に描き出しました。
「私は本当はどうしたいのか」「社会が求める私とは違うけれど、それでも私は私だ」と模索する彼女たちの姿は、ADHDという診断名の背後にある、ひとりひとりの人生の重みと向き合うきっかけとなるはずです。
今後は男女比較や、より多様な背景を持つ当事者の声を含めた研究が求められます。
そして私たち大人ができることは、「型にはめること」ではなく、「多様なあり方を支えること」かもしれません。
(出典:frontiers DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1591135)(画像:たーとるうぃず)
難しい状況になることもあるだろうと察します。
自分のことを第一に、つらいときには「いのちだいじに」まずは避難してください。
(チャーリー)





























