
この記事が含む Q&A
- 声の分析だけでADHDを診断できますか?
- 研究によると、声だけでADHDの可能性をかなりの確率で識別できることが示されていますが、完全ではありません。
- 若い女性の声は、他のグループと比べてADHDをより正確に見分けられるのでしょうか?
- はい、特に32歳未満の若い女性では、声の分析精度が非常に高くなっています。
- 声の特徴とADHDの症状の重さには関係がありますか?
- はい、症状が重い人ほど、声の特徴からADHDを予測しやすいことが示されています。
ADHD、つまり注意欠如・多動症という名前は、多くの人が聞いたことがあると思います。
学校や職場で集中が難しかったり、落ち着きがないと言われたり、自分自身や身近な人がそうかもしれないと感じたことがある人も少なくないでしょう。
ADHDは、子どもだけでなく、大人にも続く可能性がある発達障害のひとつです。
しかし、ADHDの診断は簡単ではありません。
現在行われている診断は、本人の話や家族からの情報、評価のアンケートなどをもとに、医師や心理士が判断するという方法が中心です。
このような診断方法は、どうしても「人の感覚」に頼る部分があり、診断する人によって結果が変わったり、症状が見落とされることもあるとされています。
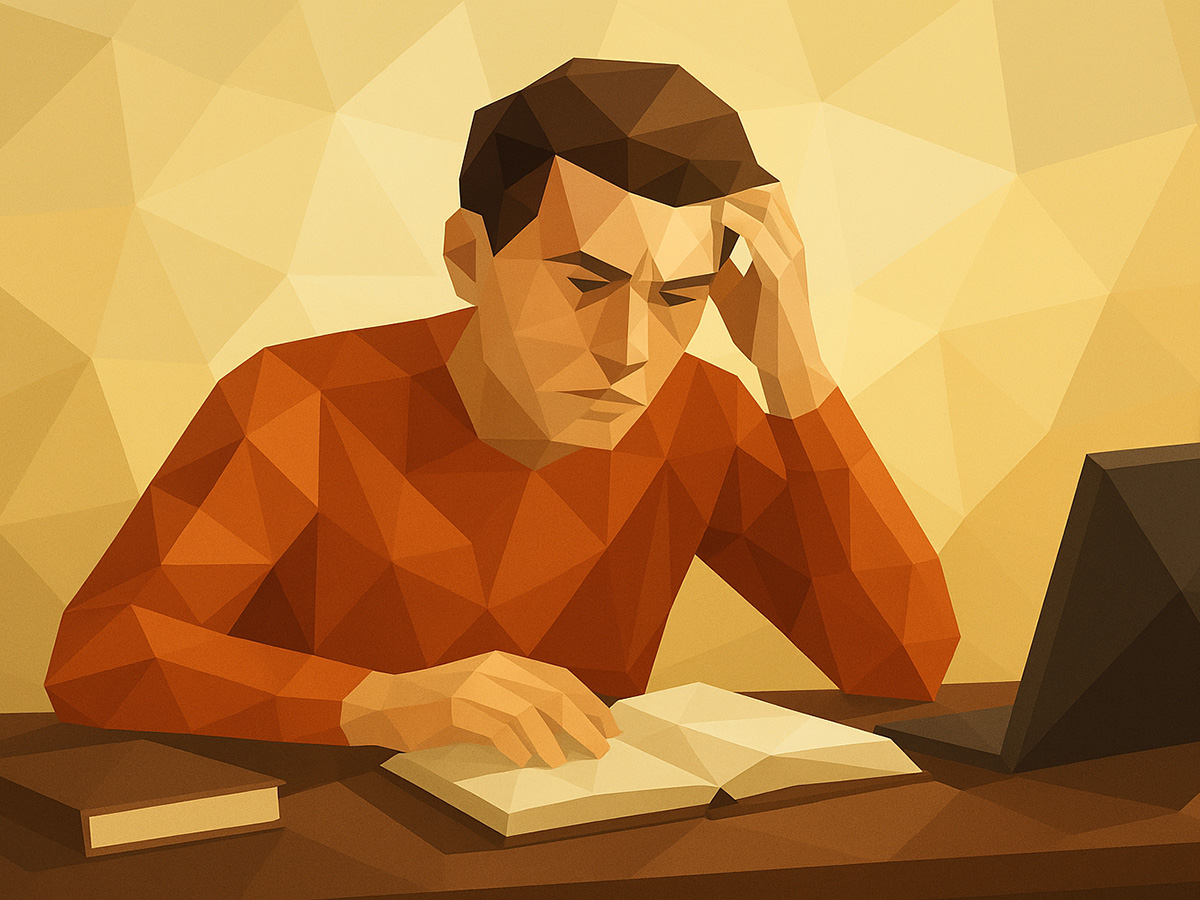
そうした中で注目されているのが、「声」です。
ADHDのある人は、話し方や声の出し方に、ある特徴が見られることが以前から知られていました。
たとえば、声が大きすぎたり、小さすぎたり、話すスピードにムラがあったりします。
では、こうした声の特徴を、科学的に測って、ADHDかどうかを見分けることができるのでしょうか?
そんな疑問に答えるために行われたのが、今回紹介するドイツの研究です。
この研究を行ったのは、ドイツ国内の複数の大学や病院に所属する人たちの研究グループです。
この研究は、「サイエンティフィック・リポーツ」誌に発表されました。
研究に参加したのは、18歳から59歳までの大人たちです。
そのうち、387人はADHDと診断された人たちです。
そして、精神的な問題はあるけれどADHDではない100人、さらに精神的な問題がない健康な人たち204人も参加しました。
こうして集まった人たちから、全部で920回分の音声データを録音して、分析に使いました。

録音は、診断評価の前に静かな部屋で行われました。
このとき、録音を担当する技術スタッフや、後に音声を解析する研究チームのメンバーは、参加者がADHDと診断されているかどうかを知らない状態でした。
録音の内容は、「アー」といった単音を出すこと、簡単な単語を読むこと、1から10までを2回数えること、そして自分の最近の出来事について自由に2分ほど話すというものでした。
たとえば「先週末に何をしたか」や「最近の休日のこと」など、自由に話してもらいました。
録音した音声からは、「声の大きさ」や「声の高さ」「声の抑揚」などをコンピュータで細かく分析しました。
声の大きさは、「ゾーン」という人の感覚に近い単位で、0.02秒から4秒まで、さまざまな時間のスケールで変化を記録しました。
声の高さについても同じように、多くの情報を取り出しました。
その結果、1つの録音から、6141個もの数値で表現できる情報が得られました。
このたくさんの声の情報を使って、「ADHDの人」と「そうでない人」をどれだけ正確に見分けられるかを調べるために、機械学習という方法を使いました。
今回は「ランダムフォレスト」と呼ばれる方法で、コンピュータに何百回も練習させながら、見分ける力を確かめました。
その結果、ADHDの人と健康な人を声だけで見分ける精度は、「AUC=0.77」でした。
この数字は、1.0に近いほど正確に見分けられるという意味で、0.5ならば「当てずっぽう」と同じ精度ということになります。
つまり、声だけでかなりの確率でADHDを見分けることができたのです。

さらに詳しく調べると、性別や年齢によって精度が違っていました。
たとえば、若い女性(32歳未満)では、AUC=0.87という非常に高い精度になりました。
これは、ほぼ確実に近いレベルです。
年齢が高いグループや男性では、少し精度が下がる傾向が見られました。
ADHDの中でも、不注意が目立つタイプと、多動・衝動が目立つタイプとがありますが、どちらのタイプでも声の分析で見分ける精度に大きな違いはありませんでした。
また、「ADHDのような症状があるけれど診断はされなかった人たち」との区別も試みられました。
こうした人たちは精神的な困りごとを抱えてはいますが、診断基準には達していません。
このグループとADHDの人を声で区別するのはやや難しく、AUCは0.60にとどまりました。
とはいえ、これらの人たちはADHDに近い症状を持っていることが多く、声にもその影響が出ていると考えられます。
音声データを1人につき1回だけ使った場合でも、精度はあまり変わりませんでした。
つまり、たった1回の録音でも、ADHDかどうかをある程度見分けられる可能性があるということです。

また、声の特徴とADHDの症状の重さにも関係がありました。
症状が重い人ほど、声にも特徴が出やすかったのです。
とくに「多動・衝動」の症状と、声の変化との間に強い関係が見られました。
声を使って、症状の強さまである程度予測できる可能性があることが示されたのです。
さらに、声の変化がとくに目立ったのは、「自由に話すときの声の大きさの変化」や、「数字を数えるときの声の高さの変化」でした。
声の変化を見るには、課題の内容も重要だということです。
性別や年齢、学歴なども声に影響を与えることがわかりました。
たとえば、声からその人の性別を見分ける精度はAUC=0.98とほぼ完璧でした。
年齢や学歴についても、ある程度予測できることが確認されました。
このように、声の中には、ADHDやその症状の重さに関係するたくさんのヒントが含まれていることが、この研究で明らかになりました。
もちろん、声だけですべてを判断することはできません。
しかし、診断の参考として、声の分析を使うことができるかもしれない、という可能性が見えてきたのです。
声は、誰もが持っていて、特別な機械がなくても簡単に記録できる情報です。
だからこそ、ADHDの診断をよりわかりやすく、そして早くするための新しい手がかりになるかもしれません。
この研究は、ADHDの診断や理解を深めるための、大きな一歩と言えるでしょう。
(出典:Nature DOI: 10.1038/s41598-025-01989-x)(画像:たーとるうぃず)
声でも、ADHDかどうかある程度わかる。
「ADHDの診断をよりわかりやすく、そして早くするための新しい手がかり」
になることを期待しています。
(チャーリー)





























