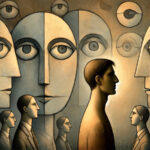この記事が含む Q&A
- なぜ女の子の自閉症診断が遅れがちになると指摘されているのですか?
- 観察検査が女の子の「表面的に社交的に見える」特徴を過小評価しやすく、目の合わせ方などの行動だけで困難を読み取りにくいためです。
- 女の子と男の子ではどのような点が診断時の評価に影響しますか?
- 共同注意への反応や他者への関わり方は男の子の方が困難を強く反映する傾向があり、年齢とともに評価が軽く出る項目もあるためです。
- 研究からどんな改善が求められていますか?
- 女の子特有のサインを理解しやすい新しい評価方法と、医療・保育の現場での訓練が必要だという点が示されています。
自閉症は幼児期から診断できるとされていますが、現実には女の子の診断が男の子よりも遅れることが多いことが知られています。
その理由のひとつとして、今回の国際的な大規模研究は、診断に使われる観察検査が女の子にとって「軽く見えやすい」ように働いてしまうという仕組みを明らかにしました。
この研究は、アメリカ、カナダ、韓国、イギリスなど18の研究機関が参加する「ベビーシブリングズ・リサーチ・コンソーシアム(BSRC)」によって行われたもので、中心となったのはアメリカ・ミネソタ大学医学部小児科の研究チームです。
対象は、兄や姉に自閉症がある幼児3,106人と、そうでない1,444人、合計4,550人で、20〜40か月の間に最大3回行われた観察検査「ADOS(エイドス)」の記録が詳しく解析されました。
ADOSとは、子どもが検査者と関わる場面を観察し、「目を合わせる」「指さしに応じる」「人と喜びを共有する」などの行動を点数化して、自閉症の特徴を測る検査です。
研究チームは、このADOSの項目が男の子と女の子でどのように評価の仕方が変わってしまうのかを精密に分析しました。
その結果、いくつかの重要な性差バイアスが見つかりました。

女の子は同じレベルの困難を抱えていても「目を合わせられる」と評価されやすく、つまり「目が合うから大丈夫」と見られてしまう傾向がありました。
また「共同注意への反応(誰かが指さしたものに一緒に注意を向けること)」や「自分から相手にかかわろうとする行動(社交的なはたらきかけ)」は、男の子のほうが自閉症の困難を強く反映する指標として働いていました。
女の子では、同じ行動の得点が必ずしも本当の困難さを表していない可能性があるということです。
さらに年齢による違いも確認され、「名前を呼ばれて振り向く」「見せる行動」「一緒に喜ぶ」といった項目は、月齢が上がるほど軽めに評価される傾向がありました。
繰り返し行動や強いこだわりの面でも違いがあり、男の子のほうが「感覚への強い興味」がより困難の指標として強く作用し、反響言語(オウム返しのような言葉の繰り返し)は年齢が高いほど強く評価されることがわかりました。

こうしたバイアスを統計的に補正して解析すると、自閉症のある子どもは一貫して社会的なやり取りや繰り返し行動に多くの困難を示していました。
ただし女の子の場合は、「診断あり」と「診断なし」の差が男の子よりも大きく出ました。
つまり、女の子が診断に至るには、同年代の女の子の平均的な行動からより大きく外れて見えなければならない可能性があるということです。
これは、女の子が自閉症の診断を受けにくい理由のひとつを示しています。
研究チームは、女の子の行動は表面的に「社交的に見える」ために困難が軽く見積もられやすいと指摘しています。
たとえば「目を合わせる」「微笑む」「愛想がよい」といった行動があっても、実際にはことば・視線・ジェスチャーを同時に組み合わせる調整に困難を抱えているケースが多いのです。
こうした特徴はADOSの得点だけでは十分に拾えず、女の子の自閉症が見過ごされる要因になり得ます。
そのため研究者たちは、「目が合うから大丈夫」と安易に判断しないこと、共同注意や声や動きの調和など細かい点を丁寧に観察すること、さらに年齢や言語発達の段階によって評価の出方が変わることを理解することが重要だと強調しています。

この研究の意義は、自閉症の診断に用いられる検査が「男の子基準」で作られている部分を可視化した点にあります。
そのため女の子は、同じ困難を抱えていても見逃されやすいのです。
研究チームは、こうした性差を踏まえた新しい評価方法の開発や、医師や保育者の訓練が必要だとしています。
とくに一次小児科や保育・療育の現場で女の子特有のサインを理解し、早く気づくことが、支援を届けるうえで欠かせません。
結論として、この研究は「自閉症は男の子のもの」という古いイメージがいまだに評価や診断に影響していることを示しました。
その結果、女の子は診断が遅れるという不公平を受けやすくなっています。
今回の成果は、その見えにくさを科学的に裏付け、改善の方向性を示した重要な一歩です。
(出典:JAMA Network Open DOI:10.1001/jamanetworkopen.2025.25887)(画像:たーとるうぃず)
「「目を合わせる」「微笑む」「愛想がよい」といった行動があっても、実際にはことば・視線・ジェスチャーを同時に組み合わせる調整に困難を抱えているケースが多い」
結局のところ、困難はあるのに見過ごされてしまう。
正しく理解され、支援を必要とされる方に適切な支援がなされることを願います。
(チャーリー)