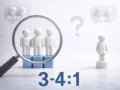この記事が含む Q&A
- 不安とくり返し行動の関係はどのように説明されていますか?
- 不安が強い人ほどくり返し行動が多い傾向があり、直接的ではなく「くり返し行動」が橋渡しとなる場合があるとされています。
- 研究で特に不安とくり返し行動が関連したタイプは何ですか?
- 体を動かすタイプのくり返し行動が不安と比較的強く結びつく傾向が見られました。
- 支援の現場で推奨される配慮は何ですか?
- 不安を減らすために行動を止めるのではなく、安心できる環境を整えその行動を許すか別の方法へ置き換える支援が有効とされています。
自閉症のある人にとって、「不安」とのつき合い方は、人生の中でとても大きなテーマのひとつです。
人とのやりとり、予定の変化、音や光の刺激、思い通りにならないこと——。
それらが重なると、胸の奥に重い緊張や苦しさを感じる人は少なくありません。
では、その不安と、自閉症に特有とされる「同じことをくり返す」「強くこだわる」といった行動は、どう関係しているのでしょうか。
それとも、別々のものなのでしょうか。
スイスのロシュ社を中心とする国際チームが、この疑問に本格的に取り組みました。
彼らは「V1aduct(ヴィワダクト)」という大規模な研究のデータを使い、自閉症の成人における「不安」と「くり返し行動」、そして「人との関わりの難しさ」がどんなつながりを持っているのかを調べました。
この研究には、ヨーロッパと北アメリカにある46か所の研究機関が参加しました。
対象は18歳から62歳までの322人。平均年齢は27歳で、男性が約8割、女性が2割でした。
全員が、知的な障害がない(IQが70以上)成人です。
もともとは、「社会的なやりとりをよくする薬」が効くかどうかを確かめる治験(薬の試験)として始まったものでしたが、途中で薬の効果が見られず中止となりました。
しかし、その過程で集められたデータがとても豊かで、今回の分析に使われました。

研究では、参加者の「不安の強さ」「くり返し行動の程度」「社会的なやりとりの得意・苦手」の3つを、1年間にわたり何度も測定しました。
不安の強さは「ハミルトン不安評価(HAM-A)」という質問票で、くり返し行動は「反復行動尺度(RBSR)」で、そして社会的なやりとりの力は「ヴィネランド適応行動尺度(Vineland-II)」という検査で評価されました。
ここでいう「くり返し行動(RRB)」とは、体をゆらす、手をふる、同じ順番で行動する、決まった話題をくり返す、特定のことに強く興味をもつ、といった行動のことです。
これは「悪いクセ」ではなく、自閉症の人にとって大切な安心の手段でもあります。
研究では、それを「低次のくり返し(体の動きなど)」と「高次のくり返し(こだわりや順序など)」に分けて調べています。
そして、社会的コミュニケーション(CSCI)とは、人との会話の流れをつかむ力、表情やしぐさから気持ちを読み取る力、または自分の思いを自然に伝える力のことです。
これもまた、努力や訓練で単純に伸ばせるものではなく、脳や感覚のはたらき方の違いによって生まれるものです。
研究チームは、この3つ——不安、くり返し行動、社会的やりとりの難しさ——がどのようにつながっているのかを解析しました。
その結果、最も強く結びついていたのは「不安」と「くり返し行動」でした。
不安が強い人ほど、くり返し行動が多い傾向がはっきりと見られたのです。
この関係は統計的に確かな関連があることを示していました。

一方で、「不安」と「人とのやりとりの難しさ」にも、いくらか関係があるように見えました。
しかし、さらに詳しく分析すると、この関係は「くり返し行動」が間に入ることで説明できることがわかりました。
つまり、社会的な困難が直接に不安を生んでいるのではなく、「くり返し行動」がその橋渡しをしているというのです。
たとえば、人とのやりとりに不安を感じるとき、その不安が高まると、同じ行動をくり返すことで心を落ち着かせようとする。
あるいは、こだわりやルールを守る行動が強くなることで、少し安心できる。
そんな循環が、実際のデータの中にも見えてきたのです。
もちろん、すべての「くり返し行動」が不安と結びついているわけではありません。
研究では、6つのタイプのくり返し行動を個別に分析しました。
その中で、不安との関係が比較的強かったのは「体を動かすタイプ(たとえば手をふる、体をゆらすなど)」でした。
「こだわりや決まりごとに関する行動」との関係も見られましたが、それほど強くはありませんでした。
また、「自分を傷つける行動」と不安の関係は、統計的にはほぼ同じ程度でした。
このことから研究者たちは、「不安とくり返し行動の関係はあるが、それは一部に限られ、小さなもの」だと結論づけました。
ただし、それは「意味がない」ということではなく、「不安を減らすだけで行動がすぐ変わるとは限らない」という慎重な見方です。
年齢や性別による違いも調べられました。
女性は男性よりも不安を感じやすい傾向があり、男性はくり返し行動が多い傾向がありました。
年齢が上がると、体の動きに関わるくり返し行動が少しずつ減る傾向も見られましたが、その変化はごくわずかでした。
また、知的能力が高いほど、社会的なやりとりのスコアも高くなる傾向がありました。
1年間の観察の中では、ほとんどの参加者で最初の数か月に少し改善が見られましたが、その後はほぼ安定しました。
これは治療薬の効果ではなく、研究に参加して定期的に評価を受けたことによる「安心感」や「環境の安定」が影響していると考えられます。
一方で、この研究にはいくつかの制約もありました。
参加者は比較的安定した成人が多く、強い不安やうつを抱えている人、知的障害のある人は含まれていませんでした。
また、調査はヨーロッパと北アメリカの先進国で行われており、文化や社会環境が異なる国では、同じ結果が出るとは限りません。

それでも、この研究はとても重要な意味を持ちます。
なぜなら、成人の自閉症の人を対象に、長期的に「不安」と「くり返し行動」と「人との関わり方」を同時に調べた研究は、これまでほとんどなかったからです。
この結果は、子どもを対象にした研究で見られてきた傾向——「不安とくり返し行動がつながっている」——が、大人でも当てはまることを示しました。
そして、「社会的な難しさ」と不安との関係は、直接ではなく、「くり返し行動」を通じたものだという新しい視点を与えました。
研究チームは、「くり返し行動は不安を和らげるための対処でもある」と指摘します。
これは、実際に多くの自閉症の人たちが語ってきたこととも一致します。
「手を動かすと落ち着く」「同じことをくり返すと安心する」——それは本人にとって必要なリズムであり、心の安全を保つための工夫なのです。
研究者たちは、「こうした行動を単に『なくす』のではなく、本人が安心してできる環境を整えることが大切だ」とも述べています。
不安とくり返し行動の関係を理解することは、自閉症の人の生活をより穏やかにするための第一歩になるでしょう。
また、この研究で使われた「不安の測定法(HAM-A)」は、もともと一般的な不安を測るためのもので、自閉症の特性を考慮していません。
研究チームは、「自閉症の成人に特化した不安の測定法を開発することが今後の課題」としています。
これは、本人の感覚や状況に合わせた支援を考える上で、とても重要な視点です。
今回の結果からわかるのは、「不安とくり返し行動は切り離せない関係にある」ということ。
そして、「社会的なやりとりの難しさ」は、それ自体が不安を生むというよりも、「くり返し行動」という間接的な形で不安と結びついているということです。
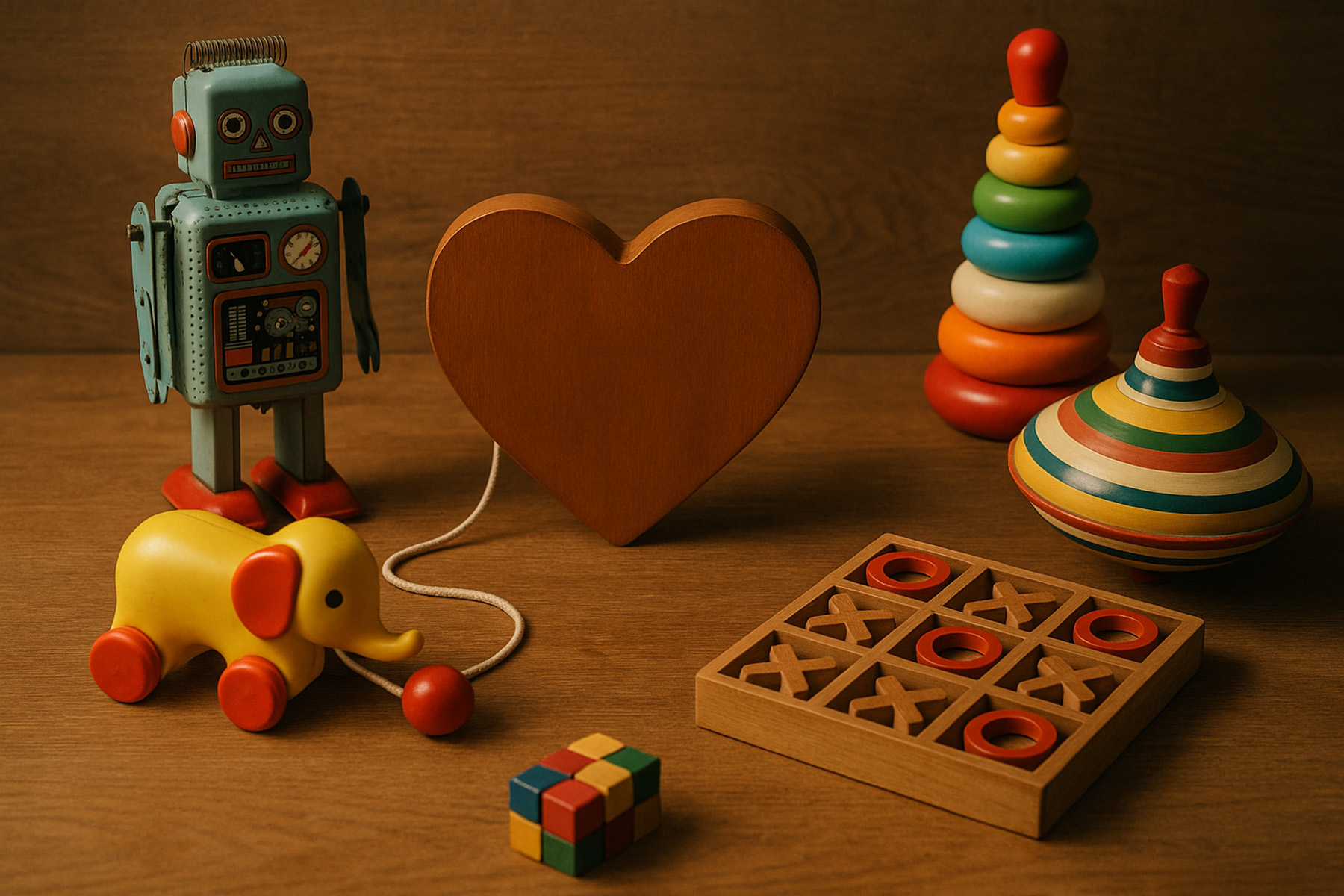
この発見は、支援の現場にも新しいヒントを与えます。
たとえば、不安が強いときに「行動をやめさせる」のではなく、「安心できる環境でその行動を許す」「その行動を置き換える別の方法を一緒に探す」など、本人の感覚を尊重する支援の方向を示しています。
研究の終わりに、著者たちはこう書いています。
「自閉症の成人における不安は非常に一般的であり、くり返し行動との間に小さいながらも確かな関係がある。
社会的な困難とは直接の関係がなく、その関連はくり返し行動を通して説明できる。
この知見は、成人の自閉症支援をより効果的にするための手がかりになる」
この言葉は、研究室の外にいる多くの人にも響きます。
不安も、こだわりも、くり返しも——それらは「問題」ではなく、「生きるための工夫」であり「自分を守る方法」でもあるのです。
大切なのは、それを理解し、認め合い、支え合うこと。
今回の研究は、そのための確かな根拠を、静かに、しかし力強く示してくれました。
(出典:Nature Scientific Reports DOI: 10.1038/s41598-025-22659-y)(画像:たーとるうぃず)
>不安が強いときに「行動をやめさせる」のではなく、「安心できる環境でその行動を許す」「その行動を置き換える別の方法を一緒に探す」
きちんと理解し、どうぞよろしくお願いします。
(チャーリー)