
この記事が含む Q&A
- ADHDの診断を子どもにどう伝えるべきですか?
- 医療記録上の診断と親の回答は異なることがあり、親のストレスや経験が影響するため、丁寧な説明と受け止め方の共有が大切です。
- 子育ての負担が大きいと診断を伝える割合は高くなるのですか?
- はい、ストレスが高い親ほど診断を報告する割合が高く、親自身のADHD診断経験がある場合には報告確率が2〜3倍になることもあります。
- 医師の伝え方は影響しますか?
- はい、小児科の説明が不十分なケースもあり、精神科や心理療法士などで丁寧に説明を受けると理解しやすくなる傾向があります。
「うちの子、ADHDなんです」
そう話す親がいる一方で、同じように診断を受けていても「とくに言わない」「知らなかった」と答える親もいます。
診断という言葉の向こうには、子どもと親の毎日の暮らし、感じ方、受け止め方があります。
ドイツで行われた大規模な研究が、この「診断をどう受け止め、どう話すか」というテーマを、初めて本格的に調べました。
研究を行ったのは、ローベルト・コッホ研究所を中心としたチームです。
プロジェクトの名前は「INTEGRATE-ADHD」。
目的は、「保険の記録に残っているADHDの診断」と、「親が『うちの子はADHDと診断された』と答える割合」がなぜ違うのかを明らかにすることでした。
調べたのは、ドイツの健康保険「DAK-Gesundheit」に登録している約85万人の子どもたちのうち、2020年にADHDと記録されていた人たちです。
そのうち、24,000人以上の保護者にアンケートを送り、5,000人以上が答えました。
「お子さんはADHDと診断されたことがありますか?」という質問に対して、「はい」と答えた保護者は、全体の7割ほど。
つまり、医療の記録上は診断されていても、3割の親はそう答えなかったのです。

研究チームは、その違いの理由を「親の心の状態や生活の大変さ」にあるのではないかと考えました。
ADHDのある子どもと暮らす親は、日々の中で強いストレスを感じることがあります。
落ち着かない行動に目を配り続けること、周囲から理解されにくいこと、学校や友人関係への対応など、心身にかかる負担は少なくありません。
その一方で、親自身にもADHDの特徴がある場合も多く、そうした特性が子育てや受け止め方に影響する可能性があります。
アンケートでは、親のストレスや心の健康、家族のまとまり、そして「健康リテラシー(健康に関する情報を理解し、使いこなす力)」も調べられました。
さらに、母親・父親自身がADHDと診断された経験があるかも質問されました。
結果は、研究チームの予想とは反対でした。
親の負担が大きいほど、むしろ「うちの子はADHDと診断された」と答える人が多かったのです。
たとえば、ストレスを多く感じている親ほど診断を報告する割合が高く、また母親や父親自身がADHDと診断された経験がある場合には、
「子どもの診断を報告する確率」が2〜3倍ほど高くなっていました。
家庭のまとまりが強い場合にはやや低くなる傾向がありましたが、健康リテラシーの高さはとくに影響していませんでした。
これは、どういうことなのでしょうか。
研究チームはこう考えました。
ADHDのある子どもと日々向き合っている親は、その大変さを身にしみて感じています。
そのため、子どもの行動に注意を払い、「これはうちの子の特徴なんだ」と意識する機会が多い。
また、自分自身にもADHDの経験がある親は、子どもの行動をよりよく理解し、共感し、受け止めやすい。
その結果、診断を「実感をもって」語れるのではないかというのです。
一方で、あまり困りごとを感じていない親や、家庭が落ち着いている親の中には、子どもの行動を「ちょっと元気すぎる」「性格の一部」ととらえる人もいます。
その場合、医師から伝えられた診断を深く意識せずにいたり、アンケートで思い出さなかったりすることがあるのかもしれません。

この結果は、ADHDという言葉が単なる「ラベル」ではなく、家庭ごとの感じ方や背景の中で違って見えてくることを示しています。
親のストレスや体験の多さが、診断をどのように受け止めるかに関係しているのです。
研究チームは以前の分析で、医師の伝え方にも課題があると指摘しています。
とくに小児科では、診断の説明が十分でなかったり、保護者にわかりやすく伝わっていないことがある。
一方、精神科や心理療法士などで丁寧に説明を受けた場合は、親が診断を理解し、受け止めやすくなる傾向が見られました。
診断というのは、「伝えること」と「受け取ること」の両方があって初めて成り立つ――そのことがこの研究からも浮かび上がります。
もちろん、今回の調査には限界があります。
参加した保護者は全体の一部であり、ADHDへの関心が高い人が多かったかもしれません。
また、この研究はある時点のデータを比べたもので、原因と結果を断定するものではありません。
それでも、ドイツで初めて「保険の診断データ」と「親の回答」を一人ひとりで照らし合わせた研究として、大きな意義があります。
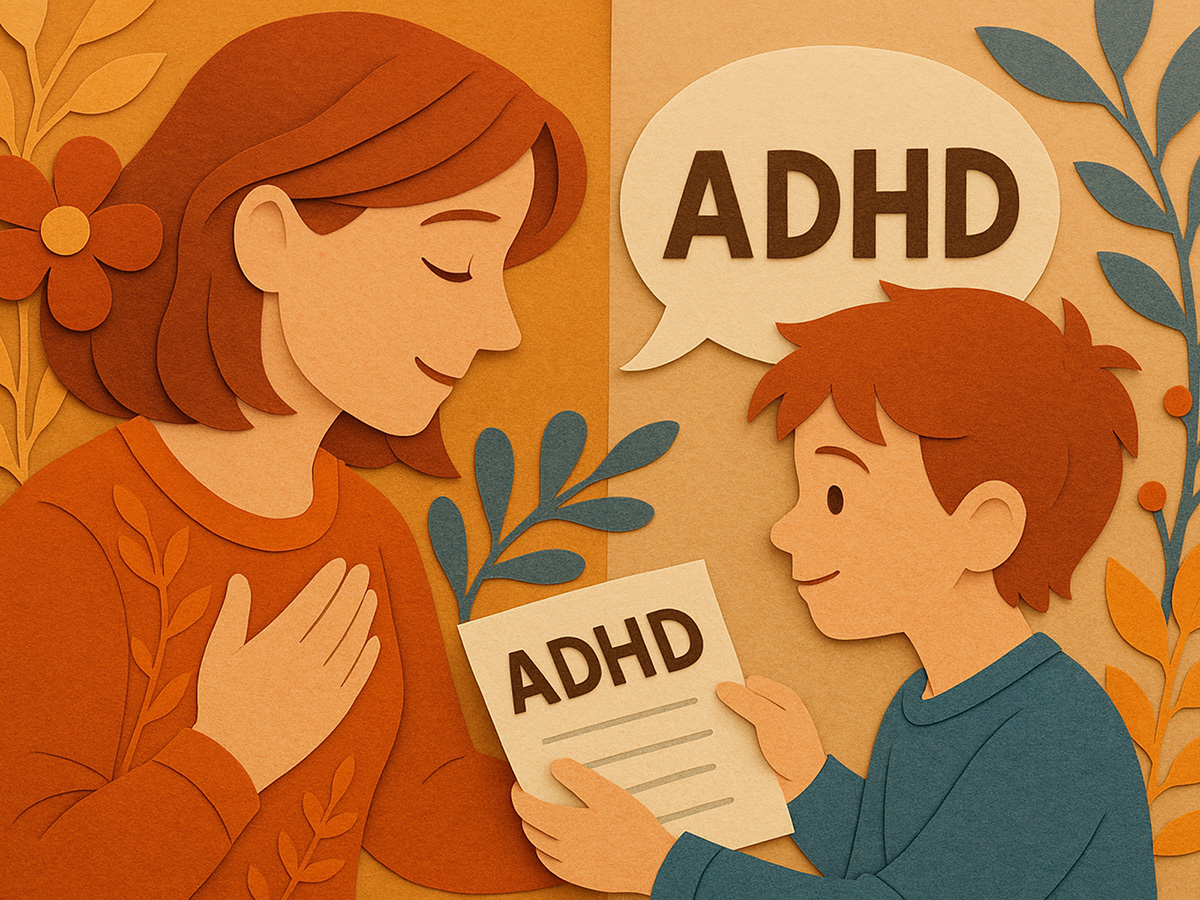
この研究の結論はこうです。
「親の心理的な状態やADHDの有無は、子どもの診断をどう理解し、どう語るかに関係している。
負担を感じていない親や、これまでADHDに関わる支援を受けたことのない親には、より丁寧な説明や情報提供が必要である」
ADHDの理解は、数字や診断名だけでは測れません。
それは、家族のなかで交わされる気持ちや体験の物語の中にあります。
自分の子どもを見て「この子の特性をわかってあげたい」と思うとき、同時に自分自身の感じ方や過去の経験とも向き合うことになる。
この研究が示したのは、まさにその「親と子がつながる場所」にある現実でした。
診断を伝える人、受け取る人、その両方が少しずつ理解を深めていくとき、ADHDという言葉は、ただの医学用語ではなく、「わかりあうためのきっかけ」に変わっていくのかもしれません。
(出典:BMC Psychiatry DOI: 10.1186/s12888-025-07575-9)(画像:たーとるうぃず)
言う、言わない、どう言うか。
それぞれの親子ごとに違っていいですし、話そうとする相手によっても違って良いです。
自分たちが幸せだと思える選択をすればいいです。
(チャーリー)




























