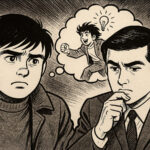この記事が含む Q&A
- 共感は自閉症の特性と幻覚のような体験と結びつき、共感が強いほど社会的なやりとりの難しさが少なく、幻覚体験は心のハブとして他の要素と結びつくという関係が示されましたか?
- 共感を育てるよりも、共感が生まれやすい場を整えることが支援の鍵であると提案されています。
- 男女差についてはどのような点が指摘されていますか?
- 男子は全体のつながりが強く、特に社会的コミュニケーションと反復的行動の結びつきが強い一方、女子では共感と幻覚との関係が顕著で、背景の心の動きが異なる可能性が示唆されています。
- 研究から「共感がない」と決めつけず、どう受け止めるべきというメッセージが得られますか?
- 「共感はわかること」ではなく「わかろうとすること」であり、環境を整えることで共感の力が自然と育つ可能性が強調されています。
子どもが見ている世界は、ときに大人が想像するよりずっと広く、深く、不思議です。
なにげない会話のなかで、誰かの気持ちをすぐに感じ取る子もいれば、言葉よりも音や光に敏感な子もいます。
中には、「誰かに呼ばれた気がした」「見えないものが見えた気がした」と話す子もいます。
それは「幻覚」や「妄想」と呼ばれる体験に似ていますが、多くの場合、病気ではありません。
子どもの心は成長の途中であり、「現実」と「想像」のあいだを自由に行き来するような時期があるのです。
今回紹介するのは、そんな子どもたちの“こころの地図”を描いた研究です。
カナダのマクマスター大学とインドの研究チームが行ったもので、約9200人もの9〜11歳の子どもを調べました。
テーマは「自閉症の特性」「幻覚や妄想のような体験」「共感する力」。
この3つの関係を、ひとつの“関係図”として分析したのです。
研究に使われたのは、アメリカの大規模調査「ABCDスタディ」というデータです。
このデータは、脳や行動の発達を長期間にわたって追う世界最大級の研究で、親の回答や子どもの自己報告、そして心理的な測定結果が含まれています。
研究チームはまず、次の3つを調べました。
「自閉症の特性(Autistic traits)」です。
これは、社会のなかでのやりとりの難しさや、決まった行動や考えにこだわる傾向を示します。
次に「幻覚や妄想のような体験(Psychotic-like experiences)」です。
たとえば「人の声が聞こえた」「自分だけ特別な力がある」と感じるなど、現実とは少し違う体験をしたときのことです。
そして「共感(Empathy)」です。
つまり「人の気持ちを感じ取る力」「困っている人に手を差し伸べる心」です。
これらが、どのようにつながっているのか。
研究チームは、特別な分析法で確かめました。
それは「ネットワーク分析」というもので、心理の世界を「点」と「線」で表す方法です。
「点」はそれぞれの要素(自閉症の特性や共感など)、「線」はそれらの関係を意味します。
線が太ければ関係が強い。細ければ弱い。
この方法を使うと、子どもの心の中にある“つながりの模様”を、ひとつの地図のように見ることができるのです。
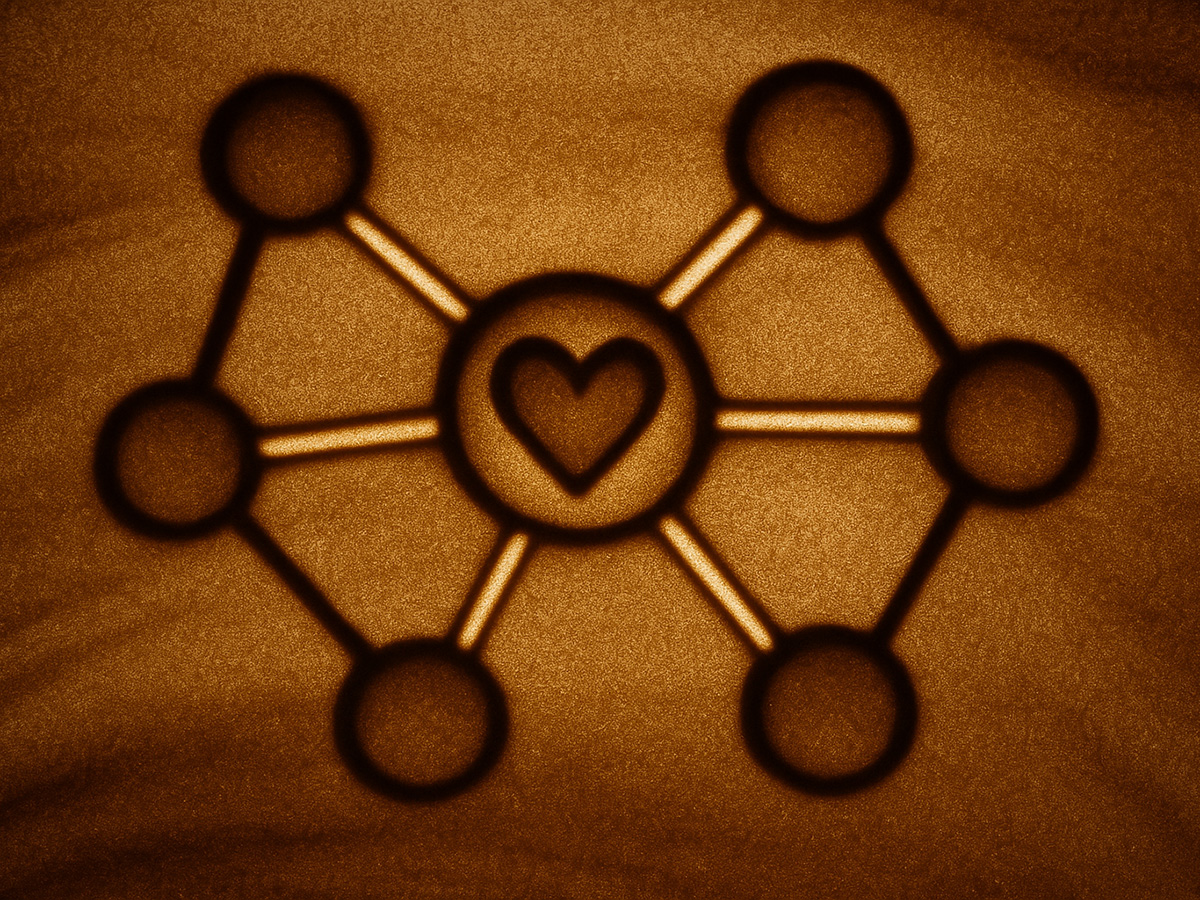
その結果、まずわかったのは、「共感」と「自閉症の特性」が反対の方向に動いているということです。
つまり、共感が強い子ほど、社会的なやりとりの難しさや、くり返しの行動は少ない傾向がありました。
逆に、そうした難しさが強い子ほど、人の気持ちを感じ取る力が弱くなっていました。
この関係は、「共感が足りないからコミュニケーションが苦手」という意味ではありません。
むしろその逆で、「コミュニケーションが難しい環境にいることで、共感を発揮する機会が少なくなってしまう」という可能性があるのです。
研究チームは、社会的なやりとりが難しい子にとって、共感は“生まれにくい”のではなく、“届きにくい”ものなのかもしれないと考えました。
さらに興味深いことに、「自閉症の特性」と「幻覚・妄想のような体験」にも関係が見られました。
社会的なやりとりに苦手さを感じる子ほど、「幻覚」を体験することが多かったのです。
また、「こだわりの強さ」と「誇大な思い込み(自分が特別な存在だと思う気持ち)」にもつながりがありました。
この結果は、「心の世界を感じ取りやすい子」は、想像と現実の境目がゆらぎやすいことを示しているのかもしれません。
では、この3つの要素のなかで、どれが中心にあるのでしょうか。
分析の結果、「幻覚」が最も強く、他のすべての要素と関係していました。
つまり「幻覚」は、自閉症の特性と共感の両方に橋をかけるような存在だったのです。
研究チームは、これを「心のハブ(中心点)」と呼びました。
この結果は、「幻覚」という言葉が恐いものに聞こえる一方で、それが必ずしも病的なものではなく、子どもの想像力や感受性と深く関係していることを示しています。
研究チームは、もう一歩踏み込みました。
次に「どちらが原因で、どちらが結果なのか」を調べるため、「ベイジアンネットワーク」という方法を使いました。
この方法は、データのなかから“流れの方向”を推定するものです。
その結果、「思考の乱れ」が「幻覚」や「誇大な思い込み」につながること、
そして「社会的なやりとりの難しさ」が「共感の低下」につながることがわかりました。
つまり、共感の弱さは“原因”ではなく、“影響を受けた結果”だったのです。
このことは、自閉症の子どもを支援するうえで重要な意味を持ちます。
共感が育たないから人と関わらないのではなく、人と関わる場が安心できるものであれば、共感の力は自然と育っていく。
「共感がない」と決めつけるのではなく、「共感を表すチャンスがまだない」ととらえることが大切なのです。
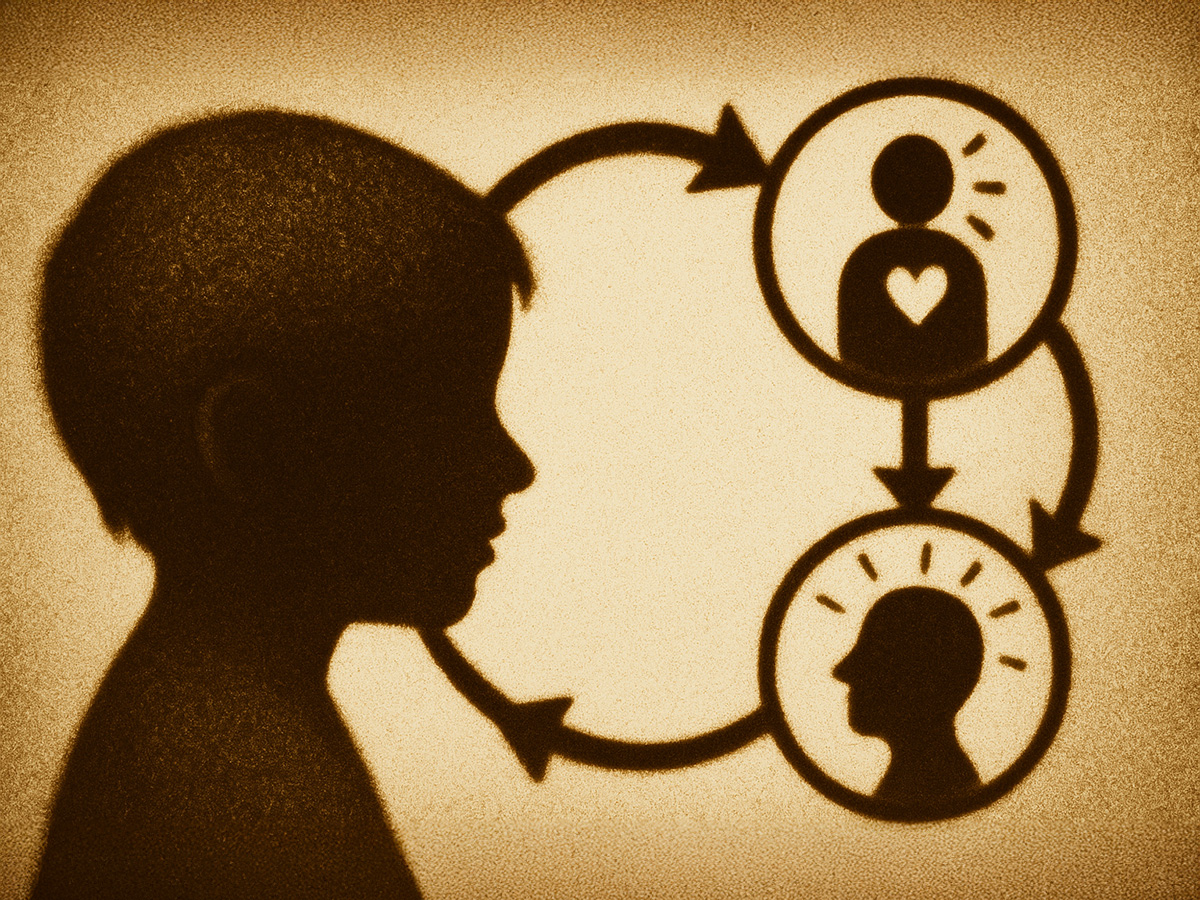
また、この研究では男女差も明らかになりました。
全体のつながりの強さは男子の方が高く、とくに「社会的コミュニケーション」と「反復的行動」の結びつきが強いことがわかりました。
女子では、共感が「幻覚」と関係していました。
つまり、女子の方が感覚的な世界と感情のつながりが強い傾向があるのかもしれません。
この結果は、支援のあり方を考えるうえで重要です。
男の子と女の子では、同じように見える行動の背景に、違う心の動きがある可能性があるからです。
研究チームはこうまとめています。
「自閉症の特性と幻覚のような体験は、別のものではあるが、どこかで触れあっている。
そして、共感はその間に静かに存在している。」
つまり、子どものこころは単純な分類ではとらえきれないということです。
自閉症の特性を持つ子も、そうでない子も、幻覚を感じる子も、そうでない子も、みんな同じ「こころの地図」の中にいて、それぞれの場所で世界を感じています。
この研究は、「共感が少ない」という誤解を正すだけでなく、「共感とはなにか」という問いをあらためて投げかけています。
共感は、誰かの気持ちを正確に読み取る能力ではありません。
「相手と自分の感じ方が違うことを知る力」でもあるのです。
だからこそ、たとえ感じ方が違っても、「あなたの感じ方を知りたい」と思う気持ちがあれば、それはもう共感の始まりです。
研究チームは、最後にもうひとつ大切な考えを紹介しています。
それが「ダブル・エンパシー問題(二重共感問題)」です。
これは、自閉症の人とそうでない人が“おたがいに”誤解しやすいという考え方です。
つまり、「共感のズレ」はどちらか一方にあるのではなく、双方の間にあるということです。
おたがいの理解がすれ違うことで、関係がぎこちなくなってしまう。
その誤解の連鎖をほどくには、どちらかが正しいかではなく、「違う感じ方を認め合う」ことが必要です。
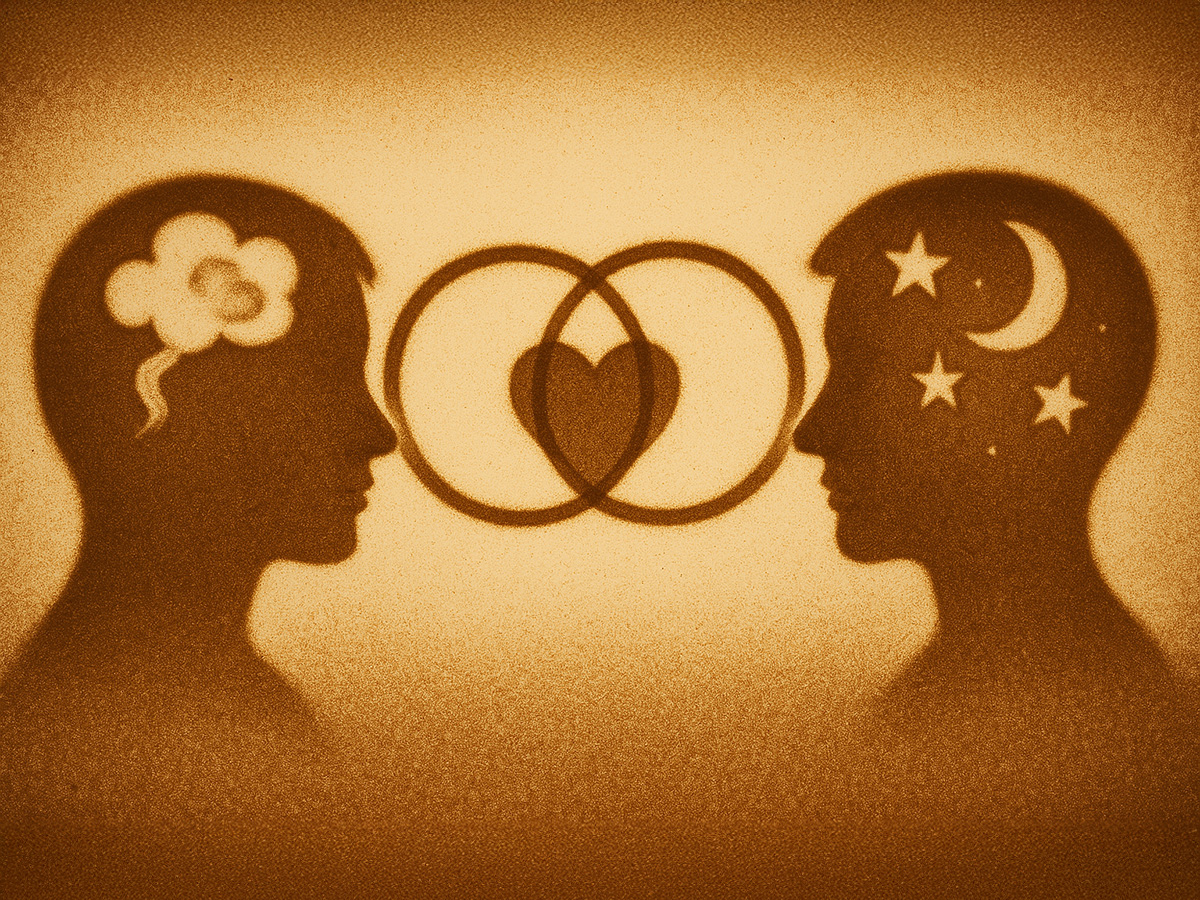
研究の限界として、共感の評価が自己申告であったこと、感情的な共感と考える共感を区別できなかったことなどが挙げられています。
また、今回は横断的な研究であるため、「どちらが先か」は確定できません。
それでも、これほど大規模なデータから、子どもたちの「共感」「自閉症の特性」「幻覚のような体験」の関係を丁寧に描き出した研究は、きわめて貴重です。
親や支援者にとって、この研究が伝えるメッセージは明確です。
「共感を教えようとするよりも、共感が生まれる場を整えることが大切」
「理解されにくい行動の裏には、その子なりの感じ方がある」
「不思議な体験を語る子を、恐れず、まず受け止める」
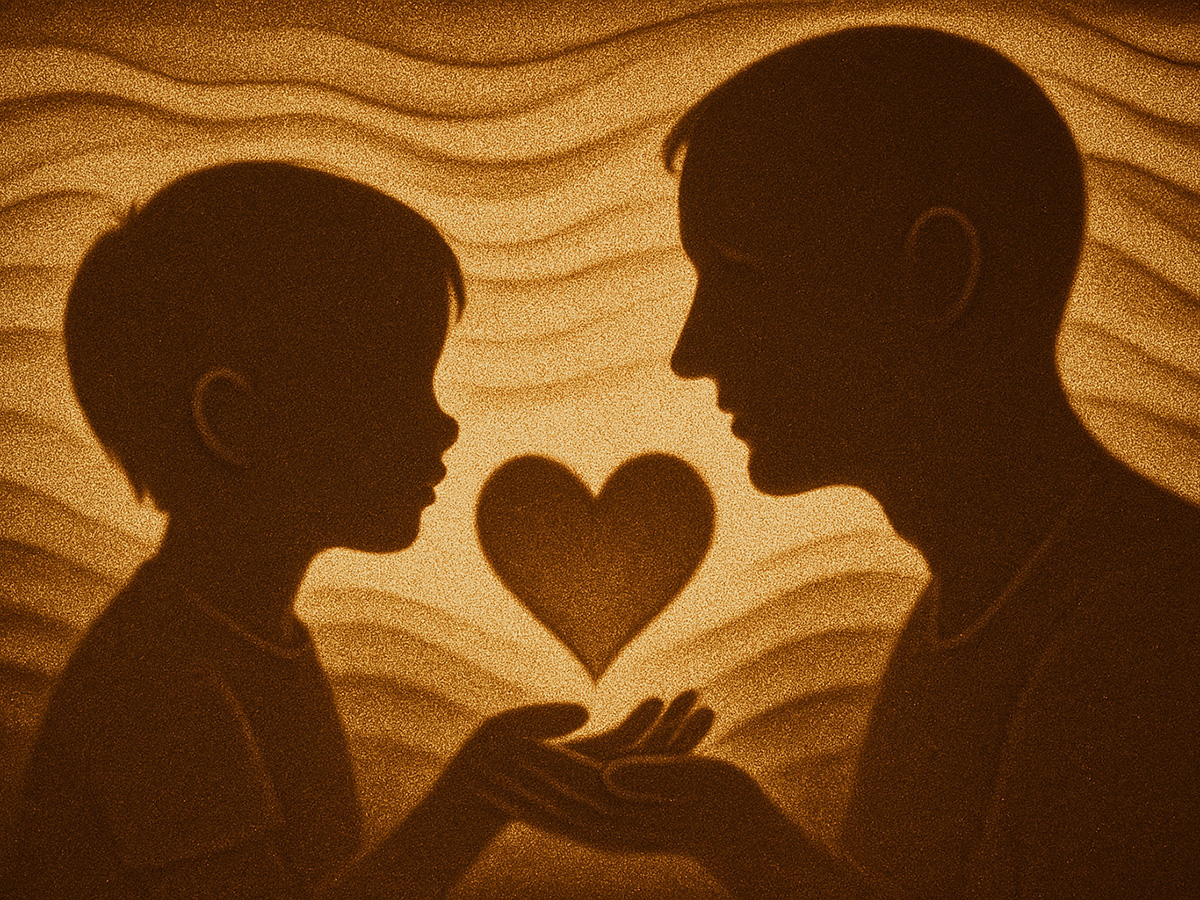
子どもたちは、まだことばにならない世界の中で、自分なりの「感じ方」を探しています。
その感じ方が他の子と違っても、それは「欠けている」わけではなく、「違う光の当たり方」をしているだけなのです。
自閉症や幻覚という言葉は、どちらも“異質”として語られがちですが、この研究はそれをひとつの連続した現象として描きました。
人の心はグラデーションのように広がっており、どこからが「特性」で、どこまでが「ふつう」かという線は、ほんとうはとてもあいまいなのです。
この研究が教えてくれるのは、「こころの違い」は分けるものではなく、つなぐものだということ。
そして、共感とは“わかること”ではなく、“わかろうとすること”。
子どもたちがそれぞれの感受性をもって生きていけるように。
親や支援者のまなざしも、また「共感」の一部であると、この研究は静かに語っています。
(出典:Nature Scientific Reports DOI: 10.1038/s41598-025-21992-6)(画像:たーとるうぃず)
うちの子は話すことができないので、本人に確認できないのですが、なんだか私には見えないものをみているようなことがたびたびあります。
「幻覚や妄想のような体験」
をしているのですね。納得しました。
(チャーリー)