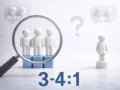この記事が含む Q&A
- 自閉症の子どもは「ひとりで遊ぶ」ほうが深い学びを得られるのですか?
- はい、ひとり遊びのほうが考える時間や試行錯誤、成功体験が増え、深い学びの得点が高くなる傾向が観察されました。
- ひとり遊びでの学びはどんな点で現れますか?
- 自分のペースで興味を追い、言葉が出にくい子でも考えを深め、感情体験が高い場面が見られました。
- 家庭環境や対人関係は学びにどう影響しますか?
- きょうだいがいる、幼稚園の友だちと遊ぶ機会があると学びの得点が高くなる傾向があり、収入が低いと経験の応用や問題解決の得点が下がる傾向も示唆されています。
子どもが夢中になって遊んでいるとき、その心と頭の中では、想像以上に深い学びが起きています。
砂をにぎった手の感触。
ブロックが崩れたときの「どうして?」という小さな疑問。
何度も組み立てをやり直す粘り強さ。
そこには、自分で世界の仕組みを確かめ、自分なりの答えに近づこうとする力が宿っています。
しかし、自閉症の子どもたちについて語られるとき、その大切な「内側の力」はしばしば見落とされてきました。
「みんなと同じように遊べない」「会話が続かない」と、表に見える困難ばかりが注目されてしまう。
そのたびに、お父さんやお母さんは胸の奥がぎゅっと締めつけられる思いをしてきたのではないでしょうか。
そんな中で、中国の東華師範大学の研究チームは、これまでとは違う視点から自閉症の子どもたちに光を当てました。
研究チームが問いかけたのは、とても力強いものです。
「自閉症の子どもにも、深く学ぶ力があるのか?」
深く学ぶ力。
それは、知識をただ受け取るだけではなく、自分の経験を手がかりに考えを広げ、応用し、問題を解決しようとする力。
いわば「自分で世界をつかみにいく力」です。
研究チームは、自閉症の子どもたち8人と、定型発達の子どもたち13人を対象に調査しました。
場所は4つの幼稚園。
年齢は5歳から7歳。みんなが普段から遊んでいる環境で、子どもたちの「学びの深さ」を丁寧に観察しました。
使われた尺度は、6つの側面からなる「深い学びの能力」評価です。
・感情をどう感じ、どう表現しているか
・問題に気づいているか
・経験を応用できているか
・解決のために考えを働かせているか
・人とやり取りしながら学べているか
・考えが論理的で柔軟か、振り返りができているか
つまり、いわゆる点数の良し悪しを見るのではなく、「その子が遊びの中で何を感じ、どう頭を使っているのか」そのプロセスすべてが評価されました。

この研究の特別な点は、2つの遊びを比較したことです。
ひとつは「みんなで遊ぶ遊び(インクルーシブ・プレイ)」。
もうひとつは「ひとり、または似た子同士で遊ぶ遊び(ソリタリープレイ)」。
多くの大人はこう思うかもしれません。
「友だちと遊んだほうが学びが深まりそう」
しかし、研究結果は、そんな “常識” をやさしく揺さぶるものでした。
自閉症の子どもたちの深い学びの得点は――ひとり遊びのほうが高かった のです。
「え?どうして?」
そう思われたかもしれません。
研究チームは、そこに自閉症の子どもたちらしい力の使い方があると見ています。
ひとりで遊ぶとき、彼らは自分のペースで自分の興味を心ゆくまで追いかけることができます。
言葉が出にくい子にとっては、「説明しなければならない相手」がいない環境は、考えることに集中できる心地よさにつながります。
結果として、
・考える時間が増える
・試行錯誤が増える
・成功体験が増える
だから、学びが深まるのです。
「ひとりでいるときも、その子は前に進んでいます」
この事実は、「友だちと関われない=問題」というこれまでの偏った見方を、やさしく修正してくれます。
もちろん、社会的な関わりはとても大切です。
研究でも、対人面は自閉症の子どもたちの得点が一番低い項目でした。
しかし、ここで大切なのは「得意と苦手は、学び方のちがいである」という視点です。
自閉症の子どもたちは、自分の感じ方と興味をエネルギーにして成長していきます。
研究の中で、一番点数が高かったのは「感情体験」でした。
・好きなものに出会ったときのキラキラした目
・集中しすぎて周りが見えなくなるほどの没入
・うまくいったときの、声にならない小さな喜び
こうした瞬間は、まさに「学びが深まっているとき」なのです。

さらに深く見ていくと、
ひとり遊びの中で、言葉を使った表現が増える子が多くいました。
自分一人なら、考えを誰かに合わせる必要も、誤解を恐れる必要もありません。
「ことばは、興味や感情と結びついたとき強く育つ」
この研究は、そんな発達の原則を自閉症の子どもたちでも確認できた、と言えます。
また、家族環境も深い学びに影響していました。
・きょうだいがいる
・幼稚園の友だちと遊ぶ機会がある
こうした子どもたちは、学びの得点が高い傾向にありました。
つまり、人との関係が苦手でも
関わりの “場” があることは大事なのだとわかります。
余白の中で、自分のペースで交わりが育っていく。
それがきっと、自閉症の子にとって自然な道筋なのでしょう。
一方で、家庭の収入が低いほど経験の応用や問題解決の得点が下がる傾向もありました。
これは、親御さんの努力不足ではありません。
ただ、生活に余裕があるほど子どもの経験の幅が広がりやすいという現実があるのです。
社会としてサポートすべき、大切な示唆だといえます。
この研究には、限界もあります。
人数はまだ少なく、女の子はわずかひとり。
でも、それでもはっきりわかったことが一つあります。
「自閉症の子どもたちには、深く学ぶ力がある」
それは、強いメッセージです。

遊んでいるとき、彼らは「できない子」ではありません。
自分のやり方で、自分の世界を広げている「学びの主体」です。
自閉症は、誰かにあわせることがむずかしい特性です。
だからこそ、遊びという自由な場で子どもたちは本来の力を発揮します。
もしお父さんやお母さんが「うちの子、ひとりで遊んでばかり…」と不安になっていたなら、
この研究はそっと肩に触れてくれるはずです。
「大丈夫。その時間も、とても豊かな学びになっていますよ。」
遊びは、誰かに評価されるためのものではありません。
比べるためのものでもありません。
うまくいかなくても、言葉が出なくても、回り道をしても、その子が感じ、考え、少しだけ前に進んだなら、それは立派な「深い学び」です。
研究チームは伝えています。
「子どもは遊びの中で、自分自身の物語を紡いでいる」
私たちにできるのは、その物語の続きを見守り、支え、信じること。
自閉症の子どもたちの学びは、ゆっくりかもしれません。
でも、それは“遅い”のではなく“ていねい”なのです。
そして何より、その歩みは彼ら自身の力によるものです。
世界の見え方がちがうこと。
それは、世界をより豊かにすること。
遊びの時間に、その子の未来へとつながる深い学びが、たしかに息づいています。
(出典:Journal of Intelligence DOI:10.3390/jintelligence13110135)(画像:たーとるうぃず)
これは、とてもうれしくなる研究結果です。
ちょっと違うように感じても、その子なりに、その子のやりかたでたしかに成長しているのですね。
見守り、支え、信じる。
(チャーリー)