
この記事が含む Q&A
- 自閉症の人が自分自身をどのように語ることができますか?
- カードやイメージを通じて、深い感情や考えを表現することが可能です。
- ディクシット・エリシテーションの手法はどのような効果がありますか?
- 感情や体験を自然に引き出し、共感や理解を促進します。
- この方法は自閉症の人たちの社会参加にどのように役立ちますか?
- 自己表現の機会を増やし、多様性や強みを社会へ伝える橋渡しとなります。
自閉症は、世界の人口の約1パーセントが持っているとされる発達特性です。
これまで長いあいだ、自閉症は「困難」や「障害」として語られ、できないことや問題行動ばかりが取り上げられてきました。
しかし近年では、本人の感じ方や考え方、つまり「生きた体験」を尊重し、そこにある強みや多様性に注目する動きが広がっています。
そうした動きの中で、自閉症の人たちが自分自身のことを、どのようにとらえ、どのようなイメージで語るのかを深く探る試みが行われました。
この研究を行ったのは、イギリスのプリマス大学心理学部を中心とする研究チームです。
研究の目的は、自閉症の人が自分自身について語るときに、言葉だけでなくイメージや物語の力を使うことで、より深い表現を引き出せるかどうかを探ることでした。
この研究で用いられた手法は、「ディクシット・エリシテーション」と名づけられました。これはボードゲーム「ディクシット(Dixit)」を使ったまったく新しい定性的な調査法です。
ディクシットは、幻想的でシンボリックなイラストが描かれたカードを使い、プレイヤーがその絵に合うヒントを出して、他のプレイヤーと意味の解釈をやり取りするというゲームです。
ヒントはあまりにも具体的でもダメで、かといって抽象的すぎても伝わらない、ちょうどよい想像のやり取りが求められるゲームで、遊びながら互いの内面世界を垣間見ることができます。
この研究では、35人の自閉症の大人たち(女性12人、男性23人、平均年齢32.6歳、うち6人は知的障害を併せ持つ人)が参加しました。
彼らはイギリス国内のコミュニティグループの一員であり、日常的にボードゲームを通じた交流を楽しんでいる人たちです。
研究者はその場に参加し、「“自閉症”という言葉に合うカードを選んでください」という形でインタビューを始めました。
参加者たちはそれぞれの手札の中から、自分が思う「自閉症」を象徴するカードを選び、その理由を語りました。
その語りは録音され、後日文字起こしされて、複数の研究者が別々に読み込み、内容を分析しました。

分析の結果、参加者たちの語りには大きく3つのテーマが見られました。
「困難」「強み」「社会」です。
それぞれのテーマの中には、さらに複数のサブテーマが含まれていました。
参加者たちの語りは、自分の苦しみや誇り、そして社会との関係の中での戸惑いや葛藤を、非常に鮮やかに、そして個性的に表現していました。
最初に語られたのは、「困難」とされる体験でした。
とくに多くの人が感じていたのは「孤立」です。
選ばれたカードの中には、一人ぼっちで風船を持って立っている少女や、鍵のかかったドア、閉ざされた空間などの絵がありました。
ある人は、「この女の子は自分の風船を持っているけど、世界はゆがんでいて、誰もそのことを理解してくれない」と語りました。
また別の人は、「自閉症の人は、ときどき自分の内側に閉じこもってしまう。だけど、その閉ざされたドアの鍵を家族が見つけてくれたこともあった」と、人生の中で少しずつ他者とのつながりが見つかってきた実感も語りました。
次にあげられたのは「圧倒」という体験です。
これは、感覚過敏や情報過多によって心身が混乱してしまう感覚を指します。
「脳のような機械がうねっているカード」を選んだ参加者は、「頭の中がとにかく騒がしくて、スーパーに行くだけでも倒れそうになる。すべてが気になってしまい、制御がきかない」と語りました。
別の参加者は、「このカードは、現実がねじれて見える感覚を表している。他の人にはまっすぐに見える世界が、自分には大きすぎたり小さすぎたりして、全部が圧倒的に感じられる」と説明しました。

また、「過小評価」という語りも多くありました。
自閉症の人が社会から「能力がない」「人間として不完全」と見なされる経験です。
ある人は「操り人形のカード」を選び、「自分は他人にコントロールされているように扱われる。だけど自閉症の人には、他にないクリエイティブな力があるんだ」と語りました。
別の人は、「自分は人間として扱われていないように感じる。それが社会の見方なんだ」と、深い孤独感と怒りをにじませていました。
そして「メルトダウン」という体験も重要な語りとして現れました。
これは、自閉症の人が強いストレスや感覚の刺激を受けたときに、激しい感情や身体の反応として現れる状態を指します。
ある参加者は、「メルトダウンはすごく孤独だ。周りに人がいても、誰も助けてくれない。逆に刺激を与えてしまうから、みんな離れていく」と話しました。
また別の人は、「メルトダウンは煙のような信号で、人によってその煙の色も形も違う。でもそれは、本人の心の声なんだ」と述べました。
こうした困難な体験に続いて語られたのが、「強み」です。
まず注目されたのは「ダイバーシティ(多様性)」でした。
参加者たちは「自閉症といっても、ひとりひとりまったく違う」と繰り返し語りました。
「ある人は芸術が得意、ある人はテクニカルなことが得意、ある人はとても静か、ある人はとてもしゃべる」と、それぞれの個性が豊かに語られました。
同じグループにいることで、そうした多様性がよく見えるといいます。

次に語られたのは「創造性」です。
ディクシットのカードには、日常とは異なる不思議な世界やシンボルが描かれていて、それが自閉症の人の発想や世界の見え方と重なると多くの参加者が話しました。
ある人は「普通の人なら思いつかないようなアイデアを出せるのが自閉症の強み」と語りました。
また「迷路の中を進むイモムシと、その上を飛びながらゴールを見つける鳥」のカードを選んだ人は、「イモムシが普通のやり方なら、自閉症の人は鳥のように上から全体を見て違う視点で問題を解くことができる」と表現しました。
これはまさに、他の人が気づかない解決法を見つける力として語られました。
さらに重要な強みとして語られたのが「情熱」です。
自閉症の人の多くは、自分が興味を持ったものに対して非常に強い集中力と深い知識を持っています。
「火山のカード」を選んだ参加者は、「自閉症の人は、まるで火山のように知識を爆発させる。
好きなことに関しては、誰にも負けないくらい詳しくなる」と語りました。
別の人は、「自分は好きなものに夢中になって、細かいところまでずっと調べ続けることができる。他の人が見落とすようなことも、自分は気づく」と述べました。
情熱を持っていることは、自閉症の人にとって喜びでもあり、周囲にとっても魅力的な部分だといえます。
そして最後に語られたのが、「社会」に関するテーマです。
社会との関係において、自閉症の人たちが感じている苦しみや不公平さ、誤解が強く浮かび上がりました。
最初に語られたのは「ステレオタイプ(決めつけ)」でした。
ある人は「自閉症の人は、天才とか、変わり者とか、感情がないとか、そういうステレオタイプで語られがちだ。だけどそんなのは一部の人だけで、本当はみんなちがう」と語りました。
また「自閉症=数学が得意」「自閉症=静か」というような決めつけは、かえって本人の個性を否定するものになってしまうという意見も出ました。

つづいて語られたのは「ポリースト(監視されている感じ)」です。
これは、日常の中で常に「間違っている」と言われたり、「それは変だよ」と否定されたりする体験です。
ある人は「社会の中で、自分には進んではいけないという“ストップサイン”が立っているように感じる」と語りました。
また、「自分はずっと、何か悪いことをしているかのように見られている。自分のままだとダメだと言われ続けてきた」と述べた人もいました。
大人になってもなお、子どものように扱われる、信頼されない、という感覚があるといいます。
最後に語られたのが「マスキング(仮面をかぶること)」です。
これは、自分の本当の姿を隠して、社会に合わせるために別の自分を演じることです。
ある人は「自分の中にはとてもやさしい部分があるけれど、それを見せると危ないから鎧を着ている」と語りました。
また別の人は、「家では明るく振る舞えるのに、学校や職場ではまったく違う自分を演じている」と話しました。
「マスクを何枚も重ねているようで、だんだんどれが本当の自分かわからなくなる」という声もありました。
こうした語りのひとつひとつは、ディクシットのカードというイメージをきっかけに生まれました。
研究チームは、この方法が非常に有効であると考えています。
なぜなら、言葉だけでは出てこない感情や記憶が、絵という媒介を通して自然に引き出されるからです。
しかもそれは、一人で話すインタビューではなく、同じ当事者同士が一緒に遊びながら語るという、安心できる空間で行われたからこそ実現したものでもあります。
このディクシット・エリシテーションという手法は、インタビューのように一方的に質問されるものではありません。
むしろ、ひとつのカードから始まる物語のようなやりとりであり、参加者どうしが共感しあい、体験を共有する空間そのものが、研究の中核をなしていました。
参加者たちは、カードを見て感じたことを語るだけでなく、他の参加者の話に反応し、自分の経験と重ね合わせながら語り合うという「対話の連鎖」が起きていたのです。
研究チームは、この方法が自閉症の人たちの「語る力」や「感じる力」を尊重する新しいアプローチになると考えています。
また、この手法にはセラピーとしての可能性もあります。
過去の研究でも、ディクシットを使ったグループ活動が、コミュニケーションの向上や人間関係の改善につながることが示されてきました。
ディクシットのカードには、寓話や神話、夢のような情景が描かれており、それらが時に、語る人の内面世界と強く共鳴することがあります。
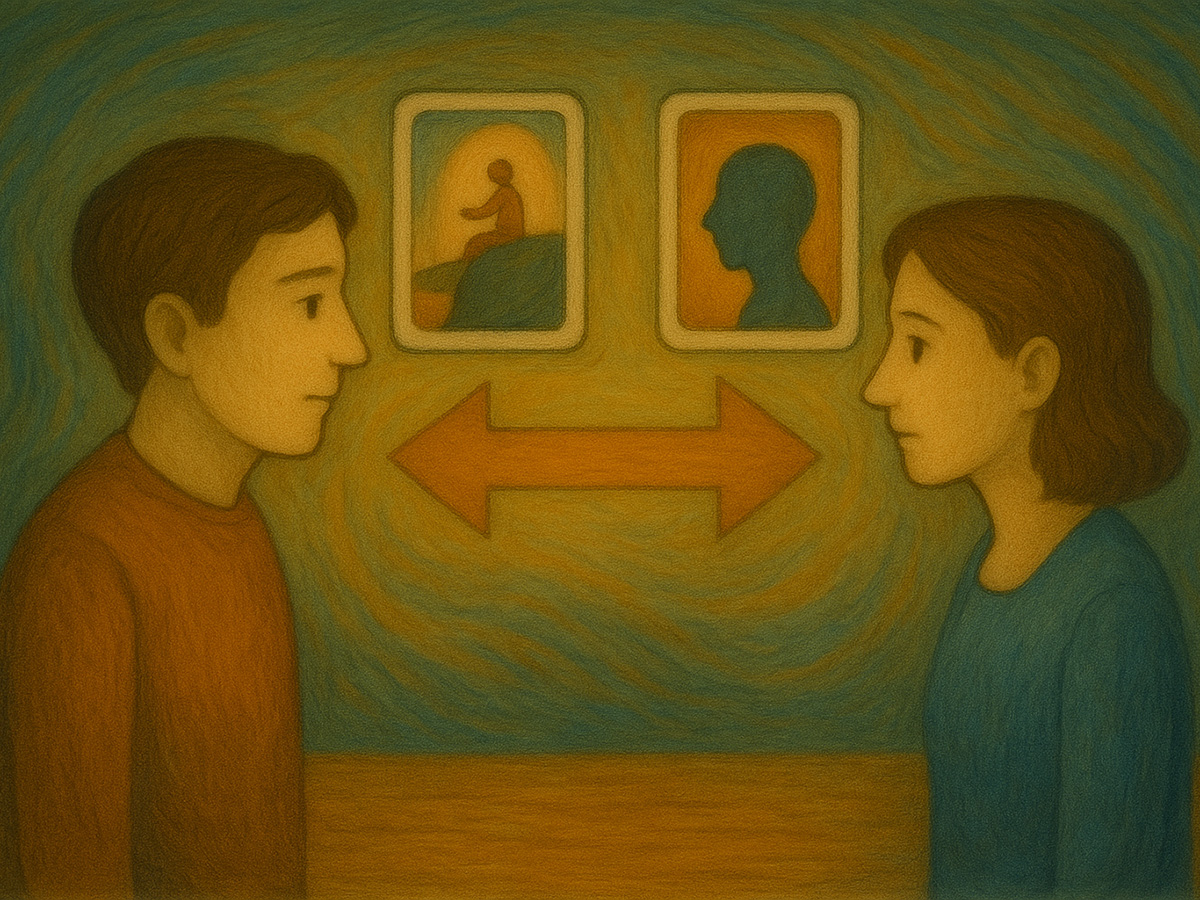
また、この研究は「ダブル・エンパシー・プロブレム(二重の共感問題)」と呼ばれる課題に対する新たな視点も提供しています。
これは、自閉症の人が「他者の気持ちがわからない」とされがちである一方で、実は「非自閉症の人もまた、自閉症の人の感じ方を理解していない」という、双方向の理解の難しさを指摘した考え方です。
つまり、コミュニケーションの障壁は一方通行ではなく、むしろ社会の構造や常識そのものに偏りがあるという見方です。
この手法では、自閉症の人たちが自分の感じている世界をカードを通して表現することができ、それを周囲の人が視覚的にも感じ取ることが可能になります。
ある参加者は、「このカードの中の女の子は、自分のように世界から浮いている気がする」と言いました。
すると、他の人たちも「自分もそうだ」と共感し、初めて共有される感覚が生まれたのです。
これはまさに、共感が相互に生まれる瞬間でした。
ゲームには、協力と競争が混ざり合った独特の構造があります。
たとえ勝敗があっても、プレイヤー同士は共通のルールの中で、相手の行動に注目し、配慮しながら進めていきます。
こうした性質は、自然と「他人を理解する」「相手の視点に立つ」といった行動を促すことにつながります。
つまり、遊びの中にはすでに、共感と理解を練習する場が備わっているとも言えるのです。
この研究では、当初からゲームを研究対象として設計したわけではありませんでした。
もともとは自閉症の人たちと一緒にボードゲームを楽しむ活動をしていた中で、「ディクシットを使って自閉症を表現する」というアイデアが自然に生まれ、それが新しい研究手法に発展したのです。
この「現場から自然に生まれた方法」という点も、研究としては非常に注目すべき特徴です。
また、カードを使うことによって、語ることが難しいとされている人――たとえば言葉を使うことが苦手な人や、子ども、小さな声しか出せない人――でも、自分の思いを表現するきっかけを得ることができます。
「このカードが自分に似ている」と指さすことだけでも、そこには豊かな意味が込められている可能性があります。
その意味を、周囲の人が一緒に想像し、聞き取り、共有していくことで、言葉ではとらえきれない「心のかたち」を可視化することができるのです。

最後に、この研究に参加した自閉症の人たちは、自分たちの語りや思いが記録され、整理され、他の人たちに伝えられることに価値を感じていました。
それは単なる研究対象として扱われるのではなく、「語る主体」「経験を持つ個人」として尊重される体験でもあったのです。
この研究は、自閉症の当事者が「語る主体」として尊重されるだけでなく、彼らがもつ強みや情熱、多様性、そして社会の中で感じている困難や誤解を、他者に伝えるための“橋”としての可能性をもっています。
研究チームは、この方法をさらに発展させていく意志を明らかにしています。
たとえば、より年齢の若い参加者、あるいは発語が難しい人たちへの応用、また、自閉症と定型発達の人が混ざったグループでの活用などです。
ディクシット・エリシテーションは、「語りたくないことを語らせる」のではなく、「自分でも気づかなかった思いや感覚が、カードのイメージをきっかけに自然と外に出てくる」という点で、これまでのインタビューとは異なります。
これによって、語る力が弱いと思われていた人たちが、じつは深い感情や意味づけをもって生きていることを、他者に伝えることが可能になるのです。
もちろん、この方法はすべての人に向いているわけではありません。
ディクシットのような抽象的な絵が苦手な人もいますし、「遊び」という形式がそぐわない場面もあります。
しかし、選択肢のひとつとして、多様な表現方法の中に加えることで、より幅広い人々の声に耳を傾けることが可能になるのです。
とくに自閉症のように、言語のスタイルや社会との関わり方に違いがある人たちに対しては、このような“共感的なまなざし”が大きな意味をもつはずです。
この研究の参加者の語りからは、自閉症であることの苦しみだけでなく、それを生きることの誇りや喜びが、静かに、けれども力強く伝わってきます。
社会がまだその多様性に十分対応していない現状の中で、自分の感じ方や考え方を正直に語ることは、勇気のいる行為です。その語りが、ディクシットという美しいカードを介して語られたとき、そこには芸術にも似た深い真実が立ち上がってきます。
自閉症の当事者たちは、自分の世界を語る言葉を持っていないのではなく、その世界を伝える“適切な方法”を持っていなかったのかもしれません。
ディクシット・エリシテーションは、その方法のひとつとなり得ます。
幻想的な絵の中に、自分の過去や感情、願いを重ね、他者と共有することで、共感や理解、そして連帯のきっかけが生まれます。

私たちは、異なる生き方や感じ方を持つ人々の声にどう耳を傾けるか、という問いにこれからも向き合っていく必要があります。
この研究は、単なるデータの集積ではなく、「人間の物語」としての力をもったものです。
そこには、孤独や混乱、誤解といった困難がありながらも、それを超えていく創造力やつながり、そして静かな抵抗の姿がありました。
ディクシットのカードに描かれた、ゆがんだ家、空を飛ぶ動物、炎をまとう人物、迷路の中の虫たち――それらは、現実のルールとは違う世界を見せてくれます。
自閉症の人たちが見ている世界も、きっとそのように、私たちの想像を超えて美しく、複雑で、多様なのかもしれません。
その世界をのぞき込む小さな窓が、ディクシットのカードであり、そこから語られる言葉なのです。
この研究の成果は、私たちに問いかけてきます。
「あなたは、他者の世界を理解しようとする準備ができていますか」
と。
そして、それに対するひとつの答えとして、遊びの中に宿る物語とまなざしが、今日もそっと差し出されているのです。
(出典:Discover Psychology DOI: 10.1007/s44202-025-00340-9)(画像:たーとるうぃず)
面と向かって、質疑応答をするよりも、カードのようなものを中心に、ゲームをプレイしているかのようにコミュニケーションをとるほうが、間違いなく、いろいろ引き出せるように思います。
ゲームの中だけでなく、ふだんの生活のシーンの中でもきっとそうです。
(チャーリー)





























